
不二と白石はなぜそれぞれの新技で天衣無縫の極みに対応することができるようになったのかを考察!ドイツ戦の上位陣と戦っていた場合は?
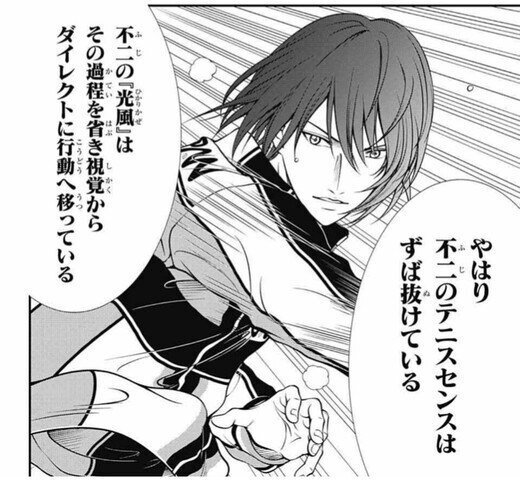
天衣無縫の極み(矜持の光)に関する考察ですが、ドイツ戦で天衣無縫の極み(矜持の光)が再定義されて1つの終焉を見たことで天衣無縫の極みはもはや「規格外の力」ではなくなりました。
現に決勝前のメンバー決定戦(校内ランキング戦のようなもののトーナメント版)ではそれぞれ越前と遠山の天衣無縫の極みが封じ込められてしまう描写が目立ちます。
幸村の零感のテニス、白石の星の聖書、そして不二の光風と次々出てきた新技にとうとう主人公ズの天衣無縫がもはや時代遅れだと言わんばかりに無効化されていきました。
しかし、幸村と赤也がなぜあれだけ苦しんで生み出した天衣無縫対策を不二と白石はサラッとやってしまえるのかということですが、これは決して天衣無縫に価値がなくなったことを意味しません。
以前こちらでも考察しましたが、天衣無縫の極みはあくまでも「自分のためにテニスをする=自分軸のテニス」という心の状態の具現化であり、それが「愛しさ」「切なさ」「心強さ」に派生しているだけです。
それ自体は「勝ち負け」とは直接的な繋がりがなく、本人の実力が伴わなければ単なる強力な武器を持っているに過ぎないと話しました。
それを踏まえて話をすると、越前と遠山の天衣無縫の極みがそれぞれ白石の星の聖書と不二の光風に破られたのは決して天衣無縫の極みが弱いのではありません。
あくまでも天衣無縫の使い手がまだ荒削りで発展の余地を多分に残しているこの2人だからこそ不二と白石の新技で抑え込むことができたのではないかと思うのです。
現に鬼VS遠山、鬼VSQ・Pがそうであるように、同じ天衣無縫使いの場合より基礎スペックや実力が高い方が勝つという当たり前の事実が示されています。
幸村や赤也があんなに天衣無縫の極み対策で苦労していたのだって「天衣無縫の極み」そのものよりは寧ろ「天衣無縫の極みを使う者の実力」に苦労していたのではないでしょうか。
そして幸村は不運にも最初に越前リョーマという「テニスを心から楽しむ」という真逆のスタンスの天才と当たってしまったために、天衣無縫の極みに後れを取ってしまったのです。
つまり幸村は天衣無縫の極みを恐れたのではなく「テニスをするのも嫌になる状態」の中で尚もテニスを続けようとし、天衣無縫の極みに行き着いたリョーマの心を「危険すぎる」と思ったのでしょう。
しかし、根が真面目で性格が不器用な幸村はそこまで思考を柔らかくできず、また病気も完治していなかったためにその辺りを混同してしまっていたのだと思われます。
現に手塚との戦いの中で病気が完治してからの幸村は天衣無縫を恐れなくなって零感のテニスや未来剥奪といった形で手塚のテニスに対応して苦しめていました。
またぼろ負けはしたものの、越前との試合の中でも最後の方では天衣無縫に追いつき盛り返す描写も見せており、決して天衣無縫の極みを使った越前との間に大きな差があったわけではありません。
実際それまでの打ち合いが示しているように、越前と幸村が普通に打ち合ったら幸村の方が実力は上だったわけですし、現に中学生最強の手塚と幸村が打った時は実力伯仲でした。
そういった描写の積み重ねやスペック等の諸々を加味して考えていくと、不二や白石が天衣無縫に対応できたのも決して天衣無縫殺しが完全に出来ていたということを意味しません。
不二の光風、そして白石の星の聖書が天衣無縫の極みに通用したのはあくまでも同じ学校の後輩である越前と遠山という勝手知ったる関係だからこそ通用した戦術だと言えます。
越前リョーマも遠山金太郎も中一にして手塚・幸村・跡部クラスに匹敵する才能を持っていますが、それでもやはりテニスの実力や総合力という点ではまだ伸び代があり完成ではないのです。
そんな風にまだまだ隙がある後輩たちだからこそ天衣無縫を使われても冷静に対応できたわけであり、これがドイツ戦の連中と戦った場合はその限りではないでしょう。
現に不二家白石がもしドイツの天衣無縫3という究極レベルまで行ったQ・Pや至高のゾーンを使える手塚と戦ったらその戦法はとても通用するようには見えないのです。
だから越前の「俺、不二先輩に勝ったことないんすけど」という指摘は言い得て妙であり、強敵との対戦経験が圧倒的に足りない不二と白石ではまだまだ手塚・幸村らのステージには及ばないでしょう。
特に白石なんてダブルスとはいえ木手・丸井コンビにそこそこ苦戦していましたから、手塚のように相手を完璧に圧倒して勝てるほどの強さはまだないということです。
不二にしても「風の攻撃技」を編み出してはいますが、まだ強敵との対戦経験が少なく、戦った相手もダブルスのみでシングルスで世界を相手に戦った経験はありません。
やはり「テニスの王子様」で物を言うのは才能もそうですが、何より「強敵の対戦経験」と「圧倒的な差をもがきながら詰めていこうという諦めない心」が土壇場で物を言います。
おそらく不二と白石がそれぞれ越前と遠山に負けたのは「後輩に道を譲った」という身内の情も多少なりありますが、それ以上に踏んできた場数の違いだったのではないでしょうか。
越前も遠山も幸村精市という大きな壁にぶち当たったり、新テニでもそれぞれ徳川と鬼に挑んで敗北を喫するところから始まり、同じ負け組として泥水を啜ってきました。
そこから這い上がってきた経験は必ず大きな自信となって2人の中に宿り、それが世界を相手にしてもなお臆さずに戦える覚悟へと繋がったのではないでしょうか。
特に越前は関東大会の真田戦以降は基本的にそんな戦いばかりで、真田戦・跡部戦・幸村戦・シャルダール戦と強敵との戦いは全てそうやって勝ちを収めています。
越前が勝つのは決して主人公補正でも何でもなく、手塚や徳川との戦いの末の敗北によって「圧倒的な力の差をもがきながらもどう詰めて勝つのか?」という経験を積んできたからです。
だから天衣無縫を用いて不二に3-5のマッチポイントで追い詰められながらも、そこから土壇場での馬力を見せてカウンターを全て返して盛り返してギリギリの差で勝ちを得ました。
不二の光風に天衣無縫が破られたからと諦めたり意固地になったりするのではなく、1ポイントずつ地道に返して追いつくという窮地を越前は何度も経験しています。
特にそれがよく出ていたフランス戦では光る打球までもカウンターされ一度は滅んだはずなのに、またそこから蘇って盛り返し差を詰めてスーパースイートスポットの先を見極めました。
圧倒的な力で勝つ経験よりも圧倒的な力の差を詰めながら接戦の末に勝つ方がステータスアップにも繋がるわけであり、その経験の積み重ねが不二との再戦の中でも生きたのでしょう。
そしてそれはお頭が徳川と並んで越前に日本を託した理由にもなっており、越前のことを「中学生(ガキ)の分際でもう覚悟を背負っている」と高く評価していたのです。
ただ、そんな越前を己の才能1つでそこまで苦しめて壁として立ちはだかった不二、そして同じようなことを遠山にした白石も十分に凄いとは思います。
越前と遠山に必要なのが「天衣無縫に依存せずテニスの実力を引き上げ才能と向き合うこと」ならば、不二と白石は逆に「強敵との対戦と土壇場での精神力・胆力を養うこと」が課題でしょう。
天衣無縫を対策できたから凄いのではなく、天衣無縫攻略を通して後輩たちに必要な課題を示唆するという先輩ならではの威厳を示せたのがあの試合の意義だったと私は思います。
だから天衣無縫の極みは到達点ではなくあくまでも「手段の1つ」であり、越前も遠山もそれに気付いた上で有効活用しつつ次の進化・覚醒をしていくことが必要でしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
