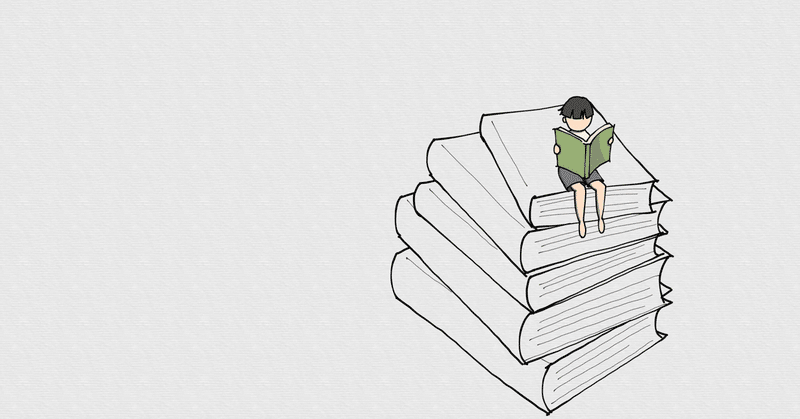
立川ひろき
僕の朝は太陽の光で始まる。
忌々しいこの光は僕に無理やり朝を始めさせる。
目覚まし時計は要らない。
ただ、カーテンを取り払った窓から差し込む光が僕を目覚めさせるのに充分な効果を持っている事に気がついたのは目覚まし時計がお母さんを壊す事を知っていたからだった。
目覚まし時計を使えば、鳴った瞬間に目覚めなければならない。
そうでなければ、お母さんは大きな足音を立てながら僕の部屋に入ってくるなり
「いつまで寝てるの!!」と叫び声を上げさせるのだ。
目覚まし時計は良くない。
これは僕が小学校に通い始めてから最初に学んだ事だった。
起きたら、すぐにトイレを済ませて洗面所で身嗜みを整える。
寝癖を治して、顔を洗って歯を磨く。
眠たげで怠そうな表情は勿論、寝癖も絶対にダメだ。
それもお母さんを壊す。
「なんでアンタ達はいつもだらしないの!!」
きっとアンタ『達』の中見はお父さんの事だ。
もう何年も会っていないお母さんの天敵。
なんで離婚をしたのか、そもそもなんで僕が生まれたのか、あの二人の間にあった事を僕は知らない。
不思議と一緒にいて、僕が生まれて、自然と別々になって、僕はお母さんに引き取られた。
僕が生活するには、それ以上の情報は不要だったし、詮索もお母さんを壊すからタブーだと思っている。
朝ご飯はいつもお母さんが用意している。
無言で用意を続けているお母さんに「お早う」と声を掛ける。
機嫌が良ければボソボソ声だけど、返事をしてくれる。
出来るだけ早く朝ご飯を胃に詰めて、足早に家を出る。
いつも、僕が学校に一番乗りをして、そこで本を読んでいる時間が僕にとっては静かで安らぎのある時間だった。
他の子達がやってくると、段々、教室がザワザワしてくる。
まるで動物の鳴き声みたいな声が教室中を埋め尽くして、頭が痛くなるが、これでもうすぐ学校の時間割が始まる一歩手前のサインだ。
学校が始まれば、時間は勝手に過ぎていく。
退屈な授業には怒鳴り声もなければ、動物の雄叫びもない。
時々、悪ふざけをしてくだらない笑い声が教室を支配して、先生の叱責の声で消え失せる。
それくらい。
学校の時間は退屈だけど平和だった。休み時間という狂乱の時間を除けば。
僕は誰とも関わらない。
友達の存在もお母さんを壊すから。
僕がどんな子と仲良くしているって情報が入れば、お母さんは色々調べて悪い噂を拾ってきては僕に言い聞かせる。
お母さんは「友達はちゃんと選んでね」っていうけど、僕には『余計な心配をかけないでね』っていう意味だとちゃんと分かってる。
だから、誰とも付き合わない。
これは学校に入ってから学んだ2つ目の大切な事だった。
学校の勉強は簡単だったし、そうでなければならなかった。
僕が勉強が分からない素振りを見せれば、それもお母さんを壊すから。
常にちゃんと分かっておく。それ以外はダメ。
そう思えば、勉強は簡単だったし、そうする他に選択肢もない。
学校が終わってからは図書室で本を読んだ。
図書室には色んな本があって、何よりも静かで古い紙の匂いが溜まっている感じが大好きだった。
時々、司書の先生と本の話をするのが堪らなく好きだったけど、それは誰にも内緒だったし、控えめにした。
きっと、お母さんは先生の悪い噂もきっと見つけてきてしまうから。
冬の朝は忙しかった。
二学期に入る頃には僕が自分で起きられるアピールを続けたお陰でお母さんの怒鳴り声を朝に聞く必要は無くなったけど、太陽が昇る時間が遅い分、支度の時間が短くなるし、お母さんは用意した朝ご飯が冷える事を嫌う。
三学期の手前頃には太陽の光なんてなくても朝、起き上がるべきタイミングは自分で見計らえるようになった。その反面、眠っているのか、起きているのか分からない感覚が一晩中続く時もあったけど、一日が無事に始まる為には仕方がなかった。
この頃からお母さんは朝ご飯を作ってくれない日も時々出てきた。
僕の起きる時間が安定しなかったから、お母さんの機嫌を損ねたのかも知れない。
そういう日は精一杯元気に「いってきます!」の声を出して学校に向かった。
ある日、学校から帰ると、お母さんは壊れていた。
もう暗くなった夕暮れの家で、お母さんはお母さんだった形に変わっていた。
寒い外から家に入っても、変わらない寒さ。
消えている電気。
動かないお母さん。
お母さんには触らなかったけど、きっとお母さんも家の中と同じ温度になっていたんだと思う。まるで、温かさの基準では、もうそこに居ないみたいに。
感情が何も湧いてこなくて、救急車を呼んだ。
「立川ひろきです。救急です。家に戻ったら、お母さんの意識がなくなっていて。はい。息もしていません」
『心臓の音はしますか?』救急隊員の言葉で初めてお母さんに触った。
硬いような少しフニャっとするような独特の質感のお母さんの腕を触った。
温度らしきモノは何も感じない。温かくも冷たくもない。
「死んでます」今、思い返せば変な受け答えだった。
暫くして救急車がやってきて、お母さんの体を連れていった。
救急隊員の人は親戚の人はいないか、とか、なんとか僕に色々聞いた。
僕はお母さんのスマートフォンを、救急隊員の人に渡した。
救急隊員の人はスマートフォンのロックを解除したのか、それ以外の方法だったのか、夜中にお父さんがウチに来た。
ダブダブのスーツで髪の毛はボサボサ、泣いてきたのか、目元が浮腫んだお父さん。
久しぶりのお父さん。
なんだか、知らないおじさんのような気もするし、凄く待ち焦がれていたヒーローのような気もした。
お父さんは何にも言わずに僕を抱きしめてから、「ごめんな」って言った。
その後も泣きながら、ずっと「ごめんな、ごめんな」って言い続けた。
僕は、その声を聞きながら眠りに落ちた。
次の日、目が覚めると、いつも通りの時間で、いつものベッドに居た。
トイレを済ませて、洗面所で身嗜みを整えた。
ダイニングでは昨日の格好のお父さんが眠っているのか、起きているのか分からない雰囲気で床に座り込んでいた。
お母さんとは違ったタイプの壊れた大人の姿だった。
間の抜けた大人の空気感。
お父さんは僕に気がつくと「ひろき、お早う」と言って、僕に微笑みかけながら、鞄の中から少しひしゃげたコンビニの菓子パンを取り出して「食べるか?」って聞いた。
僕は、その菓子パンを普段の朝ご飯より少しゆっくり、無言で食べた。
学校を休んでもいいって言うお父さんに「大丈夫」だと言って、僕はいつも通り学校へ向かった。
いつも通り、本を読んで、周りのザワザワが広がっていく。そして、先生が入ってきて、朝の会が始まる。
「立川くんのお母さんが亡くなられました」先生はいつもの形式の「お早うございます」の後、そういった。
教室がザワっとなった後、少し離れた席の男の子が手を挙げて
「立川くんはかわいそうだと思います!」と真顔で先生を見つめて発言した。
この時、僕の中で何かが弾けた。
彼の行動の意味の分からなさ…いや、本当は分かる、何か言いたいから言う、という子供っぽさ、『自分は優しいのだ』と言うポーズを莫迦真面目に実行する白々しさ、何もかも。
全てが衝動に変わって、僕は彼に掴み掛かった。
少し揉み合った後、僕は机に押さえつけられ、頭の後を拳骨で打たれた。何回か、打たれた後に、先生が止めに入って、彼が僕から離れていきながら「オマエ、ふざけんな!」とか怒鳴っているのが聞こえた。
心の中で彼の化けの皮が剥がれた事への安堵と、痛みと悔しさで涙が止まらなくなった。
先生が家まで車で送ってくれた。
お父さんは何も言わずに先生に頭を下げて、僕の手を握った。
僕は学校に行かなくなった。
今度はお父さんと二人でお母さんと暮らしていた家で暮らす事になった。
僕は部屋から出なかったし、お父さんも時々出掛ける程度で、殆ど家に居た。
静かだった。
随分と時が経って、SNSでは同世代が就職やら結婚やらの話題で盛り上がっている頃、お父さんは帰ってこなくなった。
いつの間にか気配が消えて、知らない番号から連絡が来た時、お父さんは壊れていた。
お父さんもお母さんと同じように「だった形」になった。
今、僕は家に一人。
もうすぐ、僕も「だった形」になる。
僕の家族はなんだったのだろう。
僕は何も知らない。
お母さんの事も、お父さんの事も、二人の事も。
僕自身の物語も殆ど無い。
何も無い。
お母さんが居なくなった時も、お父さんが居なくなった今も、理由も、僕自身の感情も何も分からない。
ただ、お母さんが居て、お父さんが居て、消えて。
何も分からない。
ただ何も分からないまま、僕は居て、それから消えていく。
何も分からない。
ただただ、何も分からない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
