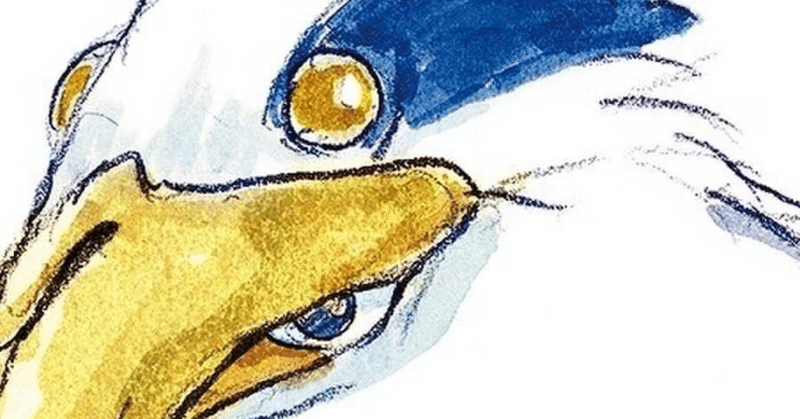
解題:「君たちはどう生きるか」が描いた若者たちに向けた願いとは
宮崎駿監督が2013年公開の「風立ちぬ」をもって長編映画作品からの引退を表明した時、それまでの一連の作品とはまったく異なる大人向けの内容から、その決断に対して大いに納得したし、同作も氏の最高傑作と呼べる出来映えだったと思っていた。当時の作品のキャッチコピーは「生きねば。」であり、これは劇中では主人公・堀越二郎の妻、菜穂子が夫に対して言う「生きて」という言葉に対応したものだし、作品としての「風立ちぬ」の大テーマでもあった。ただ、多くの観客が、この作品の背景が第2次大戦期の日本であり、二郎の取り組んでいるプロジェクトが戦闘機の開発でもあったため、それゆえに作品のテーマを「戦争に勝つための新しい戦闘機を創り出すために途中で死なないで生き延びて完成させてくださいね」といった意味に勘違いしてしまうという事態を招いていた。
戦闘機の開発は確かに二郎の生涯のテーマでもあったが、それは「優秀な航空機を創る」というものであって、「兵器開発」が主眼でもないし、ましてや「戦争に勝つために強い兵器を創る」というものでもない。だからこそ、劇中では二郎の夢想としてイタリアの航空機設計者カプローニ伯爵が度々登場し、飛行機開発の夢を語り合う場面が出てくる。その二郎の生き様は、単に社会の歯車として何も考えずに働く人間ではなく、世界や社会に、そして何よりも自身の人生に対して意味のある、中身のある「生き方」なのであって、たとえるなら黒澤明監督の「生きる」と同じ意味合いなのだ。
そもそもタイトルの「風立ちぬ」という言葉が、フランスの詩人ポール・ヴァレリーの代表作「海辺の墓地」からの引用で、「風が吹いた、さあ生きてみようじゃないか」という詩を作家の堀辰雄が「風立ちぬ、いざ生きめやも」と訳して自作のタイトルにも使ったわけで、宮崎さんの「風立ちぬ」では、だから堀辰雄への敬意も表されている。物語としては他に堀辰雄の「菜穂子」からの引用もあり、またトーマス・マンの「魔の山」も、病気になった人間はただ生きているだけの「ボディ」でしかなくなるといったモチーフも巧みに取り入れられている。そしてヴァレリーの「海辺の墓地」からも「アキレスと亀」や「鳩が動き回る尾根」という描写が実際には海を渡る三角帆を掲げた小舟やさざ波を表しているように、空を往く零戦の編隊がやがて青空で白い鳥の群れとなる形での引用がなされていた。
結局は、この「意味のある、中身のある人生を生きよう」というメッセージは観客には伝わらなかった上に、戦闘機という兵器のイメージが強すぎたためなのだろうが、「戦争を肯定している」という印象を持った人までいた。この作品は宮崎駿という、それまで子供たちを対象にしながらも大人の鑑賞にも堪えうる作品を作り続けてきた映像作家が、はじめて大人たちに向けた「大人の寓話」を作ってキャリアを締めくくろうとしたものだった。かつて黒澤明監督から「あなたは実写映画を撮るべきだ」と言わしめ、逆に「黒澤さんこそアニメを作るべきだ」と語った宮崎さんの、だからこれは本当に「集大成」とも呼べるものだったんだけれど、悲しいことに過去のジブリ作品との表面的な比較ばかりがなされて、ファンからはそっぽを向かれた作品でもあった。
それまでにも何度か引退発言を宮崎さんは繰り返していたが、それでも引退という判断は今度こそは変わりそうもないように思われた。
だが宮崎さんはさらなる新作を作り始めた。その理由について、ある程度の説明をジブリ側からなされているが、恐らく本質的なこと、翻意の詳細は今後も語られることはないのではないかと思う。
個人的には2016年に公開された「この世界の片隅に」が何らかの影響を与えているのではないかと思っている。こちらも第2次大戦時を一人の女性の半生を通じて描いており、戦争の描写は間接的なものが多かったが、それでも広島への原爆投下が物語上の大きな出来事として扱われていて、最終的には反戦の祈りというメッセージが観客に深く突き刺さるような形に仕上がっていた。この素晴らしい作品が世に出たことは喜ばしかったが、宮崎さんがこうした形ではないにせよ、もっと明確に「反戦」を打ち出した作品を作っていたら、それはそれで素晴らしい作品となったに違いない、と思っていた。だからその後宮崎さんが新作を作り始めたと聞いた時には、その内容はさっぱり見当が付かなかったけど、タイトルが「君たちはどう生きるか」と発表された時には、「これは紛れもなく反戦メッセージの映画になるに違いない」と確信したものだった。なので、唯一の宣伝用ポスターが「謎の鳥の絵」だった時には少々面食らったものの、それでも何らかの形で反戦の思いを「君たち」、つまり「若者たち」に伝えるような内容になると思っていたし、結局のところ、それはまったくその通りだった。
というわけで、「君たちはどう生きるか」は正に空襲警報から始まる。時代は1944年。太平洋戦争が始まってから3年後の出来事となる。東京大空襲が開始されたのは同年の11月24日からだが、これだと物語的にはいろいろと計算が合わなくなるので、この辺は深く考えなくていいところだと思う。むしろここで注目すべきは、爆撃を行った米軍の姿を一切描写していない点だ。もしここで爆撃機の姿や飛行音、爆弾が投下される音などが描かれていたら、その後に起きる主人公である眞人の「母親の死」の責任は米軍に直結することになる。だが本作は日本対米国の戦いがテーマではなく、太平洋戦争中の日本を背景とした「反戦」を描くのが主眼のはずなので、だからこの場面では空襲の結果として発生した「火事」が「母親の死」に直結することとして描かれたのである。
母が入院する病院が燃えていることを知った眞人は現場に駆けつけようと急ぐが、もちろん彼は間に合わないし、母は焼け死んでしまう。そしてこの出来事によって眞人は「母の死」に対する「責任」を感じ、母を「救えなかった」ことで自分を責めるようになる。彼自身の表情からはそのことを読み取ることは難しいが、彼の言動からこうした子供の感情は読み取ることができる。
翌年、眞人は父親に連れられて疎開する。そこで待っていたのは父、勝一の再婚相手であり、亡き母の実妹であるナツコだった。ナツコがすでに勝一の子を身ごもっていることも含め、眞人は平静を装いながらショックを押し隠そうとしている。
この場面で眞人が理屈では父親の再婚やナツコが継母になること、そして実母が死亡したことを理解していることがわかるが、こうした状況の変化を「受け入れることができていない」ことが重要だと思う。眞人は後に人として、そして家族としての責任感から、消失したナツコの行方を追うことになるが、その時点でも眞人はナツコを「新しい母親」としては真に受け入れることができていない。一方のナツコはすでに眞人の弟か妹となる赤子を身ごもっていることもあり、眞人の「母親」となること、そして「死んだ姉の代わり」を務めることを心に決めているが、眞人が親戚以上、家族未満の距離を保ち続けていることでストレスを感じている。こうしたキャラクターの心情はセリフでは語られないし、表情でもごくわずかにしかヒントが与えられていないので、非常に分かりにくい印象を与えるが、注意深く見ていれば分かる程度のものなので、これを「分かりにくい」として非難するのは見当違いだと思う。実際の社会でも、日本人は特に自分の心の奥底に根差した感情はひた隠しにするものだが、本作での眞人、ナツコは、こうした「隠された感情」を秘めながら描かれていく。
新しい自室で一人になった眞人は疲れ果てた様子でベッドに横たわり、そして夢を見る。母・久子が死んだ時の様子だ。燃えさかる炎の中、「おかあさん!」と叫びながら眞人は前へ進もうとする。だが久子は笑みを浮かべながら「眞人、さようなら!」と明るく声をかけ、そして消えていく…
この夢のシークエンスの意味は映画の終盤における眞人と(久子の少女時代である)ヒミとの会話に至って氷解する。久子はその人生における最大の喜びを「眞人の出産」として位置付けていた。映画の中盤から主要舞台となる異世界で、久子は同年代の眞人と出会い、その真っすぐな生き方に感銘を受け、そんな子供を後に自分が産むことに最大限の喜びを見出していた。眞人は自分と同じ時間軸の世界に行こう、とヒミを誘う。それは死んだはずの母親と、別の形でまた過ごすことができる、という眞人にとっての最後の誘惑だ。だがヒミはその提案を一蹴する。例えその先に焼死という未来が待っていようとも、この目の前にいる眞人という素晴らしい存在を産むという喜びを捨てるなどとは考えられないのである。このヒミとの永遠の別れを経て、眞人は正に「眞(まこと)」の「人(ひと)」として生き始めることになる。この異世界での記憶は実世界へ戻ると消えてしまうそうで、久子へと戻ったヒミもまた異世界での記憶、眞人との邂逅の記憶を失っているはずだが、それでも異世界で得た「眞人の出産」という確信が間違いないものであり、久子の人生が充実したものだったことがわかる。これはヒミ、あるいは久子が人生を「どう生きたか」の結果なのである。
さて、昼間に母の夢を見た眞人は、その夜も母の夢を見る。そこでは一転して母は炎の中で「眞人、助けて」と叫んでいる。そして眞人は「お母さん!お母さん!」と叫び続ける。この2番目の夢は1番目のものとは意味合いが異なる。これは眞人自身の心理状態が夢となっているもので、母は助けを求めていたはずだし、それなので自分は母を救うことができなかった、という無力さが表れていると考えていいと思う。自分が弱かったせいなのか、幼かったせいなのか、その理由は分からないが、結果は「母の死」だ。その無念の矛先を眞人は自分自身に向けている。普通ならば病院火災を引き起こした米軍による空爆が原因となるだろう。だが、そもそも米軍の空爆を引き起こしたのは遡れば日本政府によるアメリカへの奇襲攻撃だった。そしてさらにさかのぼれば両政府による貿易の衝突や、満州事変に対する国際社会からの非難などがあった。だから本作で描かれる「久子の死」の原因を突き詰めていくことは結局は水掛け論にしかならず、だからこそ異世界にいた大伯父は「争いのない世界を作らなければならない」と説くのだ。
さて、母の死に対する責任を感じる眞人の心情は、解決できない問題なので当然ながらコンフリクトを起こす。それは自分に対する怒りだ。眞人は常に自分に対しての怒りを感じることになるのだが、そうした感情は排出されなければならなくなる。だから眞人は転校初日に同級生らとケンカになる。子供たちにとって、未知なる存在は脅威だ。だからまずは攻撃的になる。最初からやさしく受け入れることができるようになるには、人間とはまだ幼すぎるのだ。それは戦争を起こす相手が、常に未知の文化や未知の種族に対してであることからも分かる。だから眞人と同級生とのケンカは、世界における戦争という構造の縮図と見ていいと思う。眞人にしてみれば、怒りの感情の捌け口さえ見つかればよかったわけで、同級生との諍いは、ある意味「渡りに船」のきっかけだったと言えるだろう。この負の感情による結果を眞人は恥じる。そこには母を救えなかった感情も上乗せされたかもしれない。いずれにせよ、眞人は石を自分のこめかみに叩きつけることで自分に罰を与える。この行為は眞人の隠された感情に起因するものだから、眞人は父からの執拗な問いかけにも嘘をつくことしかできない。しかし、この自傷行為がトリガーとなって、眞人の世界は異世界と繋がることになる。
眞人の疎開先の邸宅に出没するアオサギが異世界への導き手となる。それまでは単に「覗き屋のアオサギ」という動物でしかなかったアオサギは、眞人の自傷行為を境に魔物へと変貌する。「眞人、助けて」「お母さん!お母さん!」という眞人の2番目の夢の内容をこのアオサギが知っている点はどう理解すればいいのだろうか。アオサギは大叔父の使い魔ではあるが、眞人自身の持つ「邪悪な心」が形になったものとも考えることができるだろう。この辺の解釈は明確なリードとなる情報がないため、観客の自由の余地が大きい部分だとは思う。ただ、眞人が抱える問題を解決するためには眞人が異世界に向かうことが必要となる。そこに住む大叔父が自分の後継者を求めていた、という背景はひとまず置いておいて、自傷行為以降の眞人が人間的成長をして次なる段階へと変容していくには「冒険」が必要となる。「お前が案内せよ」と命じられたアオサギによって「下の世界」へと降りていく眞人に「御武運を」とアオサギが声をかけるのは、先に待ち受けているのがある種の「闘い」であることを予言するものでもあると思う。
話が前後するが、アオサギは最初に登場してから眞人が自傷行為を行うまでは、あくまでも好奇心の強い動物でしかないが、人間の言葉を喋りはじめてからは、彼は眞人にとっての「未知の敵」となる。眞人はまずは木刀を手にアオサギと対峙し、その後は折り畳みナイフ、手製の弓矢など、次々と武装していく。これは前述したように「未知の者」に対する潜在的恐怖が引き起こす暴力的な反応を描いているわけで、人は自己保全のために他者と戦い、あるいは生存のための食料として武器をもって捕食をする。また、武器を持つことによって誰もが殺戮者となることができるわけで、実際、過去の戦争でも平時は温厚な人物が残虐な殺戮を繰り返すことができるようになる。もっとも有名な例は第2次大戦時におけるユダヤ人に対する大量虐殺だろう。現場の責任者アドルフ・アイヒマンが行った判断は戦後、世界中に衝撃を与えた。ごく普通の役人だった男がどうしてこれほどの行為を行えたのか。アイヒマン自身は「上からの命令に従っただけ」と証言した。彼の裁判を傍聴したハンナ・アーレントは、こうした「どんな罪深い行為も他者が許してくれるならやってしまう」という行為を、人間の誰もが持つ「凡庸な悪」と表現した。実際、その後に行われた「アイヒマンテスト」と呼ばれた実験では、多くの被験者が一定の条件下で非人道的行為を行ってしまうことが証明されている。
そういった意味では異世界に渡った眞人が直面したペリカンやインコが、実世界における「平凡な人々」のメタファーであることが分かる。異世界では熟すことで人間として生まれることができる存在として「ワラワラ」という生き物が登場する。他にエサを見つけられないペリカンたちは、圧倒的に無力な存在であるこの「ワラワラ」を捕食することで命をつないでいる。また、武装したインコたちはナチスドイツのメタファーのようにも描かれており、その歴史的非道な行状もまた、多くの市民の賛同、支持、投票によって支えられていたことが寓話的に描かれている。
「ワラワラ」がペリカンに襲われる場面で初めてヒミが登場し、火を放つことでペリカンを追い払おうとする。だがこの攻撃は同時に近くにいる「ワラワラ」を焼き殺すことにもなる。眞人は「やめろ!ワラワラが焼ける!」といってヒミの行為を止めようとするが、そばにいたキリコは「これで多くのワラワラが助かる」として、多少の犠牲は容認する姿勢を見せている。これもまた戦争における為政者たちの理屈だ。ここでも根本的な解決を目指すことなく、現状のシステムの中で割り切って生きることへの不毛さが描かれているわけだ。
ヒミに焼かれて瀕死の状態になったペリカンと対話した眞人は、力尽きて死んだそのペリカンを埋葬する。それまで他者との関係を眞人は主として「対立」で維持してきた。それはナツコに対してさえも同様だったのだが、ここで眞人は「他者への理解」という新しい段階へと成長を見せている。
そして次に眞人の大きな変化となるのがナツコとの再会だ。実世界でのストレスに疲弊したナツコは異世界での平安さの中で出産をしようと産屋に籠っている。異世界では赤子を身ごもった者は、聖なるものとして安全が保障されており、そこを侵害することは禁忌とされているわけだが、そこを眞人は訪れる。ナツコは愛する夫と愛する姉との間に生まれた眞人を、理屈として「自分の息子」として愛し、守ろうとしてきた。だが眞人自身はナツコを母としては受け入れず、理解しがたいケガを負った上に、その理由も語ろうとはしない。その原因をナツコは当然ながら継母としての自分にあるとして自分を責める。病床に見舞いに来た眞人を見て、「姉に申し訳ない」と泣くのも、その責任を重く受け止めているからだ。だからこそ、自分の赤子を守るための結界の中に眞人自身がやってきたことでナツコの心は一線を越え、眞人が同級生に対して怒りを発散したように、眞人に対して「あんたなんか大嫌い」と叫ぶ。だがこの時点での眞人は実世界にいた頃の眞人ではない。だからそれまで「ナツコさん」と呼んでいた眞人は、混乱の中でナツコをついに「お母さん!」と呼ぶ。そして「ナツコ母さん」とさらに明確に彼女を母として受け入れた言葉で呼びかけたことで、ナツコ自身もまた、2人が真の母子になれたことを悟り、一転して眞人を守ろうとするのである。
異世界で成長した眞人は、だから実世界での人生を恐れなくなり、当初は敵対していたアオサギを「友達」と呼び、一度は食べられそうになったインコたちとともに異世界を脱出し、さらに逃げてきたペリカンたちをも導いてその無事を喜ぶ。それは「未知の敵」が相互理解をすることで「友」となることを意味するわけで、それこそがこの映画の描いてきた「物語」なのだと思う。
この眞人の人生を変えることになる冒険の端緒となったのが、偶然見つけた亡き母からの贈り物だったこともまた重要なポイントだ。そう、吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』だ。この本の存在とその内容は、果たせなかった母との息子との対話であり、息子に対する母の愛情が具現化したものでもある。読み進めていた眞人が涙を流すのは、その本の内容だけでなく、愛する母の子どもへ向けた愛情を実感したからだろう。この直後にナツコの消失を知った眞人が、進んでナツコの捜索に乗り出したことは、すでに眞人には変化が起き始めていることの証である。
この「行き詰っていた自分の人生を切り開いてくれた本」という存在は、誰の人生においても起こりうるものだし、それは書籍に限らず「映画」でもありうるし、多くの映像作家は、何らかの形で観客の人生に「良い影響を与えることができたら…」という願いを持っているものだ。だから映画の最後で、疎開先を去る眞人が、そこで発見した母からの贈り物である『君たちはどう生きるか』をカバンにしまって旅立っていくことには、宮崎駿監督の映画作家としての願いと希望が込められていると思う。だがそれは「こうしなさい」というものではなく、あくまでも『君たちはどう生きるか』という問いかけになっていることに優しさがあることを見過ごしてはいけないと思う。
前作「風立ちぬ」に対する無理解といった現実世界でのこれまでの経過や、本作の劇中での大人たちが、結局は社会の歯車にしかなっていないこと、生まれるまでは何もできない「ワラワラ」たちと、その対となる7人の老婆たちという存在が、知恵と知識で見守ることしかできないことからも、タイトルにある「君たち」が眞人と同世代の子どもたちに向けられたものであることは明白だ。そして本作における様々な描写が、彼らには理解不能であることも間違いないだろう。だが人生の厳しさと優しさを併せ持ったこの物語の記憶が、子供たちが成長するにつれて徐々に理解が深まっていくであろうこともまた、必然の流れだと思う。そして世界が真に「争いのない優しい世界」へと向かっていくことで、エンドに流れる「地球儀」という歌が訴えかけてくる願いも理解できるようになるのだと思う。
劇中に登場する7人の老婆と「下の世界」にいるワラワラは対となる存在で、どちらも世界に影響を与えるには無力だ。だからその造形は非常に近似していて、違いは年輪による皺くらいでとにかく「丸い」。とはいえ老婆たちに代表される高齢者らは、彼らより年少である者たちの守護者的役割を果たすことで、その存在価値を示している。老人は眞人に刃物の研ぎ方を教え、老婆らは勝一に塔の歴史を伝える。また、彼らが日常の些事全般を担うことで、若い世代がそれ以外のことに注力できる余裕を与えることになる。リラダンは戯曲「アクセル」で、主人公に「生活?そんなことは召使たちにやらせておけ」という有名な台詞を言わせたが、生活のために働いて日銭を稼いだり、いわゆる生活全般に神経を割いていては何もできないわけで、本作では眞人の家庭を裕福に描くことで、まずはその「生活要素」を排除している。
そして一般的な「大人」を眞人の父、勝一に代表させ、戦時に兵器開発で財をなし、敵国人の死に無関心な様子を描くことで、多くの大人が「なにも考えることなく、社会の歯車となって生きている」ということをしめしている。
一方、「考える大人」とはなんぞや、という答えとして、塔に住む大叔父がいる。学問を極めることで周囲から浮いた存在となり、「頭がおかしくなった」と見做される人だ。
どちらも大人たちに見られる類型ではあるが、前者はもちろんのこと、後者も「世界をよりよくする存在」となるには手遅れである。だからこそ、世界の未来は「眞人」の選択にかかってくるわけで、「まことの人」である眞人が選ぶ選択が「共生」であることが一つの答えとして示される。それは相手の糞尿にまみれるような結果になろうとも、哲学的には清らかなものとなる。これが本作が描いた一つのメッセージで、その上でまだ大人ではない若者たちに投げかけた次なるメッセージこそがタイトルとなった「君たちはどう生きるか」なのだと思うのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
