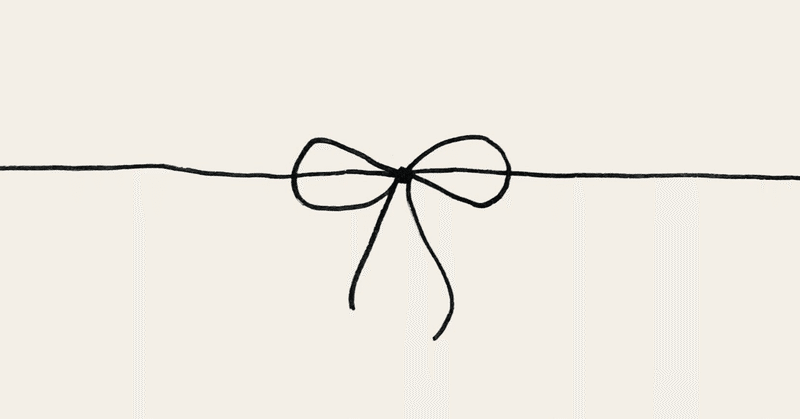
絶景 ①
※2024年3月13日 セリフ等一部加筆修正
厨房に戻ってきた途端、盛大に紀乃はため息をついた。仕方ねえ、諦めろ、と竹瑠は一蹴する。そのやり取りに、刑部は眉をひそめた。
「どうした、何があった」
「さっき、馬場さんに……」
紀乃の話をかいつまむと、今日の客への配膳については、馬場がやるので紀乃は厨房か自室で籠っているようにと言われたという。突然の申し入れに、当然紀乃は困惑した。竹瑠の方も嚙みついたが、馬場が譲らないので結局紀乃が引き下がったという。
「それはまた……」
あらかさまにがっくりしている紀乃を見て、刑部は気の毒に、と思った。慣れない時代で四苦八苦する中、紀乃はよく頑張っている、と刑部は評価している。何せ紀乃がいたのは二十一世紀、ものあふれの時代である。それがある日、妙な男の手によって、明治時代へ転移する羽目になった。
紀乃に憑いていた刑部自身もそれに巻き込まれた形だが、魂だけなので気楽だ。だが、生身の人間である紀乃は転移した先で生活のめたどを立てなくてはならない。たまたま転移先がここ、菱野屋という名前の旅館であったがため、住み込みで働くという条件でひとまず生活の拠点を得た。
そういう経緯を差し引きしても、紀乃の働きぶりは真面目であった。少なくとも、首だと言われるようなドジは踏んでいない。旅館で働くという点にかけて、刑部もさして助けらしいことはできない中、追い回しの仕事を務めている。
「馬場殿は何と」
「わかんないです、本当に突然そう言われて」
「……まあ、そういうこともあるじゃろ。今はお前の仕事をするしかあるまいよ」
「そうそう、配膳するなと言われただけなんだからな」
しかし何か事情があるのか、と刑部は訝しんだ。おそらく竹瑠のほうも同じことを思っており、いきなりひどいよな、と紀乃を励ましている。口は悪いが面倒見のいい兄貴分である。二人で慰めていたら紀乃の方も少しは気が晴れたのか、奇妙な形の野菜を二人に見せつけてけらけら笑うようになった。
その様子を見て、さて探りに行こうかのう、と考えていた時だった。カラン、と大きな鈴の音が鳴った。客が来たことを知らせる鐘だ。竹瑠は髪を縛りなおしながら、紀乃に野菜を洗うよう指示をした。刑部にも、見守り頼むよ、といって出て行った。まあ、竹瑠殿が直接客を見に行くなら、わしが行くまでもあるまい。そう考えて、厨房と紀乃の見守りに専念することにした。
菱野屋では泊まりに来た客へ直接、何が食べたいか聞きまわる。その役目は当然、板前が担う。これは竹瑠の前任どころか、二代前の菱野屋当主からの習わしだという。
客が望むものをなるたけ出す。未知の料理ならどんな料理か細かく聞くし、調達自体が困難な食材でも、代替品を探して極力希望に沿うようにする。きらびやかに献立をいくつも並べるより、菱野屋のやり方の方が客の心に残りそうだ。
千客万来というような繁盛具合ではないが、絶えず客はやってくる。それも、前に来たことがある、という客が少なくない。人によっては前の代から、というから、かなり愛されている旅館といえよう。
「よっぽど、怒らせたらまずいお客さんなんですかねえ」
芋を洗いながら、紀乃が再度ため息をついた。とはいえ紀乃なりに、前向きに考えることにしたといえる。そうさなあ、ここは色んな人が来るでなあ、と刑部は答えながら、紀乃が外された理由を考えた。なるほど、粗相があったらまずい客、となれば腑に落ちるところである。いくら頑張ってると言っても、紀乃は菱野屋で働きだして一か月。現代でも、研修中とか、若葉バッジを掲げていている期間だろう。そんな新人に、大事な客の接待は――――――想像しただけでぞっとする。よほど相手が寛容なら経験としてさせるかもしれないが、そうではないならなるべく避けるだろう。
だが予約で来たならそれはそれでもう少し前に言われてもよさそうだが。腑に落ちないながら、怒らせてはいけない客の風体に関してあれこれ話した。
「あ、これギョウジャニンニクですね。山だから生えてるのかな」
野菜を洗いながら紀乃は明るい声を出した。その様子に安堵しながら、珍しいのう、と返事をする。紀乃が洗っているギョウジャニンニクは、刑部にとってはむしろ、『紀乃の伯父が時々送ってくる野菜』という認識である。北海道では身近な野菜らしく、大体三~五束くらいを仕送りで送られてくるのが、もはや風物詩となっていた。
「現代なら餃子、と言いたいところじゃが、おひたしか天ぷらがいいところじゃろうな」
「そうなんですよねえ~。餃子っていつからあるんだろう」
紀乃の祖母はとどいたギョウジャニンニクを、真っ先に餃子の材料として使う。これもまた風物詩である。細かく刻んで調味料と一緒にひき肉と合わせ、皮に包んでこんがり焼く。話してたら食べたくなっちゃった、と笑いながら、紀乃はふきんで水けをとってざるにいれた。
そして話していると、すさまじい形相で竹瑠が返ってきた。それにぎょっとしている間に、ふう、と息をつくとああくそが、と低い声でうなった。あまりの形相に、何があった、と聞くのを一瞬躊躇われた。躊躇っている間に、竹瑠は地団太を踏みながらくそったれ、あの胡麻塩野郎、と痛罵する。罵倒表現からすると、今日の客は中年男らしい。とはいえそれだけ分かったところでどうにもならない。そのうち何かにあたりやしないかとひやひやしたところで、竹瑠は我に返った。
「ごめん、すげーむかつくこと言われたから暴れちまった」
「……物や人に当たらんところは立派じゃが、いきなり怒るから驚いたぞ」
紀乃の方は完全に驚いて、目を白黒させて固まっている。手に力を込めてぽん、と背中を軽くたたくと、はっと我に返ったようだ。お茶いりますか、とおずおずと竹瑠に尋ねる。ああ、頼む、と竹瑠は返事をすると、木椅子を寄せて座り込んだ。
「あー、本当に腹が立つ。客じゃなかったらぶん殴ってたな」
相当腹に据えかねることを言われたらしいが、いったい何を言われたのか。こんな若い板前じゃ不安だとでも言われたかえ、と尋ねてみる。返事をする前に竹瑠は、紀乃が差し出した湯呑をひったくるように奪い、一気に飲み干した。
「それくらいじゃあここまで怒らないさ、ガキじゃあるまいし」
そういうと紀乃に湯のみを突き出し、お代わりくれ、熱々で、と注文した。そしてため息をついて、「旅館はおとなしく、懐石でも出せばいい。別に飯を楽しみに来ているわけではないのだから」だとさ、と吐き捨てた。セリフの部分は物まねのつもりか、気取った口調だったが、いかんせん件の客と顔を合わせていないので、似てるかどうか判断ができない。
「えー、意味わかんないお客さんですね、その人。旅の楽しみの一つじゃないですか、美味しいごはんって」
紀乃は呆れかえった声で話に入り、湯のみを竹瑠に差し出した。そして自分も湯呑を持ちながら、木椅子に座る。意味わかんない、は言い過ぎとしても、相当偏屈そうじゃな、と刑部は竹瑠の様子から察した。もしかすると、今回馬場の突然の申し入れも、そこに起因するのではないか。旅館に寄合のようなものがあるかは知らないが、どこかでこの客は要注意、と現代で言うところのブラックリストのような注意がなされている可能性はある。
「まあ、及第点の飯を大人しく出せってことなんだろうけどなあ、一言余計なんだよ。胡麻塩頭の癖に若え嫁さんもらっていい気になってんのか知らねえけど」
中年男と若妻か。刑部は頭の片隅に入れた。妻の方は何も言わなかったのか、と探りを入れてみる。竹瑠曰く、嫁さんの方はおとなしく座ってたよ、とのことであった。ただし、茶を淹れようともせず、ぼんやり座ってるだけであったらしい。少し変わってるな、と思うが、それだけでは何とも言い難い。
「あー、いますよね、なんか奥さんの前で調子乗る、痛い人」
「誠実な態度とってる方がよほど男らしいんだけどなあ」
妙なところで二十一世紀生まれと明治生まれで話がかみ合ったな、と刑部は不思議な気分だった。とりあえず、これ以上探りを入れたところで有益な話は出てこなさそうだ。して献立はどうする、と竹瑠に聞くと、ほころんでいた顔が真顔になり、やがて赤色に変化した。しまった、まだ早かったか。
「あ――――まじでむかつく、どうしてやろうか」
献立が決まらないとまかないも決まらないんだよなあ、と竹瑠は天を仰ぎ、頭をかいた。しばらくそのままだったが、何か思いついた顔になり、立ち上がった。ひらめきが舞い降りたか。見守っていると、ざるに入れていたギョウジャニンニクをつかみ、まな板の上に置いた。そしてそれを細かく刻んでいく。刻み終わったそれを大きく深い器に放り込むと、今度は氷室を開けた。その中にはへぎ板にくるまれた肉が入っている。塊肉をこれまた細かく刻んでいく竹瑠を見て、まさか、と紀乃と思わず顔を見合わせた。
竹瑠は、途中で思い出したように、帳面に何かを走り書きして、紀乃に手渡した。そして脇道にある萃香楼という中華料理屋に行ってこれをもらって来いという。菱野屋の板前の使いだ、と言えばわかるから、と。そう言って肉を細かく刻む作業に竹瑠は没頭した。どうやらまさかが当たったらしい。懐石でも出せと言ってきた相手に中華を出すのはどうなんだ、と思うが、むしろ竹瑠なりの意趣返しなのだろう。
二人で使いに出るか、と厨房を出た。まあ、竹瑠なら心配はいらないだろう。魂だけの身体ゆえに彼の料理を賞味したことはないが、少なくとも客が料理に文句をつけているのを見たことがない。仕出し弁当の仕事をしているのも、それだけ菱野屋の料理はうまいと評判が高いからだろう。
目当ての萃香楼は、菱野屋を出て、すぐにある小道へ進んだところにあった。小さな構えだが、繁盛しているようでにぎやかな声が聞こえてくる。いい匂いですねえ、と紀乃が目を細めて言うので、多分油や香辛料の香ばしい匂いが漂っているらしい。店の戸を開けて、近くに立っていた店員に竹瑠の走り書きと、菱野屋の使いであることを伝えた。店員はちょっと待ってね、とややなまりのある言い方で返事をして、奥に引っ込んだ。代わるように髭面に辮髪の男がやってきた。かごに物が入っているらしく、いっぱいあげるヨ、余ったら色々包むヨロシ、と見た目とは裏腹の高い声で応対する。ありがとうございます、と紀乃が頭を下げて礼を言うと、板前さんにヨロシクネ、と手を振った。
「しかしもうこの時代にあるとはなあ」
竹瑠が頼んだのは、餃子――――――この時代においては、元の国での発音に倣ってチャオズと呼ぶらしい、の皮であった。紙袋の中におそらく百枚分、もしかするとそれ以上入っている。あの塊肉をどのくらい使うつもりなのかはわからないが、結構な量ができそうだ。
「竹瑠さん、大丈夫ですかねえ……」
あのお肉、結構硬そうでしたけど、と餃子がうまくできるかどうかを心配したらしい。確かにおばば様も最初からひき肉を使うからなあ、と手順を思い出した。とはいえ細かく切って刻んでいたきのを見ると、竹瑠もそれは承知の上でやっているように見えた。
「なあに、竹瑠殿なら無敵よ。腕前は紀乃が一番知ってるじゃろ」
ぽんぽんと背中をたたくような動作をして、紀乃を励ました。まずい料理を食わすという嫌がらせは、きっと竹瑠はしない。それは己自身も、菱野屋の看板も傷をつけることだ。萃香楼の店主と顔見知りのようだし、きっと料理の研鑽のため、あれこれ聞きまわったのだろう。食材自体は普通だし、これで竹瑠の気が違えなければ偏屈な客に掌返しもできるはずだ。
(*‘∀‘)いただいたサポートは有効に活用いたします!
