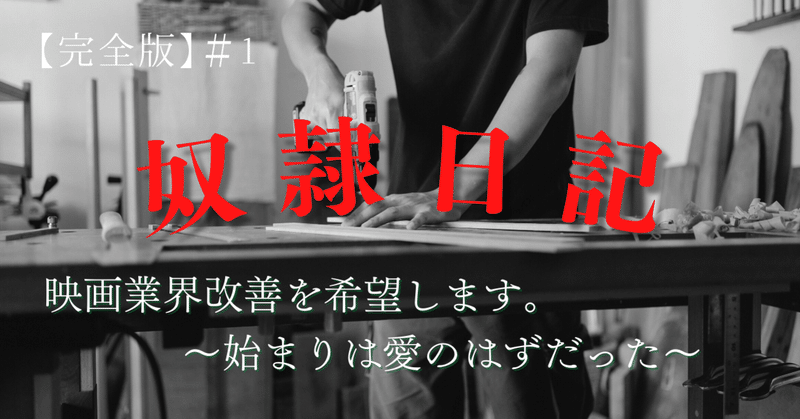
映画業界 ハラスメント体験記【奴隷日記#1】
アキさんと出会った2019年春
私がアキさんと親しい間柄になったのは、2019年春のこと。我々は当時、大学3年生だった。それまでは、単なる大学の先生という認識くらいで、ほとんど話したこともなかった。
当時の授業内課題で制作することになっていた、映画『濡れたカナリヤたち』において、ラブホテルのセットを作ろうと画策し、アドバイスを求めに行った事から、交流は始まった。セットを作らないかと私に提案したツイマ君、そして美術志望のJ太郎、私の三人で学内スタジオに赴いたのが始まりだ。以下、予告編にはなるがセットの映像がはっきりと映っているので参考までに。
そもそも、この『濡れたカナリヤたち』を企画しているときに、ツイマ君に飲みに誘われ、「面白そうだから、自分も参加したい」と言われたのが発端だ。それまでほとんど挨拶しか交わしたことのない我々が、たった一度の飲みの席で意気投合し、関係が始まった。そのときに出た「セットを作りたい」という私の欲望が、当時美術志望ながら、なんの活動もしていなかったJ太郎へと話が伝わり、そして、アキさんの元に向かうことになる。つまり、私とアキさんも初対面だったが、私とJ太郎も、初対面だった。
当時は、ただ回転ベッドで絡みを撮りたいという単純な憧れから、どれくらいの費用がかかり、どれくらいの労力を要するのかも全く理解せずに、教えを乞いに行った。アキさんにとっては小生意気な学生であったと思う。
それでも、「攻めた作品撮るやんけ」と興味を持ってくれ、その日からセット作りの準備が始まった。アキさんは、大学には似つかない作業着姿で、歯が極端に少なく、腕にタトゥーの入った、どちらかというと強面の先生で、先生というよりは番人のような存在だった。普段はスタジオでの授業以外顔を合わせない方なのだが、セット作りの教えを乞いに行った折は、近年ではセットを作りたいだとか、変な作品を作る学生が少ないらしく、殊に嬉しそうな顔で「なんでも教えてやるから、毎日来いよ!」と話してくれた。我々は彼の風貌に少しビクついて、意を決して声をかけたから、思いのほか気さくな反応に驚いた。
J太郎と人となりが見えた瞬間
その日は、とにかくイメージを描かないと話にならないということで、早々とスタジオを後にし、初対面のJ太郎と作戦会議が始まった。見事に人見知りを発動していたJ太郎は、ツイマ君の背中に隠れてボソボソと喋り、それを通訳して私に伝えるツイマ君、という構図だった。私は当然先行きが不安だったが、「こんな色使いで」「何メートルくらいの大きさで」「この映画を参考に」と注文をいくつか出し、J太郎は駐車場の片隅の砂利道で、絵を描きはじめていた。その姿がおもちゃを与えられた子供のように楽しそうだった。

イメージ画が上がって、すぐのことだった。「実現できるかわかりにくいから模型を作った」と連絡が届き、私はすぐにスタジオに向かった。正直、イメージ画を見せられても、実際に可能なのか、予算はいくらなのか、全く見えなかったので、すごく助かった。とにかく「自分はまだペーペーだから、大きい予算をもらうわけにはいかない」と言っていたJ太郎は、ペンキ台を抑えるため、春画を壁に貼るという案を提案し、それと同じく、柱や板を多く使ってペンキを塗る部分を少なくする、と話した。撮影する上で、必ず欲しかった大きな鏡は、できるかぎり面積を小さくする代わりに、その両脇にステンドグラスのフィルムを貼ることで、安っぽさを抑えるという提案をした。

この模型を見て、J太郎の口下手なプレゼンを見たとき、初めてJ太郎とまともに会話したと思う。そして、彼の力量を信じようと思えた。完成したセットの写真は、次回の記事にでも載せますが、今回のセットはスタジオ前に捨てられた余りのペンキや廃材を利用して、格安に抑え、5万円で作られることになった。
セット作り奔走の日々
そのセット作りの工程で、美術のJ太郎とアキさんは、次第に師弟のような関係性になっていった。美術志望でありながら、それまで映画制作に関わったことがなく、多くの経験するはずだった事を逃していたJ太郎にとっては、まさに光のような存在だったのではなかろうか。大学に行けば授業には行かずとも、アキさんには挨拶に行き、美術倉庫でダベりながら、映画談義に花を咲かせ、タバコ片手に作業を進める、まさしく芸大生という、日々だった。
アキさんと付き合い始めた頃は本当に楽しかった。それまでロクに準備もせず、遊びの延長で自主映画を撮っていた私にとっては、少ない予算ながら、廃材や余った塗料で工夫し、二次元で書かれたイメージ画がどんどん立体的になってくる様を見てると、「これがやりたかったんだよ!」と思えた。他の仲間とツルむのを控え、スタジオに入り浸るようになったツイマ君やJ太郎も同様だったと思う。
美術部だけでなく、うちのスタッフはほぼ全員、後輩から先輩、ときには自分たちの彼女まで巻き込んで、セット作りに励んだ。他の教授たちに「今日もセットか」と聞かれるたびに、なんだか嬉しかったのを覚えている。予算がない分、工夫をして手間がかかった。けれど、その手間を仲間と一緒に楽しんだ。まさに今、映画を作っているという実感があった。みんな初めての経験に苦心しながらも、楽しんでいたように思う。
J太郎はハンマーからインパクト、印の付け方から挨拶の仕方、何から何まで思いつくものは殆ど全て教えてもらい、当初は話下手で引っ込み思案なJ太郎も、まさしく成長を感じる微笑ましい時間だった。また、DIY経験の豊富なツイマ君とアキさんが美術談義に花を咲かせている姿に、やや嫉妬していじける姿は、師匠を奪われた弟子そのもので、愛くるしかったことを覚えている。
初めての暴力
かく言う私ではあるが、実は当初からアキさんのことを信用しきれない点もあった。例えば、どこどこの現場で会った〇〇という女優とセフレだ、とか、弟子が数十人いる、だとか。彼の語る武勇伝のどれもが信憑性に乏しく、なんとなく虚言・妄言の類を感じていた。まぁそれでも、手取り足取り教えてくれるし、気さくな方だし、別にいいか、くらいの認識だった。が、そんな私が決定的に距離を置いた出来事がある。
アキさんによる初めての暴力。それは、とある昼下がりに起こった。大学の授業をほっぽり出し、いつものようにツイマ君・J太郎・私・アキさんで作業を進めていた。私は工具の扱いが不慣れで、もっぱらその傍らの作業台で台本を改稿しながら作業を見守っていた。
その日は、アキさんの工具をJ太郎が初めて触らせてもらった日だ。それまでJ太郎は、ツイマ君の簡単なDIY工具を借りていたのだが、「美術をやっていくんなら、きちんとした工具を覚えろ」とアキさんが自身の工具を貸した日のこと。いわば師匠と言える人間の仕事道具で作業をする、そういう場面でJ太郎はビビり倒して作業を始めた。
「ガガガガガッ!」とネジを滑らせる音が聞こえ、やってしまったとばかりに半笑いでアキさんを見るJ太郎。横でニヤニヤ笑うツイマ君と私。アキさんはザクザクと後ろから近づき、握り拳でゲンコツ一発、それからJ太郎を軽く蹴り飛ばした。
「道具は真剣に扱え、怪我してからじゃ遅い!」
と言い放った。それまでの微笑ましい時間から一転、緊張感が走った。私はこういう場合、暴力がいけないと思わない。一歩間違えれば、簡単に指を落とせる代物を使っているわけで、その意識が希薄なまま作業をしていたJ太郎にとっては、至極当然の結果だと思えた。はっきりと叱責するアキさんの姿は真剣そのものだった。
「犬猫と一緒」
ただ、私が問題視したのはその後のことである。
翌日、アキさんは我々を飲み屋に誘った。きっと、アキさん自身も殴ったのは悪かった的な話をして、ほとぼりを冷ますのだと思って、我々も「いきましょう!」と乗った。ツイマ君が美術談義やアキさんの過去の武勇伝を掘り下げていた折、やはり初めてJ太郎を殴った話が始まった。飲み屋に入ってはや数時間、ようやく本題に入った。
アキさん「今回のことは、怪我もするし、道具も俺のやったから怒ったけど、今後も何かミスすれば普通に殴るよ?殴られて嫌な奴はこの世界やっていけんし、犬猫と一緒で殴られやな分からんねん。助手ってのはそういうもん。骨折られても文句は言うな」
とJ太郎の脇肉をつねり始めた。
アキさん「分かったか?」
J太郎「痛い痛い痛い、痛いですアキさん!」
アキさん「おい、犬猫がしゃべるな。ワンって言え」
J太郎「ワン!ワンワンワン!」
と、J太郎も合わせた。アキさんは、それから過去の弟子たちも同じように殴られて育った、と語り始めた。
ツイマ君もJ太郎も、その時は特に問題視してなかっただろう。何より、この時の二人はまだ、アキさんの言動に違和感を感じていなかったし、散々「映画はブラック」と聞かされているものだから、そういうもんなのかと理解していたように思う。J太郎が犬マネをさせられているのも、いつもの悪ノリの延長という感覚だった。
アキさんとの問答”殴り返す奴は殴らない”
私はと言うと、どうも納得いかなかった。J太郎がバイトのために離席し、ツイマ君がトイレに行った際、私はアキさんに尋ねる。
私「映画ってのは、暴力がある。うちの作品でも性暴力を題材にしてる。でも、それを撮る俺らが、同じことしてもいいってのはよく分からんのですが」
アキさん「そういう世界なんや、ドウ(私)は映画よー見てるから知ってるやろ。できひん奴は殴って聞かせやなしゃーない」
私「できひんってなんすか」
アキさん「できひんてのはできひんってことや」
私「じゃあ俺も殴るんですか」
アキさん「ドウ(私)は殴らんよ。お前、殴り返すやろ」
私「そりゃ殴り返しますよ」
アキさん「J太郎は殴らなわからんから今後も殴る。しゃーない。」
ここでツイマ君が席に戻る。
この件以降、私はアキさんと急速に距離を保ち始める。改めて字に起こすとひどいもんだ。今思えば、この段階で、J太郎やツイマ君に私の疑念を話せばよかった。ああいうことになるんなら、話すべきだった。反省している。
けれど、この初めての暴力以降、J太郎は美術という仕事に真剣な視線を送り、自分の作業に誇りと危機感を持つようになった。だから、私は今回のアキさんの暴力を許した。暴力ではなく、愛の鉄槌として。
ただ、アキさんの暴力は、至る所で起こり始める。買ってきたコーヒーがブラックじゃなければ殴り、弁当を先に食べただけで殴り、ひどい時には先に座ったから殴る、一回で聞き取らなかったことに苛立ち殴ると言った具合に。J太郎が殴られるのは日常茶飯事となり、そのあまりの頻度に、J太郎自身も私自身も、「おかしい」と思えなくなった。飲み会では、説教と暴力がセットになった。
次回予告
次の記事では、「濡れたカナリヤたち」のセット完成〜を書く。この頃、ようやくスタッフ以外の第三者がアキさんの暴力を目撃する。また、その暴力の件でJ太郎が、私に具体的に「嫌だ」と話し始めるようになるのもこの時期だ。その点を中心に書こうと思う。
少しでも私のことを応援したいなと思って下さった方、そのお気持ちだけで励みになります。その上で、少しだけ余裕のある方は、サポート頂けますと幸いです。活動の一部に利用させていただきます。
