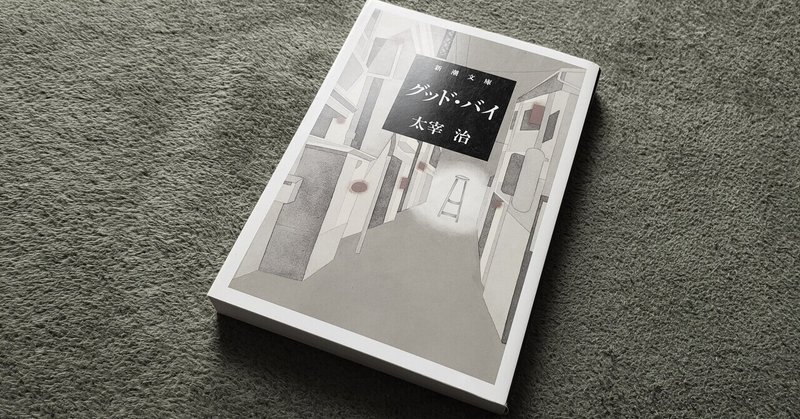
【随想】太宰治『苦悩の年鑑』
所謂「大物」と言われていた人たちは、たいていまともな人間だった。しかし、小物には閉口であった。ほらばかり吹いて、そうして、やたらに人を攻撃して凄がっていた。
人をだまして、そうしてそれを「戦略」と称していた。
どんなに卑屈な人間にもどこか純粋としか言い様のない面があるものだ。それがどんなに不合理で、理も筋もまるでなっちゃいなくて、論理的に破綻したものであろうと、そしてそれらの信ずるに値しない根拠を頭では理解していようと、尚捨てられずにずっと持ち続けている、そんな何かが一つはあるものだ。それは理屈ではない、感情でもない、強要されたものでもない、それは、その人の歴史であるとしか表現の仕様がない。それは、書き換えられるものではない。
そういうものの為に人は苦しむのではないだろうか。人の苦しみの根源とはその不変の何かに由来するのではないだろうか。苦しみとは失うことだ。得る苦しみとは、それをいつか失う苦しみだ。持たない者は失うものがないから苦しまない、という人もいる。だがそれは理想であり空想だ。何も持たぬ者などいない。全ての所有を捨てようと、社会を捨てようと、自分を捨てようと、最後に一つ、捨てたくても捨てられない不変の何かが残る。全てを捨てても尚残るもの、それが何なのか認識出来たのなら、手に収めることが出来たのなら、人生のあらゆる悩みは全て解決するのではなかろうか。
素晴らしいことです素晴らしいことです
