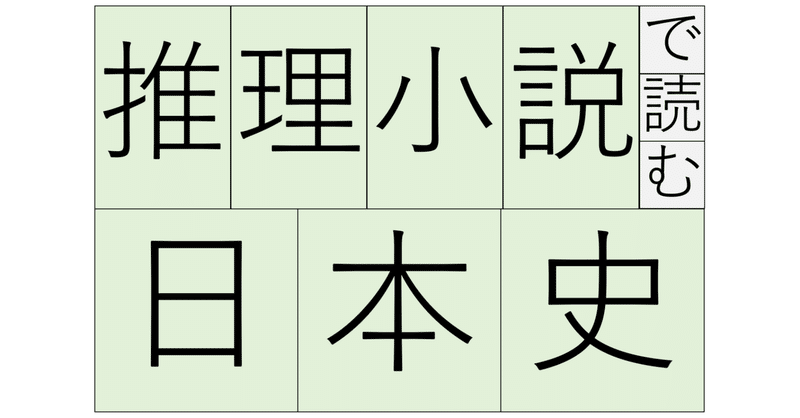
推理小説で読む日本史4 吉村達也『卑弥呼の赤い罠』
いよいよ弥生時代に進みます。「邪馬台国」や「卑弥呼」で検索すると、出てくるわ出てくるわ。あまりに多くてどれを読むか迷ってしまいます。
ざっとヒットしたものを挙げてみると……。
・黒木曜之助『暗く重き復讐 邪馬台国殺人事件』
・木谷恭介『「邪馬台国の謎」殺人事件』
・深谷忠記『「邪馬台国の謎」殺人事件』
・荒巻義雄『「新説邪馬台国の謎」殺人事件』
・長尾誠夫『邪馬台国殺人考』
・中津文彦『邪馬台国の殺人』
・斎藤栄『邪馬台国殺人旅情』
・鯨統一郎『邪馬台国殺人紀行』
・鯨統一郎『女子大生つぐみと邪馬台国の謎』
・長崎尚志『邪馬台国と黄泉の森―醍醐真司の博覧推理ファイル―』
・島田一男『卑弥呼塚殺人事件』
・澤田盛夫『「卑弥呼の鏡」連続殺人事件』
・阿井渉介『卑弥呼殺人事件』
・吉村達也『卑弥呼の赤い罠』
・西村京太郎『十津川警部 二つの「金印」の謎』
・篠田秀幸『卑弥呼の殺人』
(このほかにもいろいろヒットするのですが、それらは旅情ミステリーではなく登場人物たちが歴史を議論する小説のようですので除きます)
邪馬台国や卑弥呼がいかに人気を集めているか、いかにミステリーの世界で消費(?)されて来たかがよく分かります。木谷恭介と深谷忠記などは全く同じタイトルで紛らわしいですし、荒巻義雄は「新説」を付けただけで類似したタイトルです。
ちなみに西村京太郎のタイトルに「二つの金印の謎」とあるのは、「漢委奴国王」と「親魏倭王」の二つを指すもので、結局邪馬台国をメインテーマとした推理小説のようです。
たくさんある中から、何となくあらすじを見て吉村達也『卑弥呼の赤い罠』を選ぶことにしました。

古代史学者の新藤英二郎が「私はまもなく殺されるらしい」との遺言を残した後、自宅で死体となって発見されます。
新藤教授は邪馬台国や倭国の成立についてあまりにも過激な説を唱えているため、右翼や左翼に命を狙われていたとのことでした。
その後、新藤ゼミの学生たちがひたすら新藤教授の講義の思い出を辿る場面が続きます。
ここまで読んだところで、私はこの小説の構造を理解しました。
どうやらこの小説は、推理小説として謎解きを楽しむのがメインではなく、著者である吉村達也の邪馬台国をめぐる考えを、新藤教授の口を通してひたすら披瀝するのが目的のものなのです。邪馬台国に興味のない人にはとても読みこなせないかもしれません。
とはいえ、新藤教授の講義はなかなか読み応えがあります。
「縄文式土器を用いた狩猟文化を持っていた縄文人を古モンゴロイドの第一種日本人とすれば、弥生式土器を用いた農耕文化の弥生人は、あとから日本列島にやってきた新モンゴロイドの第二種日本人だ。朝鮮半島から朝鮮人がやってきた、というふうに民族として捉えると、まるで日本が朝鮮系の国々に占領されたかのように思って抵抗のある人が多いかもしれないが、古モンゴロイド種の生息地域に新モンゴロイド種が加わったというふうに、生物学的に捉えたほうがいい」
確かに、日本人の形成過程について議論する際、やたらとナショナリズムを持ち出す人っているよなあ……と前々から思っていました。その点についての新藤教授の戒めは、なかなか的を射ているように思われます。
杏美がたずねた。
「弥生時代の日本は、渡来人が支配していたことになるんですか」
「その『渡来人』という用語が大きな間違いだね」
新藤が、やや厳しい口調で言った。
「その言葉は鎖国時代の感性となんら変わらず、まるで移民のような感覚で渡来人を考えようとしている。だが、考古学者や歴史学者が渡来人と呼ぶ新モンゴロイド系人種は、決して外国人ではない。なぜなら、私が第二種日本人と呼ぶ彼らこそが、現代日本人の根本を形作っているからだ。邪馬台国もそうだし、ヤマト王権と古墳文化もそうだし、仏教の伝来による飛鳥文化、さらには平城京から平安京へとつづく日本の歴史は第二種日本人によって作られてきたのだ。これを渡来人と呼んでよそ者扱いする感性は、学者として根本的に誤っている」
例えば、「天皇にも渡来系の血が入っている」と言うとやたらと怒り出す人がいますが、それは人類史を真実探求のためのものでなく、政治的なものとして捉えているからでしょう。同様に、「渡来人=よそ者」と捉えるのもナショナリズムの現れかもしれません。
そもそも弥生系が縄文系よりも後で日本列島にやって来たことは間違いないわけで、それを「渡来人」と呼んでよそ者扱いするから排外的なナショナリズムがはびこるのかもしれませんね。
物語は、新藤教授の講義の追憶と、その死の真相を探ろうとする学生たちの捜査とが平行して進んでいきます。
そして最後に明かされる新藤教授の死の真相は……。
正直、さほど驚く結末でもありませんでした。そもそもトリックもなく、意外な展開もなく、推理小説としての出来ははっきり言って悪いです。
しかし、新藤教授の講義自体が一読の価値ありといえるでしょう。
「普通に歴史考察本として出版すれば良かったのでは……?」
と思える内容で、魏志倭人伝の読み解き方としてそこそこ説得力もあるので、この時代に関心のある方にはお勧めです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
