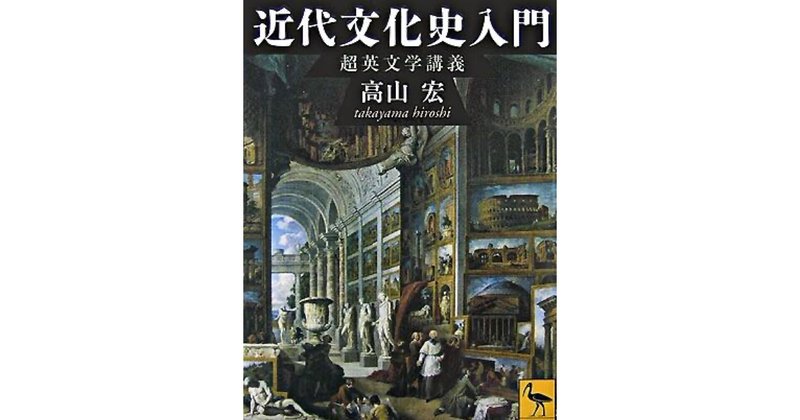
絢爛で魔術的な文化論の”超”作~高山宏『近代文化史入門―超英文学講義』
ついに出た。2020年私的ベスト本の急先鋒。
博覧強記の文学者にして「学魔」と呼ばれる著者高山宏については、名前ぐらいは聞いたことあれど本書を開くまで寡聞にしてその業績をほとんど知らなかった。「こんなすごい人がいた!」と騒いでも、何をいまさらと鼻で笑う向きもあろう。
サブタイトルにある「英文学」が確かに著者の専門ではあるらしいのだけど、堅苦しく味気ない文学史の類では、本書は一切ない。”超”英文学との謂いは、スーパーな英文学ということではなくて、英文学を”超えている”=超領域的な文化史論、ということだ。紛れもなく、本書は単なる文学史を徹底的に”超”えている。超領域的に、近代という文化全体の構成原理とその変遷を、言い換えれば現代の我々が無意識的に行っている日常の物事の捉え方に深く根を張っている観念の体系を、一挙に掴み取ろうとする広大な射程の試みの概略図である。英文学はあくまでそのためのツールの一つであり、文学史の入門書/概説書の類かと思って手に取ると見事に裏切られる。
メディアの形を一つの主題とした16世紀以降の視覚文化論として話は進むが、文明と文化、ハイカルチャー/サブカルチャー、文字と図像、合理と魔術など、様々な対立軸と関連事物がどんどん設定され、そのいずれもが軽々と飛び越えられる。その縦横無尽な滑空のあまりの振れ幅、あまりの鮮やかさとルートの多さに、気づけば高山ワールドの真っ只中で意識混濁、知識欲の充満でよだれを垂らしていた。最初からずっとクライマックスで、知の享楽に浸り続ける、これはある種の麻薬である。
本書の異貌っぷりは、出だしからすぐさま看取できる。曰く、以降現代まで続いていく自然科学(すなわち近代そのもの)の胎動期を切り開いたニュートンの主著『光学』は、当時なによりもまず詩人に多く読まれた、と語りだされる。
全体を通して問題となっているのは、美学者グスタフ・ルネ・ホッケが『迷宮としての世界』の中で明らかにした「マニエリスム」という概念。一般に美術作品の技法の一つと理解されるこの語に、そのような一面的な定義を与えることを高山は慎重に避けながら、精神史のより大きなうねりの中で位置づけることを目指す。本書に即して言えば、一見して関連のない物事同士の、非合理的で魔術的なつながりの快。技法的には、中世からの結合術(アルス・コンビナトリア)として謂われ、ライプニッツの順列組み合わせ思考や神秘主義とも関連付けられる、通常の因果性/論理学的思考と対置される知性のあり方である。
近代に至り世界を覆った合理的理性は、実はこの魔術的思考と切っても切れない関係を持ち続けていて、それが混迷の時代に文化の諸相の境界線上に定期的に顔を出してくることが、20世紀の少なくない研究が明らかにしてきた。本書は、このマニエリスム概念をテコにして、近代を取り囲む様々な文化風習を魔術的につなげまくり、表象としての世界認識の現在地をあぶり出していく。著者高山宏の思索の旅路に追従するなかで、目まぐるしく変わっていく時代精神の深く奥底で人知れず脈動を続ける幻想的な精神を捉えんとする熱狂と汲み尽くせないほどにほとばしる博学・衒学的知識が読者を唸らせることになる。
18世紀初頭のイギリス、ニュートン『光学』から始まる長く曲がりくねった迷宮は、文体論、秘密結社「薔薇十字団」、王立協会、シェイクスピアを辿り、ロマン派、ピクチャレスク、グランド・ツアーでイタリアへと渡り、オランダのチューリップバブルと静物画の周りとぐるっと周遊し、再度イギリスへ舞い戻って造園術と錬金術を大いに語る。ビクトリア朝の見世物小屋、大英博物館、『シャーロック・ホームズ』に触れながら、中世にさかのぼり、神秘主義と魔術思想を引っ張ってくる。再び後世へと反転し、ロック『人知論』とメロドラマとレアリスムと、さらにシュルレアリスムとが入り混じっていく。これらがすべて、1本の線でつながる。相互に影響を及ぼし合って、一つの観念を織りなしていく。このテーマ群は、じつに本書のほんの一部分にすぎない。
本書の実際の”雰囲気”を感じるために、また別の一部を、やや長いが引用したい。
たくさんのデータを蓄積していくことを「教養」と思う時代が、この頃から始まっている。その証拠に、主な辞書、百科事典はこの王立協会以降にできてくる。
...
一七二八年に、ある百科事典が出た。デフォーの『ロビンソン・クルーソー』の九年後、ジョナサン・スウィフト(一六六七~一七四五) の『ガリヴァー旅行記』の二年後に出たイーフリアム・チェンバーズ(一六八〇頃~一七四〇) の『サイクロペディア』である。 ...「ペディア」は、ギリシャ語の「パイデア=教養」に由来する言葉である。それを全部勉強すると、知識が 丸く閉じる。これは日本でいう円相もしくは円満具足の感覚だ。
...
ダンテの『神曲』、メルヴィルの『白鯨』からピンチョンの『重力の虹』まで、文学に名を借りた各時代の百科事典がある。今ならボルヘスとエーコ。...こういう形で文学をメディアの方へ「超」えたのがノースロップ・フライの『批評の解剖』(法政大学出版局)である。カナダはトロント大学であのマクルーハンとフライが仲間だったのは、やはり意味があるのだ。
...
この画期的な出版物『サイクロペディア』は、なかなか面白い特徴を持っている。テクノロジーというか「手わざ」の百科事典である。魚の釣り方、その釣り針のつくり方、ヤギの飼い方、その飼料のつくり方、穴の掘り方、屋根のつくり方……。そう、つまりは『ロビンソン・クルーソー』と同じ主題なのである。 この百科の知識は学者の知識ではない。
...
人間の体の中を見る医学は、ルネサンスの終わりからずっと整備され、十八世紀の前半に完結する。とくに、お産については、十八世紀中期に妊娠、お産小説が簇生する。ローレンス・スターンの『トリストラム・シャンディの生涯と意見』を読むと、トリストラム・シャンディが、お母さんのおなかからどうやって出てくるかの話である。
...
このチェンバーズの事典をそのまま「二次創作」して、一七五〇年代から七〇年代につくられたディドロとダランベールの『百科全書』には、「産科学」という絵があって、鉗子類その他のおぞましい挿し絵がある。
...
そこまで人間の体の内部に関心がある文化とは何なのだろうか。端的にいって知識、教養のあり方が変わったといえる。今まで見えないものをあきらめていた教養があったのであり、そこから先は神の領域、人間が手を出してはいけない領域だった。技術論的にいえば、不可視の領域である。見えないものは理解しない。「好奇心」というものと直結した目が現象の表層をやぶって、どんどん世界を可視のものに変えていく。「啓蒙」とは文字通り「蒙」きを「啓」く光学の謂なのだ。
近代の夜明けを告げた啓蒙思想(the Enlightenment)が、字義通り対象を光学的に視ることと分かちがたく結びついて産まれてきた観念であることを明らかにする箇所である。限られた文章の中に稠密に敷き詰められた観念と固有名詞の密度の高さに、めまいを禁じえない。それ以前の”暗い夜”の時代、目に見えないなにかを類似と神秘性のうちに理解していた時代の精神が啓蒙思想のうちにも実は伏流していたことを、著者の卓越した博物的・分類的・結合術的知性が喝破していくのだ。
たしかに、17-18世紀の視ることに狂う文化が、認識論的世界観を大きく切り拓いてきた時代ではあった。ニュートン/デカルトの光学やカメラ・顕微鏡の発明に同時代の知識人は大きく揺さぶられていた。本書ではあまり触れられていないが、哲学史的にもこの18世紀初頭に視ることにまつわる重要な議論がジャンルを超えて多く提出されている。光学研究家モリヌークスが提起した「網膜上の平面がなぜ3次元的な表象を生むのか」という問い―いわゆる「モリヌークス問題」―にイギリスの哲学者バークリーが『視覚新論』で応対した事態は認識論を新たな局面へと導いたし、大陸側でもそのほんの5年後にライプニッツが『モナドロジー』上で、歴史上初めて顕微鏡を使った科学者レーウェンフックをほとんど思想家のように扱いながら、微細な世界の表象の展開原理について言及を重ねている。
そうした啓蒙の「光」に照らされた近代300年を経て、理性の限界の発見とともに到来した20世紀のポストモダンにおいて幻想とゲテモノと魔術的精神が三たび首をもたげてくるメカニズムを、本書は捉えていくことになる。社会の混乱と分断に際して、個人の精神のうちにも喪失感が急速に広まっていく。しかし他方で、失われかけている世界の一性・全体性をフィクショナルに結び合わせるべく、歴史の諸局面で顕現してきた力がたしかにある。合理的理性の陰で眠っていた魔術的思考―ホッケがマニエリスムとして見出したもの―がそれであり、幻想文学やシュルレアリスムとして発露してくるのがそれである。
著者の主張の全体は、本書の散逸的で迷宮的な構成ゆえおぼろげにしか像を結ばないが、常にこのマニエリスムを中心として周遊し、あらゆる文化風俗をそこに紐付けていく壮大な事業を一望のもとに晒してゆく。迷宮的ではあるが、全編を通じて非常な疾走感があり、さらに滑るように軽妙で流麗な語り口が共在するため、ページをめくる手が止まることがない。著者の研究生活30年の集大成を初学者向けにコンパクトにまとめている本ゆえ、アカデミックな論証的記述がほとんどない点も、読みにくさが少ないことに一役買っている。裏を返せば、その分だけ論理の妥当性に首を傾げたくなることも事物同士のつなげ方の乱暴な箇所も散見されはするのだが、それらは本書が持つ魅力をいささかも損なうものではない。煌めくような仮説をどんどん縦横に走らせ、究極原理としての「非合理なつながり」という全体を編み上げていくファナティックでレトリカルな著者の熱気にあてられ、ただただ知の危うく怪しげな迷宮に飛び込み、混沌を味わい尽くすのみである。
本書自体が、まさに魔術的で錬金術的な一冊、なのである。
関連記事
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
