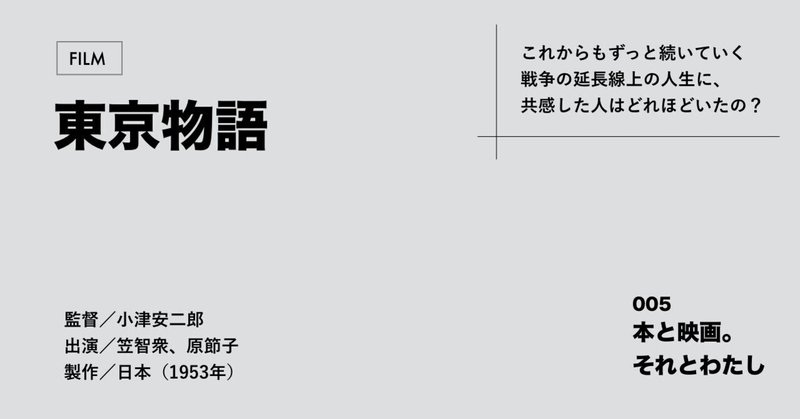
わたしの故郷の、近いようで遠い物語
これからもずっと続いていく戦争の延長線上の人生に、共感した人はどれほどいたの?
自称映画好き……といいながら、ものすごい本数を観ているわけでもないし(少なくとも1000本くらいは観ているかもしれない。予想)、むしろものすごく偏っているほうだと思う。そんなわたしは、小津安二郎や黒澤明を観ないまま30代になってしまった。今回は、小津安二郎作品の記念すべき1本目「東京物語」を。
まず見入ってしまったのは、1950年代の東京の景色だ。わたしの母は1960年に東京下町で生まれ、ちょっと早いけれど、きっと母が生まれたころの東京の街の様子はこんなふうだったろうなとつい考えてしまう。わたしが知っている母の実家は4階建てのビルだが、昔は2階建ての木造で、きっと東京物語に登場する長男・幸一の家のような感じだったのだろうと想像した。
上京した子どもたちを訪ねて、尾道から夜行列車で東京へ出てきた周吉ととみ。彼らの淡々としたテンポの物腰のやわらかい口調は、子どもたちのせかせかとした都会的な話し方と対比される。ちょうどわたしの父が故郷よりも東京での暮らしが長いように、すっかり東京の人となったことが暗示されている。そして、両親と子、孫との境界線がさまざまな会話や出来事を通じて見え隠れし、戦後の核家族化のはじまりを告げるかのようなシーンがいくつも登場する。
また、この物語は戦争の延長線上で進んでいることに、はっと気づかされる。それは、原節子演じる紀子が、次男・昌二の妻であることが発覚したときだった。紀子のような未亡人が同じ時代にいったいどれほどの数いたのだろうかと思うと、急に恐ろしくなった。公開当時この映画を観た人で、これはわたしだ、と思った人も多かったかもしれない。紀子だけでなく、ほかの登場人物だってもちろん。
フェミニズム的な視点で見ると、おやおやまあまあ、と思うことも多々あるのだが、この作品には極めて歴史的なリアルが写し取られていて、その時代に生きていなくても、なんとなく懐かしさを感じさせるところがある。それは日本語の響きの美しさからかもしれないし、戦後独特の平和な空気感からかもしれない。物語としてきちんとクライマックスが存在しながらも、終盤で次女・京子が述べた言葉は現実を鋭く突いており、最後までリアルを見据えているところが清々しい作品だった。今年は日本の名作を開拓しようと思った、とある日曜の午後。
東京物語 ニューデジタルリマスター
監督/小津安二郎
出演/笠智衆、原節子
製作/日本(1953年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
