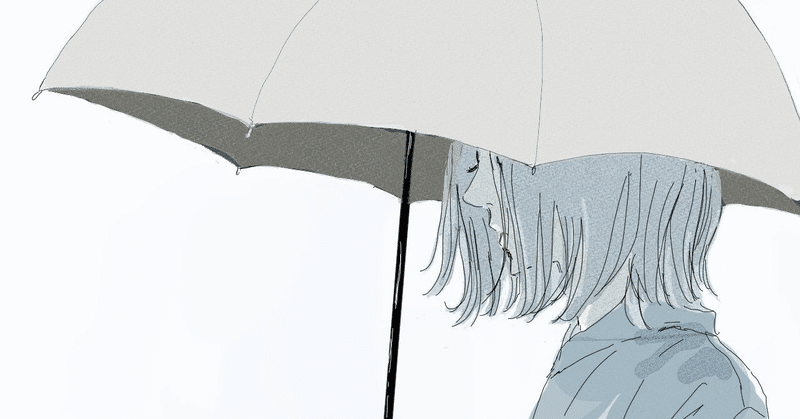
和歌心日記 3 在原業平朝臣
千早ぶる
神代もきかず
龍田川
あの人の傘は、
目の醒めるような、からくれなゐのような赤だった…
6月。梅雨だ。鬱陶しい季節。
今年は今世紀最大の長雨らしい。
最近は今世紀最大や、観測史上最長だとか、そんな言い方ばかりが目につく。
明らかに過剰な反応だ。マスコミは常に煽らないと食っていけないのか。くだらない。
いや、そんなマスコミ批判をしている僕の方がくだらない。
つまり。暇なのだ。いや暇だ。
都内の大学に通う普通の大学生。特にイケメンでもなく…勉強ができるわけでもない。
週3回のアルバイトをして、大学はテキトーに通っている。
しかし、暇だ。
何か胸の熱くなる何かに嵌りたいという願望はある。そして、そういうことをやらなければならないと先輩にも聞いた。就活で何か話せるネタを作っておいた方がいい、らしい。
就活のために大学に入ったわけ…いや、親はいい大学に行って、いい会社に入ってって口癖のように言っていた。
ならばその何かをやるしかないのか…嫌だ。
なんで言われた通りに生きなきゃならないんだ。そもそも就職なんかしたくない。
ようやく自我が芽生えたのか。遅過ぎる。
僕は大学の近くにある喫茶店でバイトをしている。
「コーヒーとAサンド」
「はいかしこまりました」
レジで働く由美ちゃんがコーヒーを作り、僕はAサンドを作る。流れるような作業、あっという間にコーヒーとサンドイッチがお客様に提供される。
良いチームワークだ。この由美ちゃん、密かに狙っている。大学は隣の女子大。同級生。
脈は…
「裕くん」
「法学部だよね?」
「うん」
「テストやばいんだけど、ちょっと教えてくんない?」
「いいよ別に」
「じゃバイトの後近くでいい?」
「うん」
多分ありだ。わざわざ俺じゃなくても学校の同級生に聞けばいい。わざわざ俺に?
「あの、Bサンドまだですか?」
おっと、ぼーっとしていた。目の前にオトナな女性が待っていた。
「出来上がりましたらお呼びしますので、お席でお待ちください」
「いいわ、早くね」
「はい、かしこまりました」
たまにいる、待っていられない客。この女性もそのタイプか。ビジネスで成功していそうな感じ。ツンツンしていてムカつくが、美人だから許してしまう自分が情けない。
チラリとレジを見ると由美ちゃんが見ている。
曖昧に笑う。
由美ちゃんは視線をレジに戻す。
バレたか…
僕は可愛いより綺麗が好きなのだ。由美ちゃんはどちらかと言うと可愛いタイプ。いやいや、暇人の俺は、まずは彼女だろ!
と自分に言い聞かせる。
「Bサンドのお客様、お待たせしました」
「次はもっと早くね。ぼーっとしてないで」
そう言うと、挑戦的な眼をでふっと笑う。
撃ち抜かれた…なんて簡単な…
「BLサンドお願いします。裕くん!」
「え?あぁごめん。了解」
由美ちゃんがまたチラリと見る。
またぼーっとしてしまっていた。やれやれ。
僕は素早い手つきでB Lサンドを作る。作るのはうまいと思う。今回も挟んだベーコンとレタスのバランスが完璧だ。自然と笑みが溢れる。
僕は職人気質だ。クリエイターがいいのかな。でも、法学部なんてクリエイターになれないか…。
「ねぇ、聞いてる?」
「うん?聞いてるよ、これは不法行為だから702条だよ」
「それはわかってるわよ。ねぇ、今日は集中力なかったね。特にあの高飛車な女の時がピーク。ぼーっとしてた」
「え?」
「え?じゃないよもう。これじゃコーヒー奢ってる意味ないじゃん」
「ごめんごめん」
曖昧に笑う。でも由美ちゃんは嬉しそうだ。これはいけるんじゃないか。
「由美ちゃんは、彼氏いるの?」
「ど、どうしたの急に」
「あ。いやなんとなく」
「今はいないよ。裕くんは?」
「あ、いや俺もいないけど」
「ふーん、変なの」
あれ、意外と来ないな。脈ありだと思ったのに、まぁ焦らずいこう。
翌日も雨だった。
僕はまたバイトに入っていた。
午後8時過ぎ、例のツンツン美人がやってきた。今日は空いてるからすぐにサンドイッチを出せそうだ。今日由美ちゃんはいない。社員の香坂さんがレジに入っている。
「カフェラテとCサンド」
「かしこまりました」
僕はカフェラテのカップを用意して抽出ボタンを押すと、素早くサンドイッチの作成にかかる。フリルレタスの上に生ハムとチーズを置く。
フリルレタスに空気を入れて置くことで歯触りが良くなる。
今回は素早くできた。
「Cサンドお待たせしました」
「今日は早かったわね、サンドイッチマンくん」
「ありがとうございます」
僕は飛び切りの笑顔で笑う。
彼女は一瞬口角を上げてCサンドを持っていく。
なんだか距離を詰めれたようで嬉しい。
翌日。天気は曇り。
僕はまたバイト。今日も由美ちゃんはいない。テスト期間に入ったんだっけか。
今日はあの人は来なかった。ちょっと残念な自分がいる。由美ちゃんも可愛いけど、今はあの女の人のことが気になる。
バイト終わり、外に出て見ると、また雨になっていた。結構降っている。傘は持ってこなかった。
喫茶店から駅までは結構距離がある。
仕方ない。走るしかないか。
軒先から一歩踏み出そうとしたところで声を掛けられた。
「傘ないの?」
振り向くとあの人が立っていた。
目が覚めるような鮮やかな赤色の傘をさして。
なんだか自信満々のような、この人の心のような色だ。
「あ、えっと、はい、今日は持ってきませんでした」
曖昧に笑う。
「入ってく?」
「え?」
「駅でしょ?」
「はい。い、いいんすか?」
「この前すぐにサンドイッチ作ってくれたお礼ね」
僕は遠慮しつつもドキドキしながら傘に入る。
「僕が持ちますね」
「当然ね」
このニッとした笑顔がとても妖艶だ。側に寄るととてもイイ匂いがする。これはヤバい。顔に出さないように気をつけるが、ドキドキする心臓の音を聞かれているようだ。
「緊張してるの?」
「え、あ、はい」
なんだバレバレか。もういいか。
「大学生?」
「W大です」
「あらそう、頭いいのね」
「いや、そんな」
「この辺が職場なんですか?、あ、いや、別にいいんです」
「ふふ。そんなところよ」
全く何の主導権も取れない。
「あなたの作るサンドイッチ、美味しいわ。私はファンよ、あなたのサンドイッチの。なんてね」
「え、ほんとですか!嬉しいです。作るのには自信がありました」
「でも、少しスピードが遅いかな。少し効率を考えた方がいいわ。まぁでもヨシとしましょう」
歩いていると車がかなりのスピードで向かってくる。
「あ!」
咄嗟にこの人のトイレ変わって車道に立つ。
案の定ビシャリと水飛沫が僕のジーパンにかかる。
「ひどいわね。ありがとう、庇ってくれて」
「いや、それにしても結構濡れたな。はは」
「ほんとね」
少し考える風のこの人。
「あの、お名前って聞いてもいいですか?」
場違いなタイミングだが名前が聞きたかった。
「え?あぁ里美よ」
「僕は裕介っていいます」
「裕介くん、スウェット貸すわよ。私の家近いから」
「え、いいっすよそんな、傘に入れてもらって更にスウェットまで」
あ…スウェット…男ものあるんだ。
当たり前か。彼氏、いや旦那さんいるか。
なんだか嫉妬心が湧いてきた。
「じゃぁ思い切って借りてもいいですか?」
「ええ、じゃあこっちに行きましょう」
大通りから一本道を逸れて住宅街に入る。
ドキドキする。
「でも僕が着れるスウェットなんて…」
「野暮な質問するのかしら?裕介さんは」
「あ、いや、全然。黙ります!」
またニッと笑う里美さん。やばい。
なんだかとても抱きしめたい衝動に駆られる。
住宅街に入ってK田川を越えて立ち止まる里美さん。
「着いたわ。ちょっと待ってて」
K田川沿にある大きくて綺麗なマンションだった。
やっぱりエリートか。僕は暫くマンションの下で、雨が木の枝の葉を叩くポツポツという音を聴きながら待った。
この待つ時間が僕は好きだ。
僕のために女性が何かをしてくれている時間。
そう、僕だけのために。
暫くして里美さんが戻ってきた。
「はい」
「ありがとうございます」
スウェットを受け取る。
「父のよ」
「え?」
「このスウェット。だから返さなくていいわ」
「いや、洗って返します」
「いいわよ」
「じゃ、またね裕介さん」
「あ、はい。ありがとうございました」
「傘持ってく?」
「いえ、ここからは近いので…」
「そう?じゃあね」
「はい」
里美さんはくるっと振り返り.あっさりマンションに戻っていく。
「あ、あの!」
「?」
振り向いて笑ってくれる。
「連絡先、交換させて頂けませんか?」
一瞬考える様子の里美さん。その表情がまた大人の魅力満載で、見惚れてしまう。
「いいわ。はいQRコードだして」
僕は言われた通りにする。
「ありがとうございます」
「じゃまたねサンドイッチマンくん」
そう言うと彼女は今度こそマンションに戻って行った。
僕は彼女がマンションに消えると、飛び跳ねた!
やった!連絡先ゲット。
探していた何かはこの気持ちのことでなかろうか、などとくだらないことを思う。
帰り道。駅のトイレでスウェットに着替えると、その足元を写真に撮って里美さんに送った。
暫くして既読になったが、特に返信はなかった。
その夜、もんもんとして僕は眠れない。何度も寝返りを打った。
そこから暫く里美さんは来店しなかった。
一週間くらい経った時、僕は我慢できずメッセージを送った。
『最近ご来店されませんね。お会いしたいです』
送ってしまってから、その文面の大胆さに恥ずかしくなった。送ってしまったものはしかたない。
暫くして既読になったが、返信はなかった。
由美ちゃんがそのうちにまた復帰した。テストが終わったらしい。
「元気だった?」
「え?うん。まぁまぁかな。テストどうだったの?」
「バッチリだったよ。ありがと」
「あ、俺は何もしてないから」
「そうだね」
「あれ、そんなことないよ!の、流れだと思ったそこは」
「ふふ」
良かった、由美ちゃんは相変わらず元気そうだ。
それからまた何日か過ぎた。
相変わらず里美さんから返信はなかった。
「いらっしゃいませ」
店長の声がして僕は入り口を見る。
「あ」
里美さんがあの赤い傘を畳みながら入って来た。
「いらっしゃいませ」
僕は勢いよく挨拶する。
少し頭を下げる里美さん。
チラリと里美さんと僕を見る由美ちゃん。
「AサンドとCサンドを3つずつお願いします。持ち帰りで。それとコーヒーは店内で」
珍しい。持ち帰りで、しかもサンドイッチ6個。
僕はまた素早くサンドイッチ作りに励む。
その間にコーヒーを持って席に着く里美さん。にこやかに僕の作る景色を見ているようだ。
「Aサンド、Cサンド計6個お待たせしました」
僕は店内にいる里美さんに向けて声をかける。
「ありがとう。今日は6個だけど早いわね」
「頑張りました。珍しいですね6個なんて」
「ちょっと、差し入れ」
「そっか。あ、の、会えてなんか嬉しいっす」
「ふふ。ありがと」
やっぱり可愛い…というより素敵だ。
由美ちゃんが驚いた顔で見ているが、それはスルーした。サンドイッチを持って里美さんが出ていく。
「また」
僕は少し歯痒い想いで見送る。
暫くしてあの赤い傘が置きっぱなしになっていることに気がついた。
「あ」
僕はわざとらしく声を出して傘を取り、ちょっと届けて来ますと言って店を出ていく。
幸い店内も空いていて店長も特に気にした様子はなかった。
僕は走って里美さんを追いかける。
なんだか嫌な予感がする。
僕は走った。K田川が見えてくる。
そこに大きなトラックが止まっている。青いお揃いの服を着た引っ越し会社よお兄さんたちが里美さんから、僕が作ったサンドイッチを受け取り挨拶をしていた。
「あの、これお忘れです」
「あら、ほんとだわ。うっかりしてた」
里美さんは少し陰りのある顔で笑う。
「お引越し…ですか…」
「うん、ちょっとね転勤で」
引っ越しのトラックが走り出す。
「え、遠い所なんですか?」
「うーん、そんなには」
「…」
言葉が出てこない。
「そんな悲しい顔しないでよ」
里美さんは優しく笑いかける。
「僕、もっと里美さんのこと知りたいです。もっともっと。やっと知り合いになれたのに」
「あらあら、何泣いてるのよ。まだそんなに親しくないでしょ、私たち」
優しく笑う里美さん
「え?」
僕は泣いていたのか。涙で風景が滲む。赤い傘が目に溜まった涙に反射して、目の前のK田川が、いや、世界が赤く染まっているように見える。
「僕は里美さんと話した時間は少ないけど、里美さんが好きです…」
なんでこんなこと言えるんだろう。僕はこんな大胆な奴じゃやかったはずだ…。
でも、今言わないときっと後悔するんだ。
「もう、大袈裟ね。ちょっと少し入院することになってね。仕事も少しお休みするのよ。だからここにはいられなくなったの。君のサンドイッチまた食べたいけど。どうかな」
「え、そ、そんな…悪いんですか?」
「どうかな。それも含めてね、調べるの」
「そんな…」
また涙が溢れる。
人はこんなに泣けるのか、自分を客観的に見下ろす自分がいる。
「また、いつか会えたら…ね」
里美さんは見兼ねて、僕を抱きしめる。
僕は動けない。
「その傘あげる。また降りそうだから持っていって」
頷く僕。
「じゃ、またね」
離れる里美さん。
タクシーが一台やってくる。
「連絡先は交換してるから、僕メッセージします。またサンドイッチ作って持ってきます!」
「ふふ。ありがと。じゃあ持ってきて。栃木県にいくの。少し遠いけど」
「はい!必ず」
里美さんはそのタクシーに乗り込む。
窓が開いて顔を出す里美さん。
「ありがとう。来てくれて嬉しかったよ。またね」
少し悲しげな顔で笑う里美さん。
僕は頷いて、見送る。
タクシーが去っていく。
取り残された僕の頬に、
ぽつり、ぽつりとまた雨が当たり始める。
僕は里美さんの赤い傘を開いてそれを見つめる。鮮やかな、目の醒めるような赤。その赤い傘がK田川の水面に映る。
千早ぶる
神代もきかず
K田川
龍田川だったっけ…
僕の目には、目の前のK田川が里美さんの傘の色でくれなゐに染まっていた。
千早ぶる
神代もきかず
龍田川
からくれなゐに
水くくるとは
続。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
