
忘れられた日本人を読んで#3 【世界中の無駄なものに心からの賛辞を ー 農家の読書日記】
↑前回の記事はこちら
べらんめえ! 猫も杓子もプロセス効率化ときたもんだ
ただ、リバタリアニズムという名の競争至上主義が定着して久しい今の時代においては、巷でいうところの成功者のライフストーリーや持論ばかりにスポットライトが当てられがちなので、例えば前編でご紹介したイタリアに渡ってズッキーニの栽培技術を勉強した直売所のばあちゃんや、土佐源氏の古老のような、一見地味だけどスルメのように噛めば噛むほどに味の出るストーリーを持った人たちにはなかなか耳目が集まりません。
(そういう人たちに限って自分語りを避ける傾向にあり、さらには世間へ情報を発信する方法を知らなかったり、知っていたとしても肝心の発信力を全く持っていなかったりするんですよね〜。口惜しや)

で、現状はといえば、動画サイトやSNSを見ても、いわゆる「競争に勝てる」人間になるための方法論をさわりの部分だけ紹介し、あわよくば決済画面まで誘導してお金を巻き上げようとする下心丸見えのコンテンツ•広告が異常なほど溢れています。
もちろん、僕は才能豊かで社会的に大きな成果を挙げている人たちを毛嫌いしているわけではないし、むしろそんな人たちのなかには、尊敬してやまない憧れの対象もたくさんいます。
しかし、あらゆる方法論がコンパクトにパッケージ化され至るところで商材・商品としてばらまかれている昨今、たくさんの人(所感としては30代より上の世代)が定義の曖昧な成功者になるためのレールを今だに血眼になって探し回っているように僕には見えて、その「自分だけが幸せになれば他はどうでも良い」「負けた奴は本人のせいだから切り捨てて当然」みたいな利己的な価値観には、子供の頃からずっと一種の薄気味悪さを感じてきたのが偽らざる正直な気持ちです。
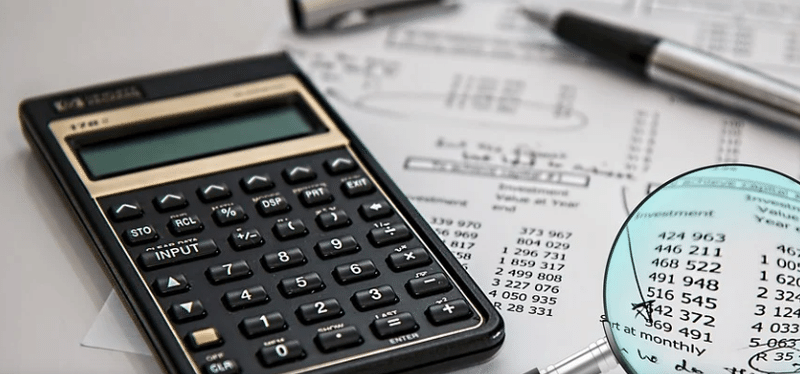
特に最近は、いかに時間と労力をカットするかという点に主眼を置いた言葉が氾濫しているように思えるんですよね。
例えば、「コスパが良い・悪い」とか「楽して稼げる副業」とか「人を操る〇〇術」とか「最速で〇〇になる方法」とか。
物事の効率を上げて生活を便利にしようとする活動自体は悪いことだとは全く思わないんですが、こうも猫も杓子も効率・コスパ向上ばかりだと何もかも味気なく感じられてしまうし、(これは極論ですが)最終的には、みんなにとって、世界が生きるに値しないつまらない場所になっていってしまうような気がしてならないんですよ。
無駄なものに目を向けると心が軽くなる
僕自身も、御多分に洩れず功利主義思想をガンガンに叩き込まれながら青春時代を過ごした人間なのであまり偉そうなことは言えませんが^^; 最近では割と、忘れられた日本人を読み直して改めて感銘を受けたことも手伝い、街中の人たちの何でもない会話や生活の営みに意図的に注意を向けるようになってきました。シンプルに言うと、世の中に対する見方がちょっと変わってきたのかもしれません。
例えば、カフェで世間話をしているおばさんたちの会話に後ろの席でこっそり耳をそばだててみたり、夜の静かな住宅街を散歩しながらそれぞれの家に住む人たちの人生に思いを馳せてみたり。
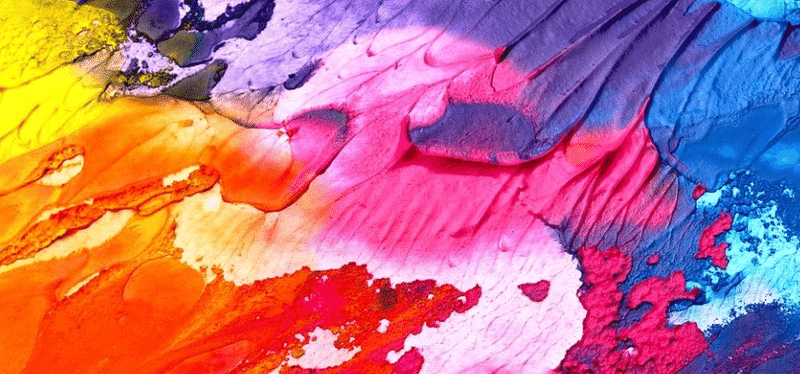
客観的に見ると怪しいことこの上ないのは重々承知してますが(笑 これがやってみるとなかなかエキサイティングで、それまで白黒にしか見えていなかった日常世界に、急にカラフルな色が塗り足されたような感覚になるんです。(僕はこうした一連の行為を、自分のなかで「心の塗り絵」と呼んでいます)
それと、自分の人生もそうした数多の営みの中のほんの一部に過ぎないことを再確認できるのも有意義な点で、30代半ばにしてようやく^^; 徐々にではあるものの、あるがままの自分を受け入れ肯定することができるようになってきた気がします。
そして土佐源氏に関していえば、こんなユニークな人生を歩んだ古老もさることながら、そんな彼のなかに光るものを見出して、卓越した取材力とセンスでその人生の物語を今へと紡いだ著者である宮本さんの審美眼が何よりも素晴らしい。
僕自身、宮本さんのような鋭い着眼点は当然持ち合わせていないものの、彼の持つフィルターを自分のなかにインストールしてみた結果、一見無駄なもののなかにこそ人生の醍醐味が詰まっていると強く実感できるようになり、これもまた非常に大きな収穫でした。
そして、そんな人生における蛇足や回り道を面白がって味わいつくす姿勢にこそ、幸せで充実した日常生活を送るヒントが隠されているように思えてなりませんし、そういった意味で民俗学という学問は極端に幸福度の低い現代日本につける最良の薬なんじゃないかなとも思うわけです。

(ちなみに最近は、廃車置き場や廃墟のような、無用の長物と化した文明の利器または生活感のかすかに残る建物が捨て置かれ、自然に呑み込まれて朽ち果てている風景にやたらと心惹かれます。その侘しい無常感に逆に慰められるというか、何故か心がホッとするんです)
直売所ばあちゃんのバイタリティの源泉について考えてみた
閑話休題。

話は冒頭に戻りますが、直売所のばあちゃんが齢80過ぎにしてイタリアへ農業の勉強をしに行った理由について、最近色々と考えてました。それで何となくこれじゃないのかなと思ったのは、幼少期から生活のために働き通しで、学ぶことをずっと我慢せざるを得なかったからなんだろうなってこと。
勉強というと、今日では耐え忍びながら行うものというイメージが一般化していますが、本来は、それまで知らなかったことを知り、新しい世界に触れて新鮮な驚きに打たれる体験を得るのは、知的生物である人間にとって何よりも楽しいことなはず。
彼女の半生や人となりについて知る機会は得られなかったのでこれは憶測に過ぎませんが、恐らく彼女は、引退して自由な時間を得てから、ようやくずっと蓋をし続けてきた勉強に対する欲求を開放することができたんだと思います。
というわけで話が二転三転して自分でも訳が分からなくなってきたので(笑 今日は自重してこの辺にしておこうと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました。このブログでは、季節ごとの農作業の様子に加えて、自分が日頃頭に浮かべているとりとめもない思考の残滓を半ば備忘録という形で書き綴っていますので、また機会があればお付き合いいただければ幸いです。
それでは!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
