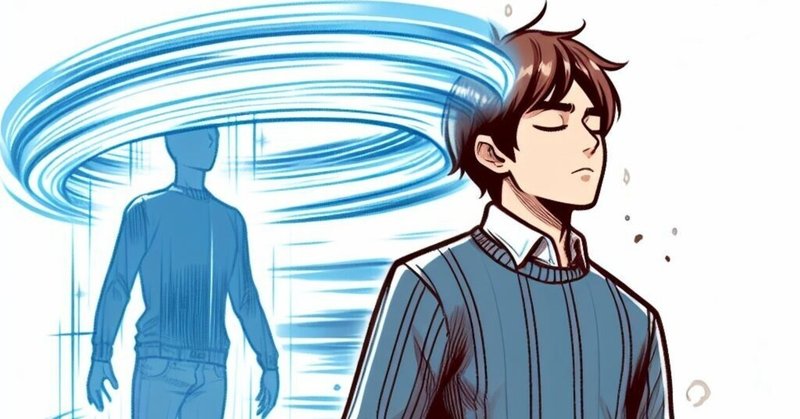
【小説】 飛びます 飛びます(その2)
「志津香…。君こそ今どこにいる?誰と一緒なの?」
思わずそう問いかけると、わずかな沈黙のあと、電話はプツンと切れた。
僕は、電話をかけ直そうとして思いとどまった。
頭の整理が全然できなかったからだ。
何が現実で、何が夢で、何が起こって、何を見たのか、今の電話だって本当にあったことなのか、自分に自信がなくなっていた。
まずは一旦落ち着いて、志津香が帰ってきたらちゃんと話をしようと思った。
その夜はソファーでまんじりともせず朝を迎え、夏美を保育園に送ったあと、職場に年休の電話を入れた。
それからまたソファーに座り込み、何をするでもなくずっと死んだようにボンヤリとしていた。
お昼を過ぎた頃、玄関のドアの鍵がカチャリと開く音が微かに聞こえた。
しばらくすると、やつれた顔の志津香が薄手のコートと小さめのキャリーケースを手に、ふらふらとリビングに入ってきた。そして、ソファーに座っている僕を見て、目を見開いて立ちすくんだ。
「お帰り、志津香。お疲れ様。ずいぶん早かったね。大雪だったけど飛行機は飛んだの?」
時間が止まったのかと思うほどの数秒間の沈黙のあと、
「……ただいま…。飛行機は…飛行機は、なんとか飛んで、それよりも昨日はごめんね、私、変な夢を見たみたいで、寝ぼけて夜中に電話しちゃって、びっくりしたでしょ、私、何か変なこと言ったでしょ、ごめんね、そのあとすぐまた寝ちゃって、スマホのバッテリーは切れちゃうし、充電器を持っていくのを忘れちゃうし、あ、今日はなんで家にいるの?平日でしょ?体調が悪いの?大丈夫?病院に行った?」
志津香はその場に立ったまま、絞り出すように早口でまくし立てた。
「僕は…大丈夫だよ。疲れたでしょ?コーヒーを淹れるから着替えておいで。」
「うん…。」
志津香はまるで僕から逃げるように寝室に入っていった。
僕が機械的にコーヒーを淹れ終わると同時に、普段着に着替えた志津香がリビングに戻ってきて絨毯の上にぺたんと座った。志津香は何か言いたげに僕を見たけれど、その目は明らかに泳いでいた。僕は、緊張のあまり震えだそうとする手を必死に抑えながら、ローテーブルの上におそろいのコーヒーカップを2つコトンと置いた。
ソファーに腰掛けた僕は、動揺を悟られないように、努めて明るい声で聞いた。
「昨日はびっくりしたよ。いったい、どんな夢を見たの?いや、実は僕も昨日変な夢を見ちゃってさ。」
志津香がピクッと反応して僕を見た。
「…どんな夢だったの?」
「よく覚えていないんだけどさ、志津香が僕の知らない男と仲良く手を繋いでどこかに行っちゃう夢だったような気がする。だから、僕もとっさに変なこと聞いちゃった。ごめんね。」
大嘘だ。そんな生易しい夢じゃない。僕はその夢を鮮明に覚えていた。部屋の中のねっとりとした空気、絡み合うようなキス、黄金色の月明り、東京タワー、志津香の美しい裸身、「なんで…。」と言った志津香の唇の動き、相手の男の整った顔、僕は全部覚えていた。
「夢なのに嫉妬するなんて笑っちゃうよね。ホント、自分が情けないよ。志津香がそんなことするわけないのにね。」
自分でも、最後の言葉に力が入ったのを自覚していた。でも、それを止めることはできなかった。
志津香はこわばった顔で僕の話を聞いていたけれど、突如スイッチが入ったかのようにいつもの柔らかな表情に戻って言った。
「ごめんね。泊りの仕事が多かったから不安にさせたよね。でも心配しないで。私はあなたと夏美がいるから、こうして生きていけるの。安心して好きな仕事もできるの。私が帰る家はここしかないの。昨日…あなたに突然捨てられる夢を見たの。それがつらくて、悲しくて、耐えられなくて、とっさに電話しちゃったんだと思う。私の人生にはあなたが必要なの。あなたが私を必要としてくれる限り、いえ、たとえ必要としてくれなくてもずっと一緒に居たい。あなたのいない私の人生は想像できないの。それだけは信じて。」
話し終えた志津香の顔は、いつの間にかテレビの画面で観る大人の雰囲気を纏ったしっとりとした表情に変わっていて、それが僕を余計に不安な気持ちにさせた。
僕は嘘つきだ。
志津香もたぶん嘘つきだ。
でも僕は志津香の言葉を信じることにした。
昨日見た光景は夢だったと信じることにした。
志津香の電話も偶然だったと信じることにした。
そして、志津香も何かを信じ込もうとしているように見えた。
それから僕らは冷めたコーヒーを飲み、遅い昼食を宅配で済ませ、何事もなかったかのようにたわいない会話をぎこちなく交わし、久しぶりに夫婦二人で保育園に夏美を迎えに行った。夏美はパパとママが二人で迎えに来てくれたことをピョンピョン飛び跳ねながら体全体で喜んだ。
それから半年が経ち、いつもの日常が、いつものように過ぎていった。
志津香にはようやく専属のマネージャーが付くようになった。ドラマにも呼ばれるようになり、バラエティー番組でも自分のポジションを確立した。仕事は前よりも順調なようだった。
夏美は近所のカトリック系の幼稚園に入園し、友達も増えた。
僕はと言えば、相変わらず家事と育児に追われながら、経済産業省が景気回復のために突如立ちあげた補助金をぶんどるために奮闘していた。
僕ら3人は以前と変わらず仲良く穏やかに過ごしていた。
ただ、僕と志津香は、互いに口にしてはいけない、触れてはいけないことがあることに気づかない振りをしながら暮らしていた。だけど、それに触れた時点でこの幸せな家庭が一瞬にして崩壊するということだけはハッキリと分かっていた。
その日、僕は午前中を無意味に長いミーティングに費やしたあと、気分転換に昼ごはんを食べに外に出た。なじみの小汚いラーメン屋に入り、店の白髪頭の親父さんに軽口を叩きながらいつものように担々麺と半チャーハンのセットを頼んで店の隅のテーブル席に座った。いつもそこそこ混んでいる店なのに、珍しくその日に限って僕以外に客はいなかった。親父さんは、僕の注文したセットを持ってきたあと、厨房で電子タバコを吸いながら新聞を読み始めた。
僕は、ほどよく辛い担々麺を一気に食べ終え、年季の入ったガラスコップで中途半端に冷たい水をゴクゴクと飲み干していると、突然目の前が真っ暗になり、フッと体が浮かぶような感覚に捉われた。
『あ、来た。』
僕はとっさに椅子から立ち上がった。
その瞬間、僕はどこかの騒がしい雑踏の中に立っていた。右手は空のコップを握りしめたままだ。
でも今度は冷静だった。いつかまた前と同じことが起こる強い予感がしていたからだ。
そして、これが夢だとしても現実だとしても、必ず近くに志津香がいるはずだと思った。
視線を左右に動かすと、少し先にあるカフェからサングラス姿の志津香が小走りに出てくるのが見えた。少し遅れて、40代くらいの見覚えのある端正な顔立ちの男が出てきて、志津香に追いつき並んで歩き出した。僕は、少し離れて二人の後を追い始めた。男は志津香に盛んに話しかけていたけれど、志津香は男を無視しているようにも見えた。
男は、足を止め、いきなり志津香の右手首を掴むと、路地裏の方に向かおうとした。
男の手をやんわりと振り払い、弱々しく抵抗する志津香を見て、僕はとっさに二人に向かって駆け出した。
僕は怒りに身を任せて少し手前から右手のコップを力いっぱい男に投げつけ、「おい!やめろ!」と大声で叫んだ。
僕の叫び声に、二人が振り返ろうとした瞬間、またフッと宙に浮かぶ感覚に襲われて思わず目を閉じた。
目を開くと、小汚いラーメン屋の中にいた。手にしていたコップは、どこにもない。
「おう、兄ちゃんいつの間に戻ってきた?急にいなくなったから、食い逃げされたかと思ったぜ。はっはっは。」
「親父さん、僕、どれくらいの間いなくなってた?」
「うーん、3分くらいかな?」
やっぱり夢じゃない。これは…現実だ。
「親父さん、ごめん!お代はここに置いておくね!」
僕は、テーブルに千円札を置いて外に飛び出した。
そして、すぐに志津香の携帯に電話をかけた。
呼び出し音が鳴るが志津香は出ない。
留守番電話メッセージが流れてきたので、電話を切り、焦りながらもう一度かけ直す。
やっぱり出ない。もう一度かけ直そうとした時、志津香から電話が入った。
「志津香!大丈夫か!」
「えっ?えっ?何が?どうしたの?」
「今、どこ!?」
「渋谷だよ。今日は街ロケがあるの。もうすぐ集合場所に着くところよ。」
「大丈夫?何かあったんじゃない?」
「…大丈夫だよ。ちょっとしたトラブルがあったけど…。なんとかなったから。」
「本当に…本当に大丈夫なんだね?それなら良かった…。もし、何か困ったことが起きたらすぐに連絡してね。とにかく無事で良かった…。じゃあ、電話を切るね。」
「あ、ちょっと待って!さっきあなたの声が聞こえたような気がしたんだけど、あなたも渋谷にいるの?」
「…いや、役所の近くでごはんを食べてるよ。」
「…そう。……ありがとうね。」
「何…が?」
「なんでもない…。」
ちぐはぐな会話を終えた僕は、その場に呆然と立ち尽くした。
僕が今、志津香のところに「飛んだ」のは紛れもない現実だ。
ということは、前に「飛んだ」時に僕が見た光景も現実ということだ。
今まで無理やり塞いできた心の傷口がまたパックリと開いてビュウビュウと血を吹き出し始めた。
そして、志津香だって今回のことで確信したはずだ。
もういつまでも現実から逃避してはいられない。
どうやって話を切り出そうか数日間悶々と悩んでいた夜、バラエティ番組の収録から帰ってきた志津香が言った。
急に明日から4日間のハワイロケが入ったこと、事務所の先輩が急病で倒れたので代役として白羽の矢が立ったこと、お世話になっている大物芸人さんの還暦お祝い企画なので断れないこと、をなぜか浮かない顔で僕に告げた。
そして意を決したように、ロケから帰ってきたら話したいことがあると僕の目を真っすぐに見つめて言った。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
