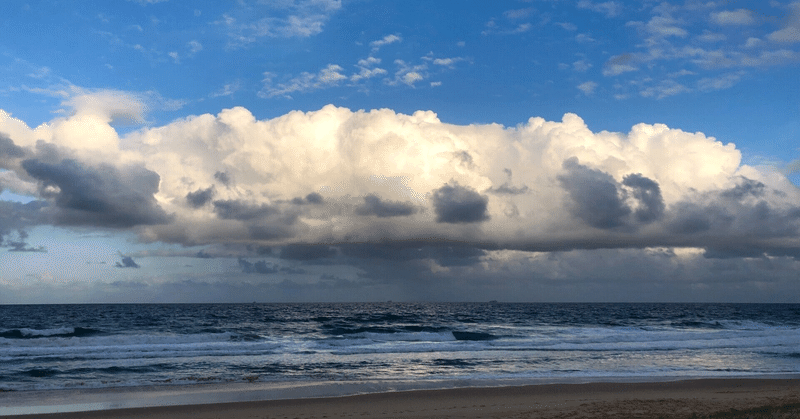
面白さのために、ストーリーの変化量を求めて
ある日、いつものように会社や学校から帰ってきたら、自宅が空き地になっていた。朝、目覚めると虫になっていた。両親から突然、自分に婚約者がいることを告げられた──
面白いストーリーのために欠かせないのは、変化量である。あげた例はどれも導入部分のことであるが、ストーリーの中のいくつかの箇所同士は、とにかく変化量が多いほうが、ストーリー的に面白さが増す。それというのは、
・冒頭と、事件が起こった後
・事件を解決しようと決意した時と、事件が解決された後
・事件解決のたの作戦の、前半と後半
特に、これらの3組は、それぞれの変化が劇的であるほど、ストーリーは基本的に面白くなる。
第一に、何も起こらないはずの冒頭の日常と、事件が起きた後の惨状は当然のことながら、急転直下のほうが感情が揺れ動いて面白い。そんなこと起きるはずがないという予想を裏切って、その事件は起こってしまう。
第二に、事件解決に着手した瞬間と、解決した後の瞬間だ。ここはもっとも重要である。なぜなら、それらは普通に考えても大きな変化があるものだが、「どのように解決したのか」は置いておいて、ありえないくらいに状況が一変している方が面白いからである。
この2つは基本的に、多くのストーリーにおいてここだけでは整合性が取れないはずである。「世界の滅亡の危機をどうにかしようと立ち上がる」→「平和な世界が訪れた」。「とことん嫌われている相手から好かれようと努力する」→「2人は幸せな愛を育んでいる」。「追ってから逃げつつ冤罪を晴らそうとする」→「全ての誤解を解き、平穏な日常を取り戻す」。
こんなもの、整合性が取れるほうがどうかしている。というよりも、この部分の整合性をどう取るのか、ということは、私達がストーリーに求める1つの面白さなのだ。
だからこの「事件解決に着手」→「事件解決後」は、まったく、突拍子もないほど、想像できないくらいに変化している方が面白い。
第三に、事件解決の作戦の前半と後半だ。これはグラデーションである。そして、期待どおりに変化していくことが求められ、変化量そのものよりも、それがどのように変化していくか、ということに注目される部分だ。
作戦の前半は、当然に事件が最大の力を振るっていて、登場人物たちは不利な状況である。しかし、それが少しずつまともになってきて、努力とか友情とか、挫折とか、反省とか、奮起とか、そういった試行錯誤により有利な状況に変わっていく。
そのような、ある種ゆるやかであるが、しかし劇的なことも起こりつつ、事件は解決へと進んでいくという変化が必要なのである。この「事件を解決するための作戦」は、ストーリーのオープニングとエンディングを繋げるための重要な橋渡し役であるから、劇的な出来事を含みながら、堅牢にストーリーの変化が表現される。
しかし終わってみれば、この作戦の前半と後半では、ずいぶんと景色が違って見える、というのが面白さなのだ。
このように、ストーリーの面白さとは変化量である。ある物事や状況や感情が、別の場所では少しどころかまったく異なっているという体験。それはなぜか? と考えてしまう知識欲。現実では味わえない急転直下。しかし必ず解決の糸口があるという希望。そういった、ストーリーの鑑賞者にとっての感情の揺れ動きを引き出すために、変化量というのはとてもとても大切である。
ストーリーが単調と言われてしまうのは、この変化量のなさに尽きるのだ。だからストーリーが面白いと言われるためには、感情を揺り動かす……揺り動かさざるをえない、変化量こそが、求められている。
※このテーマに関する、ご意見・ご感想はなんなりとどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
