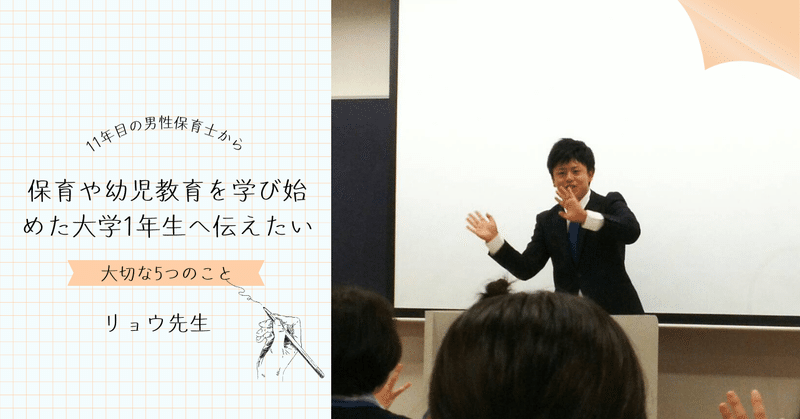
保育や幼児教育を学び始めた大学1年生へ伝えたい、大事な5つのこと
はじめに。こちらの記事は後半部分が有料となっています。
そして、この記事全体の内容としてはタイトルにもありますように、保育や幼児教育を学び始めた大学1年生、短大1年生、専門学生1年生に向けた内容です。
なぜか?それは私が3年間、上記の学生らに毎年お話させてもらっている内容をそのままこの記事に掲載しているからです。ほぼ原稿に近いです。
無料記事部分はその年によって変えていますが、本題に関してはほぼブレていません。それが11年間、保育に関わったものとして感じたことだからです。
実際、学生のみなさんからも高評価を毎年いただいております。学校の講義ではなかなか伝えられない内容だからでしょう。
もちろん学生ではなく、興味を持ってくださった方でもご一読してもらえると嬉しいです。
注:本記事には画像はありません。また講義で使用した画像は権利上、この記事には載せておりませんのでご承知おきください。なお、記事の部分は有料エリアには含まれておりません。
前置きが長くなりました。
それでは、どうぞ!!
オープニング
まずはこちらの画像を見ていただきたいと思います。
この画像を説明すると、雲梯の下にビール箱を積んで渡る遊びをしているところです。
このビール箱は子どもたちが自分で持ってきて積みました。
さて、この画像の遊び方について皆さんはどう思いますか?
私は2つの考え方のパターンを想像しました。
ひとつ目は、
“雲梯の下にものを置くと万が一転んだ時に危ないので、どかして遊ぼう“
“足場があることで雲梯が出来るようになっているように錯覚すると危ない。自分だけの力で昇り降りできる力が育てられるように、足場は外そう“
という考え方。
ふたつ目は、
“雲梯に興味はあるけれど、まだ手が届かない。けど、「やってみたい」という気持ちをまず尊重してあげたいから見守ろう“
“ビール箱がある状態で雲梯の面白さや、これならできるという自信を積み重ねていったら、「今度は一つ減らしてやってみようか」という遊びに繋げていき、雲梯が出来るようになっていきそう“
という考え方。
皆さんはどんなことを想像できそうですか?
もう1枚、画像いってみましょう。
これは、鉄棒の下に敷いてある運動用マットですが、この写真の園では靴を脱がなくても良いルールになっています。
ところが、この日は数人の子どもたちが靴を脱いで上がって、鉄棒をしはじめました。
その姿を見て、
“マットの上だけど、外遊びだから靴を脱がなくていいよ“と伝えるのか、
マットの上が特別な空間と認識して靴を脱いでみた子どもたちの気持ちを汲んで、“このマットから降りるときは靴を履くんだよ〜“と伝えて、その姿を見守る。
じゃあ、そこでおままごとが始まったら?
“マットは運動にだけ使うもの“とするのか、
“なんかお家に見立てているから邪魔せず見守ろう“なのか、
皆さんはどんな言葉を子どもたちにかけられそうですか?
自己紹介
それでは改めまして、皆さんこんにちは。リョウ先生と申します。
今年もこのように、大学1年生の皆さんの前でお話しをする機会をいただき、ありがとうございます。
冒頭ではまず2枚の画像を見ていただきましたが、いかがでしたか?
今、私が何をしているのか?と問われ、答えるとなると…。
保育教諭として働きながら先の画像のように保育のあらゆる場面で“こういう考え方もあるよな“ということを日々探して、考えて、文章にしています。
今年で3回目となるこの講義の時間ですが、去年、一昨年と圧倒的に違う部分があります。それは私が3月末で10年間働いた保育園を離れ、4月から関西に移住し、働き始めているということです。
今の園を選んだのは、直感。「この園は楽しそう。成長できそう。なんかワクワクする」という自分の感覚だけを信じて今に至ります。
自分の直感は正しかったなぁと思うのは、毎日が刺激的で学ぶことが多いからです。
毎日が刺激的の正体
じゃあ何が刺激的なのよ、ということですが。
それはこれまで自分が当然のように思っていた知識や経験が必ずしも全てではないと思う場面が多いからです。具体例を挙げてみようと思います。
①施設長(園長)が男性なのか、女性なのか
②子どもの人数
→以前は園児数90名程度。現在は140名程度。以前していたような保育の展開の仕方では保育が回らない時もある
③一斉保育なのか、自由保育なのか
④職員の休憩の取り方
⑤外部講師の指導有無
などなど。10年間勤務した園の保育の方法と、現在働いている園の保育の方法の違いが多く、それがすごく刺激的に感じるのです。
冒頭の写真に対して、それぞれ2通りの考え方を述べましたが、あれは想像ではなくて、私の経験談です。遊び方1つにしても、あそこまで考え方に違いが出てくるのです。面白くないですか?
ぶれない部分を獲得する
私は今の園で働きながら、
保育の方法に正解/不正解のレッテルを貼らないようにする
ことを大事にしています。もちろん子どもを叩く、恫喝する、汚い言葉を浴びせるなどは不正解とかではなくてそもそも論外です。
その園で、その保育方法が行われているのには理由があるわけで、これは正しくてこれは間違ってるみたいな優劣をつけてしまうと、保育が面白くなくなると思っているからです。
だから、こういう方法もあるのか!と捉えることを心がけています。
ということで、何を今さらということですが、
園が違えば保育の方法に違いが出てくるのは当然である。のですが、
その保育の方法はあくまで子どもたちや保護者と関わる手段の一つでしかなくて、
まず、保育者としてのベースが出来ていることはどんな園でも求めらることになります。
そのベースの、さらなるベース。ここを作るのが大学時代の学びになります。
ようやく核心に辿り着きました。ここからがこの講義の本題です。
ここから先は
¥ 680
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
