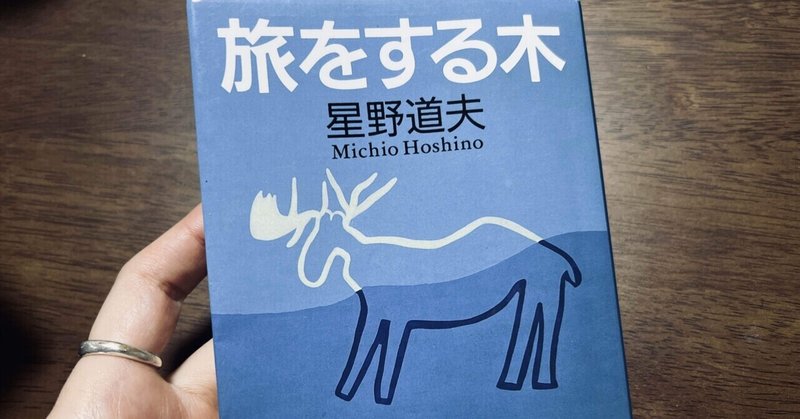
『旅をする木』を読んで
読み終えたばかりの本の表紙を眺めながら、遥か極北に広がる大自然と人々の暮らし、その歴史に想いを馳せる。
『旅をする木』(文春文庫)を読んだ。長年、アラスカに生活の拠点を置き活動された写真家・星野道夫さんのエッセイ集である。
冬の寒い日の読書に、オススメしたい一冊をご紹介。
*このnoteは『旅をする木』のネタバレ・引用を含む、読書感想文です。未読の方はあらかじめご承知おきください。
*
コロナ禍以降、Kindleを導入して、紙の本を買うにしてもAmazonの利用頻度が格段に増えた。本屋巡りをするような気分で、ちょっとした時間に「次は何を読もうかな」と、スマホの画面を眺めるのが、すっかり当たり前の日常と化している。
ある日、何気なくAmazonのアプリを立ち上げて、本から本へと移動していると、とあるタイトルに心惹かれた。
『旅をする木』
星野道夫
やさしい青色の表紙に描かれているツノの生えた生き物の絵が愛らしい。
本の紹介文を読むと、アラスカ(厳密に言うと、フェアバンクスでオーロラを観ること)に長年憧れている私にとって、とても魅力的な一冊に感じられた。
ただ、その時は、とりあえず他の気になった本たちと一緒にポチッとほしい物リストに追加して、その場から離れてしまった。
私の場合、ここから実際に手に取って読むに至る本は2〜3割。一冊一冊を読むのにそこそこ時間がかかるタイプなので、リストを増やすばかりで、長い間手付かずになってしまうことが多い。
ところが、『旅をする木』は違った。
それからほんの数日後、ある写真展を観に行った帰り。ギャラリーショップに立ち寄り、棚に陳列されている本を端から順に眺めていたとき、見覚えのあるタイトルを見つけて、思わず足を止める。青色の背表紙に並ぶ『旅をする木』という白い文字が独特の存在感を放っていた。
機械的なアルゴリズムが作り出す出合いとは違う、運命的な何かを感じる思いがけない再会にドキッとして、「きっと、これは、今読むべき本だ!」と感じた。
*
そうして『旅をする木』を読み始めた1月の終わり。
日本列島には<10年に一度の記録的寒波>がやってきて、途中、あまりの寒さに震えて手元のスマホで気温を調べると、私の住む地域は「−3℃」と表示された。
この本の中には「マイナス二〇度」「マイナス四〇度」「マイナス五〇度」という言葉が当たり前のように登場する。え?どういう世界なの?と、思わず固まった。
私は何度も星野さんが触れた極北の空気を想像してみた。
どんな冷たさだろう。
どんな感覚だろう。
どんな匂いがするだろう。
アラスカのそれとは比べ物にならないだろうけれど、今自分を取り囲む染み入るような冷たい空気と窓の外を激しく舞う白雪に、私の想像力はますます刺激された。
そんな10年に一度の寒さの中、星野さんの言葉にじっと耳を傾けるような気持ちで、1ページずつ読み進めていった。
*
『旅をする木』は、「アラスカの雄大な自然を讃える本」ではなく、「アラスカの自然を通して人間の生と死を見つめる本」だ、と思う。
極北の大自然と向き合うことが、常に人間の暮らしを見つめることと繋がっているように感じられる。
33篇の中には、アラスカの地に暮らす人々がたくさん登場する。先住民族の人々や、開拓時代にやってきた人々、アラスカに魅せられ他の地から移り住んできた人々。
星野さんはそんな現地の人々と積極的に交流し、彼ら/彼女らの声に丁寧に耳を傾け、自ら広大な自然へと足を踏み入れ、言葉を紡いでいく。
そんな星野さんの文章からは、<自然への畏敬の念>と<人間の営みを愛しむ心>の両方が滲み出ている。
その二つは星野さんが日本で暮らしていた頃から持っていたものかもしれないけれど、アラスカに暮らす人々からの影響も大きかったのではないか、と私は思う。
『ビーバーの民』という節で、とある夏の夜、星野さんはアサバスカン・インディアンのチーフであるデイビッド・サーモン氏と会い、彼らの祖先にまつわる物語を聞いた後の心情を次のように綴っている。
未踏の大自然……ぼくが魅かれてきた、この土地のもつ手つかずの広がりが、今は少し違って見えた。たった一人の古老のインディアンに会ったことで風景が何かを語り始めていた。
星野さんのアラスカでの暮らしは、こうした経験の連続だったのではないだろうか。
そして、今度は星野さん自身が語り部の一人となって、日本の読者に向けて、自然の美しさと厳しさ、先人から伝え聞いた歴史や知恵、アラスカで知り合った人々の暮らしや人間の生と死について、静かにあたたかな言葉で語りかけてくる。
この一冊を読み終えたとき、私の中の憧れの地であるフェアバンクス、そしてアラスカの自然に対するイメージもまた少し塗り替えられていた。
そして、想像で終わらせずに、いつかアラスカに降り立ち、上空を舞うオーロラを眺めながら極北の空気を自らの五感で味わいたい、という夢がより一層膨らんでいる。
*
私が『旅をする木』の中で最も気に入ったのは、『生まれもった川』という節だ。
人間の風景の面白さとは、私たちの人生がある共通する一点で同じ土俵に立っているからだろう。一点とは、たった一度の一生をより良く生きたいという願いであり、面白さとは、そこから分かれてゆく人間の生き方の無限の多様性である。
『生まれもった川』の冒頭である。私はこの「人間の生き方の無限の多様性」という言葉に希望を感じた。と同時に、現代の社会がより人間の多様な生き方を受け止められるような寛容で柔軟な世界になっていって欲しい、と改めて思った。
少し話が逸れてしまうけれど、私は長い間、漠然と、「人にはある一つの目指すべき生き方がある」と思い込んで生きてきた。うまく言葉に出来ないのだけれど、自分自身が望む/望まないに関係なく存在する「社会が求めている模範的生き方」…とでも言うのだろうか。
それは、ざっくり言葉にすると、<一生懸命学び、向上心を持って育ち、自分の好きなことを見つけ、その延長線上にある職に就き、キャリアを積み、互いに尊敬し合える誰かと出会い、共に生きる>というような道だ。
今、文字にしてみると、色々と見えていないことや具体性に欠ける点も多いし、偏狭的だし、「なんだかな…」と思う。でも、まぁ、10〜20代の頃の私は私なりにそんな<道>を目指してもがいていた。
だからこそ、大学を卒業する頃、徐々に自分が目指していた道から外れていっていると気づいたとき、猛烈に焦り、無力感に襲われた。「真面目に必死にやってきたのにどうして…」という想いだった。
それでも、私は学生から社会人になり、会社員として、なんとか<道>に沿って行こう、せめて見失わないようにしよう、という想いで歩き続けた。
けれど、20代後半に差し掛かったところで、私は突然自分の身体に違和感を感じ始める。みるみるうちに体調を崩していき、遂にはいつも通りの日常生活を送ることもままならなくなった。
そして、幸か不幸かそれを機に、あらゆるモノの見方を見直すことになった。考え方を変えなければそれ以上進めなくなった、と言った方が正確かもしれない。
とはいえ、基本的に頭は働かず、身体を動かすのもやっとの状態だったので、急激に考え方が変わって劇的に大変身を遂げた!というわけではない。
「そもそも<目指すべき道>って何…?私自身が望んでいる生き方だっけ?もっと私らしい生き方があるのでは?」と、長年自分の根っこの部分にあった価値観を見直してみようという考えになったのも、正直、つい最近のことだ。
ここで、『旅をする木』に話を戻したい。
『生まれもった川』という節では、フェアバンクスに暮らす星野さんの友人ビル・フラー氏が登場する。フラー氏は非常に多彩な人生を送ってきた人で、その経歴の多様さにはとても驚かされる。彼の生き方を、星野さんはこのように表現している。
誰もが何かを成し遂げようとする人生を生きるのに対し、ビルはただ在るがままの人生を生きてきた。それは自分の生まれもった川の流れの中で生きてゆくということなのだろうか。
勿論、フラー氏の人生も楽しいことばかりではなかっただろう(むしろ深い悲しみも知っている人だという記述もある)。けれど、「世の中にはこんな生き方をしている人もいるのか」と知ると、それだけで、とても励まされ、救われた気分になった。
星野さんがたまにフラー氏の元を訪れたくなった気持ちもわかる。この節を読んで、私も彼の生き方にとても勇気づけられた。
*
私は今も自分の身体と心の状態と向き合いながら、他の誰でもなく自分自身が心地いいと思える生き方を模索している途中だ。「在るがままに生きる」という言葉とは、現状まだまだ程遠いけれど、トウヒの木のように私なりの旅を続けながら、迷った時にはきっとまたこの本に手を伸ばすだろうと思う。
*
『旅をする木』を読み終えた頃には<記録的寒波>は過ぎ去り、空には久しぶりに晴れ間が広がっていた。
外へ出てみた。
髪をなぶる冬の風が、心地よかった。
2023.02.05
