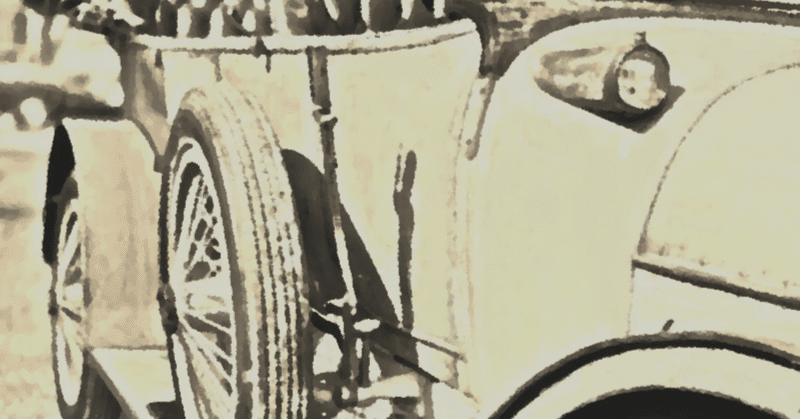
[短編小説]イターラ・フェルナンド一世・マルヌ川
けたたましい自動車のエンジン音がアパルトマンの前で停まったかと思うと、しばらくして玄関の呼び鈴が鳴った。
ドアを開けるとマリアが立っていた。以前と変わらぬちょっとはにかんだような可愛らしい笑顔を久々に見られた。最近流行りのパンツルックがよく似合っている。
「サブロウ、久しぶりね」
「マリアじゃないか。今自動車で乗り付けたの、まさか君じゃなかろうね」
するとマリアは事も無げに「もちろん私よ」とすまして答える。
僕は「へえっ」と首をすくめながら彼女を居間に招き入れた。
マリアはスペイン出身の女流画家だ。実家が随分裕福らしく、実際のところ画業も半分道楽のように見受けられる。
かくいう僕もまた画家である。もちろん道楽でやっているつもりは無いが、日本に居る僕の家族や友人たちにはそう思われているかもしれない。まあそう思われても仕方のない、まだまだのヒヨッコだ。
物音を聞きつけて奥の間からベンジャミンが現れた。彼はアメリカから来た彫刻家で僕とアパルトマンの家賃を折半して一緒に住んでいる。マリアとも旧知の仲だ。
「やあ、マリア。最近見かけなかったけど、一体何処に行ってたんだい?」
ベンジャミンの問いにマリアは変わらぬ笑顔で答えた。
「イタリーよ」
「ええっ?」僕もベンジャミンも驚いて思わず顔を見合わせてしまった。
「聞こえたでしょう、さっきのエンジンの音。クルマを買いに行ってたのよ」そう言って通りに面した窓に向かって親指を振ってみせる。
二人して窓から顔を出してみると少し古めかしい形の見慣れぬ自動車が駐車してあった。
恐慌ですっかり冷え込んでしまった現代世界とはまるで無関係のような道楽っぷりに僕はすっかり呆れてしまった。
「イタリーまで旅行した上に自動車まで買ったってのかい? この不景気にどうなってるんだ、まったく」ベンジャミンも同じように呆れ顔で声をあげた。
「まあ、そう言わないで。イタリーの知り合いが格安で譲ってくれるっていうものだから、思い切って買っちゃったの」
お茶を飲みながら話を聞くと、前から探していた自動車なのだと言う。
イタリーから船で地中海を渡って昨晩ようやく帰り着き、つい先刻まで寝ていたのだそうだ。で、寝覚め一番この新しいクルマを僕らに見せびらかしたくて乗り付けてきたという訳なのだった。
そういう事なら、と外に出て件の自動車を間近に見せてもらう事にした。
「イターラじゃないか! こりゃすごい!」
ベンジャミンは一目見るなり驚きの声を上げた。
残念ながら僕は自動車には疎いのでよく分からない。クルマ好きのベンジャミンに聞いてみると、このイターラというのは中々伝統ある自動車会社のようなのだ。
ちょうど僕らが生まれた頃に北京からパリまで行われた ――ベンジャミン言うところの"伝説的な"―― ラリーカーレースで見事優勝したのがこのイターラ社製の自動車だったという。
マリアによれば、これは先の大戦前に製造されたものらしい。なるほど古臭く見えたのも無理は無い。しかしエンジンはロータリーとか云う、今見ても先進的で特殊な方式のもので、それが故に手に入れたかったのだそうだ。イターラ社自体は去年だか一昨年だかに無くなってしまったというから尚更貴重品だ。
「二人とも、どう? 今度の週末はドライブと洒落込まない?」
僕にもベンジャミンにも断る理由は無い。当然二つ返事で承諾した。週末が楽しみだ。
* * *
数日後、僕らの住むアパルトマンの前に再びイターラが停まった。
マリアはこの間とはまた違った装いのパンツルックで現れた。曰くパンツルックは大層楽で、自動車の運転もしやすく、もうヒラヒラのスカートなど穿いてられないという。ただしパーティーの時は別だけどね、と自説を締め括って彼女は笑った。
一方僕らも活動的ながら出来るだけ洒落た服を選んだ。折角レディーとのお出掛けなのだから。
中々良い感じの若者グループになったんじゃないかな。オホン。
僕らが乗り込むとイターラは大きな音を立て、しかしそれとはそぐわぬような滑らかさで進みだした。エンジンは至って快調で僕らの住むモンパルナスからセーヌ川のほとりまではあっという間だ。今日は幸い天気が良く、ポカポカの陽気で、風を切って走るのは大変心地良い。
マリアの運転は落ち着きのある堂々としたものだ。助手席のベンジャミンは後で運転を替わってもらえる約束を交わした事もあってか上機嫌で地図係をしている。
一方の僕はと云えばクルマの運転は全く分からないので専ら後ろの席に陣取り、マリアとベンジャミンの後ろ姿と街並みの流れていく様子を代わりばんこに眺めていた。
セーヌ川のほとりを西に進むとじきにエッフェル塔が見えてきた。
高さ三百メートルの途方も無い建物だ。数年前にアメリカに何とか云うビルジングが出来るまでは世界一の高さを誇ったという。
「クライスラービルジングって云うんだよ。ニューヨークにあるんだぜ」ベンジャミンが誇らしげに言う。彼は事ある毎に大都会ニューヨークの自慢をするのだ。ニューヨークには行った事が無いが東京よりも大きな街、その一面に高いビルが建ち並ぶと聞く。さぞかし壮観だろう。
そのうちイターラはエッフェル塔の脇を走り抜け、気付けばイエナ橋を渡っていた。もうしばらく走れば今度はエトワール凱旋門だ。
マリアは凱旋門の前にイターラを停めると、トランクから見慣れぬ小さなカメラと三脚を取り出した。最近ドイツのコダック社から発売されたレチナというカメラで、フィルムの装填が大変簡便で使いやすいのだという。
凱旋門とイターラを背景に皆で何枚か記念写真を撮ってまた出発した。今度はベンジャミンと交代だ。彼の運転するクルマに乗るのは初めてだが中々上手いものである。話を聞くと母国アメリカでもよく乗り回していたそうだ。
ベンジャミンの駆るイターラはシャンゼリゼ通りを抜けて、またセーヌ川のほとりに出た。そのまま川沿いに走ると、あっという間にルーブル宮殿の辺りに到着だ。この先にある橋を渡れば六区、そして六区を通り抜ければ十四区、即ち懐かしのモンパルナスという訳だ。
ベンジャミンはマリアとの約束通り、橋の手前でイターラを停めた。
運転席を交代したマリアは僕とベンジャミンの方を交互に向きながら、「この橋を渡ってモンパルナスに着けば今日のドライブは終わりって事になるけれど、もっと走ってみたくはない?」と意外な提案をしだした。
「セーヌ川はこの先で支流のマルヌ川と分かれるのは知ってるでしょう? マルヌ川沿いの田舎に私の祖父が遺した別荘があるの。一つそこまで行ってはみない?
もちろんご馳走するわ。どうせ二人とも予定は無いんでしょう?」
僕は異存ない。ベンジャミンもまた然り。なら話は決まりだ。
すると早速ベンジャミンはまた運転させてもらう約束を取り付けた。よほど自動車の運転が好きなのか、それともマリアに良い格好を見せたいだけか。そういう意味では僕はかなり出遅れたという事になる。何となれば僕はマリアにメロメロなのだ。そしてベンジャミンもそうだ。つまり僕らは親友でもあり恋敵でもあるのだ。
そんな事は思いもよらない ――それとも分かっているのか?―― マリアの発案で、まずは近くのカフェで腹ごしらえする事にした。それから再出発だ。
マルヌ川は随分曲がりくねった川で、律儀に川沿いを走ると目的地までは一昼夜かかってしまう。しかしベンジャミンが地図と首っ引きで近道をマリアに指示してくれたおかげで至って順調に別荘へ向かう事が出来た。それ自体は良いのだが、またベンジャミンに良い所を取られてしまったかと思うと快くはない。
そのうち流れゆく景色にも飽きてきたので、皆で流行歌を歌ったり、めいめい勝手に自分の話したい事を交互に話したりなどした。
そのうちベンジャミンが、自分はニューヨークではアート・スチューデンツ・リーグという名のある美術学校で学んだのだと話し始めた。そして、今はパリこそが世界一の芸術の都だが、いずれニューヨークがそれに取って変わるだろうと熱弁を振るった。それほどに母校のアート・スチューデンツ・リーグでの日々は充実していたのだという。
「俺がパリに来る前年に入ってきた、ポロックって奴が凄かったんだ。彼は本物だね。きっとアメリカを代表する芸術家になるよ。もちろん他にも凄い奴がいっぱい居たんだぜ」どうだ、と言わんばかりのベンジャミンだ。
僕の出た東京美術学校だって負けてはいないぞ。そう言うとベンジャミンにもマリアにも笑われてしまった。西洋人にすれば日本人などはまだまだなのだ。悔しいところだが実際そうなので仕方ない。日清・日露、それに先の大戦を経て日本もようやく一等国の仲間入りをできるかと思ったがもうしばらくかかりそうだ。
「サブロウ、あなたはまずフジタよりも有名にならなくっちゃね」マリアは穏やかに言う。パリ、ことにモンパルナスでは藤田嗣治は未だに日本人芸術家のアイコンだ。彼を越えるのは並大抵の事じゃない。だがそれくらいの意気込み、野心がなければこの生き馬の目を抜くパリではやっていけない。「もちろんさ」と僕は答えた。そこに嘘偽りは無い。
「私もピカソやローランサンより有名になってみせるわ。もちろんそう簡単じゃないって事は分かってる」
彼女の志も大変高いのであった。正直ピカソの名前まで出るとは思わなかった。道楽などと侮って申し訳ない気持ちだ。
「俺だってカルダーより有名になってみせるさ。ハハハ」ベンジャミンは大きな体を揺すって笑った。「純粋なるエコール・ド・パリよ再び、だ!」
僕達もつられて笑った。まるでそれに応じたかのようにイターラのエンジンも唸りをあげた。
* * *
道を進むうち景色はどんどん長閑になっていった。田園が連なりところどころに木立がある。遠くの山には時折城郭らしき建造物が見えた。マリアの別荘はもうすぐだ。
別荘と言えば僕の実家もかつては持っていたのだ。恐慌のあおりで手放したと、ずっと前に手紙が来たのだが。
まだ景気の良かった時分に政治家や貴族院の連中に人気の別荘地・無乾町の一角に土地を取得して建てたのだ。僕が小学校に通っていた頃だったろうか。そこは海の近くで、夏休みには兄や姉たちとちょくちょく泳いで遊んだ思い出がある。
僕の家は所謂船成金というやつで、日露戦争や先の大戦で造船を手懸けて大儲けした。一代で財産を築いた父は、成金であるが故に社交界では下に見られ、また軽んじられ勝ちなのを引け目に感じているのだ。
別荘を建てたのも、三男坊の僕が画家を目指して東京美術学校に入り、あまつさえ洋行まで承知したのも、家柄に箔を付けたかったからなのだろう。
この辺りは無乾町とは違い海沿いという訳ではないが、やはり別荘地特有の雰囲気があるのか、何となく懐かしい気持ちになってきた。
やがてイターラが停まったのは、マルヌ川のほとり、開けた田園地帯の真ん中に立つ、古めかしくも小洒落た門の前だった。垣根に囲まれていてよく分からないが、別荘ということもあってか敷地はさほど大きく無さそうだ。
マリアは通用門の鍵を開けて中に入っていく。僕とベンジャミンはその後ろを付いて行った。
敷地の中は手入れの行き届いた庭園となっており、その向こうに瀟洒な邸が建っている。邸もきちんと手入れが為されているようだ。
と、玄関の扉が開いて一人のお爺さんが出て来た。少し腰が曲がっているものの、実に矍鑠としている。
「マリアお嬢様、随分急にいらっしゃいましたな」お爺さんは嬉しそうにそう言い、こちらに歩いて来た。
「ごめんなさいね、エンリケ。どうしても友達を連れてきたかったの。ほら、前に話したことのある仲良しの二人よ」
マリアは彼に駆け寄ってハグすると、僕達の方を向いて言った。
「彼は使用人のエンリケ。ずっとここの管理をしてくれているの。
エンリケ、こちらはサブロウ、日本人よ。こっちはアメリカから来たベンジャミン」
「ほほう、日本人……ということは中国よりもさらに東の方ですね。それにあなたはアメリカからですか。どちらの生まれで? ほうサンフランシスコ? 大陸の西の外れですな。どちらも随分遠くからいらっしゃったのですねえ。誠に結構な事ですな」エンリケは大層感慨深げな様子だ。
「エンリケ、二人にご馳走するって約束しちゃったの。何か出してもらえる?」
その言葉にエンリケは明るく応じた。「勿論ですとも、マリアお嬢様。在り合せの物しかございませんが、腕によりをかけてご用意いたしますぞ!」
エンリケは驚くほど素早い身のこなしで踵を返した。
「おおい、レオノール! マリアお嬢様がいらっしゃったぞ! 夕食の準備じゃ!」大きな声で邸内に呼び掛けながらエンリケは邸の中に入っていった。
「レオノールっていうのはエンリケの奥さんで、一緒に住み込んでこの別荘の管理をしてもらっているの。祖父の代から仕えてくれているのよ。私が赤ん坊の頃から可愛がってくれてね」
マリアはそんな話をしながら邸の中を案内してくれた。邸内は落ち着いてとても良い雰囲気だ。
まずは敷地の庭園とその向こうの景色を一望するガラス張りのサンルーム。ソファが備えられて談話室も兼ねている。次に大きな暖炉が特徴的な応接間。備え付けの戸棚には方々の国の珍しくも上品な土産物たちが飾ってある。さらに寝室。もちろん僕とベンジャミンに一室ずつだ。落ち着いた設えでアパルトマンのガタガタベッドとは天と地の差ほどもある立派なベッドが備えてある。
最後に大きな長テーブルが据えられた広間に案内された。テーブルには真っ白なテーブルクロスが敷かれ、料理が乗せられるのを待っている。設えられた調度品は些か古めかしいが、落ち着いた意匠の立派なものだ。
「今晩はここで夕食よ。楽しみに待っててね」
テーブルの向こうにある出入り口は厨房と繋がっていて、二人が忙しく働いている様子が見えた。
「エンリケとレオノールが早速調理してくれてるわね。二人の料理は絶品なのよ。スペイン料理とフランス料理の合いの子ってところね」
なるほど、料理は実に美味しかった。
加えてエンリケとレオノールが甲斐甲斐しく給仕してくれて大変良い心持ちだ。ことに葡萄酒が美味しくてつい飲み過ぎた。ベンジャミンも同様だ。
二人して眺めの良いサンルームのソファに座って酔いを冷ます事にした。
夜闇の向こうの山々から月が顔を出して実に風流だ。今宵は満月か。
「ところでサブロウ」ベンジャミンがおもむろに話を始めた。
「前々から思っていたんだが、マリアは一体何者なんだろう? イターラにレチナ、おまけに管理人付きの別荘まで。ちょくちょく外国へ旅行にも行ってるし、彼女の住むアパルトマンだって僕らのより大分家賃が高い。随分な金持ちだとは思わないか?」
ベンジャミンの口調はあくまで穏やかだが、抑えきれない好奇心もまた大いに含まれている。実のところその辺は僕も気になってはいたのだ。だって、もしマリアと結婚するなら知っておいた方が良いだろう?
そこへマリアが現れて話に加わった。
「別に隠してた積りは無いのよ。三人の友情がおかしくなっても困るなって思って、何となく言いそびれてただけ」
マリアは僕達の向かいのソファに座り、意を決した様子で話し始めた。
「……私はね、スペイン王家、トラスタマラ家の血筋なの」
もしかしたら貴族か大政治家の子弟辺りかと思っていたが、まさか王族とは。驚いた。ベンジャミンも目を見開いている。
「私の家系は十五世紀のアラゴン王、フェルナンド一世まで遡れるのよ。と言っても傍流のまた傍流。それに私の家はもう私だけなの。元々病弱だった母は私を出産してすぐに死に、父も跡を継ぐはずだった兄たちもスペイン風邪や戦争で皆死んでしまった……」
「そうなのか……」僕はなんだかお気楽な自分が恥ずかしくなってきた。ベンジャミンも同じ様子だ。しかしマリアは明るい声でこう続けたのだ。
「ま、だからこそ贅沢できるって訳なんだけどね。後先考えなくて済むもの。アハハ」
マリアのこの明るさにはいつも救われる。ますます好きになってきた。近いうちに ――ベンジャミンに抜け駆けされる前に―― 正式にお付き合いを申し込もう。無論結婚を前提にだ。それが日本男児のけじめというものだ。
「二人とも、宜しければお風呂に入ってね。それで今日はお休みにしましょう」
マリアは席を立った。「私はお先に休ませてもらうわ。何かあったらエンリケに尋ねてね」
「おやすみ、マリア」僕とベンジャミンはほぼ同時に言い、顔を見合わせた。目には見えないが僕らの間には火花が散っているのだ。
「今夜はとても月が綺麗ね」
マリアはサンルームのガラスの前で一時足を止めて外を眺め、微笑んだ。
「とても良い夜だわ」
* * *
「……サブロウ様……」
しわがれた声と共に肩を揺さぶられて目が覚めた。
ううん、誰だい……?
「サブロウ様、サブロウ様」
……もう、朝か?……とても眠い……。
目を開けると部屋は薄暗い。まだ夜も明けてないじゃないか。
橙色の灯りが揺れている。
ランタンだ。
ランタンを持ったエンリケ爺さんがベッドの前に立っている。
「どうしたんですか? エンリケさん。こんな時間に……」眠い目を擦りながら欠伸交じりに問いかける。本音を言えばすぐにでも布団に潜り込みたい。
「サブロウ様、夜分遅くに申し訳ございません。マリア様から大事なお話がございます。さ、これをお召しになって一緒にいらしてください」
マリアが……? 一体何事だろう。
僕は差し出された羽織りに袖を通しながらベッドを降り、エンリケの後を付いていった。
エンリケは邸内の一角に僕を連れてきた。昼間マリアには案内されてない場所だ。
「さ、こちらへどうぞ。マリア様がお待ちです」エンリケはそこに設置された分厚い大きな扉を開け、掌でその扉の奥を指し示した。ここからは一人で行かねばならないのか。
中は短い渡り廊下のようになっていて、その先にさらに扉があった。把手を捻ると、扉は滑らかに向こうへ開いた。が、室内は真っ暗だ。
途端に衝撃が後頭部に発し、目から火花が散った。思わず後頭部を抑えてよろめいた。誰の仕業か首を後に捻ろうとした途端にもう一撃! 更に間髪入れずもう一撃加えられると、最早意識が朦朧として身体の自由がすっかり利かなくなった。
それを見計らったかのように、(恐らくは二人組の)誰かが僕の両脇を抱え、たちまち薄暗い室内に引き摺り込んだ。
全く抵抗できぬまま着物を引き剥がされ、頑丈な丸太の杭へ後手に縛り付けられた。脛・腿・胸・首それぞれに革製と思しきベルトが掛けられて締め付けられ、猿轡を噛まされた。まるで銃殺刑が執行されるかのようだ。
気付けば頭が割れるように痛い……と思ったら、頭頂部から頬にかけて血がつたっていた。実際に頭が割れているのだった。
やがて室内が徐々に明るくなっていった。室内各所に松明が設けられ、それらが順に点火されているのだ。エンリケとレオノールだった。彼らが手分けして松明に火を点けているのだ。
明るくなって、ようやく僕の縛られている杭の真横、5メートルばかり右に同じように杭に縛り付けられている人物が居る事に気付いた。
それはベンジャミンだった。僕と同様着物を剥ぎ取られ、猿轡を噛まされている。何とか脱出しようともがいているが人力ではどうにもならないだろう。
やがて彼も僕に気付いてお互い目を見合わせ、モゴモゴと言葉にならない声を掛け合った。
「マリア様の御成りじゃ! 静かにせんか!」エンリケが怒鳴った。が、こんな目に遭って黙っていられようか。僕もベンジャミンも抗議の声を上げ続けた。
いつまでも静まらぬ僕らに業を煮やしたか、エンリケは僕を、レオノールはベンジャミンを、それぞれ手にした騎馬鞭様のもので強かに何度も打ち据えた。これにはひとたまりも無い。僕らは黙るしかなかった。
僕らの正面には見たことも無い様式の祭壇らしきものが組まれていた。また周りの壁や床にはまるで曼荼羅のような図柄がびっしりと描き込まれている。恐らくは僕の知らない異国の宗教か何かの神話を象っているのではないかと思うが全く見覚えが無い。画の勉強の為各国の宗教や神話などの本はかなり読んだ積りなのだけれども。
ふいにエンリケとレオノールが跪き頭を垂れた。同時に音も無く誰かが僕らの間を通り抜け、祭壇の前で立ち止まって振り向いた。
それはマリアだった。黒を基調とし金糸で模様が入れられた長いローブを身に纏っている。ローブの模様は壁や床に描かれたものと似た様式のようだ。
「二人とも、驚いているようね」
おもむろにマリアは口を開いた。
「……まあ無理も無いわ、こんな事になってはね。でも今夜を逃せばもうチャンスは無いの。許してね。……まあ、許してくれなくても同じだけど」
そしてマリアは平然と恐るべき宣告を僕らに放った。
「結論から言えば貴方達は二人とも死ぬ事になります」
死ぬだって? 殺されるということなのか?! 冗談じゃない!
僕もベンジャミンもたまらずまた抗議の声を上げた。もちろん猿轡を噛まされているので言葉にはならない。
「静まらぬか! この無礼者!」老夫婦はまたも僕らを打ち据えた。
僕らが黙ったのを見てマリアは言葉を続けた。
「勿論何故死ななければならないのか、それはちゃんと教えてあげるわ。だって友達じゃない。何も分からずに死ぬのでは可哀相よ。でしょう?」
猿轡を噛まされている上に散々に打ち据えられた僕達にはもうこれ以上文句を言う気力は残っていなかった。ただ夢であって欲しいと願うばかりだ。が、こう雁字搦めでは頬っぺたをつねる事もできない。
「アルタミラという洞窟はご存知かしら?」
マリアは僕達に語り始めた。
* * *
スペイン北部の大都市、サンタンデルから西へ30キロほど行ったところにアルタミラという名の洞窟がある。およそ一万五千年前、即ち旧石器時代の壁画が残されている場所だ。十九世紀の終わり頃に当時の領主の娘によって発見されるまでひっそりと眠っていた。しかし、それは意図して隠されていたのだ、というのがマリアの弁であった。
時は十五世紀初め、当時まだカスティーリャの王子であったフェルナンド一世がこの洞窟を発見し探検した結果、壁画からさらに奥 ――現在は土砂に埋まって行き止まりとなっている場所よりもさらに奥―― に全く未知にして異質な文明の遺跡を発見したのである。有史はるか以前、旧石器時代よりもさらに前の時代に栄えた古代文明の遺物であった。
時あたかも国土回復運動の只中、切り札と為り得る新技術の発見を直感したフェルナンド一世は密かに発掘物を自らの宮廷に運ばせ、洞窟の深奥部を誰の目にも触れさせぬよう閉ざしたのであった。
その後十余年に渡るフェルナンド一世とお抱えの錬金術師たちの研究は遂に実を結び、解読に成功した。それは別の次元、言い方を変えると別の宇宙から強大な力を引き出す恐るべき秘法であった。
しかし、その実験を行った科学者は力を制御出来ずに暴走させ大惨事を引き起こし、その余りの恐怖にフェルナンド一世は一切を封印する事を決意したのである。
当時既にアラゴン王となっていたフェルナンド一世であるが、教会大分裂を終わらせたが為に対立する事となったベネディクトゥス十三世の手によって封印直後に謀殺され、その短い生涯を終えた。
フェルナンド一世の研究を知るのは王家の中でも限られていた。そのうちの一人こそがフェルナンド一世の私生児たるマリアの先祖だったのである。
彼はフェルナンド一世、引いてはトラスタマラ家との密約によりマリアの代まで続くほどの莫大な財産を授けられ、その代わり封印の事実と秘法を代々管理する使命を与えられたのであった。マリアの先祖は秘法の悪用を恐れ、また自らの身の安全を図るため、秘法を分割し、トラスタマラ家の擁護の許に当時の領地の各所に散逸させた。
それから数百年、スペインとヨーロッパを巡る戦乱と混乱にまみれた長い年月の末、秘法の存在は遂に忘れ去られたのだ。
唯一マリアの家系を除いては。
「ただ、残念ながら我が家に代々伝わる古文書も半分忘れ去られていた状態でね、すっかり痛んで読めなくなってしまっていたわ。時の流れは残酷ね。でも、それを少しずつ復元して解読しつづけたのが私の祖父と父、そして三人の兄達よ。皆死んでしまったけどね。研究結果は私に受け継がれた……"最後の鍵"を残した状態で。
でも、遂に私はそれを見つけたの。この間のイタリー旅行でね。
もちろん"最後の鍵"以外にも分断され封印された要素は幾つもあって、それらは祖父から三代に渡る研究でようやく全てを手に入れられたの。アルタミラを始めとしてスペイン全土はもちろん、周辺のポルトガル、フランス、モロッコの辺りまでも調査したわ。この部屋に描かれた模様、床の細工、器具、設えに至るまでが全財産をもって揃えられ、"最後の鍵"を待っていたのよ」
「フェルナンド一世はアラゴン王であると同時にシチリア王国も統治していたの。だから最後の鍵は元のシチリア王国、つまり現在のイタリー南部に在るのではと睨んで、以前から兄達と何度も足を運んでいたのよ。もちろん小さい頃の私にとっては只の楽しい旅行だったんだけどね。
1928年のエトナ火山の噴火で隆起した土地から未知の遺跡が出土したのはきっと貴方達はご存知ないでしょう。それほど大きなニュースにもなっていないし、重要視もされてないもの。でも、それが突破口になったのよ、幸いなことにね。ただし、それに私が気付いたのも本当につい最近の事。その頃には祖父も父も兄達も皆居なくなっていた。
で、その遺跡の奥にまるで只の岩のような顔をして収まっていたのがこれよ」
マリアは祭壇に鎮座した短い棒状のものを手に取って差し出して見せた。
それは滑らかな形で、非常に良く磨かれた岩石で出来ており、何かの模様が彫り込まれた上に一分の隙も無く黒光りする石が嵌め込まれている。
マリアはそれを持ったまま静かに前に進み ――その時僕は初めて彼女が裸足だと気付いた―― 僕らの前方、3メートルほどの所の床に穿たれた直径五十センチほどの窪みに"最後の鍵"を置いた。窪みの中心部はそれがぴたりと嵌る形に彫られており、そこに嵌めこまれた"最後の鍵"は確りと上向きに固定された。
そういえば、視界を広げてみると部屋の床ほぼ全面に渡って窪みや溝のようなものが彫ってある。それらは別の溝や窪みと合流しながら最終的には"最後の鍵"が設置された窪みに向かっているようだ。僕らが括り付けられている杭の周りも直径1メートルほどの円形に彫られて、底面は浅い皿のようになっており、その一端に溝が連なっている。
このような溝の作りはどこかで見た事がある……。
そうだ、ちょうど奈良県にある酒船石のようだぞ。あれは酒や薬を製造するためのものではないかという説が何かの本に書いてあったが、これもそうなのだろうか。いや、それにしては僕らまでその中に居るのは些かおかしくはないか……?
マリアの話は続く。
「古代文明では儀式によって呼び出したものを"神"と崇めたわ。"神"は彼らの差し出す生贄と引き換えに膨大なエネルギーを与えることで古代文明は繁栄し栄華を極めた。ところが何かを境に神と人間の蜜月は破れ古代文明は滅びた……。分かっているのはそれだけ。何が起こったのかはよく分からないの。でも昔の事はそれくらいで十分よ。だってもうすっかり秘法が解明されたんですもの。あとは私が儀式を執り行い"神"に祈るだけなんだから」
「儀式には色々なものが必要なのよ。特に大事なのが新鮮な生贄 ――つまりあなたたちよ。秘法での言い方をすれば"シィョヌグロー"ね。人間の身体は血液と共にある種のエネルギーも血管を流れているの。それを取り出して上手く使えば梃子のように働いて別宇宙への扉を開く事ができる。
勿論ただ儀式をすれば良いってものじゃないのよ。地球と月、太陽、それに太陽系の惑星の位置が重要で、その絶好の条件が揃うのが今晩だったの。今がまさにその時。だから急いで"最後の鍵"を見付けなくてはならなかったし、"シィョヌグロー"も用意しなくちゃいけなかった。なかなか大変だったわ」
「こんな苦労をしてまで何故?って思うでしょうね。元々の祖父の悲願はこの秘法でトラスタマラ家を復興させるというものだった。父や兄達もそれに倣って一生懸命働いたわ。でも皆死んでしまった。祖父はスペイン風邪、父と兄達は内戦や無政府主義者のテロでね。
私も当初は志を同じうしていたのだけど、途中で馬鹿馬鹿しくなっちゃった。何しろ私の祖国スペインときたら、フェルナンド一世の頃からまるで不安定、天下泰平となった事などないの。特にここ100年は酷いものよ。繰り返される内輪揉めにはもう飽き飽き、それが正直な気持ち。
トラスタマラ家だって、もうとっくに滅びてるの。ハプスブルグ家に吸収され、そのハプスブルグ家も度重なる近親婚で滅びた。今の王家はブルボン家に摩り替わってしまってる。もう頑張る意味なんて無いって気が付いてしまったって訳。
私の人生、祖父や父、母や兄達の人生って何だったんだろう。そうは思わない?
だからね、せめてこの馬鹿馬鹿しい世界をもっと馬鹿馬鹿しくしてやろうと思ったって訳。エンリケとレオノールも着いて来てくれるっていうしね」
「やる事は単純よ。世界中を引っ掻き回して混沌とする。あらゆる災厄、争い、諍いで世界を埋め尽くし、その様を高みから見物する。きっと凄く楽しいわ」
「手始めはスペインよ。コミンテルンやらファシストやら火種には事欠かない。その中でもフランコっていう大虚けに目を付けてるのよ。あいつは有望株よ。ちょいと焚きつければかなり面白い事をやってくれそうだわ。スペインを滅茶苦茶にしたら今度はヨーロッパ、続いてアメリカにアジアよ」
「もうひとつ。貴方達を"シィョヌグロー"に選んだのは偶然じゃないのよ。
地球は今の科学では検知できない一種のエネルギーを持った粒子を中心部から放出しているの。それが地球上の全ての生き物に影響を与えてるのよ。誰も気付かないけどね。
この粒子は場所によって僅かに性質が違うの。特に経度、つまり東西方向で顕著よ。結果生まれた場所によって"シィョヌグロー"としての組成が違ってくるって事なのよ。
サブロウは東京、ベンジャミンはサンフランシスコの生まれでしょう。両都市はここから東西に9000キロほど離れてる。まさに理想通りよ。
初めて貴方達二人と出会った時はこんな偶然があるのかと家で小躍りしたわ。絶妙のバランスだったんだもの。"シィョヌグロー"としての出来と組み合わせがね」
「騙すような形で連れてきてしまってごめんなさい。それだけは心が痛むわ。本当は貴方達とも一緒に居たいのよ。でもダメなの。貴方達には"シィョヌグロー"になってもらわなくてはならないのだから。
もう会えなくなるのはとても寂しいわ。でも理解してね。最上の条件を揃えなければ実現出来ないの。
貴方達は"シィョヌグロー"として新たな秩序 ――いや無秩序の方が正しいかしら―― の礎となる。それはとても名誉な事よ。でしょう?」
マリアはすっかり頭がおかしくなっているようだ。余りの論理の飛躍に頭が着いて行かない。
「ああ、いけない、時間が差し迫ってるわ。これで話はおしまい。さあ、儀式を始めましょう」
そう言うなりマリアはローブの帯を解いた。ローブはそのままマリアの身体をするりと離れ、音も無く床に落ちた。驚いた事にローブの下は一糸纏わぬ全くの裸であった。しかし彼女には恥らう様子など微塵も無い。
* * *
それにしても何という美しい裸体だろう。モンパルナスのキキもかくやとばかりだ。
肉置きのよいそれでいて引き締まった肉体を滑らかで淀みの無い薄桃色がかった乳白色の肌が覆う。程よい大きさの乳房は鞠のように丸く、乳頭がつんと上を向くほどに張りがある。しなやかな肢体はまるで陶器のように艶めき、華奢なようでいて強さもある。背中から尻、そして太腿から足先への連なりはアルプス山脈の雪渓の滑らかさにもひけを取らない。彼女の髪の毛と同じ金色の毛が薄く下腹部のさらに下端を覆いその奥に潜む外性器を柔らかく隠している。
こんな異常な状況でなければ抱きしめてベッドに連れていきたいところだが生憎そうもいかない。
マリアはその場に仁王立ちしたまま、何やら呪文らしきものを唱え始めた。しかしそれはこれまで全く聞いたことのない独特の響きと韻律を持っていた。
カパヌギャリィハン カイーランガン=ク=イトー ピヌノイグビトゥイン
マンギャーリン・マッパヒラム=ナッ・プエルサ
バグーイン=アン・イトン=ムンドゥ・サ・イバン=ム=ンドゥ
ガーミッ=アン・カパヌギャリィハン・ナ・イバン=ム=ンドゥ
マリアの声が響く中、エンリケとレオノールは部屋の隅にいくつも置かれていた陶器の広口瓶を手に取ってはせっせと運び、その中に入っているものを床の窪みに流し込んでいった。中身は得体の知れない液体で、ものによって色が違う。窪みに溜まった液体はやがて溝を伝って流れ、別の窪みで合流し、それぞれ違う色をした不気味な燐光を放った。
やがて祭壇の辺りが明るくなり始めた。祭壇に置かれた大鏡が明るく輝いている。僕らの後ろに大窓がありそこから光が射しこんで反射しているらしい。鏡にはちょうど満月が映っていたようだったがすぐに眩しくて見えなくなった。
と、脇腹に衝撃が走った。目を下げると僕の右脇腹に、何かが突き刺さっている。草刈鎌のような三日月状の刃だ。それには長い柄が付いていて、その先端を持つのはエンリケだった。僕の血液が腹から刃を伝って床に点々と落ち始めた。同時に凄まじい痛みが押し寄せてきた。
顔を右に向けるとベンジャミンが悶え苦しんでいるのが目に入った。彼の左脇腹にも僕と同様草刈鎌状の刃物が突き刺さっている。それを突き立てているのはレオノール婆さんだ。
老夫婦はマリアの詠唱に合わせるようにして、ほぼ同時に刃を自らの手前に引いた。
刃は僕の腹を右から左に、ベンジャミンの腹を左から右に一文字に切り裂いた。よほど入念に研がれていたのだろう、まるでバターを切るように全く淀みなく僕らの腹を刃が横断した。
一瞬の間を置いて切り裂かれた腹から血が噴き出した。血液は腹から噴き出すのみならず咽喉をも上がってきて口の中は血の味でいっぱいになった。
床に落ちた僕らの血液は、さっき老夫婦が流し込んだ液体同様、足元の窪みに溜まり、溝を伝ってその先の窪みに集まった。その窪みには、先刻マリアが据えつけた"最後の鍵"がある。やがて"最後の鍵"の溝は僕らの血液に満たされた。すると"最後の鍵"が内側から禍々しい光を発し徐々に明るさを増していった。あたかも僕らの血を吸って精気を取り戻したかのように。
やがて燐光を発する液体がそれぞれの溝を伝って四方から流れ下り合流し、"最後の鍵"の窪みに到達した。
燐光と"最後の鍵"の発する光は入り混じり、世にも奇妙な様々な色を発して混ざり合い、やがてそれは炎となった。が、不思議な事に全く熱を感じなかった。むしろ冷たく感じるほどだ。
冷たい炎の上がったのを見るや、エンリケが前に進み出でた。その両手に何かを押し戴いている。焼き物のゴブレットのようだが、西洋で見かけるものとは様子が違う。炎を象ったような形で、全体に縄目のような模様がある。かのモース博士が品川で発見したという縄文式土器の様式によく似ているのは偶然か。
今度はレオノールが長柄杓を取り出してきた。"最後の鍵"の窪みにそれを差し入れると冷たい炎ごと液体を汲み上げ、エンリケの持つゴブレットにそれを流し込む。ゴブレット全体が光を発し冷たい炎を噴き上げた。
エンリケからゴブレットを渡されたマリアは一切の躊躇も無くその中身を飲み干してしまった。その途端マリアの身体の内側から光が発せられた。あたかも曇りガラスの向こうでランタンが灯されたような橙色の光だ。しかしランタンとは違い、そこから温かみは全く感じられないのだ。
「ああ、実に素晴らしい! 素晴らしい気分だわ! あははははは!」
いかにも気持ち良さそうにマリアは僕らに向けて叫び、高笑いした。
「さあ二人とも、よく見ていなさい。いよいよお出ましよ! 別の世界からの使者、混沌そのものよ!」
そしてまた呪文の詠唱を始めた。その声はもう僕らの知っているマリアの声ではなかった。
カパヌギャリィハン クーニン=モ=イトー ピヌノイグビトゥイン
マンギャーリン・マキパグトゥルグァン
ハッヤーアン=メイ=ドゥマティン・ムラー・サ・イバン=ム=ンドゥ
ゴァウィン・イトン・イバン=ム=ンドゥ
マガ・タオー・サ・イバン=ム=ンドゥ
マリアは詠唱しながら"最後の鍵"の窪みの冷たい炎の中に入っていった。冷たい炎に炙られながら窪みの真ん中、"最後の鍵"を跨ぐ位置まで行くと正座のような体勢で腰を下ろして祭壇に向かって座礼した。
慇懃に礼を済ませると今度は少し上体を起こし、場所を確認するように後手で"最後の鍵"を掴み自らの臀部を"最後の鍵"の方に持っていった。冷たい炎越しに露わになったマリアの外性器は全体が紅色に紅潮し、光を反射してぬらぬらと妖しく艶めいている。
その体勢を保ちながら両手で自らの陰唇を大きく開いた。ぱっくりと口を開けた紅い肉の壷は外性器同様ぬらぬらとした光沢を纏っている。そこに"最後の鍵"をあてがうと、上体を起こしながら臀部全体で"最後の鍵"を包むようにゆっくりと挿し入れていった。
マリアはそのまま身体を起こし、足を立て、蹲踞の姿勢となった。しっかりと最奥部まで挿入されたのを確かめるような数秒の間の後、マリアの腰は上下に運動を始めた。
一種エンジンの如く、"最後の鍵"というピストンがマリアの内性器をシリンダーとして往復運動するのだ。
彼女の身体の内側から発する光はそれに呼応して次第に強まっていき、同時に内性器からは燐光を発する液体が大量に滴りだした。液体を受け"最後の鍵"の発する光は強まり、冷たい炎も勢いを増すと、マリアの律動もまた勢いを増し、更なる内性器からの液体が"最後の鍵"に注がれる永久機関だ。
最早詠唱の声は野生の鳥獣の如き金切り声となり、それでもなお続けられ、のみならず繰り返される度に声量を増して部屋中に響き渡った。
マガ・バゲイ・ムラー・サ・イバン=ム=ンドゥ!
マガ・タオー・サ・イバン=ム=ンドゥ!
アン・カパヌギャリィハン・ナ・イバン=ム=ンドゥ!
ムラー・サ・イバン=ム=ンドゥ!
ムラー・サ・イバン=ム=ンドゥ!
刹那。
マリアと"最後の鍵"から凄まじい閃光が放たれた。それはまるで太陽を虫眼鏡で見たかのような恐ろしいほどの眩さであった。同時に冷たい炎が部屋全体を覆い尽くした。
* * *
気付くと、冷たい炎も"最後の鍵"の光も燐光も全て消え、赤黒い松明の明かりだけが静まり返った室内をゆらゆらと照らしていた。
マリアはいつの間にか祭壇の前に立っている。
そして同じく祭壇の前、マリアの面前に黒い影のようなものが居た。それはエンリケでもレオノールでもない。老夫婦は部屋の隅で跪いている。ならばあれは誰だ? あれがマリアの言う別の世界からの使者、「混沌そのもの」なのか。
黒い影はどうにもつかみどころの無い、まるで煙のようなぼんやりとした輪郭しか見えない。しかし確かにそこに「在る」のだ。視界の端ならばはっきり見えるのに、真正面から見るとたちまちぼやけて見えなくなってしまう。人の形をしているようだが、そうでないようにも感じる。ほんの僅かに垣間見える(ように感じる)その顔は醜く恐ろしい(正確にはそのような印象のみで、思い出す事も出来ない)。
マリアはその黒い影に近づき、固く抱擁した。そしてあの醜く恐ろしい(印象の)顔に、自らの顔を持っていき濃厚に接吻を交わした。
接吻を終えた彼女は恍惚の表情のまま一歩下がり、胸を突き出すような格好をした。
黒い影は両腕(と言って良いのか分からないが)をマリアに伸ばし、両の乳房の間に差し込むや着物を脱がせるが如く一気に左右に開いた。マリアの身体はちょうど鎖骨の辺りでYの字を描くように裂け、首から下の部分は真っ二つに破れた。
しかし破れ目からは血の一滴も出ず、どす黒い煙のようなものが立ち昇るだけだった。その中から何かが脱皮するように這い出し、まるでツナギを脱ぎ捨てるようにマリアの身体を捨てた。それは禍々しくも美しく大きな翼を持った一羽の鳥 ――ただし鎖骨から上のマリアの身体を纏ったままの―― だった。
鳥は全身を震わせた。すると余分な肉が剥げ落ち、マリアの首だけが残った。その姿は北欧の古い伝説に出てくるハーピーとかいう妖怪にそっくりだ。実のところマリアの美しい顔がそのまま残ったので僕はその時少しばかり安堵したのだ。
次に黒い影は部屋の隅で平伏すエンリケとレオノールの許へ歩み寄り(あれを歩くと言うのならば、だが)、彼らの背中を撫でるようにした。途端に二人の背中がぱっくりと割れ、それぞれ中から一匹ずつ、羽のあるトカゲのようなものが生まれ出でた。
つい先程までエンリケとレオノール、そしてマリアだったものたちは一斉に、けたたましく甲高い声を上げた。たちまち部屋中が揺れ始め壁や天井には見る見る皹が走って崩れだした。松明は倒れ、そこら中に炎が燃え広がった。僕らが縛り付けられている杭も倒れ、杭ごと床に投げ出された。
揺れはますます激しくなった。僕は為されるがままに床を転がったが、途中で何かが引っかかってその場に留まった。僕の切り裂かれた腹から小腸が飛び出して瓦礫に絡みついているのであった。
自縄自縛ならぬ自腸自縛か……ふふ、こんな時に何を考えているのだ。いやこんな時だからこそ考えてしまうものなのだろう。恐らく余りの事に脳が現実を見るのをやめたのだ。
そんな奇想に我知らず口の端を歪めていた僕の上に容赦無く瓦礫が降り注ぐ。気付けば半身を埋め尽くされていた。
崩れて無くなった屋根の向こうに明ける直前の夜空が露出した。夜空は燃え上がった炎に照らされ赤く染まって見えた。
おもむろに黒い影がその夜空に向けて、まるで伸び上がるように上昇し始めた。エンリケとレオノール、そしてマリア(だったものたち)は相変わらずの甲高い声を上げながら翼を羽ばたかせてその後を追った。
彼らはしばらく邸の上空を旋回した後方角を定めて真直ぐに飛び去っていった。
あの黒い影の一行が世界中に災厄を、争いを、諍いを、混沌をもたらすというのか……。
まずスペイン、更には欧州全土、アメリカ、アジア、そして日本……。
僕にはその様が見えるように思え、戦慄を覚えた。もしかしたらそれは黒い影が最後の戯れに僕に見せ付けたのかもしれない。
やがて、次第に薄れゆく意識の中、明けきらぬ西の空に遠ざかる彼らを見ながら僕は絶命した。
<了>
いたーら
【イターラ】
◇[登録商標]Itala
○[古][交]1904~1934(明治37~昭和 9)イタリアのトリノ(To-
rino)で製造された一乗用車。
---
★ふぇるなんどいっせい
【フェルナンド一世】
【フェルナンド1世】
◇Fernando I
○[人]アラゴン王(1379~1416. 4. 2)。在位:1412~1416。
---
まるぬがわ《まるぬがは》
【マルヌ川】
◇[フ]Fleuve Marne
○[地]フランス北東部を北西流する、セーヌ川(Fleuve Seine)
の支流。長さ525キロメートル。
ラングル高地(Plateau de Langres)に発源する。
ストラスブール(Strasbourg)でマルヌ・ライン運河(Canal
de la Marne au Rhin)によってライン川(Fleuve Rhin)と結ば
れている。
参照⇒せーぬ(セーヌ,析奴)
出典: 私立PDD図書館/百科辞書
http://pddlib.v.wol.ne.jp/japanese/index.htm
いつもサポートありがとうございます! (╹◡╹)ノシ
