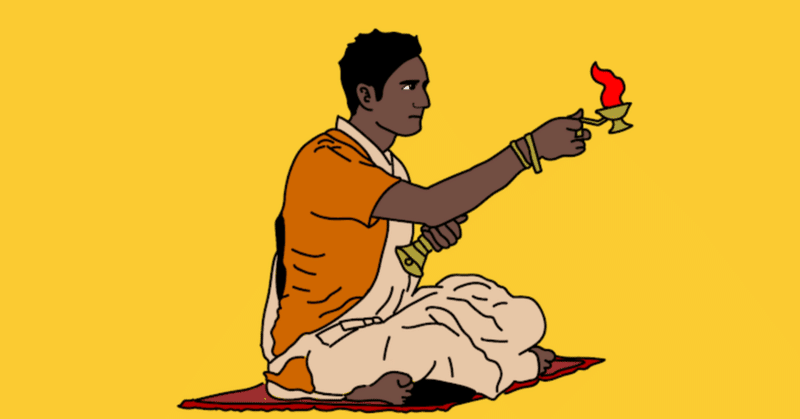
海外一人旅が20歳女子に与えた影響
もう10年も前のことになる。
大学生だった私はバイト先の先輩に美味しいチャイを作ってもらい、「インドにはこれよりも美味しいチャイがあるぜ」と言われて、よしインドに行こう!
その数ヶ月後には初めての一人旅でインドへ。
嘘みたいな本当の話。
何か人とは違う経験をするキッカケが欲しかった。理由はなんでもいい。ただ若いうちに新しい経験をしたかった。
まだその頃はYouTubeにも旅系メディアはほとんどなく、情報を集めるのはブログと地球の歩き方。
言葉通り右も左も分からない状態でインドへ行き、しっかりと揉まれたわたしはその後家族から「インドかぶれ」と呼ばれるように(笑)
インドのことはなんとなく旅好きなら知っていることと思います。想像しうるほぼすべてのトラブルにあいました。しっかりと。
10日間の旅だったけど、いろいろな感情がうずまき忙しかった。
住所が分からずホテルに帰れなくなった時「me with you」と手を握ってくれた同い年の女の子。そしてみんなで読めない英語をなんとか読もうと親戚中に電話して無事にホテルまで送ってくれたあの子たち。
これまでの日本人は触らせてくれたと言って胸を触ってくるタクシー運転手。無理だと言ってもお酒を飲ませようとしてくる通りすがりのおじさん。後をつけてくる人。マッサージしてあげるよとセクハラしようとするホテルのスタッフ。
砂漠にお布団をひいて輝く星空を視界いっぱいに見たとき。建物がなにもなくて地球って丸いんだなあと感動。そんなときに「君は僕のマハラーニー。僕はマハラジャ。」と言ってくる砂漠ツアーガイドのセクハラ。翌日乾いたラクダのふんを燃料に作って食べたカレー。
子供が渡してきたハエのたかったフルーツを、美味しいねと一緒に食べた屋台でのひとこま。
そんな刺激的な10日間の後、あまり間をあけずに旅に出た。
2ヶ月間、東南アジア周遊
2ヶ月間、インド
当時は「自分探しとかださい」「インド行って人生観変わったとかださい」と思っていたため、あまり周りにはインドが自分に与えた影響について語らなかった。
10年経ったからいえることを、これから書き記そうと思う。
結論から言うと、これまでの価値観が崩壊した。
理由の1つは20歳という多感で経験値の低い時期だったこと。
学生時代に勉強しかしてこなかったガリ勉が突如気づく。世界にはこんな国、こんな人、こんな場所があるのだと。そしてわたしにはこんな感情があったのだと。
今だから言える。20代前半での1人インドはおすすめできない。不安定な価値観しかないときに行く国ではない、と言う意味で。
あらゆる沈没バックパッカーからのドラッグや沈没のお誘い。捻じ曲がった感覚を持つ猛者の旅人からの植え付けられる言葉。そのどれもが20歳にとっては衝撃。
本質を見る力がなければあっという間に影響されてしまう。それが悪いとか良いとかではなく、若いうちに歪んだ価値観に触れる環境に身を置くことは、ほぼ洗脳だと言っていい。
ちなみにちょっと勉強ができる中途半端な大学生は影響されがち。「1人で海外も行けないなんてださい」とか「日本でサラリーマンするなんてバカ」とかそんなふうに狭い物差しで周りを見下して、出会った人には何カ国行った自慢でマウント。仕事できている日本人のビジネスマンと出会ったら「人脈広がったわ」と中身のないやってやった感。そのどれもがしょうもなく、またそんなわたしも片足をつっこんでいた。
足を突っ込むのはとても簡単で、難しいのは日本に帰ってからのこと。
しっかりとした土台がないくせに上部だけの「新しい世界みてきた」感覚。これがとても厄介でこの感覚を完全に捨て去るまでに5年ほどはかかった。
なぜなら、しばらくは旅の思い出を語りネタとして面白がり、過去の自分を美化するから。
語れば語るほど、新しい世界を見て変わった自分を正当化したくなるし
だけど同時に目前に迫ってくる社会人としての責任や、大人が日々を積み重ねていく尊い行為の意味が分かってくる
じゃあ、本当のわたしってなんなんだろう?
私は何がしたいのだろう?
正直、この悩みをもたない人生でありたかった。
憂鬱な気持ちが数年続いたのを変えたのは仕事だった。
目の前にある作業。仕事。
先を見ずに目の前のことをひたすらこなす。
そんな生活を1年送った頃、バックパッカーかぶれをようやく卒業できました。
若いうちになんでも経験したほうがいい。
とは基本的には賛成。
だけど20前後は自分が思っている以上に周りの影響を受ける。海外一人旅を検討している人はぜひこのことを頭に入れておいてもらえたらと思う。
もしわたしがいま10年前に戻り、インドにまたいくのか?と聞かれたら
それでも迷わずいくと思う。
旅に出る理由は「知りたいから」それだけでいいという考え方は今ももっているから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
