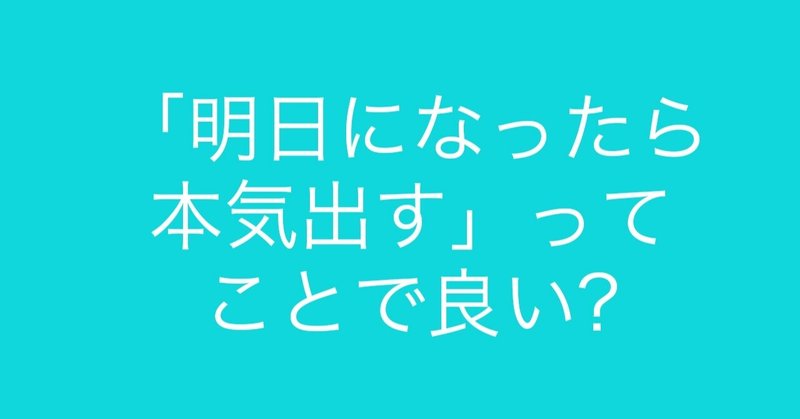
AI確変で一発逆転を狙った文学部の妄想。波頭 亮著「文学部の逆襲」。
今回は私には珍しく辛口レビューをお届け。
その本がこちら
波頭 亮 (はとう りょう) 著「文学部の逆襲」
だ。
私は基本的に本を購入する時、できる限り「まえがき」「あとがき」「目次」などをよく読んで、内容を精査するようにしている。そのお陰で購入した後に「これは外れた」と思う確率は低いのだが…、今回は久々の「大外れ」。レビューを書くのも止めておこうと思っていた。
しかし、よくよく読むと、逆に「このような本が出回るような事態が日本の知的水準の停滞につながっているのではないか」という逆転の見方もできることに気づいたため、今回敢えて「辛口レビュー」ということで投稿することにした次第だ。
というわけで、今回はあえて批判的に読んだ感想として受け止めていただけると幸いだ。
本書の概要
本書における著者の主張はおよそ次のようなものである。
「ここ30年あまりの間、日本は経済的に衰退し、社会にも先の見えない停滞感が充満している。
その理由は資本主義というシステムが機能不全を起こしているからである。資本主義の機能不全とは”富の偏在”のこと。すなわち”富める者はさらに富み、貧しき者はさらに貧しくなる”という格差の拡大だ。
そもそも資本主義とは構造的にそのような富の偏在が起こりやすい特性を持つ(同じスタートラインから始めても、資金力が高い方が有利になる。さらに勝ち組の方には、より多くの資金や人が集まるからである)。だからこそ、富の再分配を適切に行う役目を国家が担ってきた。
ところが、現在はその国家が率先して、富の偏在を拡大する政策ばかりを行っている。なぜなら、巨大な富を持つグローバル企業が国家を懐柔し、メディアを操り、SNSを駆使して、自分たちに有利なように世論を動かし、国家を動かしているからだ。
だが、このような時代の閉塞感を打ち破る事象がいま起こっている。それがAIによる技術革新だ。
AIの発展によってら今後生産性は格段に向上する。人間はほとんど働かなくても豊かさを享受できるようになる。もちろん豊かさの分配もAIによって適切に行われるようになっていくだろう。そうすれば、人間が労働に囚われる意味もなくなる。さらには、今までのような「労働=生きがい」というような価値観は時代遅れになるだろう。
そのような新しい時代には、より内面的な価値を高まる物語。すなわち、人がより良く生きるということ、人間らしく生きていくということはどんな意味があるのかという問いに答えるような新しい”大きな物語”が必要になる。
それに答えるのが哲学、文学、歴史学といった「文学部」の領域である。したがって、これからの新しい時代には、文学部の持つ力が大きな意味を持つことになる。昨今ないがしろにされて来た文学部の逆襲が始まる日も近い。」
以上が本書の筋道である。
率直な感想は・・・
このような主張をご覧になって皆さんはどういう印象を抱くだろうか。
私の率直な感想としては
「アホらしい」
の一言である。
確かに著者が言う通り、現代の資本主義という経済システムが機能不全に陥っていることは事実である。それを解決するためには富の偏在を解消することが必要なのも間違っていない。
だが、それをAIという技術革新によって解決できるという主張は、あまりにもお花畑的な発想ではないだろうか。
なるほど、AIによって生産性の飛躍的向上が見込める分野があることは間違いあるまい。デジタルサービスは言わずもがな、例えば製薬の分野においてもAIによって桁違いの開発スピードが見込まれるのは確実だ (仮想世界で実験を行うことで、現実世界での創薬の段階を飛躍的に効率化できる)。
しかしながら、当たり前だがAIは万能ではない。たとえば建設業や農林水産業などの分野では生産性向上は可能にしても、物理的な肉体をAIが持たない以上、その度合いもどこかで頭打ちになるだろう (100年先を視野に入れれば話は別だが)。
ましてや日本のような災害大国であれば、AIが組み立てたストーリーが一瞬で灰燼に帰すことも十分ありえる。そのような事態を想定すれば、もしもの時に人間が代替できるレジリエンス (強靭性) を確保しておかなければならないことは誰にでも想像がつく。
その上、著者は「AIの発展によって”どのように”富の再分配が適切に行われるようになるのか?」という具体的な内容については、全く言及していない。つまり結局「何だか知らんけどAIはすごいんだから、うまい解決方法を思いついてくれるだろう。」という程度の主張なのである。
文学部の現在における重要性を説くべし
本書のタイトル「文学部の逆襲」は、以上のような「AIによって資本主義の構造的問題が解決され、お金のために働くことをしなくなった”新しい歴史のステージ”においてこそ、文学部はその本当の力を発揮するのだ」という意味である。
はっきり言っておこう。
これはまさに一昔前にネット上で散見された
「明日になったら本気出す」
と同じ類である、と。
著者が言っているのは「AIという”機械”が眼前の問題をクリアしてくれたら、文学部にできることがある」ということであり、それはすなわち「現時点で文学部にできることは何もありません」と言っていることと同じなのだ。
確かに人間が生きていくために”物語”が必要なのは間違いない。
どんな人間であっても「何かのために生きる」という目的がなくては生きていくことはできないものだ。たとえその目的が「お金」や「名誉」、あるいは「異性にもてること」であったとしても。
どのような怠惰な生き方をしていたとしても、「ただ生命を維持するためだけに生きる」ということは人間にはできない。人間とは必ず自らが生きる意味・・・すなわち物語を求めずにはいられない生き物なのである。
文学、歴史学、あるいは社会学などのいわゆる人文学系の叡智が意味を持つのは、まさにそのような物語の創出である。
それも著者が主張する通りである。
だったらその答えを今こそ示すべきではないだろうか。
それができずに「AIによって人類が新しいステージへ立った時にこそ・・・」などと言っている時点で、「文学部なんて何の役に立つのか?」と言われて当然であると思われても仕方があるまい。
現在のような理系学部が重宝され、プログラミングや専門職など即物的な学問が重んじられ、文学部廃止が議論される原因も、まさにそのような人文学部の実力不足にこそあるのではないか。
バタイユの「有用性と至高性」
このような意味においては、古典的著書の方がはるかに有意義な考え方を私たちに示してくれる。たとえば、20世紀初頭のフランスの思想家ジョルジュ・バタイユは「有用性」と「至高性」という2つの概念を提唱した。
有用性とは「役に立つこと」である。
資本主義の世界では人々はこの有用性、すなわち役に立つことに重きを置く傾向が強い。しかし、役に立つものというものは逆に言えば”役に立たなくなった時点で価値を失う”ということでもある。
たとえば英会話の能力は現在でこそ”役に立つ”が、近い将来リアルタイムの自動翻訳が行われるようになれば、”役立たず”になり、その価値を失う。
これに対して「至高性」とは役に立つかどうかに関わらず価値のあるものを意味する。
この至高性を感じる瞬間とは、何も特別な環境でなければ得られない体験でも、多くのお金がなければ得られないような体験ではない。
労働者が一日の仕事の後に飲む一杯のワインによって与えられることもあれば、「春の朝、貧相な街の通りの光景を不思議に一変させる太陽の産前たる輝き」によってもたらされる
こともある。ごくごくありふれた日常の中で感じられる”至高のひととき”のことである(上記、井上智洋「人工知能と経済の未来」参照)。
プログラミング教育、英語教育など”役に立つもの”に過剰な価値を置く現代社会に異を唱え、”人が生きる上で本当に価値があるもの”を世に問うこと。これこそがいま文学部が世に示すべきことではないだろうか。
「明日になったら本気出す」などということを憚りなく公言できるようでは、残念ながら日本の文学部に陽が差すことは当分ないだろう。
というわけで今回ご紹介したのはこちら
波頭 亮 (はとう りょう) 著「文学部の逆襲」
でした。
今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
