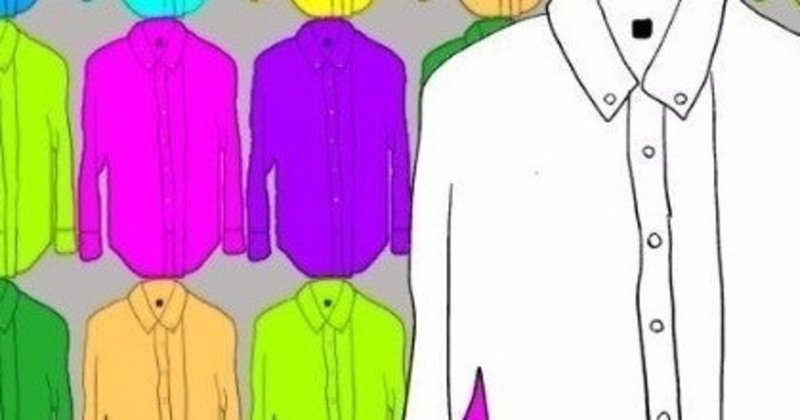
ダイバーシティで弱くなる-ダイバーシティ (3)-
自分の経営方針の中で特徴的なのは分散だと思う。特定の顧客に隷属する経営は独立した経営と言えない。また、特定の売れ筋に集中すると、その旬が過ぎると腐るのみである。
だから、経営方針は、売上高最大の顧客が売上比1%以下になることだし、商品ラインナップは常に新しいもの、同じ商品でも常にアップグレードを目指してきた。ひたすらこれを大事にやってきていた。
この経営は荒波に強い。この方針でリーマンも震災も乗り切ってきた。しかし、この方針はハイコストである。顧客が増えるほどに手間がかかるし、商品が増えるほどに手間がかかる。ただ、まぁ、それでもなんとかやってきていた。当社なりのダイバーシティである。
そこにCOVID-19がやってきた。
COVID-19は2つの点を浮き彫りにした。まず、上述のとおり、当社には明確な売れ筋がない。作らないといった方が正しいだろう。それは、当社が社名の通り、ソリューションを志向し、顧客のニーズに寄り添っていろいろなものを作り続けてきたからだ。これが、顧客に満足いただける選択肢の広さにつながっていた。しかし、これは一方で注力すべき商品のなさにも繋がっていた。
もう一つは当社には大口顧客がいないことだ。大口の軛を逃れたから、大手から中小まで幅広く、業種も幅広い。BOP戦略も大手に展開したし、うまくいってはいたが、このお客さんだけを考えておけば良いという顧客がいない。これは強みのはずだった。
先日、ダイバーシティについて書いた。そこには書ききれなかったが、多様性の低いユニバーシティは変化の激しい環境に弱い。一方で、多様性の豊富なダイバーシティは変化の激しい環境に強いとされる。
なぜか。この定見は生物多様性から得られた知見である。暑さに強いが寒さに弱い動物ばかりでは氷河期を生き抜けない。寒さに弱い動物と分散していないと生き残れない。しかし、ここに誤謬があるのではないか。寒冷の二項に分散していたら、半分は生き残れるが半分は死ぬ。分散を強めれば、絶対に全滅はしない。投資の格言に「たまごは一つのかごに盛るな」があるが、全滅を避けるためのものだ。
閑話休題。2点挙げたのは、分散するというのは、とある商品、とある顧客に資源を集中投下しても収益に直結しない状態にするということなのである。しかし、何かをやらねば収益は全くなくなってしまうし、何か一つを行うことはその他をすべて捨てることでもあった。時間は有限で、時間をかけたから収益につながることが全く見えない環境ではダイバーシティは「弱く生き残る」戦略であるかのように見えた。
ちなみに、分散するという意味では事業も本来分散すべきであったが、これは中小企業は「何屋かが分かる」ことが生き残りの最善手であるが故に集中をし続けてきた。この何屋かがわかることはユニバーシティの極地である。ユニバーシティの中にダイバーシティがある。そして、そのうち一つを選びユニバーシティを取り上げるとまたさらにダイバーシティがある。こんな風にフラクタルな状態が経営だとすると、ダイバーシティ経営というものに正しさはないようにも思う。
次回はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
