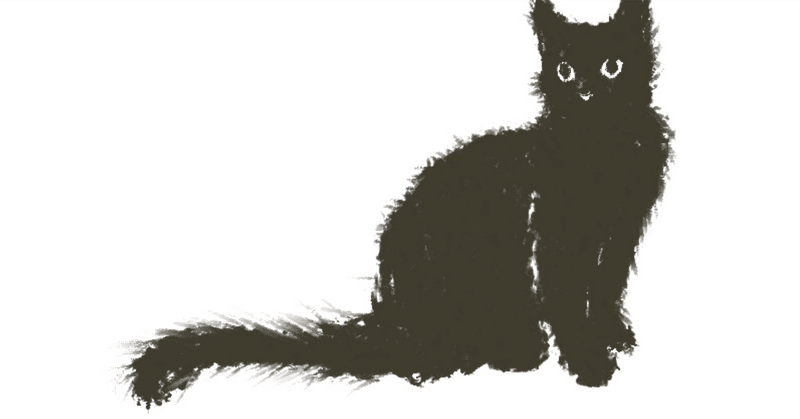
創作小説『鳥の骨格標本に左右される猫は、猫を超越しうるか?』①
圧力による侵入
白い羽ひとつひとつで透明の雨粒を弾き返し、紺色の空を夢中で翔ていた。両翼を広げ、風を受け止める。もう衝動を妨げる者などありはしない。自らが喰らう肉を狩ることが禁止されたこの世界で、兼ねてからの願いが今やっと叶う…かもしれない。そのとき突然雷鳴が響く。破れた風船のように気持ちを縮こませながら、現実という名のブラックホールへと吸い込まれていった。
雨音が耳を濡らし、夢から目を覚ます。四日、五日? もうずいぶん降り続いている。晴れの日にそっぽを向かれたようだ。無人のはずの上階からドンドンと、雨雲が生まれるような鈍い音が聞こえてきた。タバコに火を着け、フィルターに雑に粉を入れ、コーヒーメーカーのスイッチを押し、煙を吐く。コーヒーメーカーの濁音が溺死寸前の喉から絞り出された声の如く部屋を埋めた。昨日観た映画に出てきた雪のように白い幽霊のシャウトを思い出す。
今日も雨だ。それでも、生きていかなくてはならない。
パソコンを開き、書きかけの小説に二、三事付け加えて、閉じた。上階の濁ったドンドンという音を打ち消せるような気のきいた言葉がひとつも出てこないからだ。
コーヒーを口に含む。もし雨がコーヒーだったら今よりもっと最悪だろう。黒い液体に呑み込まれていく世界の住人でないことに、少しだけホッとできた。所詮僕はニヒルな猫だ。幸せについて考える権利など行使しない方がきっと幸せなのだ。
呼び鈴が招かれざる訪問を告げる。ドアスコープに映る巨大な目玉。ピクリとも動かず、何かの終焉を告げるようにこちらを見ている。これが深淵の正体か?目玉の主はこのアパートの大家である中年のヒグマだった。新しい奥さんを紹介したいとやってきたのだ。
玄関を開けるとすぐに、大きく出っ張ったヒグマの腹が僕のテリトリーを侵食する。そんなわけで、なんとなくコーヒーを出さなくてはならなくなった。
ヒグマの手土産は、この前ポロっと取れたという黒光りした爪だった。ゆうに十センチ以上はあり、爪というには手のひらにずっしりと重い。僕の爪とは似ても似つかず、劣等感さえも抱けない。そもそも何に使うんだこれ。
薄く笑う雪豹の新妻は色白でとても美人だ。前妻のアムールヤマネコと大きく違うのは、まだ顔に傷がついていないことだろう。
ヒグマはコーヒーを美味しそうに飲みながら、上の階から聞こえてくる音を無視した。そのせいで、こちらから切り出せる唯一の話題も消えた。
「美味しいねえ。このコーヒー。マンデリンかな」
適当に笑ってごまかす。モカとマンデリンを間違えるようなヤツとコーヒーの話はしたくない。
そ大体ヒグマは、部屋に入ってくると大きさのせいもあり、まるでこの空間全部を支配しているかの如くだった。
雨は激しさを増していき、ドンドンという上階からの謎の音も止む様子はない。湿った沈黙が続き、ヒグマはコーヒーをもう一杯欲しいと言った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
