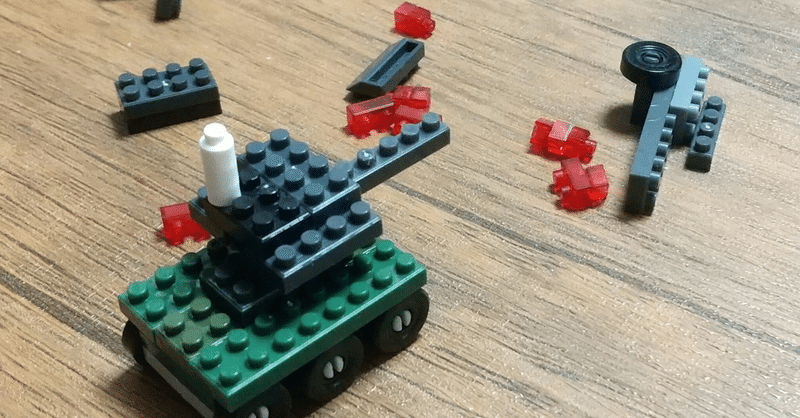
【読書感想】ウクライナから問う(現代思想2022.6臨時増刊号)
渦中のロシア・ウクライナ、その歴史・政治・文化を探る
ロシア軍によるウクライナ侵攻を機に、世界全体が大きく揺れ動いている。複雑に進展する不確かな情況のさなかにあっていたずらに煽情的な言説も飛び交うなか、事態の背景にある歴史を踏まえた射程の長い議論の場を開いていくために――政治、思想、文化など多角的な視点から「いま何が起こっているのか」を問う。
【声】
1.ブチャの後で / ユーリィ・アンドルホヴィチ/加藤有子訳
現代ウクライナを代表する作家による「声」ということで、訳者解題では「強い」言葉が使われているとしているが、別にそうは思わず、故国に虐殺という不条理がもたらされていること、それはブチャというただ一つの都市ではなく、国のあらゆる場所で起こっていることだと怒りをあげるために必要充分な筆致が尽くされていると感じる。
【ドキュメント】
2.困難な戦争避難も次には慣れていく――あるウクライナ在住者の記録 / アベル・ポレーゼ/石岡丈昇訳
キエフから避難する社会学者の脱出記。解題が要約しているように「ブリュッセルの上空を通過する民間機の音、チェルニウツィーで作られるカベルネのワイン、大切な持ち物をキエフに置いてきたままの息子、ロシアに住む元妻のいとこからの電話、国際会議で知ったジョージアにおけるロシア人の受け入れをめぐる情報、モンペリエのバーで踊る人びと、マルセイユの海岸」などの風景やエピソードを交えながら、直接的に爆撃や行軍の被害を受けなかった避難民もまた深刻なトラウマを刻まれ、これまでの常識が覆ることによる衝撃と苦痛を感得している様子が描かれている。
上記のエピソードの中では、子どもが運命を受け入れるいじらしさに涙し、ユーゴ内戦を描いた『セルビアン・フィルム』がなぜあれほど暴力を前面に押し出していたかを「信じられないことに、ついにわたしは、この映画が作成された理由を理解した」シーンに胸が縮まる。ジョージアに逃れたロシア人は「私は戦争とプーチンに反対します」という声明書に署名を求められる。言論と思想の自由を否定する作法が、ヨーロッパ側にも訪れはじめている。マルセイユでは「良い雰囲気」のバーよりも、「海岸に行き、海を眺め、磯のにおいを嗅ぎ、打ち寄せる波の音に耳を傾けること」「ただぼんやりすること」が傷を癒やしてくれると。人文に影響する歴史的事象を、リアルタイムで見つめている。
【討議】
3.戦争とアイデンティティの問題――ロシア史・ソ連史のパースペクティヴ / 塩川伸明+池田嘉郎
『現代思想2017年10月号 特集=ロシア革命100年』にも寄稿している東京大学閥の歴史学者ふたりによる分析対談。ヨーロッパへの憧れと反発の交じったアンビバレントな思いから説き起こし、ソ連解体の衝撃を大英帝国とのアナロジーで読者に分かりやすく伝えてくれる。西欧中心主義の綻びが、西欧そのものではなく「周縁化されていた西欧」から始まったとみる視点が腑に落ちた。そしてこれから「ウクライナは最初からウクライナだった」という歴史認識がひろまり、また第二次世界大戦を大祖国戦争ではなく、それぞれの民族からみた関わり方から捉え直すようにもなる、歴史認識の変化のスイッチにもなるだろうと。
ソ連における民族カテゴリーが「現地化政策」「アファーマティブアクション」によってなされ、民族間の優劣というフィクションが成立し、ソ連邦の一部であるロシアの鬱屈も溜まっていったというソ連史と、その影響としての中央アジアのような「疑似国民国家化」という流れは、単に冷戦の、西側の相手方として現前するラスボスのソ連ではなく、その国内事情、ソ連時代が一定期間続いたことで涵養された思想哲学や民族意識に想像力が及んで興味深い。
E・H・カーはちょうど『歴史とは何か』を読み終わったところだったが、1968年には何も語らなかったという。その後、独ソ戦やアイデンティティ・ポリティクス、マンネルハイムの毀誉褒貶などの話題が及んだ後、戦争に反対する国内層の厚さについて、1968年プラハの春で悔しい思いをした知識層がペレストロイカで雪辱を果たしたが、今回は「戦争がどのようなかたちで終わろうと肩身が狭い」といって、文化面での分断が生じることを危惧する。
【境界の歴史】
4.二〇世紀初頭のウクライナ・ナショナリズムとロシア・ナショナリズム――「独立説」と「一体説」の系譜 / 村田優樹
ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人を合わせた東スラブ系を「ロシア民族」とみなす「一体説」と、ウクライナ人とロシア人は歴史的にも現在においても別の民族であるとみなす「独立説」がいずれも近代以降のポリティクスによって生まれたものの見方であるとし、その歴史的系譜を跡付ける。
19世紀中頃の知識人の間での論争は、ポーランド語やドイツ語と比べてウクライナ語が厳しく弾圧された特徴があるが、それは体制に組み込まれた、ウクライナ出身のエリートたちが主導していたと分析する。次に20世紀に入って、「論争は民衆を巻き込み、また制度や権力を対象とする政治運動に発展」していく。ウクライナ語教育と、民族領域自治をもとめたウクライナ・ナショナリストの動きは、「独立」を画策しているとして、また母なる都市キエフの独立を危惧するロシア・ナショナリストに反論され、対抗されていく。
一方、農民たちは「身近な町、村や教会に帰属意識をもった」とあるように、ナショナリストたちの焦燥は大衆に受け入れられていたわけではなかった。佐藤亜紀『ミノタウロス』の時代に入っていくが、そこではミハイロフカ村の主人公ヴァシリは、近郊都市エリザヴェトグラドや港湾都市ニコラーエフ、あとはせいぜい州都のオデッサくらいしか地理感覚がなかった。
そのような状態は、第一次世界大戦とロシア革命というナショナリズム勃興装置としてのイベントを経て、ソヴィエト新体制が「独立説」を認めるかたちで急速に成立することによってようやく変化する。ここにおいて国民投票のような民主プロセスを経なかったことがロシア・ナショナリストたちのつけいる隙にもなっているし、ウクライナ人たちの歴史的なアイデンティティの喪失感にも繋がっているのではないかと指摘している。
5.埋葬されない帝国の記念碑――ウクライナ戦争と境界の消失 / 平松潤奈
前半はウラジミール大公像の出現を題材に、記念碑の「過去と区切りをつけた現在の社会の持続的安定性や、国家間で合意された国境の不可侵性によって支えられ、また逆に合意や区切りや安定といった抽象性を、限定的な物質的量塊によって表現する」性質と、ヨーロッパの東半分では冷戦後に「記憶は石に定着せず、市民は歴史小説や映画をとおして記憶を反復強迫的に体験し、政治は歴史論争によって形作られていく」といった戦争の背景を説明する。
その後、「ホロドモール(人為的大飢饉)」を巡る議論について『アファーマティブ・アクションの帝国』を参照しながら紹介していく。「ウクライナ出身のフルシチョフによる1950年代後半のスターリン批判においても、この問題はとりあげられなかった」が、ナチスドイツによるウクライナ占領期が唯一声を挙げる機会だったと。ゆえに実際に声が挙がったこともあったが、「飢饉のことを少しでも語れば、それは”ヒトラーのプロパガンダ”となる」とも。ロシアがウクライナを「ナチス」と呼ぶ根源がここにあると理解できた。
またウクライナのことを「ジェノサイド」の主体とも呼ぶが、それはロシアが「ロシア以外の国は、加害責任をロシアに課してみずからを全面的な被害者とみなし、犠牲の記念碑を立てることが可能であった」のに対し、「ロシアだけは全面的な被害者となりえず、全面的な加害者の立場に立たされた」ことによって、「一方では加害責任を問う国々に対して鏡像的な記憶政治によって相手を非難するようになり、他方で自国内の犠牲の想起の活動に対しては概して抑圧的な対応をするようになった」ために「スターリン時代のジェノサイドの加害責任を問われたことに対して、相手に同じ言葉を返すという鏡像的身振り」をとることになるとする説明は分かりやすかった。
そのほか「陸続きの植民地は、海外植民地と異なり、宗主国と植民地の境界がはっきりしない」ことによる中心部における弾圧の成立なども腑に落ちる。
6.実体化する境界――「ロシアーウクライナ」の二項対立の図式をめぐって / 中村唯史
「ロシア-ウクライナ」の二項対立は「マリウポリの住民の三分の一がロシア人であり、六割を占めるウクライナ人も含めた全市民の九割以上がロシア語を主要な使用言語としていること」をはじめとする、ロシア系市民、ロシア語話者の死傷・遭難を覆い隠す力として働くことを、ユーリー・ロトマン『文化のタイポロジー的記述のメタ言語について』における「我々/内部」と「彼ら/外部」の二項対立の理論的分析に基づき分析する。
中盤では著者の専門である帝政ロシア~ソ連時代の文学・文化の担い手たちが多く登場し、彼らの民族意識や言語戦略などが語られて興味深い。
「ソ連体制は「資本主義国家」という他者と「社会主義」の自己を分かつイデオロギーの境界が最上位にあり、民族、言語、宗教等々を分かつ境界がこれに従属する構造だった」ところ、「ペレストロイカ以降は、この支配的だった境界が急速に弱体化するにつれて、それまで従属的だった諸境界が支配的な力となっていった」のだが、そのときに、民族国家としての経験を持たなかった領邦たちが様々な軋轢や齟齬に直面することになったという。
7.割れた洗礼盤――「ロシア世界」という想像の共同体とその終焉 / 高橋沙奈美
すごいボリューム。のめり込んで読んでしまった。①「ルーシ受洗」というロシア世界イデオロギーを画す出来事、②東方正教会の「独立教会制」、③世俗権力の動向に翻弄されたウクライナ正教の分裂の歴史、④ロシア正教会・ウクライナ正教会の戦争に対する姿勢に分けて順を追って論じている。
①については、「988年のキエフ大公ウラジミールの正教受容」によってロシア、ウクライナ、ベラルーシの三兄弟が分かちがたく結びついたとのイデオロギーが「エスニック・ナショナリズムを注意深く排しながら」描かれているとする。
②において、ニカイア公会議によって「ひとつの都市には、ひとりの主教、ひとつの教会」と定められたことで民族ではなく世俗の国境に従って教会制度を発展させた東方正教の(ローマ法王を頂点とするカトリックとは異なる)組織的特徴が、19世紀から20世紀にかけての社会変動によって多くのディアスポラが生じ民族を単位とした教会へと再形成されていった流れが示される。そして、ロシア正教会は「こうした現状に対して、領域による独立教会という原則に立ち返るよう訴えている」という。「ロシア正教会にとって、「聖ルーシ」の中核をなすウクライナは、正統に認められた「教会法上の管轄領」であり」戦争の正当化へと結びつけられていくことになる。
③では分裂したウクライナ正教が、2014年のクリミア併合・ドンバス紛争を期に統合されていくダイナミックな状況を分析する。1686年以来のモスクワ総主教座に認められたキエフ府主教座に対する権限が取り消され、コンスタンティノープル総主教座から認められたOCUは、政治的な圧力も含めた管轄変更を促進しつつも、UOC-MP(ウクライナ正教会モスクワ総主教座)に属する教会を切り崩すことがなかった。
④では、今回の戦争でモスクワ総主教座の戦争支持姿勢が明確化するにつれて、「総主教座のための祈祷をとりやめる」というプロテストに繋がったが、それでもなお合同に向けた動きには繋がっていかないという、各教会の保守的な姿勢が見える。しかしそれは「世俗的な物差しで教会を測ってはならない」という徹底した信仰心に起因するものでもあり、評価は難しい。
8.ウクライナの隣人としてのポーランド――戦後ポーランド知識人の思想と行動から辿る二国間関係 / 中井杏奈
戦後ポーランド知識人3人に注目してウクライナとの二国間関係を読み解く。「一方的とさえ思えるほどの強い眼差し」と言うが、アンソロジーの編纂、ソ連からの独立の承認、マイダン革命の支援といったスポットの業績を中心に据えただけでよく分からなかった。冒頭や末尾にある二国間関係のファクトを掘り下げてもらった方が一般読者向けにはありがたかった。
【何が起こっているのか】
9.ウクライナ文化の危機の本質――侵攻の口実にされた「文化」と時代錯誤の植民地主義 / 加藤有子
イェール大学スナイダー教授による「植民地主義」という指摘を切り口に、オリエンタリズム以来の、差異を見出すことで侵略を正当化するロジックとは対称的に、プーチンの侵略が差異を認めず、差異がないことを侵略の根拠としているとの分析や、同一性の根拠として文化や言語の類似が挙げられていることに対して、類似性が歴史的な所産であることなどを指摘している。
ウクライナの代弁者として各国では当事者を招聘したオンライン集会が開かれているのに対し、日本ではロシア研究の視点が全面に出ており、また「ヨーロッパの中心で起きた侵略」という驚きの文脈が語られることでオリエンタリズムを強化するとの危惧も示されている。
10.未来なき社会はおぞましい夢を見る / 白井聡
ロシアの侵略は「NATOの東方拡大はしない」という冷戦後のアメリカの約束違反に対する抗議であると捉えればまだ理解できるが、そこに「新ユーラシア主義」という西欧でもアジアでもない独自の精神共同体を構想し、反ファシズムを掲げて大祖国戦争という過去の栄光を参照する姿が理解の及ばない滑稽なものに映る。しかしそれは未来を失った社会におけるある種当然の帰結であり、日本も同種の危機に陥る可能性があると警鐘を鳴らす。
11.「解放」という名の侵略 / 岩下明裕
アメリカと同じ「大国」であるにも関わらずロシアが国際社会において軽く取り扱われることを「差別」ととらえる、プルシェンコ発言に代表されるルサンチマン。
国際司法裁判所の法理、コロナ禍による外交の停止が国の指導者たちを内向させたのではないかとの仮説。そして根室と稚内の外交停止という危機など。比較的ライトに書いてある。
12.ドンバスの保護、ウクライナの脱ナチ化――露ウ戦争の目的と矛盾 / 松里公孝
「政策の結果予測であり、善悪判断ではない」として、ロシアの戦争目的であるドンバスの保護とウクライナの脱ナチ化を実現するため(あるいはそれと矛盾する形で)どのように戦局や作戦行動が推移したかを分析してある。
ウクライナ全土への展開は議会承認の範囲を超える越権だったが、そのことによって、2014年当時有効だった「釜」という包囲線を敷くことには失敗している。また全土に戦火が広がることで、「ドンバスがロシアを招き入れた」との視点が、戦後にウクライナとドンバスの戦争を招来しかねない。
脱ナチ化については、マリウポリ籠城戦における「人間の盾」批判が、過激派とレッテルを貼った者たちを追い詰めたらどうなるか予測できなかった、という自己矛盾となっていること、またウクライナのモチベーションの高い右翼活動家を戦火のどさくさに紛れて抹殺する意図があるのではないかと仮説を立てている。
13.ロシア語を話すユダヤ人コメディアン VS ユダヤ人贔屓の元KGBスパイ / 赤尾光春
文字が小さくて読むのに時間がかかるが内容は充実。ユダヤ人ゼレンスキーのバックグラウンドや、プーチンのユダヤ人との融和政策が戦端によって変質している姿などをイスラエルの立場やホロコーストの歴史修正などに触れながら多面的に論じてある。
14.ロシアによるウクライナ軍事侵攻は道徳的に正しいのか? / 眞嶋俊造
戦争の正義(jus ad bellum)の6原則「正当な理由」「正当な機関」「正しい意図」「最終手段」「成功の合理的な見込み」「結果の比例性」のうち、ロシアの軍事行動は「正しい意図」が「不正を正し、平和を回復する」という理由から「非軍事化」や「非ナチ化」を意図するのところまで導き出すのは行き過ぎとして、原則を充足していない故に、道徳的正しさを持たないと結論する。
【〈大国〉の実相】
15.疑念の文化 / サーシャ・フィリペンコ/奈倉有里訳
ペテルブルグに留学したベラルーシ人が、ロシア人は「おそらく」ではなく「実際」から話を始める、疑念の文化を喪った国民であって、プロパガンダの浸透しやすい国民性を軍国主義教育によって植え付けられてしまったと描写するエッセイ。
16.キエフの聖職者が作ったロシア国家像 / 下斗米伸夫
キエフ公国からソ連を経て現代ロシアまで、正教との関係や学説などの推移。専門的で分かりにくかった。
17.イデオロギーと暴力 / 乗松亨平
リアルポリティクスの観点からは非合理的なプーチンの行動の裏の「隠された思想」を取り沙汰するのではなく、イデオロギーとリアルポリティクスの関係を検討する。具体的には西側の悪を真似る「復讐のイデオロギー」と罵倒語をはじめとする「暴力の言語」「テロルの論理」が、20世紀のイデオローグから継承されていると分析している。
18.「ドゥーギン=陰のメンター」説を解体する / 浜由樹子
アレクサンドル・г・ドゥーギンがプーチンの陰のメンターという説が出て来たのはプーチンの行動の不可解さに基づくもので、実態とは言い難いと言うことを、ドゥーギンの思想的出自や展開、政治勢力との関わりを紐解きながら確認していく。一つ前の乗松論考と合わせ読む。
19.地政学か、普遍主義か――ロシアとドイツ右翼の共同戦線? / 大竹弘二
90年代以降に「帰還」したロシアドイツ人がドイツ国内で溶け込めていないことを例にしつつ、西欧の新右翼がロシア「ネオ・ユーラシア主義」と手を携える様子を活写している。タクソクラシー(海洋支配)とテルロクラシー(陸上支配)、普遍主義と反普遍主義の闘争といった、西欧普遍主義への反発が、「エスノプルーラリズム」、文化的な差異に基づいて政治共同体が圏域を作って棲み分ける国際秩序構想の新右翼と親和するという。「精神的人種」の考えは人種主義のレッテル貼りを避けるために都合が良いものの、本質主義的である点で人種主義の誹りを免れないし、無理のあるイデオロギーであるとする。
20.「新世界秩序」陰謀論と「第三のローマ」としてのロシア / 辻隆太朗
「既存の秩序や日常を打ち破る事件や出来事は、陰謀論の土壌となる」とし、新世界秩序(アメリカによる世界の支配)への挑戦がロシアの使命とする。ユダヤ/フリーメーソン/イルミナティ陰謀論は、ソ連崩壊に伴う急速な社会変化に伴って流行した。
グラスノスチの情報公開によりこれまでの「消毒された」情報の反動として暴露的な情報が横溢したことが権威ある人々にとって「不道徳」と堕落・退廃と捉え保守的心情に訴えて憂える陰謀論の形式を踏襲した。
後半ではロシア正教会との関係や「第三のローマ」のしての自負がロシアにおける陰謀論胚胎の特殊事情になっていること、ネオ・ユーラシア主義の陰謀論的性格を指摘している。
21.ロシア的身体――映像の中の君主たち / 畠山宗明
抽象的で分かりにくかった。プーチン、ゼレンスキーともに映像を通し自己表象をしていることを示し、強い権力者、自己同一性、可塑性を示すプーチンと、多彩な引用を駆使するゼレンスキーが対比的かつ類似的であるとしむむ、『イワン雷帝』をはじめとしたロシア映画における君主の身体性にかかる表現を分析している。
【表現の/と政治】
22.「プーチン政権は最終章に入ったと思います」ボリス・アクーニン、戦争そして「本当のロシア」を語る / ボリス・アクーニン/ジェシー・ケイナー(聞き手)/ターニャ・ミツリンスカヤ訳
ディアスポラロシア人の支援機構「本当のロシア」を立ち上げた作家へのインタビュー。ロシア国民もまた被害者であるという視点。経済制裁とともに情報制裁をとるのは政権を延命させる悪手であり、20年代の亡命者やソ連時代の知識人の本を読むことが役に立つと訴える。
23.アート・廃墟・再生――ウクライナとロシアの美術界の現在 / 鴻野わか菜
亡命し制作するパヴロ・マコフ、キーウにとどまるニキータ・カダン、ロシアで活動するパーヴェル・オジェリノフへのインタビュー記事。現代思想のために寄稿依頼の後にインタビューしたのか、インタビューしてあった記事の発表の場を求めたのか不明だが、タイムリーな質問とアートの役割を三者三様に回答してある。
24.ロシア知識人の苦悩――カインは何度アベルを殺すのか / 沼野恭子
ロシア知識人による言動の記録。街頭デモは弾圧され、プーチンへの私信やガーディアンへの寄稿では悪夢・恥という言葉が頻出した。『われら』や『一九八四年』のモデルとしてディストピアを表出し、「ロシア語が話されているならそこはロシア」というプーチン演説に話者としての戸惑いを得る。「非スターリン化もなければ、共産党のためのニュルンベルグ裁判もなかった」ロシアに「非プーチン化」ができるかをオープンエンドとする。
25.フェミニストはなぜ戦争と闘うのか / 高柳聡子
2月25日の朝に登場したフェミニスト反戦レジスタンス(FAR)は、暴力を減らし、人々が互いに平和に共存するためにあるとして戦争に反対する。ロシアの家父長制は家庭内暴力を許容する法制度に結晶しており、女性たちは「静かなピケ」によって可視化を続けてきた。その延長にFARの活動はあると報告する。リーダーのダリア・セレンコは93年生まれと若く、詩人である。欧米のような第二波フェミニズムがなかったロシアはまだまだ男性軍事中心主義が居座り、芸術分野による抵抗と対話の模索が緒についたところだったと。
26.混沌から分断へ――現代ロシアの文学と政治 / 松下隆志
文学を通して90年代~00年代のロシア思想を振り返る。90年代の自由化は文学の社会的影響力を低下させたが、ポストモダンを導入した。00年代からは急速に保守化し、権力と文学がお互いの距離を探りながら進んだ。10年代以降は権力に阿る言説が存在感を増してきている。出てくる作家や作品があまり馴染みがないので流れだけざっと振り返るに留まる。
【冷戦という時空間】
27.ソ連/ロシアの宇宙開発の国際政治上の意味 / 鈴木一人
面白かった。ソ連の宇宙開発がミサイル研究過程における偶然により人類史に名を残した経緯、冷戦後に廉価な商業シャトルとして市場に独自の地位を得たこと、そしてウクライナ侵攻においてイーロンマスクから技術供与を受けたウクライナに、20世紀の遺産のみで戦うロシアが太刀打ちできなくなったことがコンパクトにまとめてある。
28.“原子力国家”ソ連とウクライナ / 市川浩
ザポロージェ原発、チェルノブイリ原発跡地の占拠による放射性物質の飛散や兵士・住民の被曝が危惧される情勢の中、ソ連原発政策を振り返った梗概。原子力の平和利用をアメリカに先駆けて掲げ、黒鉛チャンネル炉及び核不拡散条約後は軽水炉を東側に普及させていく。後半はウクライナのエネルギー構造(ドンバスの石炭は製鉄燃料に使われ、民生用は乏しい)や、原発反対運動の進展など。
29.プーチンが踏みにじる“古き良き“ソ連――あるいは、ウランバートルとキーウとモスクワをつなぐ文化圏の終焉 / 島村一平
『ヒップホップ・モンゴリア』の著者によるウランバートルとキエフの景観の類似性、フルシチョフカやブレジネフカと呼ばれる集合団地や、食文化の類似性を描写したソ連文化圏の記憶。それが今回の侵攻で破壊されたとの見立て。
【深層と周縁へ】
30.ユーラシアの臨界点――ウクライナ危機に寄せて / 福嶋亮大
文芸批評家による6項目にわたる分析。
アジア政治史において、10年代は西洋近代の価値観に対するバックラッシュの時期だった。ポスト帝国のロシアは二流国に転落することを何より恐れている。梅棹忠夫のユーラシア帝国分析に欠けている「帝国同士の接触」としてネルチンスク条約の再評価。ポジティブな歴史を偽装する帝国など、面白い視点だった。
31.キエフとモスクワのあいだ――前近代アフロ・ユーラシア史からの視界 / 諫早庸一
モンゴル帝国の歴史(ジョチ・ウルスとフラグ・ウルス)を紐解くことで、ウクライナの地が黒海を通して中東との深い関係にあることを再確認する。無理矢理著者の専門に近づけた感もあるが、あまり馴染みのない歴史の話題を読めて面白かった。
32.色褪せた規範のゴミを紛争地に捨てるな / 酒井啓子
欧米の価値観にもとづく国際秩序に対し、旧植民地諸国が否を突きつける現象の描写と、「いい介入」と「悪い介入」の差をつけるために持ち出される「人道」という美辞麗句が力を失っていくことを喝破する。失われた規範を埋めるように、自分たち自身の「正しい規範」が代替として持ち出されていく。中東の視点から欧米中心国際秩序を見直すきっかけが提起される。
33.シリアとウクライナ――大国間の「代理戦争」がもたらす悲劇 / 青山弘之
続いてシリア内戦との比較視点。アメリカをはじめとするシリアで蛮行を繰り返す欧米諸国が、ウクライナ戦争勃発後にだんまりを決める様子と、それらを全く報じないメディアを批判する。「ロシアの非道を強調すればするほど、身動きが取れなくなるのが、ウクライナをめぐって正義を振りかざす欧米諸国の外交の実情」であるとする。また、シリア国民がロシア側とウクライナ側の両方に傭兵として雇われることで、ウクライナの地でシリア国民が対峙する悲劇が起こる懸念があるとする。
【いま〈戦争〉を問う】
34.ウクライナ戦争の背景 / マウリツィオ・ラッツァラート/杉村昌昭訳
こちらは西欧全体というより、アメリカの「反革命」戦略に視点を寄せて、20世紀以来続く世界戦略の失敗が、被抑圧者からの反発を頻発させ、収拾をつかなくさせる現状を解きつつ、革命について分析しながら連帯を促すテキストになっている。
35.再領土化(バックラッシュ)の地政学的衝突という悲劇――ウクライナ危機をめぐる錯視について / 土佐弘之
ネオリアリストによる現状分析である「宥和を上手くすれば侵攻は防げた」との言説を、プーチンを合理的なプレイヤーとみなす幻想に陥っていると批判し、国際政治は既に大国間のパワーポリティクスだけではなく、デジタルプラットフォームを通じた共感の政治にも大きな影響を受けているし、プーチンの思想にファルス回復運動の側面があると指摘する。
後半の国際機構の不全、リベラル民主主義対専制主義という図式の相対化、資本主義とリベラル民主主義の蜜月の終わり、権威主義的資本主義が専制主義と収斂的に同じモノへと向かっていく予測なども面白かった。
36.自由と平和を呼びかける〈声〉とその射程――中心と周縁について再び考える / 五野井郁夫
ウクライナ国旗の絵文字や青と黄色のアイコンなど、世界市民の政治行動として直接民主主義の方途だけが現在のところ一般市民が世界政治に参加するための手段となっている、という分析から。その後ロシアにおける言論統制と、それにもかかわらずVPNによるロシア国民のアクセスを通じて、情報を通じた支配と自由の間の格闘が描写される。最後に、「中心-周縁」問題は紛争だけではなく第一世界の都市にも偏在するとし、声をあげる重要性を説く。
37.肉体、領土、男性国家――戦争における物質性の復権 / 海妻径子
ゼレンスキーの髭やロシアの宮殿などから、表象の持つイメージについて説いたあと、フェミニズム的観点から、専制主義による暴力的抑圧の拡大や、闘う男らしさへのヘゲモニー付与、今後のジェンダー再編予測など。
38.ウクライナ侵攻とダブルスタンダードーー「避難民」対応が映し出す不条理な世界 / 平野雄吾
シリア・クルド・アフガニスタン・ミャンマーなどの難民と、ウクライナ難民との扱いのダブルスタンダードから始めて、「避難民」という言葉の創出による難民の取り扱いへの批判逃れを描写し、欧米でも起きている二重基準を「キリがない」と論じる。
【応答への方途】
39.ウクライナ侵攻を報じるマスメディアの荒涼たる砂漠にようこそ / 金平茂紀
9.11やソ連崩壊を回想しながら言葉の力を振り返る前段、日本メディアの現地取材が腰が引けていたのは「自己責任」論以来の風潮を反映していると分析する中段、ショックドクトリン=惨事便乗型資本主義で好き勝手に言う現論陣たちを批判する後段。
40.「戦争の語り」と私たちの社会――ウクライナと地続きのドイツで戦争の報を聞いて / 柳原伸洋
ドイツメディアが「国際情勢や経済をはじめとして大状況を重視する保守系新聞と、個々人を頻繁に取り上げるリベラル系新聞に分かれた」ことから、個人の力・エピソードの価値が高まることで戦争が抑止されてきた経緯を振り返る。日本は「八月の戦争ジャーナリズム」が繰り返されてきたが、戦争情報を「消費し尽くされ、弛緩の段階に達していた」とも言えるコンテンツへと没却してきたと分析する。後半では若い人たちの声を拾うべしとしつつ、ドイツの街頭デモが戦争を語る行為を可視化していることに触れ、人々は戦争に触れるだけの余力のない”忙しさ”が強いられていると仮説する。
41.グレーゾーンの彼方 / 若林千代
沖縄研究者による「グレーゾーン」に視点を置いた分析。P216沼野論考でも触れられていたアンドレイ・クルコフのテキストを引用しながら灰色を「自然と人間の交差する領域の豊かさ」や「二つの地平に挟まれた」特徴を今回の状況のアナロジーとして理解しようとする。
【アンソロジー】
42.ウクライナ人の世界を知るための四文献 / 原真咲選・訳
モスクワ人魂/ドメィトロー・ドンツォーウ
1952年 モスクワ人を相手が羊か狼かによって態度を変える人間として描く。
モスクワ、マロシェーイカ/ユーリイ・シェヴェリョーウ 1952年 モスクワに対するウクライナの文化的侵攻が近世から継続してきた系譜を辿る。
ウクライナ軍と国民に告ぐマニフェスト/伝イワーン・マゼーパ
18世紀の反乱時におけるマニフェスト。
誰もが平和を切に求めり/イワーン・マゼーパ
同じく反乱首魁による詩。
解題に力が入っている。冒頭でロシア人イメージのルネサンス期からの継承、続いて歴史を奪われた歴史、そしてキリスト教周縁世界としての位置どり、後半で18世紀の民族崩壊とその後の圧政、というようにウクライナ精神世界の重要なエポックが盛り込まれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
