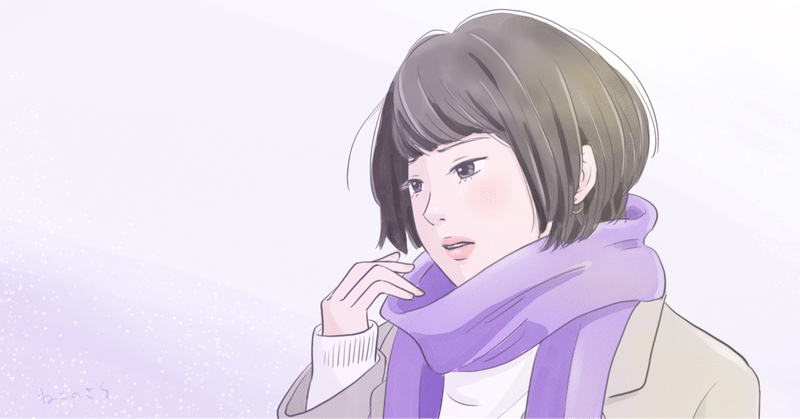
【心得帖SS】無自覚で「ファンネル」飛ばしていませんか?
「…なによこれ、感じ悪いわね」
先ほど届いたメールの文面を見て、四条畷紗季はムッという気持ちになった。
少し気持ちを落ち着けるためにマイマグを持って給湯コーナーに向かう。
「怖い顔してるね、サキサキ」
ドリップコーヒーをカップの上で蒸らしていた星田敬子がそう言って尋ねてきた。
「ん、ちょっと嫌なメールを読んじゃって」
先ほどの気分を思い出して、やや陰った紗季が応える。
「なに、不動産投資とかの迷惑メール?」
「違うよ。本社の商品開発部から」
「あら、意外ね」
「それがおかしいのよ」
憤懣やるかたない様子の紗季は、手にしたスマホから先ほどの社内メールを呼び出して敬子に見せた。
『こんなくだらない事で、開発メンバーの手を煩わせないでください』
「…これだけ?」
「そ」
ルイボス茶のティーバッグをマグカップに浸した紗季は、鮮やかな赤茶色がぐるりと染み渡っているのを眺めていた。
「個人アドレスじゃなくてチームアドレスというのもタチが悪いわね」
送信元のアドレスを確認した敬子が唸る。
「取引先のバイヤーさんから『あの商品(凄く長い名前)』の効能に関して問合せがあったの。うろ覚えだったので商品開発部の裏付けが欲しくてお願いしたら、返事の代わりにこのメールが来た…」
うううっと思い出しイライラに入った紗季の頭を、敬子はポンポンと叩いた。
「サキサキの依頼ルートは特段違和感無いし、〆切とか無理な設定もしていないと思うよ」
敬子が首を捻る。
「少し探りを入れてみた方がいいのではないかしら?」
「探りって…あっ!」
『紗季さん、この間は有難うございました』
「こちらこそ、楽しかったよ。由香里ちゃん」
白衣を着た祝園由香里が、画面の向こうでにこやかに手を振っている。
2人は其々の事務所のミーティングスペースに篭って、リモート通話を繋いでいる。
ひと通りの近況報告が終わったあと、紗季は早速本題に入った。
『…そうですか、紗季さんまで』
少し考え込むような姿勢を見せる由香里。
「心当たり、あるんだ」
『はい…』
『紗季さんは、あの商品(凄く長い名前)を開発したチームはご存じですよね?』
「知ってるわ。御幣島さんを含めた5人のメンバーだったよね」
ホームページの会社紹介にも出てくるので、御幣島密も参加していた開発チームのエピソードは当然認識している。
『当時のチームリーダーはもう定年退職されましたが、後を継いだ御幣島チーフは更に努力を重ねて成果物を産み出して行った。でも…』
「残りの3人は、違ったのね」
紗季の額から、つうと汗が流れ落ちた。
『残りの方…お名前は伏せますが、一応御幣島チーフと同じグループに所属していますが、過去の成功体験に囚われて、ここ数年殆ど研究開発ができていません』
心底哀しそうな表情を浮かべた由香里は、話を続ける。
『変にプライドが高いので、開発プロセスに関して何かと口を出して来て、何度か進行の妨げになったことがあります。表向きは御幣島チーフの名前にぶら下がって話を進めるので、若いメンバーの中には彼等の影響を受けているものも出てきました』
彼女の話を聞いて、紗季の中で何かが繋がった。
「分かった、私への嫌がらせメールはその取り巻きの1人かも知れないのね?」
『思い当たる人物が、浮かんでいます』
由香里は唇を噛んで言った。
『研究開発に没頭するあまり、周りが見えなくなった人。優れた商品を生み出すことがゴールになって、お客さまの顔を見ようとしなくなった人…』
そこで言葉を区切った由香里は、蒼白くなった顔を上げて次の言葉を捻り出した。
『彼は私の…同期です』
「で、その男の子はどうなったの?」
話がひと区切り着いたところで、敬子は紗季に尋ねた。
「昨日退職願いを出して、受理されたみたい。もともと辞めようと思っていたらしいけどね」
開発至上主義に陥っていた彼は、紗季に限らず社内の様々な部署とトラブルを起こしていたらしい。同期のよしみで都度由香里がフォローしていたが、治まるどころか段々エスカレートしていったそうだ。
「あと、ファンネルを飛ばしていた老害は?」
「ファンネル…ガ●ダム?」
「ネット用語なのだけれど、支持者や仲間、立場が下の者を使わせて自分自身は直接関与せずにコトを進める輩のことを指しているわ」
「なるほど、それでファンネル」と腹落ちした紗季は、由香里から聞いた情報を思い起こした。
「3人とも、来月付で関連会社に出向となるみたい」
ロジスティクス部門を請け負っているその会社では、開発時代の栄光を振り翳す機会もおそらく出てこないだろう。
紗季は、リモート通話の最後に由香里から聞いた御幣島密の言葉を思い出していた。
『過去の体験にしがみ付き、現状に満足しているだけでは何も生まれない。一歩前に進むこと、深く掘り下げることが、自身の成長に繋がるのだ』
「私も、無意識のうちに奢りや昂りが出ていないか、気を付けておかないとね」
由香里の哀しそうな表情を思い出して、紗季はしみじみと言った。
「そうよ、サキサキは人気あるから『ボ、ボキのサキたそに、め、面倒な仕事を押し付けるなよぉーっ!』みたいな無自覚ファンネルたちを飛ばさないようにしないとね」
「…何よそれぇ」
油断していたところに敬子の発言で妙な想像をしてしまった紗季は、パンと手を叩いて次の仕事への準備を開始した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
