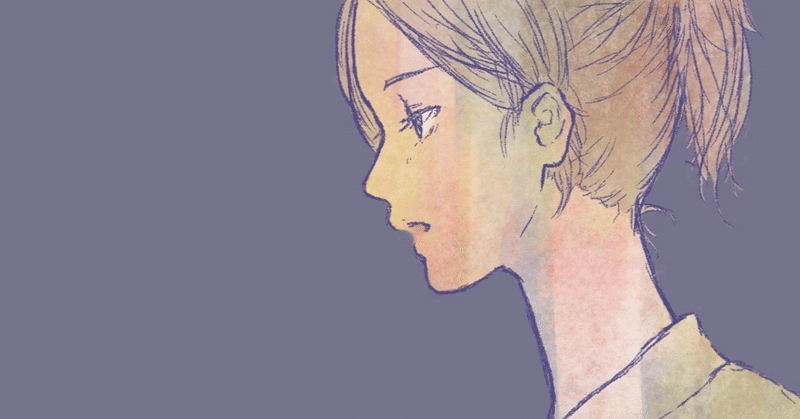
【備忘録SS】それは「寡黙な」協力者。
「この時期は、どうしてもタスクが積み上がるからなぁ……」
部内会議の最後に、寝屋川慎司副部長が口を開いた。
「皆んな、1人で抱えずにチームでタスクを熟すように」
わざとらしくこちらを見てくる彼を無視して、四条畷紗季はトントンと書類を整えた。
「本八幡君、ちょっといいかな?」
会議終了後、紗季は隣に座っていたグループメンバー、本八幡ハジメに声を掛けた。
「……はい」
トレードマークである大きな黒縁眼鏡を軽く上げて、ハジメは頷く。
「それじゃあ、向こうのミーティングルームでお願いね」
頭の中でタスクの振り分けをシミュレーションしながら、紗季は足を向けていった。
「……という感じだけれど、本八幡君から見て、何か違和感あるかな?」
ざっくり引いたスケジュールとタスク配分を共有したあと、紗季はハジメに尋ねた。
「……はい、特に問題は無いかと思います」
手元のパソコンを操作していた彼は、チャットを1件、紗季に送付した。
「四条畷課長の案を元に、取り急ぎ叩き台を作成してみました。内容OKであれば、このままメンバーにアナウンスします」
「うわ早っ、そして内容バッチリ」
彼女が伝えたいと思っていたことを、ほぼ完璧に表現したものが出て来たので、紗季はハジメの肩をバンバンと叩いて言った。
「これでOKよ本八幡君、案内宜しくね」
「はっ、はい……」
彼女のアクションに、少し身を縮こませたハジメは、そそくさと打合せテーブルから立ち去って行った。
「……あれ?」
「あー、それってセクハラかもですよぉ」
鼻の頭を少し赤くした市川春香が、紗季の方にグラスを向けて言った。
例の一件以来、すっかり打ち解けた2人は、定期的に例のバーで【情報交換会】という名の飲み会を行っている。
「紗季さん、無自覚女子のオーラが出ていますから、気を付けた方がいいですよぉ」
「む、無自覚女子って……」
前場所では、男女問わずフラットな雰囲気でコミュニケーションが取れたので、異性への接し方で頭を悩ませたことが無かったのだ。
しかも、上司と部下という関係性は、初めての体験である。
「春香ちゃん、どうしたらいいのかな?」
「うーん、本八幡君が何を考えているのか、もう少し知りたいですねぇ」
ポケットからスマホを取り出した春香は、アドレス帳を開いてタップする。
「……あ、私、市川でーす。ハジメ君、今どこにいるの?」
(どうして、こうなった……?)
カウンター席の隣で、俯いているハジメを眺めながら、紗季はこれまでの行動を振り返って反省していた。
ちなみに彼を呼び出した張本人(春香)は、別の飲み会に声が掛かったため、入れ替わりでお店を出て行った。
「あ、本八幡君は何を飲むかな?私はビール縛りにしているけど」
「はい……では同じものを」
ほどなく店員が運んできたジョッキに手を付けることなく、彼は虚空を見つめている。
(きっ、気まずい……)
これまでの酔いが一気に醒めていく感覚をおぼえた紗季は、彼の方に向き直った。
「じ、じゃあ、乾杯しようか。本八幡君にはいつも助けて貰っているし」
そう言って、半ば強引にグラスをカチンと合わせる。
ぼうっとグラスを見ていたハジメは、おもむろにそれを持ち上げると、一気に空にした。
「あれ?もしかして結構飲める方なの?」
店員を呼び止めて追加のオーダーをしている彼を見て、紗季が尋ねる。
「いえ……お酒を飲んだのは久しぶりです」
「そうなんだ」
「折角課長にお誘いいただいたので、勢いを付けたくて飲んでみました」
「……やっぱり、わたし訴えられるのっ?」
「え?」
紗季の悲痛な叫びに、ハジメは驚いて聞き直した。
「僕が、恩人の四条畷課長を訴えるはず無いじゃないですか」
「おん……じん?」
「まあ、課長がご存知ないのは当然です」
2杯目の生ビールに軽く口を付けたハジメは、取り出したスマホから、ある画像を呼び出してこちらに向けた。
「あれ、これって、昔の会社紹介ページ……」
そこには、目一杯作り笑顔を浮かべた数年前の紗季が映っていた。
「わっか、私若っか!」
「……今でも、十分お若くてお綺麗ですが」
「有難う、お世辞でも嬉しいわ。それでこれがどうしたの?」
褒め言葉を完全にスルーされたハジメは、少し赤くなった顔を誤魔化すように軽く咳払いをして、話を続けた。
「当時の僕は、色々躓いていて、落ちに落ちていました。そんなとき、四条畷紗季さんの言葉に救われたのです」
『成功しても失敗しても、経験は年輪のように積み重なっていきます。前を向いて挑戦した自分を、どうか褒めてあげてください』
「うわぁ……この女はなんて恥ずかしいことを言ってるのォ」
黒歴史が明らかになったような羞恥心から、紗季は両手で顔を覆った。
一方、すっかり落ち着いたハジメは、そんな彼女に優しい瞳を向けて言った。
「課長の言葉に救われて、今の僕があります。同じ部署で仕事が出来る嬉しさと、何としてもお役に立ちたいという気持ちから、最近若干空回りしていたことは自覚しています」
申し訳ございません、と彼は深々と頭を下げた。
(何だろう、少し似ているな)
紗季自身も、京田辺一登が上司として着任してきたとき、同じような気持ちで業務に打ち込んでいたことを思い出した。
彼女はグラスを手に取って、彼に声を掛けた。
「じゃあ、まずは目の前のタスクを乗り切るところから始めますか」
「はい」
2回目の乾杯は、心地良い音を奏でながら、2人の周辺にゆっくりと拡がっていった。
◾️Kindle書籍「ショートストーリーでわかる 営業課長の心得帖」全3巻好評発売中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
