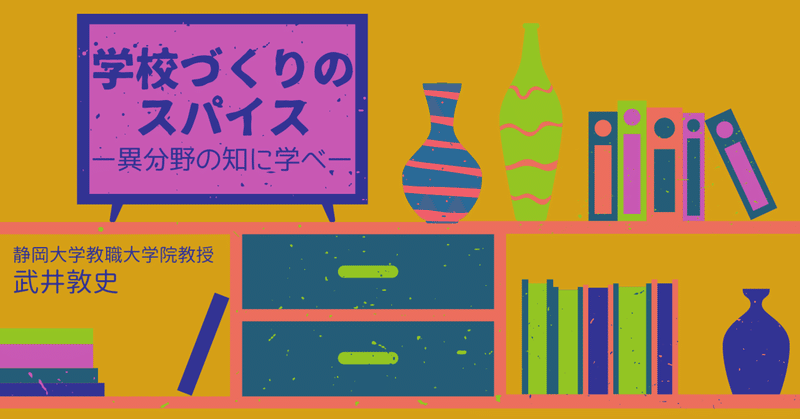
#70「育てる」ことと「賭ける」こと|学校づくりのスパイス(武井敦史)
【今回のスパイスの素】
シェル・シルヴァスタイン
『おおきな木』
今年もまた旅立ちの季節がやって来ました。節目を迎えると、人はしばしば自らしてきたことの意味を省みて原点に立ち返ろうとします。今回はシェル・シルヴァスタインの手による『おおきな木』(篠崎書林、1976年)という絵本を手がかりに、教育という営みの原点に筆者なりに立ち返ってみようと思います。
本書の原作が初めて刊行されたのは1964年ですから、もう半世紀以上も前のこととなります。2010年には小説家の村上春樹氏も翻訳を手がけて話題となりましたが、今回はあえて本田錦一郎氏の古い訳本を使用してみます。

「与える木」の受難
この作品の登場人物は一人の男の子とりんごの木だけです。ストーリーは男の子が幼少期から晩年までの間にりんごの木と交わした五つの対話で成り立っています。
初めの場面は幼少期です。りんごの木があって、一人の子どもが木と戯れます。木の葉を集めて冠をつくったり、木登りやかくれんぼをしたり、りんごを食べたり、木陰で昼寝をしたりします。子どもは木が大好きで、木もそれがうれしかったそうです。
やがて子どもが少し成長すると、以前のようには木のところにやってこなくなりました。ある日ひょっこりやって来ますが、もう木登りはしないと言います。かわりにお金が欲しいのだと子どもが木に告げると、木はりんごをもぎ取って売りに行けばお金になると言います。その言葉を聞いたその子は、りんごを集めて売りに行きます。
その後しばらくして、大人になったその子が木のところにやって来たときには、家が欲しいと言い出します。木はそこで、枝を切り払いそれで家を建てるように提案します。すると彼は家を建てるためにすべての枝を切り払って持って行ってしまいます。
さらに時が経ち、年老いた彼がまた木のところに来たときには、悲しいことばかりがあって遊ぶ気にもなれず、船でここから離れてどこか遠くに行きたいのだと木に告げます。それを聞いた木は幹を切り倒して船をつくり、船出してどこかに行けばよいと提案します。そして今度も彼は言われたように根元から木を切り倒してしまいます。
最後に彼が晩年になって切り株となった木の前にあらわれたとき、木はもはや与えるものがないことを告白します。すると、年寄りとなった彼にも欲しいものが何もなく、ただ休む静かな場所さえあればいいと告げます。そこで、木は切り株に腰掛けて休むように言い、男もそれにしたがいます。
五つの場面をとおして、木は子どもに対して見返りを求めず、喜びを分かち合おうとします。そしてどの場面でもそうすることで木は「うれしかった」ことが記されています。
ただ、この作品のなかには一ヵ所だけ、木がうれしかったことが語られた後に言葉が続いている場面があります。男が木を切り倒し、船をつくって行ってしまったシーンの後です。続く言葉は……「だけど それは ほんとかな。」です。
この一言がこの作品を単なる愛の賛歌にはとどまらない、心のひだを感じさせるものへと高めていると筆者は感じます。
この本の原題は“THE GIVING TREE”(与える木)です。けれども「与える」という行為は、ちょっと考えてみるとそれほど単純なことではありません。
教育という賭け
人は皆、自分がかわいいはずだし、自らの願望を遂げたいという欲も持っています。人間も地球で生存競争を生き残ってきた生物である以上、ほかの動物同様に生命を維持して、より繁栄を謳歌したいと考えるのは当たり前のことです。
そしてもちろん、教師も一人の人間です。
けれども、どんなに自分の欲を追求して成功したとしても、人生最後の結論は決まっていて、そこから逃れることはできません。これがもう一つの「当たり前」です。
そして人もほかの動物同様、それを知っているので、他者へとバトンタッチすることで命の灯をつなごうとします。
ただ人の場合、ほかの動物とちょっと違うのは、生命そのものだけではなく、自らの生きた過程でつくりあげてきたものまでもつなげていこうとする衝動を持っていることです……財産であれ、仕事であれ、思想であれ、生き方であれ……。そしてだからこそ、教育という営みが人類の歴史を通じてここまで拡大してきました。
これまで数多の宗教が、欲望の弊害と与えることの美徳を強調してきましたが、「与える」ことが成り立つのはバトンを受けとる側がいるからです。しかし自分が相手に対して与えようとしたものが、本当に相手の幸福につながっているかどうか、バトンが受け継がれていくかどうかは、何かを与えようとした、その時点ではわかりません。
この意味において、教育とは本質的に「賭け」です。しかも多くの場合、自身ではその結末までは見ることのできない未完の賭けです。教師とは、この未完の賭けを仕事にすることのできる幸運な人たちです(と筆者は思っています)。
「だけど それは ほんとかな。」というこの本に出てくる不意の投げかけは、まさに「与える」ことにともなう不安感、「賭け」としての側面を鋭く照射しています。
教育という営みがおもしろいのは、それが他者の幸福を願って行う大きな賭けだからだと筆者は思っています。けれども昨今の教育活動の隅々に至るまで基準やマニュアルを求めずにはいられない社会の風潮を目にすると、この原点を忘れてしまっているのではないかと感じることがままあります。
教育が命をつなぐ賭けであるとするならば、自らの美しいと感じるものに心を込めて潔く……そう考えてこの仕事に向き合ったほうが、教師にとっても子どもにとっても、日々の生活はもっと輝いたものになるのではと思うのですがいかがでしょうか?
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
