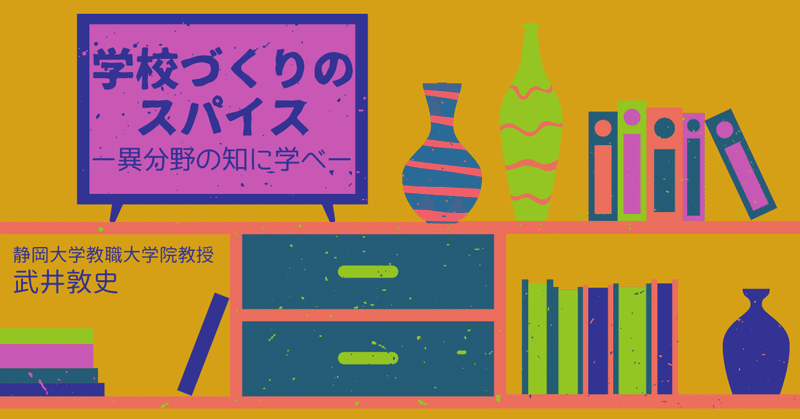
#59「仮」の効用~長尾重武『小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く』より~|学校づくりのスパイス
「動的な生」に特徴づけられる縄文の思想が現在も生き続けているということを前回は指摘しました。今回取り上げるのは、平安末期からの混沌の時代にまさにこの「動的な生」を体現した随筆家、鴨長明の発想です。
今回はイタリア建築史の研究者である長尾重武氏の『小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く』(文藝春秋、2022年)を取り上げます。建築という視点に照らして方丈記を解釈しているのが本書のおもしろいところです。今回は本書にヒントを得ながら、教育における「仮」の効用について考えてみます。

不思議な方丈庵
方丈記は鴨長明が都の外れに小さな庵を建て一人そこで暮らす様子を描いた作品で、タイトルはこの庵に由来します。方丈記は「方」は四角形、「一丈」はおおよそ3メートルなので、方丈というとおおよそ9平方メートルの広さ、現代の基準に直すと4畳半よりわずかに大きいくらいの庵ということになります。
方丈記の前半では、「安元の大火」「治承の辻風」「福原遷都」「養和の飢饉」「元暦の大地震」といった自然災害や火事などについて述べられており、方丈記全体の半分以上がこうした京都が荒れ果てていく様子についての記述で占められています。
長明は賀茂御祖(かもおみや)神社(通称:下鴨神社)のトップである正禰宜惣官(しょうねぎそうかん)の次男として生まれながら、父が早死したことで出世の道を外れた後、和歌や音楽でその才能を認められ、ふたたび下鴨神社の摂社である河合神社の禰宜に推挙されるも、跡目争いから出世の道は絶たれてしまったようです。
社会的地位という意味では、いわば凋落の人生をたどった長明ですが、京都の外れに小さな庵を結び、その生活を楽しむことで長明自身は安らぎを取り戻していきます。方丈記の後半のかなりの部分が、この庵の構造とそこでの生活の様子を語ったものですが、本書を読み進めていくと、この「方丈庵」にはある不思議な点のあることが浮かび上がります。
方丈庵の特徴の一つとしてあげられるのは、長明はこれを「最期を迎える家」として建てた(15頁)ということです。なんと「長明が臨終の床についたとき、目にすることができるのは、西側に掛けられた阿弥陀像、法華教をおいた経机や普賢菩薩(ふげんぼさつ)像など」(92頁)となるように、自身の臨終のあり方まで用意周到にデザインされていたということです。
もう一つの大きな特徴は方丈庵が組み立て式のモバイルハウスであったこと(15頁)です。「土台を組み簡易な屋根を葺き、継ぎ目ごとに掛け金を掛けて解体してどこに移設しても容易に組みたて可能な家として設計された」(32頁)とのことで、車に積めば2台で移動できると方丈記には記されています。
さて、この二つの発想には一見矛盾があります。最期を迎える家ならば、移動可能にする必要はなく、逆に移動する機能を備えているならば、その後の生活が想定されていると考えるのが普通です。
では、なぜ長明はこうした矛盾する要素を一つの庵に組み込んだのでしょうか?
秘密を解く鍵は「ただ仮の庵のみのどけくして、おそれなし」という方丈記中の一文に隠されています。住処を常に「仮」のものとすることによって、無常の世の中でも執着から離れ、死も畏おそれることなく生きることができると長明は考えていたに違いありません。
このような死生観を重ねて見ると、「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」という冒頭の有名な一節に込められた世界観もより奥行きのある言葉として伝わってくるように筆者は感じます。それは、未来に向けてひたすら財を蓄積しようとするのではなく、蓄積によって生まれる制約から自由になって幸福を見つける知恵であり、縄文以来の「動的な生」の考え方にもつながる発想です。
「仮」の効用
方丈記は「「死の形」を自らの小さな家で構想しえた一人の文人の、生の最終章のあり方を力強く述べた作品」(126頁)であり、そこには「仮の美学」が感じられます。
そして現代、方丈記が再注目されつつあります。方丈記をタイトルに冠する著作はここ数年で20作以上も出版され、長明の現代版とも言えるミニマリストやアドレスホッパー(定住しない暮らし方)といったライフスタイルも広く認知されるようになりました。
これら個々の現象自体は一種の流行なのかもしれませんが、背景にあるのは「拡大・発展こそ正義」とする近代の世界観がいよいよ説得力を失い、身近なところにある幸福を大切にしようとする時代意識の転換であると筆者は考えます。
この「仮」の発想を取り入れることで、学校という場所も、次の二つの点で、もっとしなやかなものにしていくことができると考えています。
第一に自分や他人の欠点や失敗に寛容になれることです。「旅の恥はかきすて」という諺がありますが、その時点の当人にとっては重大と思える事態も、長期的に見れば些細な出来事であることが少なくありません。学校で生じるさまざまな問題や失敗も、一過性のものであると考えることができれば目くじらを立てずとも済みます。
その結果、第二に何かにちょっとトライしてみることも容易になるでしょう。授業でもほかの教育活動でも、その実践を完成形と考えると、気軽な試行錯誤を取り入れることはむずかしくなってきます。つまずくことを回避する一番確実な方法は、確実にできること以外に手を出さないことだからです。
完成を求めると組織は保守的になり、「仮」を取り入れることで組織のフットワークが軽くなっていくのは必然です。
現在の学校社会は、この「仮」の発想を失うことで、寛容さを失い、閉塞感を強め、新しいことに踏み出すことに臆病になっているように思えてなりません。どのようなプロジェクトでも、議論が活発になるのは仮説的に実践を行ってみる本格実施の前の試行の期間です。
次期学習指導要領の議論が始まろうとしていますが、このチャンスに教育にも「仮」の発想を取り入れてみてはいかがでしょうか。
【Tips】
▼『方丈記』は中田敦彦さんの動画チャンネルでも紹介されています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
