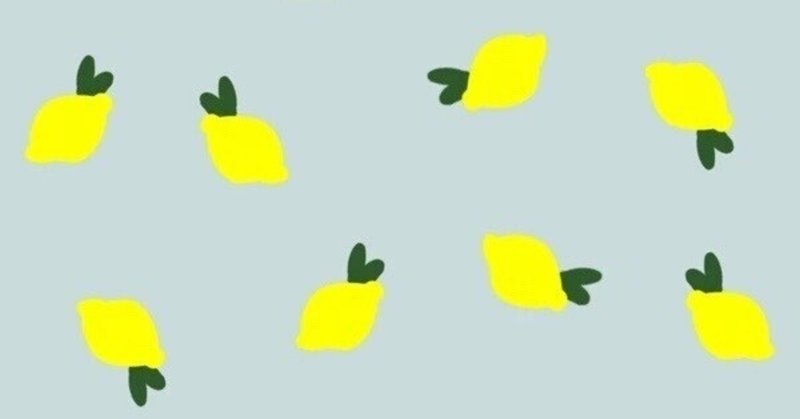
檸檬読書記録 『思い出すこと』
今日の本は
ジュンパ・ラヒリ『思い出すこと』
作者・ジュンパ・ラヒリは、ローマのアパートで「ネリーナのノート」という、詩が書かれたノートを見つけた。
そこに書かれていたのは、ジョンパ・ラヒリによく似た女性で…。
これは自伝なのか創作なのか。
小説ともとれる、詩集。
この本、一目惚れして衝動買いしたもので、最初の詩「失くしもの」をパラりと読んで衝撃を受けた。
本というのは大概、最初の段階で好みかそうでないか分かる気がする。
けれども、いつもは少し悩んだり、図書館で借りて少し読んでから買ったりするから、時間がかかったりする。だが、この本はこれ以上考えなくても、好きに違いないと直感した。
早く手元に残して、じっくり堪能したいと思った。
そして直感通り、やはり凄く自分好みだった。
まず、最初の詩、自分が衝撃を受けた「失くしもの」。
強烈な一例。
ノオルの十三歳の誕生日祝いに
組み立てた、その月のこと。
彼女の部屋の本の背に
立てかけてあったがそこにない。
プールで泳ぎながらつくったくだらな詩なと
消えてしまえ。
(娘よ、おまえはダイヤよりも真珠よりも大切)
ここだけだと、少し状況が分かりにくい。
だけど、最後の補足(注)を読むと、一気にこの詩が興味深いものになる。
ここでは本当の目的語である「カード」が欠けているのが興味深い。《ノオルの十三歳の誕生日祝いにカードを組み立てたその月のこと》。それが部屋からなくなってしまったのだが、詩からも消えてしまったに違いない。
あえて、需要な「カード」という言葉を入れなかったらしい。失ったものを、際立たせるために。
自分はこれで一気に虜になった。
だがこの詩は、まだ終わらない。
まさに悲劇。
(略)
娘の本に一冊残らず
目を通して振ってみたのに。
泥棒や悪魔の仕業という
仮定を除外してからは、
娘がなにも言わずに
わたしの愛情の印を破ったか
捨てたかしたのではと心配になる。
探しても探しても見つからず、ネリーナの不安は募る。混乱していく。
だがある日、散々探して見つからなかったカードが見つかる。
娘が「ママの机の上になにがあるか見て」と言うので、ネリーナは従って見てみると、そこには散々探しても見つからなかったカードが置いてあったのだ。どうやら娘が見つけて、置いたらしい。
そして、ネリーナは気づく。
見つかったことをどう祝おう?
安堵はない。
それどころか、すぐにわかった
ほんとうはその品を
娘にプレゼントしていなかったと。
娘もそのことを知っていた。
だからあんな大人びた振る舞いをしてみせた。
母親らしい思いやり
それはわたしにこそ必要だった。
まさかの衝撃。
ネリーナが本当に失っていたものは、何だったのだろうか。
そう考えると、深さに溺れそうになる。
ネリーナが感じたであろう衝撃が、こちらにまで及んでくるようだった。
その後も、ネリーナは色んなものを失っていく。失くしていく。
記憶、物、ジュエリー。
だがどれも、ただ単純に失くした、だけではないように思えた。
目に見える・感じられるものを失くしたことによって、目に見えない何かを失くしているような。
ただ残念ながら、それが何か、というのは、頭の悪い自分では掴みきれなかったのだけれど…。
詩の中には、失われていくものが多く登場する。
同時に、死がよく登場する。
「母方の祖母の突然の死の
プロローグとなり、
祖父は壁にかかった遺影となって
わたしたちを迎えてくれた。」
「それは二十年前に亡くなった
姑の形見にもらった一着。」
「さまよっている。
水に流された遺体のように。」
「人生の枠組みは
『死ぬ』も含めて
取り除かれるべき不定詞の連続。」
「海の向こうの病院でわたしを待っているのは、生者というより死者に近い
汽車の下に身投げしたようなからだ。」
「死がもたらした饒舌と混乱。」
「ペソア言った。
死は道の曲がり角。」
「心の奥底でわたしは
同じ病院に入院して亡くなった
カルヴィーノに思いを馳せていた。」
等々、死に関する文章が度々出てくる。文章だけでなく、単語さえも。
「葬儀」「旅立った」「幽霊」「殺人」「腐敗」「死者」「死後」「魂」「煉獄」「骸骨」「葬式」「亡くなった」「死海」「墜落事故」
失ったものが端々に伺え、死が蔓延している。だからか自分は、作者はいない、消えてしまったということを強く感じてしまった。
何よりも、ネリーナは詩の中でこう書いている。
こうしてわたしは死者となる。
この詩の作者は存在しない。
かれらの決定により亡き者にされる。
実際は違う意味でそう書いているのだか、余計に作者=死者・いない者という感じが、自分の中で強まった。本当に失ったのは、ジュンパ・ラヒリの中にあったネリーナという感じを。
この詩が出てくるのが、後半というのも余計にそう思わされた。
この本の面白いところは、それだけではない。
表紙。その、色。
目を引くような鮮やかな「黄色」の表紙をしているのだが、その色にもおそらく意味がある。
詩の中で幾度も登場するのが、「黄色」という色なのだ。
勿論他の色も登場するし、「白」「黒」「灰色」といった色も多く出てくる。けれどモノクロに分類される色以外で多いのが「黄色」もしくは「金色」なのだ。
「金の指輪」「黄ばんだ切り抜き」「にごった黄色」「金色の靴」「純度の高い金」「偽の黄金」「黄色い表紙」「黄色い濡れ落ち葉」「葉はだんだん黄色味を帯び」「金属柱」(そして「金曜日」は、流石に関係ないかな。)
等々、結構様々登場する。
何よりも「黄色」が登場するのが、ほぼ詩の冒頭部分「金色のケース」が見つかる。ことから始まる。
ある日、ローマの家のリビングで
鉛筆と携帯充電器を入れた
わたしの金色のケースが見つかる。
調べ物をしていた図書館のガラステーブルに
置き忘れたと思っていた。
貴重なものはなにもない、
ボローニャの混み合う店で
カテリーナからプレゼントされたという
思い出を別にすれば。
失われたもの、同時に思い出が「黄色」によってもたらさせているように思える。
末尾の注釈にも、何度か「黄色」「金色」についての説明が出てくる。
例えば「黄ばんだ切り抜き」。
(略)私の印象ではそれほど黄ばんではいないが、作者は文中に現れる他の黄色や金色に反響させるため、色の細部にこだわったのだろうと思う。
例えば「偽の黄金」。
(略)金は作中で何度もなくなり、執拗に探し求められている。
例えば「黄色い表紙」。
この品物の色は(略)黄色い靴とともに、本中のさまざまな金の品物を思い出させる。
注釈も「黄色」「金色」に注目させようとしている気がする。
途中で、だからこそこの本の表紙は「黄色」だったのかと気づいた時は、凄く興奮してしまった。最初の詩で惹かれて買ったけれど、実は表紙の鮮やかな黄色にも惹かれていたから、余計に。
おそらく、この本の中には他にもたくさんの仕掛けのようなものがあるのだと思う。
そしてそれは、詩だけでは不十分で、注釈を読んでこそ分かったりもする。自分は基本的には注釈を読まないのだけれど、これは注釈までも面白く、作品の1部になっている。
作家の言葉、研究者の注釈、詩を書くネリーナ、3人の登場人物がいるが、全部が混ざって1つの作品になっているのが、この本の最大の面白さだと思う。
最後に、もう1つ個人的に気に入っている詩を。
どうしていまになっても
曇ったガラスに指を這わせると
興奮するのだろう?
つかのまの落書きが
禁断の書のように思えるから?
美しいものを損ねる楽しみ?
湿った鏡に痕跡を残す楽しみ?
滑らかな表面のいたずら書きは
傷をつけると同時に清らかにする。
わたしの描いた
笑う顔、ゆがんだハート、
若々しい走り書き、液状の風景は
窓の外にあるものの一部。
インク無しで描かれた幻の痕跡。
わたしも子どものころから
決まりを守らなかったことの証し。
なんだか少し分かる気がする。
曇ったガラスもそうだけれど、真っ白な、誰も踏み入れていない積もった雪も、同じ感覚になる。
まっさらで綺麗だけれど、汚してしまいたくなるワクワク感がある。
本の中には、物語のような、興味深い詩がたくさん出てくる。目を瞑って開いた瞬間に場面が変わるような、繋がっているのに反対に繋がっていない矛盾が、物語ではなく詩だと実感出来るのも、面白い。
死が匂い、失われることが多くあるのだけれど、死や消失を強く感じるからこそ「生」「言葉」「存在」を凄く感じられて、最初に惹かれた直感通り、個人的に凄く好きな作品だった。
実は同じ作品を紹介している方がいる。↓
正直、こちらの方が分かりやすくまとめられているので、とても読みやすい。こちらを読んだ方が、理解も深くなると思う。
そして自分とは違う、言語の面についても言及されていて、とても興味深い。尚且つ、同じ作者の違う作品も絡めているので、濃厚で深みある、読み応え抜群な内容になっている。
なので、是非是非。
noteをしていると、知らない本と出会える。だからこそ良いのだけれど、同時に、自分が知っている・読んだ本の違う視点、違う見方や感想や考え方を知れる・読めるというのも楽しい、醍醐味でもあるなと思った。
1冊の本で2倍楽しめたから、他の方が読んで感想を書いて、違う見方や共感を読めて、楽しさがもっと倍になったら良いなと、密かな願望を抱きつつ、今回は閉じようと思います。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。
皆様にも素敵な本の出会いがありますよう、願っております。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
