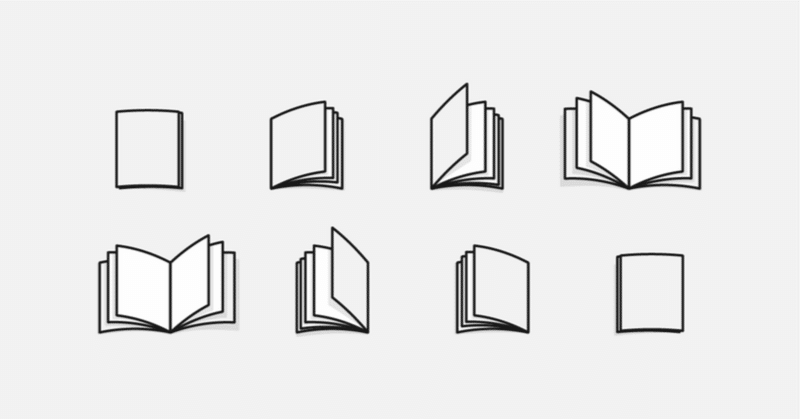
雑感記録(192)
【喫茶店で一服】
今日は朝から取引先とミーティングがあった。
集合時間は10:30。いつもは大抵11:00集合なのだが、今日は何故か30分も早かった。僕は先日の記録にも書いた通り、時間には余裕を持っていたいタイプの人間である。今日は集合時間の1時間前には最寄駅に到着していた。
それで、早く着いたのでこの会議がある度に毎回時間を潰しているカフェに今日も行ってきた。

この定例会議がある際には必ず行っている喫茶店である。昔ながらというか、店内の雰囲気も凄く落ち着いている。いつも時間を忘れてしまいそうになって焦る。そのぐらい時間を忘却させてくれる場所でもある。僕はあまり1人で喫茶店には行かない人間だが、不思議とここは吸い込まれるようにして入っていったことを覚えている。
時間があればモーニングを食べたいのだが、出てくるのに時間が掛かりそうなのと、ここから歩いて会議の場所に向かうことを考慮すると頼めない。せいぜいコーヒー1杯ぐらいが関の山である。しかし、ここのコーヒーがまた美味い。もしかしたら、お店雰囲気フィルターが掛かってしまっているから倍美味しく感じるのかもしれない。いずれにしろ、美味しいと感じられることは幸せであるとつくづく思う。
僕は喫茶店やカフェで本を読むのが実は苦手である。
無論、読めないことは決してない。カフェで読もうと思えば読める。しかし、どうも気が進まないのである。外で読むと如何せん人の目を気にしていけない。集中しようと思っても意識が散乱してしまって、その作品に没頭することが出来ない。何と表現すればいいのか難しいのだが、文字は追えるけれども、意味は追えていないみたいな感じになりがちである。
実際1人で喫茶店に行くと手持無沙汰である。純粋にコーヒーの味やお店の雰囲気。これを味わうのも愉しい。ところが、これだけでは何かが物足りないと感じてしまう。何とも自分は欲深い人間であることかと痛感する。その慰めという訳ではないけれども、せめて意味は追えなくとも言葉だけでも味わおうという気概を持って読書をする。
僕が読んだのは、先日の記録で友人と埼玉県深谷市の須方書店で購入した、古井由吉の『招魂のささやき』である。初期のエッセー集らしいのだが、これがまた最高である。古井由吉の作品は、前の記録でも書いたが所謂「古井由吉的言語」で書かれており、読むのには相当な時間を掛けねば読めない。
ところが、このエッセーは思いの他サクサクと読めてしまうのだ。当然に、所々躓くところはあるが、小説作品と比べたらそこまでではない。やはりエッセーには不思議な力があるのかもしれない。
そういえば、今エッセーと書いて思い出したが、柄谷行人が古井由吉の小説について書いていた時。何の本だったか、あるいは対談だったか…。思い出せないんだけれども…「古井由吉の小説はエッセー的だ」とか言ってた気がする。詳細に覚えてないのが辛いところではある。結局これは「話すように書く」ということのある種、究極系な姿が古井由吉の小説であるということなのだろう。僕も以前、それと比べるには遥かに低俗で最低な文章を残してしまったことが悔やまれる。
そんな訳で、僕は朝からコーヒーを啜りながら古井由吉のエッセー集を読む。この時間が何とも幸せで、この時間が永遠に続けばいいなと思っていた。
先日、知人の運転する車に同乗して、ひさしぶりに東名高速道路を近間まで往復した。その帰りの夜道でつくづく感心させられたことは、私のごとき、車を運転しない人間でも、ここ十年二十年の間に速度の感覚がすっかり変ったということだった。
(福武書店 1984年)P.48
本当に、偶然にもこんな書き出しを読んだ。「速度の感覚がすっかり変った」とはどういうことなのだろう。加えて「感心させられた」というのはどういった所でなのだろうと疑問に感じた。僕も歳をとって(というとまだ早い気もするが、しかし事実歳はとっている)時間が過ぎゆく速さについては感じるところがある訳だ。これはかなり前の記録で時間についてのことは散々書いている。何を書いたか忘れてしまったが。
全然関係ない話をするが、小説の良い所というのは「時間を留める」ということにあるのではないか?と僕は思うのである。僕等が手から溢してしまった時間というものを丁寧に辿ることが出来る可能性の世界なのではないのかと考えている。僕等の時間の可能性を開く時間とでも表現すればいいだろうか。あまりうまい具合に言葉が出てこないのが悔しいのだが…。
僕等は当たり前のように、例えば今日みたいに「10:30集合」とか「14:00から会議ね」というように時間に依拠しながら生きている。時間は無限であり有限である。僕等が依拠する時間は有限である。個々人が所有し尚且つ共有されるところの時間である。僕等が「時は金なり」という時の時は有限性のある時間である。ところが、小説空間を流れる時間は無限であると僕は少なくとも考えている。
その小説に固有の時間とでも言うのだろうか。そういったものは時間の差はあれども存在するように思う。例えばだけれども、最初から最後まで1日の出来事を書こうと思えば書ける訳だし、飛び飛びで「それから数日後」というような言葉で先へ進ませたり、あるいは「あの頃は…」と書き始めて後ろへ戻ることも可能である。小説空間の時間は縦横無尽に広がっているのである。しかし、その時間があまりにも僕らの身体に依拠する時間に合わなすぎると軽く感じられてしまう。これは久生十蘭の『昆虫図』のゆるゆる感想文で触れた。
先に行き過ぎても面白くないし、後ろに戻りすぎても面白くない。それは読んでいる読者の「今」がそこには存在しなくなってしまうからである…。
と脱線して変なことを考えてしまった。古井由吉の話に戻ろう。
その後、古井由吉は新幹線に乗って本を読んだことの経験を語る。
つい何ヵ月か前にそのひかりで広島まで往復した際には、家では仕事のあいまに少しずつ読んで半月あまりもかかると思っていた本を、退屈のあまり、半分近くまで読んでしまって、あとで頭が痛くなったものだ。列車の中ではかなり分かったつもりでいたのが、あとから読み返してみると、読んだ痕跡がまるでないような、そんな箇所が多々あって、呆れさせられた。
(福武書店 1984年)P.48,49
僕は個人的にだけれども、「列車の中では…呆れさせられた」という部分は何だか分かる気がする。電車で読書すると確かにこういうことは多い。というよりも、僕は忘れっぽい人間だし、忘れたらまた読めばいいんだよという質の人間である。実際、僕はその現象を受け入れてしまっている訳なのだが、こうして改めて文章にされると実感を持って僕の方へやってくる。
これは僕の勝手な想像に過ぎないからあてにしないで欲しいが、これは畢竟するに小説つまり読んでいる作品の中の時間と、今その作品を読んでいる読者の時間の齟齬によるからなのではないかなと思うのだ。1番引っ張られるのは、読者である。小説世界の時間はどんなことがあれ変わらない。これは事実としてそうである。しかし、それを読む側の環境は同じではない。
ここで重要だと思うのは3つの時間軸が存在しているという点にある。①読者の読む時間(時間をスピードという言葉に置き換えると分かりやすい)、②小説に固有の時間、③読者の読書環境の時間ではないかと。それぞれがどの配分でというか、読者に影響を与えているかを考える必要があるのではないかと思われて仕方がないのである。
①と③は密接な関係である。特に③によって①が変わってくる。古井由吉のこの話で言えば、新幹線の窓の景色や速度感(③)が古井由吉の読む時間(①)に作用していると言えるはずだ。彼が何を読んでいるかは知らないが、そこに流れる時間は固有のものであり、僕らが改変することは不可能である。詰まるところ、③が①に大きな影響を与えて、「読んだ痕跡がまるでない」ような状態になるのではないかと思われる。
でも確かに、自分の経験上から言っても何か分からないでもない。
これで最初の「僕がカフェで読書をするのが苦手か」という所に繋がってくるんだけれども、要するに自分の読む時間と外界の時間が合っていない、仮に合わなくても調和が取れていない状況に陥りやすいからである。例えば自宅で読む時と比べてみると分かりやすいと個人的に思う。僕の自宅はまず以て時計がない。つまり部屋に流れる時間はあってないようなものだ。何かに邪魔されることなどなく、ただ空間に概念としての漠然とした、具体的な数字を持った時間は存在しない。
そこに僕の読む時間が加担する訳だが、ほぼ皆無に等しいその時間は、僕の読む時間にのみ支配される。自分の読む時間に全振りしているのである。そこに在るのは僕の読む時間と小説に固有な時間だけであって、外界の時間がそもそも存在しないというテイになっているので集中して読めるし、それこそ古井由吉が言うように頭に入りやすいのである。
って、何かこれ過去に書いたような気がする…。
それで、古井由吉はこれらの経験について語っていく。この後、それは詩を読むときにも起こり得る現象だという話をしてこのようなことを書いている。長いが以下に引用する。
自分は、新幹線とか、高速道路を突っ走る車とか、はたまたジェット機とか、そんなものの中で物を書いたり読んだりしているのと一緒ではないか、と。読んだ詩が私の内から零れるというよりも、読んだときの私の静かさが、私の時間から零れるというべきではないか、と。
乗り物の内部にいれば、自分で運転しているのでもないかぎり、全体が運ばれる速度を、忘れることはできる。飛行機がその良い例だ。しかし飛行機の中で人はほんとうに物を考えられるものかどうか。あるいは、物を考えたとしてもそれが地上の時間へ同質的につながっていくものかどうか。この辺の微妙なところを心理学者につぶさに調べてもらいたいものだ。地球上の人間はほんとうには物を考えられないようになっている、というのも、地球が人間には到底耐えられない速度で動いているので、じつは静かさの中にも人間をたちまち破壊する狂奔が含まれているので、という悪い冗談もある。天上の音楽というのは虚無の嘲笑である、と。
(福武書店 1984年)P.49,50
この「読んだときの私の静かさが、私の時間から零れる」という表現に僕は心底感動してしまった。読んでいる時の自分の静かな時間が、自分の有限性のある時間から零れる。つまりは、僕は散々外界の時間とという話を書いてきた訳だが、そんなものは無くて、そこにある時間というのは読む側と小説に固有な時間しか無くて、その自身の読みの時間が自身の有限性の時間からはみ出てしまうからこそ頭に残らないし忘れてしまう。読んだ痕跡が残らない。
確かに、言われてみると、本を読むときに外界の時間などなく、そこにあるのは読む人間が持つ固有の時間と、小説などの書物にある固有の時間のみである。外界の時間は冷静に考えれば、自分の有限性の時間を構築する1つの要素にしかならず、それをそもそも分けて考えることの方がおかしいのである。僕がこれまで言葉を費やしてきたことが間違えていることがここで判明する。
さらには、この「地球上の人間はほんとうには物を考えられないようになっている」というのも何となくだが分からなくもない。僕等は当たり前のように生活して生きている訳だが、そんなのお構いなしにあらゆるものは動いている。そうして同時に時間も進んで行く。その中で、静けさ、一瞬の時間の停止は出来ない。それは停止しているだけであってその静けさを看取することは難しいのである。つまり、僕等は止まりたくても止まることが出来ない。
自分の時間から零れた静けさ、これを受け止めようと思っても無理だ。それは自分が止まっているつもりでも、地球は動き続ける。そしてあらゆるものもそれに合わせる様に動き続け先へ先へ進んで行く。その静けさについて考えることなど不可能に等しいと。流れる時間の中では。
だからこそ、僕は本を暗唱できるとか「1回読めば覚えます」ということの凄さが分からない。少し前後するが引用したい。
読んだあとから記憶に留めてその内容を巧みに語る人がいるけれど、私にはどうも、その物覚えの良さが薄気味悪く思える。それだけの重みに内に押入られたら、精神のバランスの力学からいっても、そう達者な口はきけなくなるはずではないか。
一度は忘れなくては自身の内で育たない。釣った魚を冷蔵庫の中に貯蔵するのとわけが違う。読んでからまた、自分が読んだということと、めぐり合わなくてはならない。それまで往々にして三、四年、いや十年二十年かかってもしかたがない。それはそうなのだ、と私はいまでも思っているが、また少し違ったことを考えることもある。
(福武書店 1984年)P.49
僕が思うにだけれども、暗唱できるとか、1回読んだ小説を暗記できるとかそういうことは結局、小説固有の時間と自分の固有の時間を無理矢理に合わせに行ってる。つまりは自然の摂理に合っていない行為だと思っているのだ。しかし、ここで注意をしたいのはそこにある時間性が双方にあってこそ初めてこのような現象が起きるのだと思う。
例えば、仕事などの場面で何回言っても忘れてしまう人間が居たとしよう。しかし、この場合には時間性を問題にしても仕方がない。それは双方に流れている時間、つまりはお互いの固有の時間を共有してしまっているのだから、このような言い訳は通用しないということだけ注意しておきたい。人は忘れる生き物だが、こと仕事に関しては無理がある。
些か話が脱線したような気がするが、僕がカフェで読書することが苦手な理由は畢竟するに「読んだときの私の静かさが、私の時間から零れる」ということが怖いからなのかもしれない。さっきは散々、時間性の齟齬なんてテイの良いことばかり書いてきたけれども、実際は流れる時間の中でちゃんと読みたい、「静けさ」と真摯に向き合いたいと思ってしまうから読めないのかもしれない。
僕は止まれもしないのに止まろうとしてしまう。カフェに居ると時間を忘れ、あたかも止まれた風に装ってしまうのである。自宅で読む場合は本当にそんな時間という概念を気にせず読む。自然にその「静けさ」と向き合うことが出来るからこそ集中して読めるのだろうと思われて仕方がない。
そんなことを考えながらコーヒーを啜る。この喫茶店には幸運なことに喫煙スペースがある。タバコを1本蒸かして、時計を見る。そろそろ出なければならない。時計とはつくづく嫌な道具である。
会計を済ませ向かった。
そんな1日。
よしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
