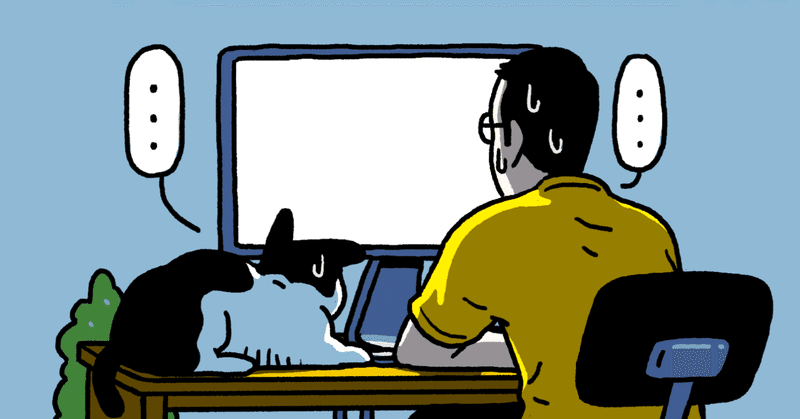
雑感記録(263)
【そこにある場所】
人はたったひとつの自分の一生を生きることしか出来なくて
あといくつかの他の人の人生をひっかいたくらいで終わる
でもそのひっかきかたに自分の一生がかかっているのだ
それがドタバタ喜劇にすぎなかったとしても
『世間知ラズ』(1993年 思潮社)P.41
ここ最近、将来のこと、先のことについて漠然と考える様になった。先のことなど分かりはしないのに、先々のことを考えているなんて阿保らしい。だが、こういうことを考えられるのはある意味で人間という生き物の特権なのかもしれない。それに先のことを夢想することは誰にも咎められることはないのである。夢想するだけなら。それでいちいちクヨクヨするのはまた別の問題である。
恐らくのキッカケとして、これは先日の記録でも書いた訳だが、父親と酒を酌み交わしたことによるものが大きい。
先々のあることないことを半ば強制的に想起させる場だったとでも言うべきか。あの場はそんな感じだった。それがこうして尾を引いて今日まで続いている訳である。
だが、僕はあることないことを想像するのは好きだ。先にも書いたが、想像するだけであれば誰にも咎められることは無い。それにこういう話をした所で、真に受けて貰えない…というのも些か変な表現ではある訳だが、それは想像の話であるということは相手も了承のうえで進むからである。何故なら「今、この瞬間」という場に於いてそれを越えた場の話をしているに過ぎないからである。
僕は今日、久々に『獣道』という映画を見た。ちなみに松本清張が原作の作品ではない。

この映画は有り体に言えば、居場所を求めた人たちの物語である。「人たち」と書いた訳だが、厳密には高校生である。若者特有の…というこれも紋切型な表現になってしまうのが憚られる訳だ。とかく「自分の居場所がない」という問題については、どこか「若者特有の悩み」というある種の特権性がある訳だ。僕はこの映画を見る度に「若者だけじゃなくて、大人だって居場所を求めたいんだよ」と思ってしまう。
だが、僕にとってこの映画そのものが「居場所」なのである。それは暗に「映画が僕の生きる道」とかそういうことを示している訳では決してなく、至極単純な話である。書くことも恥ずかしい訳だが、この際書いてしまおう。書かなければ始まらない。この映画のロケ地、つまり映し出される場所が僕が実際に育ってきた街だからである。
しかし、これが「居場所」という問題と繋げるにはあまりにも短絡的すぎる。ここで書いている、そして映画で描かれる「居場所」というのはある意味で「自分が自分で居られる場所」という様な意味合いである訳だ。そもそも僕が言っている「居場所」というのはあくまで地理的な問題に過ぎない。それでは何だか悲しい気もする。どうにかこうにか繋げてみようと思う。
僕は先日、これまたこんな記録を残した。
タイトルと趣旨的には些かズレる訳だが、この記録の最後でわざわざ、嫌味のように『はがない』の画像までご丁寧につけて「僕は友達が少ない」ということを書いた。厳密には「友人は多いが、友達は少ない」ということである訳だが…。とはいえ、この記録を書いた後で冷静になって、結局テイの良い言葉でその実、友人の少なさを隠しているように思えたのである。自分のくだらぬ醜いプライドみたいなものが全面的に表現されている記録だと、読み返し赤面する。
だが、書いてしまったということは、それは書いている時に僕自身が思っていることなのだから消す必要も無い。これもまたこれで僕の本性というか、自分自身なのであるから受け入れねばなるまい。僕にとって「書く」という行為は自分自身を赤裸々にしてしまう傾向があるらしい。それはそれで自分を見つめ直すという意味に於いては非常に有用な営みである。……と言い訳じみた、というか言い訳を書いてみる。
そんなことはさておき、この『獣道』に映し出される僕の地理的な「居場所」というのは同時に精神的な「居場所」でもあることは事実である。
しかし、不思議なことに「誰かと」共有できる類のものでは決してない。例えば映し出される商店街の通りを見て、そこで思い出されるのは僕が主体でそこに居るのは僕だけだ。友人や友達の影は1ミリも存在しない。考えている主体は僕なのだから、それは当然に僕が出て来るのはある意味で当たり前なのかもしれない。だが、冷静にその後振返ってみても僕には友人と過ごした記憶ではなく、僕1人での記憶しか思い出されない。
何度も書くようだが、考えている主体、言ってしまえば主人公は僕な訳で、他の人物が入る余地はないのかもしれない。とはいえ、僕が映像を見る度に「ああ、ここそう言えば『1人で』行ったな」というように、これまた紋切型の如く「1人で」という挿入句が入る。これは当然に入れなくていいと言えばいい訳だ。余計な一言である。しかし、どうも僕が酷い人間なようにも思えて来るし、寂しい人間であるような、複雑な感情になってしまう。僕の記憶には僕しかいない。
意図的に消している?いや、そんなことはない。誰かと何かをしたという記憶は鮮明に思い出される。その風景を見れば「あいつと…」となるのかもしれない。待て。「かもしれない」と書いてしまっている時点で、僕には永遠に僕だけの記憶しか思い出せないのではないのか。何だか哀しい人間だなと改めて思う。
東京に来て、これは当然の如く友人などと過ごす機会など無くなった。全く以て無くなった。そもそも、友人が少ないことに加えて、地元から離れてしまったからこそ会えることも物理的・地理的に不可能である訳だ。また、皆にはそれぞれ生活があり、大切にしたいことや物事は異なる。それに対する貴重な時間を奪ってまで「会おうよ」と言える勇気は僕にはない。そんな烏滸がましいこと出来る訳もない。
だから僕はこういう映画で映される些細な光景や、本を読むことで得られる感覚、曲を聞いて思い出される感覚、そして散歩することで想い出に浸ることしか出来ないのである。だが、いつかその想い出も泥濘に沈んでいく。
人間は忘れる生き物だ。
だからこそ、僕は上手に忘れたいと思う。
人間は簡単に忘れてしまう生き物だからこそ、その忘れ方にも丁寧に向き合っていきたいと思う。僕がいたあの「居場所」には僕しかいない。だけれども、そこには僕だけじゃなくて友人たちと過ごした時間がある。それをただポカンと忘れることは何とも哀しいことではないか。と書いてみたが、ある意味で僕しかいない記憶だからこそ、もしかしたら心置きなく忘れることがいつか出来るのかもしれないと思ってみたりもする。
先のことを漠然と考える。しかし、それは結局過去の集積でしかから想像することは出来ない。僕が常々「後ろに進むことで前に進んでいる」というのはこういうことだ。そういう想い出やら感覚、そして「居場所」によって僕の今の立ち位置や将来的な立ち位置は想像できるのではないか。
僕の「居場所」は結局どこにあるのか。山梨か、あるいは東京か。僕には分からない。ふと遊牧民族の人たちはどうやって自分の「居場所」というものを措定していたのだろう。いや、むしろ「居場所」という概念などが存在しなかったのではないか。これは僕の想像の域を出ない。
そして、本当に「居場所」というものが必要なのかどうか、あるいはそもそも存在しているのかどうかということもある訳だ。
この『獣道』という映画では伊藤沙莉が演じるアマンダという女性が「居場所」を求め宗教にはしったり、ヤンキーになってみたり、風俗嬢になってみたり、最終的にはAV女優になる訳だが、落ち着かない。だが、そのどれにも共通していることがあるとしたら、1度「居場所」を見つけてしまうとその安心感を得ると同時に自分自身の何かを失うという喪失感も得るということである。そう考えると、僕が転職するのもある意味で必然だったのではないかと思われて仕方がない。
ここではテイの良いことを書いている訳だが、結局その「居場所」で失ったものを恢復するために転職をした。そして転職をしてしばらく経ち、東京で失った「居場所」を恢復するために僕は躍起になっている。そして「居場所」を求めて歩き、過去の想い出に浸っている。だが、「今、この瞬間」の僕はそこには存在しないのである。結局、僕には「居場所」というものは地理的にあっても精神的には見つからないのかもしれない。
自分自身が生まれ育った街というのは、しかし特別である。多感な時期を過ごしている訳だし、何より家族が居る。小さな時から一定の大人になるまでの期間を過ごした家族というのも1つの「居場所」だ。「帰る場所」という紋切型の表現である訳だが、正しくと言った感じである。僕には変わらない帰るべき場所が存在していることは言うまでもない。そこは自分自身を恢復できる唯一の場所なのではないか。
それで、先々のことを想像するんだけれども、1人で居続けることも、それも僕が僕で居られる「居場所」であることには変わりない。だけれども「帰る場所」というのが実家以外にもあればいいなとふと想像してしまう。
実家では過去の想い出というもので僕は「居場所」を恢復することが出来る。だが、その先はない。過去に戻ることしか出来ない。だが、人は止まれない。もう1つくらい「居場所」を求める、つまりは記憶を創出していく「居場所」があってもいいんじゃないかと想像している。それはこのnoteでも良いと思うし、会社でも良いと思う。
だけれども、そこは「帰る場所」ではなくて、「立ち返る場所」でしかない。それは自分自身で居られるというよりも、「今、この瞬間」の僕を創出して認識して行く場所でしかない。記憶を創出する場所ではない。現在位置を確認する定点的な所でしかないのである。
二人友達が来て三時半まで飲んでしゃべっていた
寝ようと思って小便しながら外を見たら
外はもう明るく小鳥が鳴き始めていた
こういう一日の終りかたは久しぶりだ
日記を書きたかったが眠くて書けなかった
一日の出来事のうちのどれを書き
どれを書かないかという判断はいつもむずかしい
書かずにいられないことは何ひとつないのに
何も書かずにいると落ち着かないのは何故だろう
小便してからぼくは五時間ほど眠り 夢はすべて忘れ
起きてこうして日記の代わりの詩を書く
そうだ思い出した 友達のひとりは酔って
妻を尊敬しているが愛してはいないと繰り返し主張し
もうひとりは嫌いな作家の名を五人あげようとして三人しかあげられず
みんなで藍色のガラス鉢から桜んぼを食べた
一日はそうして終わったものだと信じたいがそうはいかない
残ったのは(そして失ったものも)言葉だけじゃないから
詩は言葉を超えることはできない
言葉を超えることのできるのは人間だけ
ゆうべぼくは涙が出るほど笑ったが
笑った理由を今日はきれいさっぱり忘れている
『世間知ラズ』(1993年 思潮社)P.32,33
よしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
