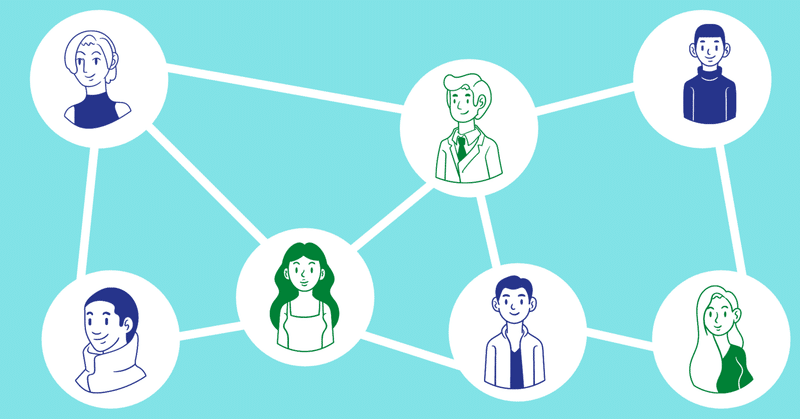
【KLDマガジン】ローカル×システムコーチング体験談~チームの相互理解は何を生むのか?~
システムコーチングとは、要は「複数人に対するコーチング」です。1on1のコーチングは徐々に人口に膾炙してきたところではありますが、複数人の関係性(=システム)にアプローチするこちらは少し珍しいかもしれません。
そしてすごく平たく言うと、システムコーチングとは「組織のチームビルディング」や「夫婦関係のサポート」などの文脈で活用されています。
私自身も既にコーチとして100時間を超えるトレーニングを積んでいますが、8月から本格的な資格取得コースに進むため、クライアントさんを募集しています。が、そうは言っても、「実際に何をするのか実感が湧かない」というのが正直なところではないでしょうか?
そこで、5年前に実際にシステムコーチングを自ら経営する会社に導入した経験のある、KAWASAKI LOCAL DOORでもおなじみの石井氏にインタビューしました。ローカルという文脈でのシステムコーチングの事例について、イメージを持ってもらえると嬉しいです。
Q:システムコーチング導入の目的は?

「元々、1on1のエグゼクティブコーチングを受けていたので、コーチング自体には関心を持っていた。自分の経営する会社が3つあったが、それぞれバラバラに業務をしている状態だったことが気になっていた。
さらにシステムコーチングを受けた2017年はカフェ事業もスタートさせたばかりの頃であり、各々のチームでお互いが何をしているのか分かっていないんじゃないか、という課題感のある状況だった。
この状況を改善させたいと思いシステムコーチングを導入することにし、各社数名ずつワークに参加してもらった。」
Q:どのような効果を期待していた?
「決して人間関係が悪い状態ではなかったが、より深い相互理解が必要だと感じていた。父親の代に作り上げたチームだったので年配者が多く、自分が新しいことを取り組むにあたっても、どのように伝えたらよいのか悩んでいたこともある。
仕事の中でのチームのコミュニケーションにポジティブな変化を起こしたかった。」
Q:実際にどんなことをやった?

「数か月間にわたって複数回のワークを行った。例えば、とある重要テーマを書いた紙を部屋の中央に置き、ワーク参加者が立ち位置や姿勢でそのテーマに対する態度を表明しあう、というようなこともあった。(※『システムのコンステレーション』と呼ばれるシステムコーチングのツールの一つ)
ワークをするにあたっては、どのような意図でこれが行われるかといったことへの丁寧な説明があり、また率直な意見表明への後押しもあって、思いもしない意見が参加者から出てきた。
例えば、『自分が会社を支えていきたい』という若いメンバーの意見だけでなく、『そんなあなたも含めて支えていきたい』という他のメンバーの意見が出るなど、驚きを感じた。」
Q:やってみてどんな変化があった?
「お互いの立場を理解することができたんじゃないかと思う。それぞれが自分の立場しか見ておらず、すれ違いが起きていた。気を使い過ぎて『ここから先は手伝っちゃいけないんじゃないか』と思っていた、というようなギャップもあった。
従業員同士で支え合うという意識を確認できた。実際に業務効率が大幅に上がったチームもあるし、あれからだいぶ時間が経ってからの酒の席でも、システムコーチングを取り入れたときの話が出る。
何よりも現場作業員に笑顔が見られるようになった。こちらが感謝していることが伝わったんだと思う。」
Q:どういうケースで役に立てられると思う?
「自分自身は経営をするうえで社内コミュニケーションをしっかり取りたいと思っていたので、システムコーチングの導入でコミュニケーションが円滑になり無駄が無くなったと思う。また、話し合うことで、凝り固まっていた役割認識を変えることができたと感じている。
自分自身がパーソナルコーチングを実際に受けるまでは、コーチングは『霊感商法』みたいなものだと思っていた。(笑)しかし今では、コミュニケーションを重視する経営スタイルであれば、有用なツールだと感じている。」

・・・ということで、インタビューは以上です!システムコーチングを試してみた、興味があるという方はぜひご連絡くださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
