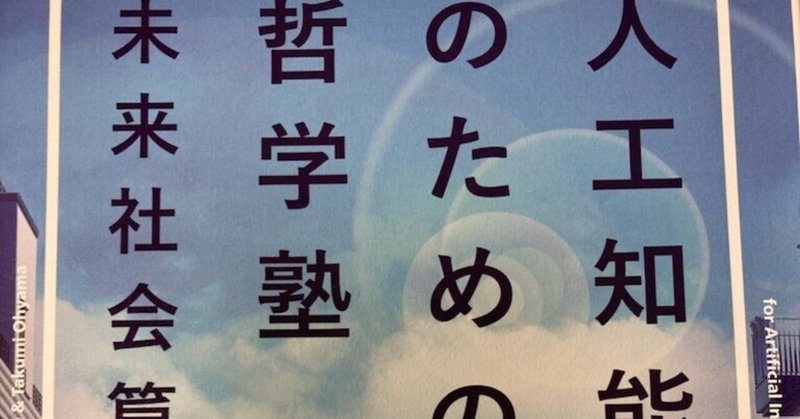
人工知能が社会に考えなければならないこと 三宅陽一郎、大山匠『人工知能のための哲学未来社会篇』 動画「名著を読み解く」#3
コロナ禍に突入して以降、人工知能に関する議論や報道が下火になった感がある。だが、報道の比率が新型コロナやロシア・ウクライナ情勢にシフトしたに過ぎず、人工知能研究に関する本が続々と出版されて書店に並んでいることに変わりはない。
ここ数年出版された人工知能関連本の中でも、最も「未来社会」へ志向した人工知能本が、三宅陽一郎、大山匠による『人工知能のための哲学 未来社会編 響き合う社会、他者、自己』(ビー・エヌ・エヌ新社)だ。
初版から1年10ヶ月ほど経つが、日進月歩が著しいテクノロジーの世界でも、本書の議論は今なおとても新鮮である。
人工知能とこれからの社会の共存が進み行く社会で、考えなければならない視点を多分に含んでいる。
人工知能が社会で共存する際に考えなければならない五つの問い
本書はセミナー「人工知能のための哲学塾 未来社会篇」全五夜の講演を元に加筆されており、大変わかりやすい語り口となっている。
第一夜 人と人工知能はわかりあえるか
第二夜 人工知能はどのような社会を築くか
第三夜 人工知能は文化を形成するか
第四夜 人と人工知能は愛し合えるか
第五夜 人工知能にとって幸福とは何か
この五つの問いを見るだけでも、ワクワクしてこないだろうか?
これら五つの問いを、人工知能の開発者三宅陽一郎(第一部)と、哲学者大山匠(第二部)による共同講演という形式になっており、巻末に両者の対談が収録されている。
本書は人工知能と人や社会がどう関わっていくのか、あるいは、関わることが可能の中という点をメインに考察しているため、人工知能単体における科学的説明や定義、哲学史の系譜学ばかりが描かれている従来の退屈な著作とは一線を画して、大変面白い内容になっている。
五つの問いの意味
五つの問いは、人が外国や異文化に飛び込んで生活する際、どのようにして「他者」と関わっていくのか、という問いとほぼ同じである。
人が他者や社会と関わり、揉まれることによって、誰しも葛藤や悩みを抱くものである。人工知能といえども、人間と同様、社会の中で「生きていく」ためには、人工知能がどのように人や社会、文化と関わっていくのかを抜きに考察、開発することはできない。
理系的な人工知能開発と文系的な哲学的立脚点、全く異なる両方のアプローチを俎上に載せた議論が、ますます不可欠なのである。
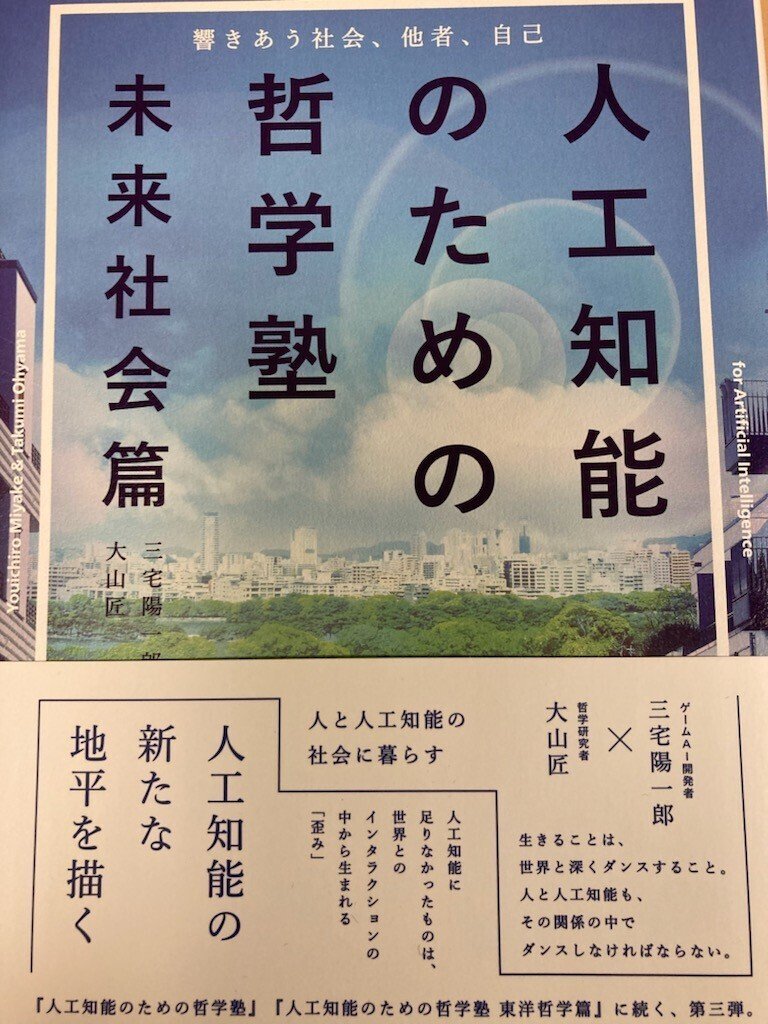
人工知能にとっての幸せにむけて
人が生きていく目的とは、人同士が深く関わり、文化を享受し、人と愛し合うことを通して、幸福を追求していくことだろう(異論はあるかもしれないが)。先の五つの問いの最終形は、人工知能がどう「幸福」になるのか、ということだ。人工知能の幸福追求に向けて、わかりあえること、文化、愛、幸福、それぞれの深い考察が不可能である。そのためには、人類史レベルにおける哲学、社会学、科学的な知見を総動員させる必要があるわけだ。
人が生きる際には、自己が他者に反映し、他者が自己に反映する「入れ子構造」が生活空間で生じる。この入れ子構造は他者を文化に置き換えても同様である、人間の自我は、自分の内側=主我(I)から客我(Me)を通って社会へと流れていき、社会から客我(Me)そして主我(I)を通って自己が更新されていく。社会の対象が火広がることが自分自身も変わっていく(創発的内省性)。
一方で、他者は思い通りにコントロールが不可能であるため、コミュニケーションを成立させるためには、コモングラウンドが必要だ。そのため、人工知能にもコモングラウンドを持たせる必要がある。だが人工知能は身体的構造を持たず、言語構造が違うため、お互いを理解し合うのは非常に困難だ。また人工知能は、コンテクストを持つことも作り出すこともできない。人工知能は与えられた世界の見方でしか世界を見ることができないため、フレームの外にある存在さえ知りえないのだ。さらには、人工知能は自分の外側と内側の区別を付けることができない。人間とはあまりにも非対称な人工知能が精神形成を形成するためには、存在の内面が変化するようにしなければならない。
こうしてみると、人工知能が人間と同様に思考し、独立した存在として社会に溶け込むためには、まだまだあまりにも高いハードルが立ちはだかっているようだ。
人工知能の煩悩と精神変化
人間は社会生活を通して内面が変化し発達する生き物である。だが、そのことはあまりにも自明すぎて、自我を意識することをほとんど意識していないことに気づかされる。自我にもいろいろあるが、人工知能開発には、文化や社会、他者とのコミュニケーションや摩擦を通して、人間がどのような「煩悩」を抱いたり、傷つくのかといった、「精神の発達」についての研究が不可欠である。
人工知能を作るという事は、煩悩を人工知能に与えることであります。つまり、環世界やエージェントアーキテクチャ、華厳の説く縁によって世界との結びつきを作るということになります。人工知能に煩悩を与える事ができるのかというのが,僕自身の一つの大きなテーマになっています。もう一つは禅、人工知能からどのように煩悩を取り除くか、です。
人工知能もまず、自分勝手な他者モデルから出発し、たくさんの他者との出会いによって傷つくこと(=自分の世界に亀裂を入れて、他者モデルを改訂し、同時に自我の領域も更新する)を重ねながら、発達的に自我と知能を形成していく必要があります。
煩悩を感じて、人間のように心が傷つく事をも覚えるような人工知能がはたして可能なのか?そうして、それが実現したらどのようなことになるのか。それは技術的にも倫理的の、今後の大きな課題であろう。
人工知能研究の限界を突破した先に
三宅陽一郎パートのポンチ絵が実にわかりやすくて、これを眺めるだけでも大変な学びになる。だが、ポンチ絵の「モデル」だけで、人間と社会や文化の関わりを全て表現し尽くすこともまた不可能だ。「モデル」表現の「限界」は、人工知能研究の「限界」をも意味する。
しかし、人間は限界を超えようとする生き物だ。
限界を乗り越えて人工知能が開発された社会はどんな社会なのか。ディストピアを創り出さないためにも、文理両方の視点からの共同研究、さらにはジャーナリスティックな監視がいっそう求められるのは間違いない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
