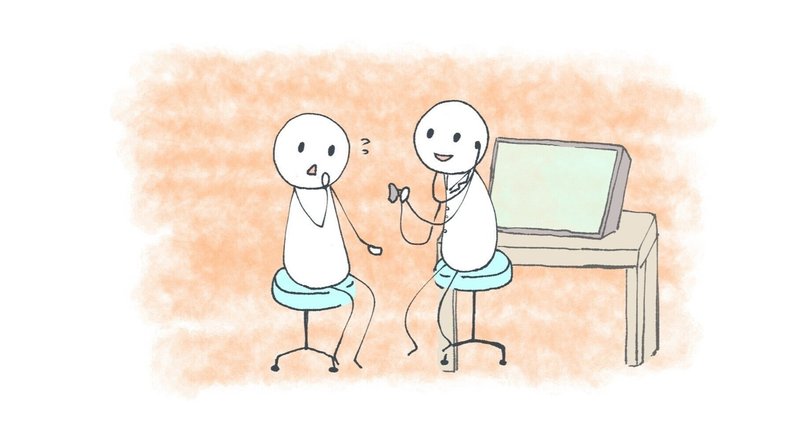
【適応障害休職中】主治医との関係性から病気を捉える
医師との関係も私の人間関係のひとつ
どれだけの人が、「主治医」「かかりつけ医」と呼べる存在の医師に出逢っているのだろうか…?
昨日、産婦人科の定期受診あと、ふとそんなことを考えた。
若い時の私は、心身にどこかしらの不調を抱えていて、特に20代前半は不定愁訴を抱えてドクターショッピングを繰り返していた。どこの、誰に診てもらっても、軽快してゆく感覚や納得感も得られなかったのだ。
今になって思えば、それはおそらく、当時の私の究極的な所ではいつも他人や社会を信用出来ないという態度のせいだったのだろうし、もっと言えば、それは取りも直さず「自分自身を信頼出来ない」ということの裏返しだった。
現在、私は信頼出来る医師の元で、安心して治療を続けている。卵が先か鶏が先か、という類の話ではあるけれど、そういう実感のおかげか、持病は軽快し、完治は目指せなかったとしても、まぁそれとうまく付き合って行きたいし、折り合えるのではないかと楽観出来るようになった。それは多分、私自身の変化が、ダイレクトに医師との社会的な人間関係に変化をもたらした結果であるように思う。
今日は、そんな話を少し。
長くなりそうなので、何回かに分けて、まずは現在の所感から話てみたい。
次回は、「ドクターショッピングに明け暮れた20代→不妊治療→挫折→初期流産2回→出産→適応障害からの気づき」という個人的な体験から考えたことを、特に「不妊治療」の経験にフォーカスして語るつもりでいます。
「ずっと診てもらいたい」医師との出会い
私にとっては産婦人科と精神科の医師ふたりが、「主治医」である。
産婦人科の女性医師とは、もうかれこれ7〜8年近くの付き合いで、私が東京からUターンして農業と不妊治療をはじめ、やがて不妊治療を断念し、「普通に月経が来るようになるように」「女性のからだであることを健康的に終えるために」、治療を立て直そうとするタイミングで出会ってからずっと診てもらっている。
それまでは、不妊治療専門のクリニックに通っていて、そこは「実績で成果がある」と地元では有名だった。
無月経を治す治療と妊娠を目指す治療はスタートから根本的に違う、まずはどちらか選択しなければならないと、当時の私がビビってしまうぐらいの口調でそこの男性医師に告げられ、最初からあまりあまり印象が良くなかったのを今でもよく覚えている(苦笑)
慣れない農作業と、通院までの長い道のりと時間、受診の度に「まだダメだね」(卵が大きくならない、育っていないという意味)という言葉が繰り返され、あの時はかなり心理的ダメージが大きく、疲弊した。
筋肉注射の後の絶不調感(ダルさ、ボーっとして頭が働かない、判断力が鈍る、悲観的になる)などもしんどく、夫が「そんなに辛いなら、もうやめよう。俺はそこまでして子どもがほしいとは思わない」と背中を押してくれ、当時の私は不妊治療をやめた。
しかし、20代のはじめから10年近く無月経の状態は続いていて、一向に改善しなかった(=一度も自然な月経は来ず、放っておけば1年どころか3年以上来ない=排卵が一度もない)
はじめは「面倒なものが来なくて便利」などと悠長に構えていたが、さすがに「普通に来るはずのものが長らくやって来ない」リスクの方が怖くなってきた。それで、地域の総合病院の産婦人科を再受診することに決めた。
「再受診」というのも、不妊治療を考えるにあたり、専門クリニック以前に一度、同じ病院の産婦人科を受診していた経緯があった。
その頃の主治医のことは、正直あまり好きではなく、多分その感情のせいで、処置や処方にも疑問を感じていたのだと思う。その医師に診てもらっていた頃は、自分で努力して体質改善をしなければと自覚し、食事改善や運動を徹底して続けていた頃で、東洋医学(中医学や漢方、薬膳なと)を独学したり、マクロビオティックなどにも傾倒していた頃だった。そのため、西洋医学にはアンフェアな態度でいて、懐疑的になっていたように思う。私が良かれと思ってしていた診察室での質問や、自分の心身に対して行う治療に対する説明を求める姿勢なんかが、もしかするとその医師には気分を害するような、ともすれば目障りな印象を与えていたのかもしれない。
結局、その医師を信用出来ず、経過においても目に見えた成果も感じられなかったため、静かに別のクリニックに移ったのだが、それ以来の、再び同じ病院である…「自宅から近い、唯一の総合病院」という理由だったので、正直期待もしていなかった。
それでも、「信頼出来る医師に出会いたい」という思いは捨てきれず、
次に出会う医師がフツーに話が出来そうな人であれば、敬意を持って心を開き、相談の仕方や手順をきちんと踏んで、関係づくりを丁寧にするよう努力しよう
と決めていた。今思えば、これがやっとこさのスタートラインではなかったかと思う。
患者が医師を「自分だけの名医」にする
再度通いはじめてから、初回の診察で「このまま無月経を放置すると、将来的に骨粗鬆症のリスクが高まる」と言われ、3ヶ月に一度でも月経を来させるようにしたほうが良い、ということだった。
その医師(以後、H医師とする)は小柄な女性で、生真面目そうな雰囲気だった。眼鏡をかけていて、声も大きくない。断定せず、それでも考えられるリスクはしっかり伝え、ひとつの処方を押しつけてくるような強引さはなかった。あくまで、私の決定や気持ちを優先する姿勢が、当時の(今もだけれど)私には嬉しかった。
たまたま別の症状で消化器内科を受診した時の事。消化器内科の医師が、「あなたには絶対この漢方が合うから、飲んでみなさい」と言う。不思議と嫌な断定口調ではなかった(笑)ので、内服を続けてみた。すると、なんと、、、
1ヶ月ほど経過してから、月経が突如として再開したのだ!!
まさにミラクル。これまで、いくら努力したところで、うんともすんとも言わなかった私の子宮が、ツムラの漢方(フツーの保険適用内ヤツ)を1ヶ月飲んだだけで…
「ただいまー帰ったよ。あれ、オレ、今日帰るって言わなかったっけ…あらー、おかん、ごめん!」という風な、久しぶりの帰省にも関わらず一言も告げないまま帰ってくる息子よろしく、あまりに突然の帰還!!
「もー、アンタ、帰るなら先に言っといてよ!買い物なんにもしてないよ、残り物しかないのよっ!」というオカンさながら、あまりに驚きすぎて、もう驚きを通り越して肩すかしをくらって、呆れに近い心境になるという…
(余談)まぁ、全ての事柄や努力が何らかの関連性を持って、月経が戻ってきたと考えたいなと…ストーリーの落とし所として(笑)食事に運動、減量や生活の質改善、不妊治療のストレスから解放された、などなど。すべてが時間の経過とともに連関を持ち、戻ってきたと…漢方それだけが理由ではなく…(苦笑)何より私自身がカタルシスを得るためにもね…
そのことをH医師に知らせると、「さすがM先生(消化器内科の医師のこと)!」と、なぜかうっすら笑っていた。正直、「頼りないなー」とも少し思ったのだけれども、他の医師の知識や経験を尊敬出来る態度、その結果を受けて、新たな治療の展開を考えてくれたことなどが、私にこれまでとは違った医師観を与えた。
H医師が主治医となったのはたまたまで、幸運だったのかもしれない。そして、私の人生のなかでそのことが起こった時機、その時の心身のコンディション、H医師のキャリアの中で私と出会った時期など、すべてのタイミングが良かったのかもしれない。
それでも、その後、また私が予期せぬ展開が待っていた。
月経再開から、基礎体温を測ることと、ホルモンバランスを保つための服薬を続けて、3ヶ月くらいが立った頃だったろうか。
「タイミング法で、妊娠を考えてみませんか?」
晴天の霹靂。
子を持つということへの執着をようやく捨てて、仕事に打ち込み、比較的幸福度も高い状態で過ごしていた頃だったと思う。まさか、今度はタイミングだけで妊娠が望めるなんて、本当に、想像もしていなかった。
まぁ、そこからまた色々あったのだけれども。スタバの夜シフトでバリバリ頑張っていた時期の妊娠、初期の化学流産×2回、2回目は手術も必要だったし、喪失感と言えば本当に言葉に出来ないほどだったし、今も胸が痛い。それでも、3度目に妊娠し、ひどいつわりに苦しみながら、通常の妊娠経過をたどり、緊急帝王切開で出産した。心身のダメージを乗り越え(いまだに付き合っていることもあるけれど)、今こうして娘の育児に向き合うことが出来ている…
これは、様々なこと共に経験し、力をかして下さったH医師と良好な関係を築けていたことの賜物だと、つくづく思うのである。
2度も流産を経験し、打ちひしがれていた私に、「むしろ妊娠出来たことを前向きに捉えましょう。体に、力が戻ってきていると教えてくれてるのかも知れない」と、私の感情は蔑ろにせず、そっと背中を押してくれた。
稽留流産手術、緊急帝王切開術の出頭は、同じ科の別の医師だった(総合病院で、当日の勤務医が担当になる)けれど、私の手術後、診療外で病室に見舞って下さったりした。出産後、私は私で退院時にH医師に感謝の手紙を渡したり、というやりとりもあった。
ネガティブな事実を前に、その分野で専門知識を持ち、経験則やこれまでの私の診療歴をトータルで見て、最適解を提案し、プロフェッショナルとして寄り添ってくれたH医師の存在は、私にとって以前には体験したことのない、新しい社会的な人間関係だった。
公的であり、私的な場でもある病院という場所で、もちろんいち患者としてではあったのだけれども、完全な受け身でなくいられたことが、もしかするとH医師にとってもより良い診療を施すために有益な態度であったのかもしれないと、今になって思う。
病は、気から
そんなことを考えてみれば、「病は気から」ということわざも、あながち間違ってはいないと思ったりする。
※もちろん「気から」などとは到底言えない症状や病を抱える場合があり、ここではあくまでひとつのたとえとして、この言葉を使ってみたいのだが。
医師の言葉や処置・処方が信じられるか。
(医師の人間性やコミュニケーションの取り方、専門性に大きな問題がないという前提ではあるけれど…)それは取りも直さず、私の、私自身の心身に対して、他者に対しての姿勢が大きく関係しているように思うのである。
自分のからだを通して見えてくる、私の、自分自身の人生との向き合い方が、おそらくそのまま、医師とどのような関係を築くか、ということに関わってくる。
だって、何百人、何千人という患者と、診察室で日々向き合う医師からしてみれば、多分私が日々どんな思想でどんな生活を送っているかは、病状や検査結果や診察を通して嫌でも透けて見えているはずだから。
それをさらけ出して、いかに主体的に自身の心身に責任を持ち、かつ医師にプロとしてサポートを依頼できるのか。
主体性と、客観性のバランスをいかに保てるのか。自主的でいるべきところと、人を信頼し、任せるべきところの見極め、というのか。
これはおそらく、家族関係や、仕事のうえでも言えることだ。
などと考えていれば、きっと日々の行動も、自然と「より善い行動を選ぼう」という風になるのではないか、と思う今日この頃。
なかなか甘くて美味しいものの誘惑に打ち克つのはムズカシイのだけれども、それはヒトとしてのご愛嬌かなぁ。
アイディアを形にするため、書籍代やカフェで作戦を練る資金に充てたいです…
