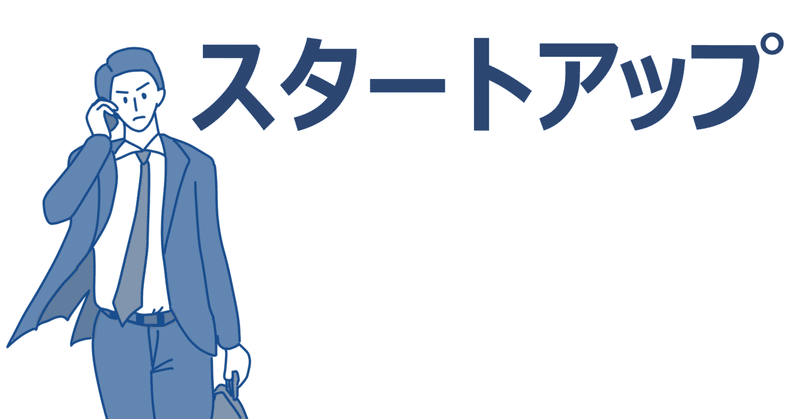
ベンチャー企業での「何とかなる」か「何とかする」について
こんにちは。
ベンチャー企業、中小企業、大きい会社で僕が経験した色々なエピソードをガバナンスを切り口にして、それぞれの立場での考え方の違い、その理由を色々な角度で考えてお伝えしています。
前回のnoteではベンチャー企業と中小規模の会社と大きい会社とを比べて「スピード感で驚く」を取り上げました。
おさらいすると、大きい会社で指摘されるスピード感とは、概して社内の意思決定の工程に向けられたものが多い。
例えば、承認をもらうまでに凄い時間がかかってやってらんねーよ〜。
そうですよね。スピード感を阻害する判断決定までにある色々なレイヤーは確かに無駄な工程がないとは言わないけれど、それは会社の意思決定を複眼で見て判断ミスをなくす、あるいは不正をなくす趣旨もあるのです。
一方、ベンチャー企業の前のめりな状態を近くで見せてもらっている感想としては、スピード感とは判断、意思決定の速さを表す言葉。
誤解を恐れずに言えば、意思決定は社長自身の基準や仕事感が拠り所となっていて、必要十分な検証はなく行われている。
それは果たしてお客様への価値向上のための判断になっているのだろうか・・?
という自問でした
今回は
起業準備編
(1)「スケジュール」と「成り行き」で驚く
(2)スピード感!で驚く
(3)「何とかなる」と「なんとかする」
(4)自社紹介のやり方で驚く
(5)契約で驚く
(6)メモを残すことの大切さ
です。
事業の目的
ベンチャー企業でも中小規模の会社でも大きい会社でも、企業の目的、ゴールがあります。
例えば、「世界中のあらゆる人々に、〇〇を通じて喜び、幸せを提供します」などで、企業理念やフィロソフィー、もしくはビジョン的な表現がしっくりくると思います。

さて、ゴールにたどり着くためのルートは色々あります。
複数のルートがある場合は事前に最適なルートを決めて、そこからゴールを目指します。
一方で、事前に決めた最適ルートでも途中で変更することがあります。
山登を例に取ると「登山パーティーのメンバー一人が体力的に辛そうだ。今日中に頂上にたどり着く予定を変更して、今日はここでテントをはろう」(目標の変更)であったり、あるいは「昨日の雨の影響を考えて、当初のルートとは別のルートに迂回して登ろう」(手段の変更)とリーダーは状況に応じた判断が必要になります
何とかする
読み方:なんとかする
手段や経緯がどういったものかは不問に付すが、とにかく結果は不都合のない状態にする、といった意味合いで用いられる言い回し。「どうにかする」とも言う。
山登りの例では、今日中に山の頂上にたどり着く予定だったけれど、登山パーティーのリーダーは状況の変化に併せて「何とかした」行動です。
「何とかする」と「何とかなる」の違い
このふたつの言葉の違いですけれど
「何とかする」は、自分が動いて物事を解決する
「何とかなる」は、自分以外の人、要因などによって、物事が解決する
と解釈されています。
なんでこんなに言葉の解釈をグダグタと言っているかというと、「何とかする」は、ガバナンスでいうところの「危機管理体制」に通じるものだからです。
「危機管理体制」を構築するとは、
・何か起こるかもしれないことは事前に考えておきましょ。
・考えておかないと、もし何か起こったきにはリカバリーが難しくなって、その身を委ねる「何とかなる、ならざるを得ない」状態になっちゃうよ。
なのです。
登山パーティーのリーダーは、事前に下見をしたり、知識や技術や経験をもとに準備して行動中に気を配り、万が一のときを想定しているのだと思います。(登山をしたことがないので、間違っていたらごめんなさい)
ベンチャー企業における「危機管理」
僕自身、会社で内部統制の仕事をしているので、「何か起こるかもしれないことを事前に考える、って難しいじゃないですかぁ。どうすれば良いんですか??」とよく言われます。
「確かに難しいですよね〜。でもですね、自分の会社がどんな業務を行っているかは、よく解っているでしょうからアレコレと想像をしましょうよ」
「一人で想像することには限界があるのならば、社員みんなで色々な知見を持ち合わせて考えましょうよ」
とやり取りをしています。
ベンチャー企業が猪突猛進している場合、「みんなで事前に考えておきましょ」が難しいと思います。
何かを決めるときに従業員の意見をすべて聞きいて満場一致で、なんで悠長なことをしていると生き残ることは出来ないので社長自身が意思決定をすることも多いと思います。
社長自身の意思決定を先程の山登りの例で言えば、
今日中に山頂にたどり着くのが怪しいけれど、行ってしまえ!
悪天候がなんだ。立ち止まっている場合ではない!
後ろから別の登山者が来ているぞ!
とにかく俺について来い!!!
なんとかなるよ!!!!
に近い感覚です。
ここまで極端で極悪なリーダーはいないと思いますが、もちろん社長の意思決定が正しい場合もあります
また意思決定が間違って、社内で揉めてしまうこともあるかもしれませんが、それは間違いを問題視しているのではなく、勝手に決めるのってよくないっじやない?たと思います
が、社長の根拠のない意思決定がズレると危険です。ムチャクチャ危険です。
事業自体が危険というよりは、組織のあり方が危険です。
聞く耳を持つ
いくら準備をしても危険にさらされることはあります。
でも準備するときには、耳障りかもしれまいけれど他人の意見に耳を傾けましょう。
耳を傾けるタイミングは危険にさらされた時ではなくて、日頃からです。
日頃から意識して行うことが、内部統制です。
実際にベンチャー企業でも、周りが頼りないから「俺が俺が」で会社の意思決定をおこなう部分は見受けられます
ベンチャー企業ではリーダーが先頭に立って、グイッと前進することは重要だと思いますが、その前提要件としてガバナンスの趣旨をキチンと理解することが大切だと思います。
ガバナンスはなんだか難しそうで、ガバナンスなんて(←この「なんて」は多いです)事業が軌道に乗ったあとで考える、はヨロシクありません。
大きな会社では事業の裏にガバナンス体制がひっついていますが、ベンチャー企業でガバナンスの体制構築が難しい場合は、先ずはガバナンスは必要なんだ、と日頃から頭の片隅に貼り付けておいてください。
面倒くさいでしょうけど。
ではまた
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
