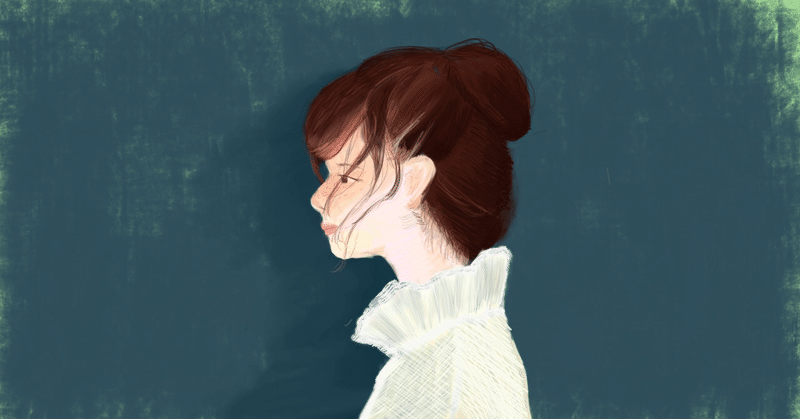
二度、温かい思いをした
私が中学生の時、女子はクラス内で固定の仲良しの子を決めていて、いつもペアか3人単位で行動していた。毎年クラス替えのたびに、新しい仲良しの子を探し、一年ともに行動することを「契約」していた。
中学校に入学してすぐ、小学校の時にはなかったこの慣習に気づいたけれど、私には違和感があって、とても嫌だった。そして、同じクラスに「仲良し契約」をしたい子が見当たらなかったから、一人で過ごすことにした。4月初めに急いで誰かと契約しなければ、その年一年、友達がいないまま惨めに過ごすことになるとは、予想しなかった。
固定の仲良しさんがいないから、休み時間にお喋りをする相手もいない。「あの子、変わっているよね」と言われているのかな、と周囲が気になった。5月の連休明けにはもう、入学当初の自分の行動を悔いたが、年度途中の「仲良し契約」は誰も受け付けてくれなかった。私は、仲良しさんがいない恥ずかしさと手持ち無沙汰を隠すために、休み時間には必ず本を読んだ。
担任の先生は、国語担当の女性のN先生だった。私の読む「コバルト文庫」をたまに覗きこんで、「これなら私にでも書けそうね」と言うような、お茶目な先生だった。隣のクラスでは、秋の遠足の時の班を生徒に自由に決めさせたのに、私のクラスではN先生が「くじ引きで班を決めましょう」と言った。それは、私が誰の班にも入れてもらえずに、浮いている状態になるのを、N先生が避けようとしてくれたからだと、私はすぐに気づいた。
私は周りに誰もいない時に、ちょっとべそべそしながら、「先生、くじ引きにしてくれて、ありがとうございました」と伝えた。するとN先生は、「本当は、あなたに近い考えの人もいるのかもしれないよ。同じ友達と1年ずっと一緒にいなければならないのは疲れるから、あなたみたいに「休憩時間は、私も一人で本を読むことにしようかな」と言っている人もいるのよ。」と。
この言葉を聞いた時、私は、N先生が私のことを悪く思っていなかったことが嬉しかった。私は、N先生にとって手間のかかる面倒な生徒なのだろうな、と心配していたから。
家に帰って、改めて先生の言葉を思い出してみた。そして、誰なのかまったく見当もつかないけれど、本を読んで休憩時間を過ごしたいと思っているクラスメイトが、少なくとも1人はいることに、もう一度温かい思いをした。
大人でも子供でもない、13歳の女の子たちの、時に残酷で敏感な性質を、N先生はよく理解してくださっていた。同調圧力を感じながらも、一人で我が道を行く私を、優しく見守ってくれていた。
N先生との一度の会話で、二度温かい思いをしたことを、私は忘れていない。そして、今でも、集団に溶け込めない思いがする時、全員が私を100%嫌っているわけではなく、もしかしたら私の行動を好意的に思っている人がいる可能性もあることを、冷静に思い出すようにしている。
