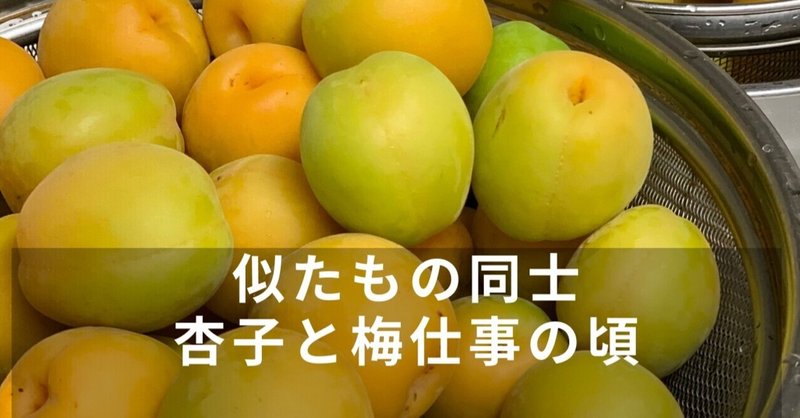
杏子と梅仕事の頃!~似たもの同士の果実で疲れ知らず ~
6月は、杏子と梅の収穫と加工に忙しい頃。
杏子と梅、どちらもバラ科のサクラ属で同じ仲間です。日本の風土に馴染み、早春に咲く花は枝っぷりとともに鑑賞し、6月には実を楽しみます。
実はどちらも酸味が強いので、加工して食を楽しむ等日本の文化に欠かせない果実のひとつとなっています。
さあ、私の杏子と梅仕事の忙しい季節がやってきました。
〇東京育ちの杏子と梅
杏子の生育は寒冷地に適し、梅は全国各地固有の品種で育成しされています。
今年は、東京でも寒暖の差が激しかったので、立派な果実が育ちました。
青い実が熟して、黄色く色づくのも例年より早かったように感じています。
青い実と言えば
杏子の種や未熟な青梅とその種には、青酸配糖体アミグダリンが含まれ、そのまま食べて人の酵素と一緒になると、頭痛、めまい、発汗等の中毒様症状を起こすことが知られています。
子供の頃、青梅は絶対にそのまま食べないように、と注意されたのを思い出しますよね。
そう聞くと青梅が怖い、と言う人もあると思いますが、大丈夫です。
毒成分アミグダリンは、実が熟すか、酒、砂糖、塩等で加工することで毒性が無くなります。
国産杏子は黄色く熟しても酸味が強いので、ジャム等の加工に適しています。種の剝がれが良いので手作りの加工もしやすいのです。
梅酒や梅干し、ジャムは、実の熟し具合で、加工後の酸味、甘みが異なりますのでお好みで実の熟度を調整すると良いと思います。

〇杏子・梅の健康効果
色々な効果が知られていますが、私は酸味と香りに関心があります。
① 杏子・梅の酸味
酸味は、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸等で、食物の糖質代謝に有効に関与し、体の疲れ予防や回復にとっても役立ちます。
一般に、エネルギー代謝がうまくいかないと、栄養素が不完全燃焼となり、疲れやその回復も遅くなります。
杏子や梅の酸味成分であるクエン酸やリンゴ酸等の有機酸は糖質の代謝を促し、栄養素をエネルギーに変換する働きがスムーズになり、疲労回復だけではなく、疲れにくい体を作ることも可能です。
特にクエン酸は、唾液の分泌を促して食欲を増進させます。そして胃液やその他の消化酵素の分泌を高めて消化吸収を助けてくれる働きがあります。
② 杏子・梅の香り
杏子と梅の熟果の香気成分は、ベンズアルデヒドで、鼻に広がると、さわやかな気分にさせてくれる特徴があります。
じめじめした梅雨時から、日向臭い夏の匂いに、さわやかな香りは大切です。
杏子と梅仕事。6月の梅雨時に仕込んで夏以降にいただく、夏の疲れの回復にいかがでしょうか?
〇杏子と梅のmy加工方法
私は、杏子ジャムと杏子酒、梅酒、梅漬けの塩と砂糖の塩梅は、実の収穫量が毎回異なるので、重量比率で決めておき、毎年悩まないようにしています。
【杏子ジャム(砂糖少な目)】
杏子種取り後の重量に対し、砂糖は杏子の25%
例えば、種取杏子1kgに対し砂糖250g
① 杏子は、つまようじで丁寧にヘタを取り除き、水洗いしてペーパーで拭いておきます
②杏子の縦の筋に沿って包丁を入れ、ひねって種を外します
③ 鍋に杏子を入れ、分量の砂糖を振り入れて、砂糖が溶けるまでおいておきます
④ ゆっくり加熱し、一時間程かき混ぜながら煮ます。ボールの水にジャムを落とし、混ざらなければできあがりです
⑤ 瓶と蓋は熱湯消毒し、ジャムを詰めて蓋をする前に湯につけ、少し沸騰させてから蓋を閉ます(脱気)
標準は、杏子の重量に対し30~40%の砂糖を使用しますが、完熟の杏を使えば25%でも十分に美味しくいただけます。
ジャムは消毒した瓶に詰め脱気して冷凍した場合、1年は十分に保存できます。

【ブランデー梅酒】
梅酒定番の焼酎をブランデーに変えるだけで味わいが深くなります。ゆっくり溶かすために砂糖は氷砂糖を使用します。
梅(種付き)の重量に対し氷砂糖50%
例えば、梅1㎏に対し氷砂糖500g
① 梅は水洗いし、ペーパーで拭いておきます
② 消毒した瓶に、梅と氷砂糖を交互に入れていきます
③ そのまま冷暗所に保存し青梅が黄色く熟してきます
④ 早ければ3ヶ月後から飲めますが、1年経過すると味わいが深まります

【杏子酒】
杏子の風味を活かすため、焼酎でシンプルにつくります。
杏子(種付き)の重量に対し氷砂糖50%
例えば、杏子1㎏に対し氷砂糖500g
① 杏子は水洗いし、ペーパーで拭いておきます
② 消毒した瓶に、杏子と氷砂糖を交互に入れていきます
③ そのまま冷暗所に保存します
④ 早ければ3ヶ月後から飲めますが、杏子の香気がまだ十分ではありません。1年経過すると味わいが深まります

【梅漬け】
梅干しは、忙しい方は干さずに「梅漬け」をおすすめします。
梅(青梅か少し熟している梅)種付きに対し塩18%
赤しそは梅の15~20%
赤しその塩18%
例えば梅1㎏に対し塩180g、赤しそ150g~200g+塩27g~36g
梅漬けの塩の割合は20%が標準とされていますが、15~18%でも保存は十分に効きます。塩漬けして梅酢が上がってきたら、赤しそを同じ割合の塩でもみアク抜きして一緒に漬けましょう。
① 梅は水洗いし、ペーパーで拭いておく
② 消毒した瓶に梅と分量の塩を交互に入れていく
③ そのまま梅酢が上がり、梅が熟して黄色くなったら塩もみししたしそを入れる時期です
④ 良く洗った分量の赤しそを分量の塩でもみ、アクを抜いて、梅の上にのせ冷暗所で保存します
⑤ 夏が過ぎたら食べられますが、半年寝かせると塩味と酸味が落ち着いて食べ頃です
⑥しその赤い梅酢は、別に取り出し新生姜を漬けて「紅生姜」にしても美味しいです。また、「梅ドレッシング」にしてサラダにも使えます。
しその葉は、乾燥してもめば「しそふりかけ」になる等、無駄はひとつもありません。


忙しくてもお出かけ控えめな今日、杏子や梅仕込みの仕事は、思いのほか心が落ち着きます。
今回もありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
