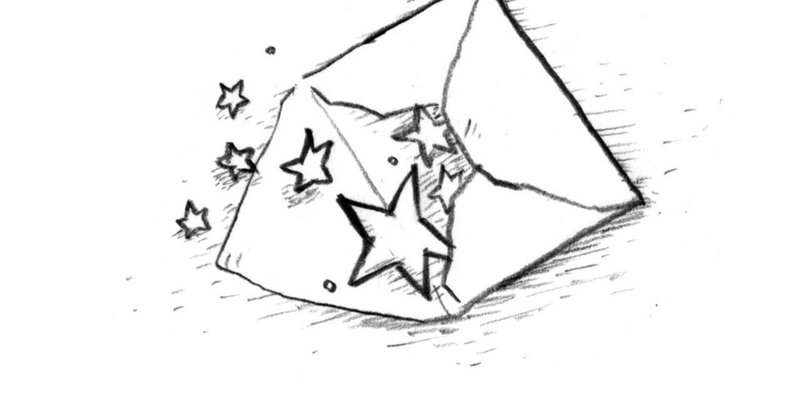
その人のこと
出会った時から、もう恋に落ちていた。私はいずれ、良い形か悪い形かは分からないけれど、きっとこの人に会いたくて会いたくて泣いてしまう日が来るのだろう。19歳ながらにそんな予感がした。私が遠慮がちに挨拶をすると、作業をやめてこちらをチラッと見たその人は名字を名乗るだけの簡単な自己紹介をした。慌てて私も名乗る。よろしくお願いします、と付け足しながら、私は既にその人の下の名前を知りたくなってしまっていた。もう、その時点で始まっていた。
それでも出会った瞬間から始まる予感がしたのはやっぱり私だけだったようで、私たちが出会ってから4年間、何かが始まることはなかった。小さいコミュニティの中でその人の人気はそこそこ高かったようで、私が彼に出会った時にはもうその人には綺麗な彼女がいた。それはそれは綺麗で、女性らしくて、闘争心むき出しがちな私がやる気すら失うくらいの素敵な人だった。
その人は、人当たりが良いように見えて、実は誰にも興味が無いような人だった。私はそういう種類の人が物凄く気になってしまう。そういう人に「面白い」と思ってもらえる人間になりたい。あるいは、少しでもその人のテリトリーに近付いてみたい。同じ目線で同じ温度で話をしてみたい。その人はいつも冷たすぎる常温だった。私に向けられているであろう言葉も、全然温度がない。反対に私から届けようとした言葉も、その人に届く前にしおれてしまっている気がした。どんなに頑張っても、何故かコミュニケーションが取れていないような。私は、いつかその人に興味を持ってもらえることを密かに目標にしていた。
私は「憧れ」と「恋心」を履き違えてしまっているのだろう。いつもそう思っていた。私の中のその人は、「憧れ」の対象であって、恋愛としての好きではないのだ。どうしても踏み出せない壁があって、私は律儀にその線をこえないよう慎重に守っていた。そうすれば、絶対に失うこともない。私は臆病者だった。恋に変えていつか失うより、憧れの位置で一生無くさず見ていたい。後輩という立場は、利用するのに丁度良かった。程よく甘えても近付いても自然だ。連絡先もすんなり手にいれて、大学内で偶然出会ったら挨拶が出来た。誰にもその人への気持ちを明かさず、自分にはずるく言い訳をしていた。それでいて、勝手にその人を心の拠り所としていた。
そんな中でも私はちゃんと「人に言える」恋をして、その人とお付き合いをした。趣味も興味があることも(今考えてみると性格も)あんまり合っていなかったけれど(なんで付き合ったんだと聞かれても、当時は彼しかいないと私は信じて疑わなかったのだ(笑))、紆余曲折ありながらも一年くらいは交際が続いていた。それでもその期間も私の心の拠り所はその人だった。バイト終わりに、彼氏とあんまり上手くいかないときに、くしゃくしゃした心のまま、化粧が落ちた汗まみれの顔のまま、時には寝巻きやジャージで半乾きの髪で、私はその人に会いに行った。会いに行くと言っても私の一方的なもので、その人はいつも私に目もくれず自分の作業に集中しており、二、三言、言葉が交わせればラッキーな方だった。でもそれだけで私のくしゃくしゃした心は元通りになって、かわりに少しだけ弾んだハッピーな気持ちと後ろめたい気持ちが残った。
その人との真夜中の帰り道、二度試したことがある。私もその人も、自転車を愛用していた。でも、せっかく一緒に帰れるのに、自転車に乗ってしまえばあっという間に分かれ道に着いてしまう。だから私は、わざと自転車に乗らず、押してみた。もう少し話したいなんて一言も言わなかった。ずるいから。こっそり試したのだ。それでその人が自転車に乗ってしまえば私も当たり前のように自転車に乗って帰ればいいし、自転車を押して歩いて帰ってくれるのならばラッキーだな、なんて。自転車、乗って。いや、押して歩いて。でも、もし私がその人の彼女の立場だったら、その人が自転車乗らないと悲しいな...でも、押して。一緒に歩いて。あわよくば、私に興味持って。そうやって、ずるい駆け引きをした。
結局その人は、二度とも、自転車を押して歩いてくれた。どうして自転車乗らないの、なんて意地悪な質問もしてこなかった。くだらない会話に付き合ってくれた。そんな風に人を試す時点で私はどっぷり沼にはまってしまっていたし、そんな女のこと、その人が好きになるわけないとどこかではわかっていた。でも、嬉しかった。希望が持てた。頑張ればあわよくば、がこぼれてくるかもしれない。でも、私はその人の彼女になりたいわけでもなかった。勝手に依存して、勝手に安心していたのだ。もしも恋人になってしまったら、いつか終わるから。それくらいなら、この距離がいちばん安全だ。この距離は、始まらないけれど終わらない。
そうやってすぐに大学の四年間は過ぎた。たまに羽目を外して私はその人に告白まがいのことをしてしまうことがあったけれど、その人は賢く緩く私を否定せずに受け入れて流した。私も私で「先輩が好きです」なんてことは言わなかった。「先輩の才能が好きです」「先輩の持っているものが好きです」と、言い続けた。そうすれば、「恋」でなく「憧れ」でいられるから。でも、それでも私にとっては大事な大事な人生の告白だったのだ。私はとてもとても狡く慎重だった。一歩間違えば全部無くす。きっと相手は、自分に興味があると分かった時点ですっと逃げる人だから。そう思いながら限りなくゼロに近いところで漂って、でもゼロではなくて、私たちは何も始まらなかった。多分、私があと少し踏み出せばきっかけがあったのかもしれない。自分で言うのも何だけど、脈が全くないわけではなさそうだった。でもきっと、あの頃その人と運良く付き合うことができていたとしても、すぐに破綻していただろう。自分に好意があると知ると面倒になるその人と、自分の思ったようなコミュニケーションが取れないと落ちこみ悲しむ私。そんなの、絶対にやめた方がいい。現実にならなくても未来は見えていた。だから、あの時始まらなくて良かった。あの時の最善の距離を私たちは結果的に選択できていたのかもしれない。
そして。
その人と私は、出会ってから5年目の冬に、ようやく始まった。
私は物分かりが良くなっていたし、学生時代よりも少しだけ自分を肯定する力が育っていた。その人と私は、以前よりも同じ温度と密度の言葉でやり取りが出来るようになっていた。不思議だ。昔も今もその人を好きで憧れているのは同じはずなのに、何なら昔の方が私からの気持ちは強すぎるくらいだったのに、何故か今だったら上手くいく。「大学の時、隣で話してても全然違うとこにいるみたいな感覚だったんだ、でも、今は違うよ、ちゃんと会話できてる気がする」って打ち明けると、その人は何故か少しだけ笑っていた。「人生はタイミング」誰かが言ってた。そんなの冷たい言い訳だと思っていた。でも、そうじゃないかもしれない。
あの時なにも始まらなくて、良かった。
なんて、その人には絶対言わないけど。
この先終わるかもしれないリスクを背負ってでも、あなたと近くに居れることが今はちゃんと嬉しいと思えるよ。あなたと恋が出来て、本当に良かった。
ゆっくりしていってね
