
怪談箪笥 (ショートストーリー)
昨年、Gakkenより刊行された短編アンソロジー『3分間のまどろみ カプセルストーリー 青』収録の「怪談箪笥」を公開いたします。
作者としては縦書きで読んでほしいお話なので、文庫ページメーカーを使用しました。(末尾に通常の横書きも掲載しています)
名前もつけなかったこの家具商人のことを私は気に入っていまして、また違うお話も書きたいなと思っています。
それでは、お楽しみいただけましたら幸いです……
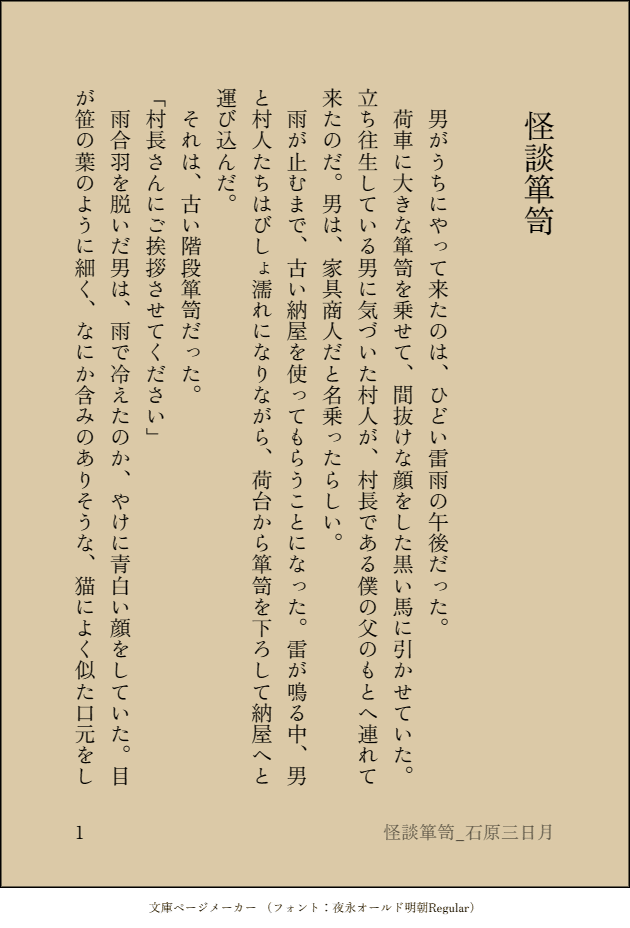
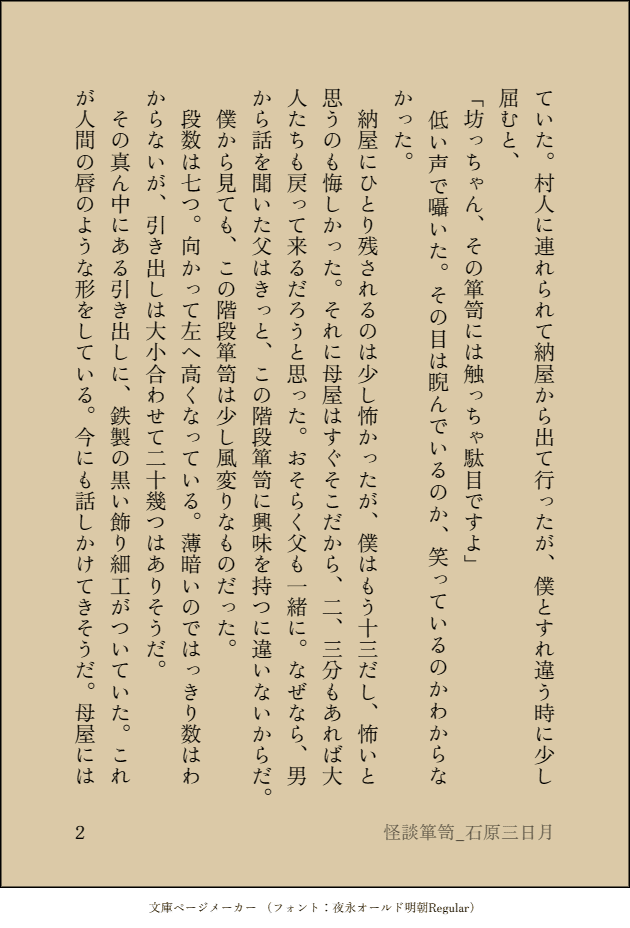
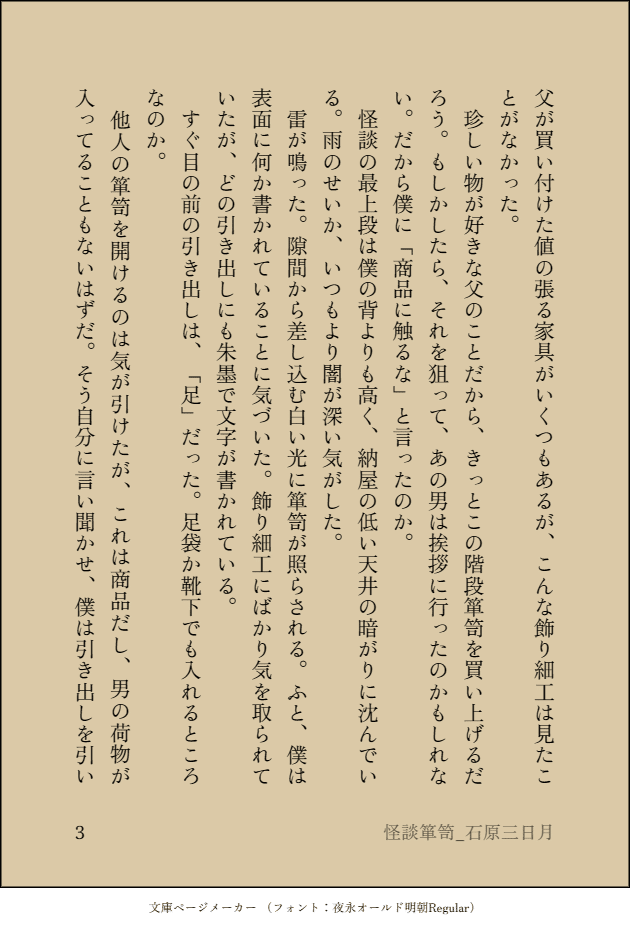
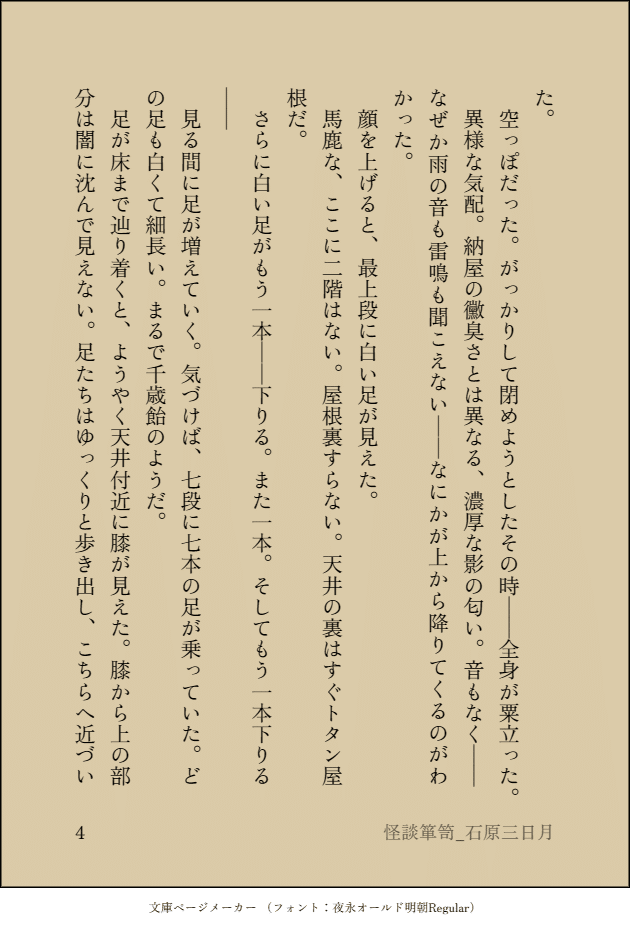
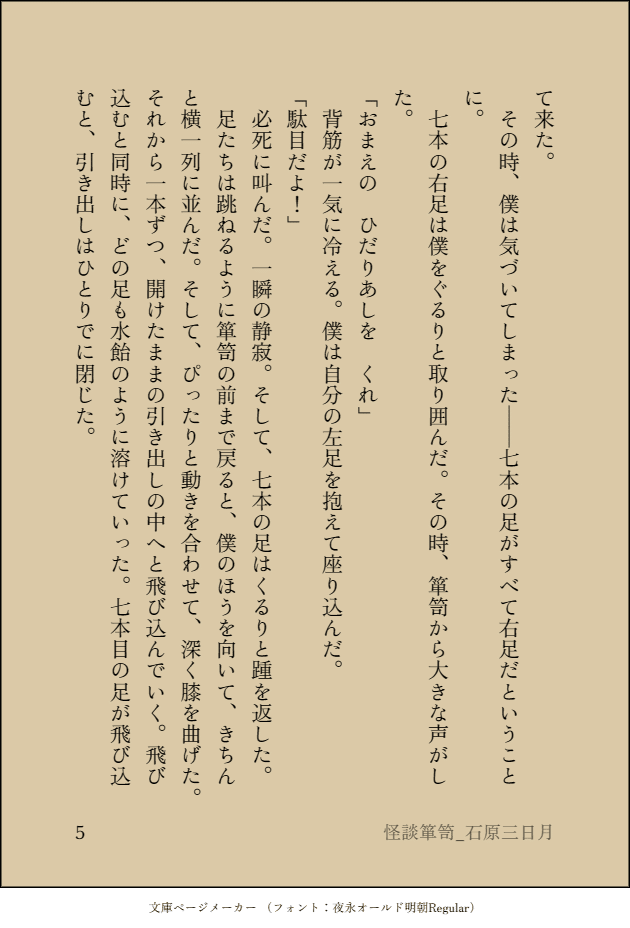

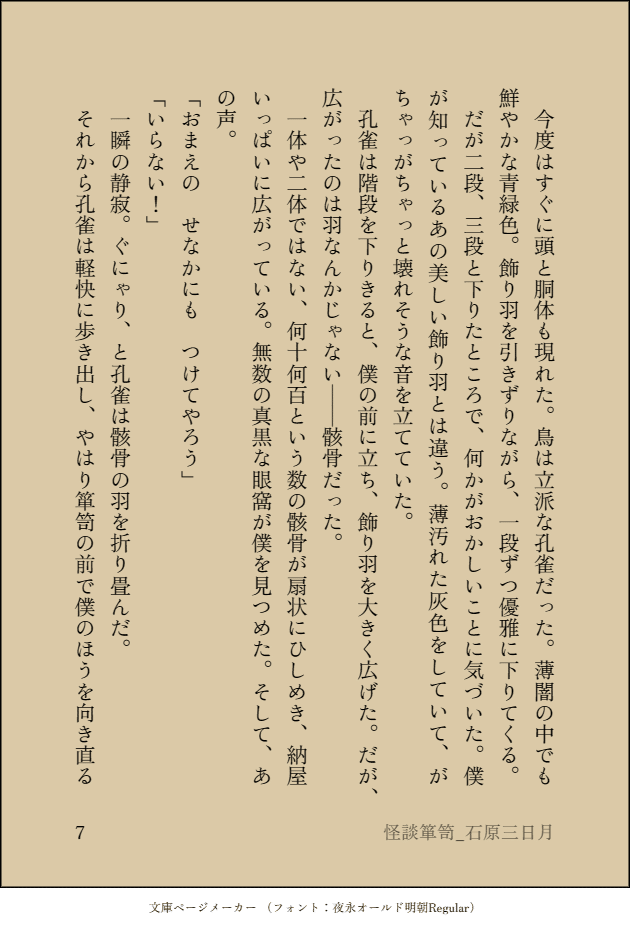
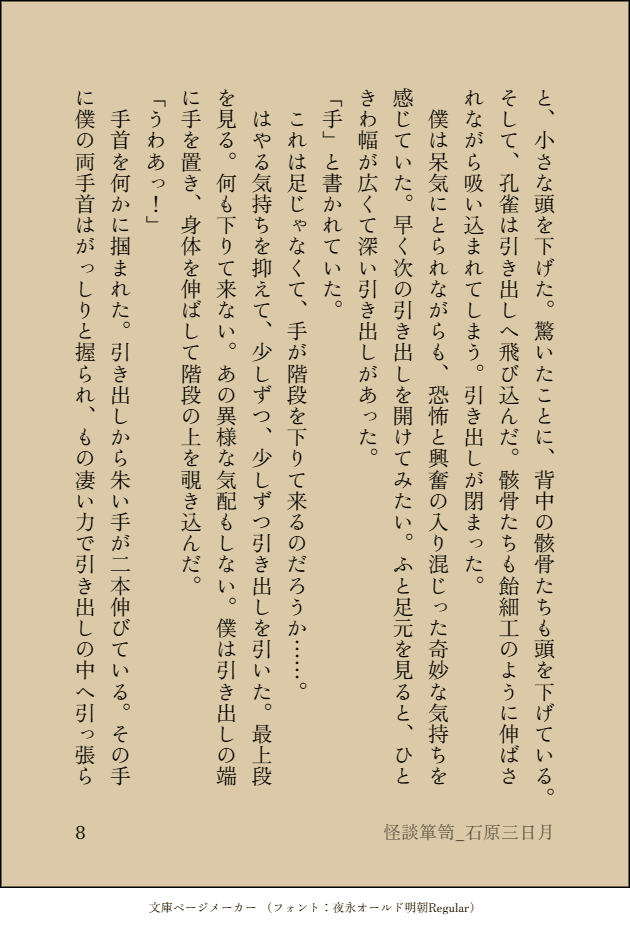
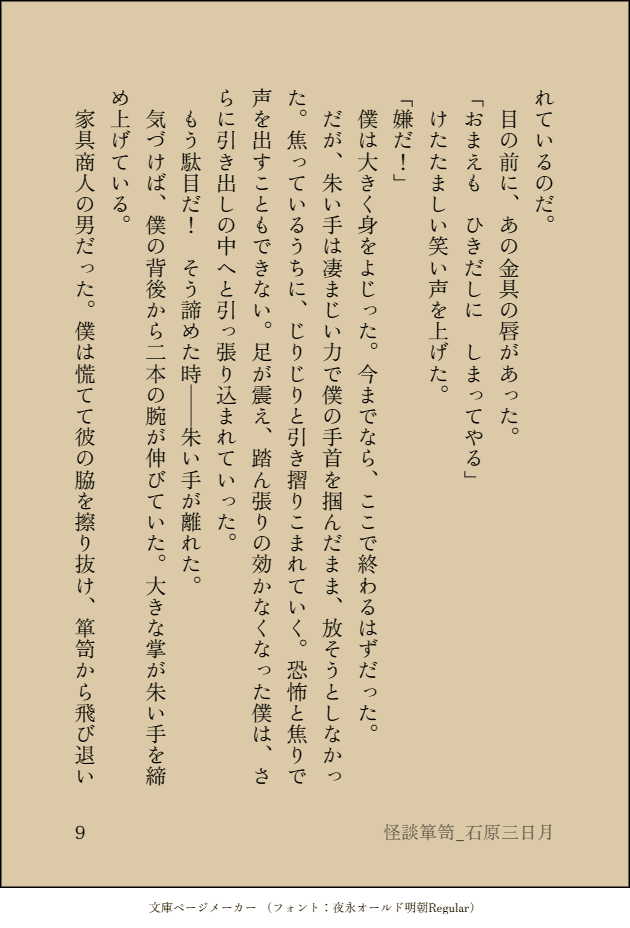
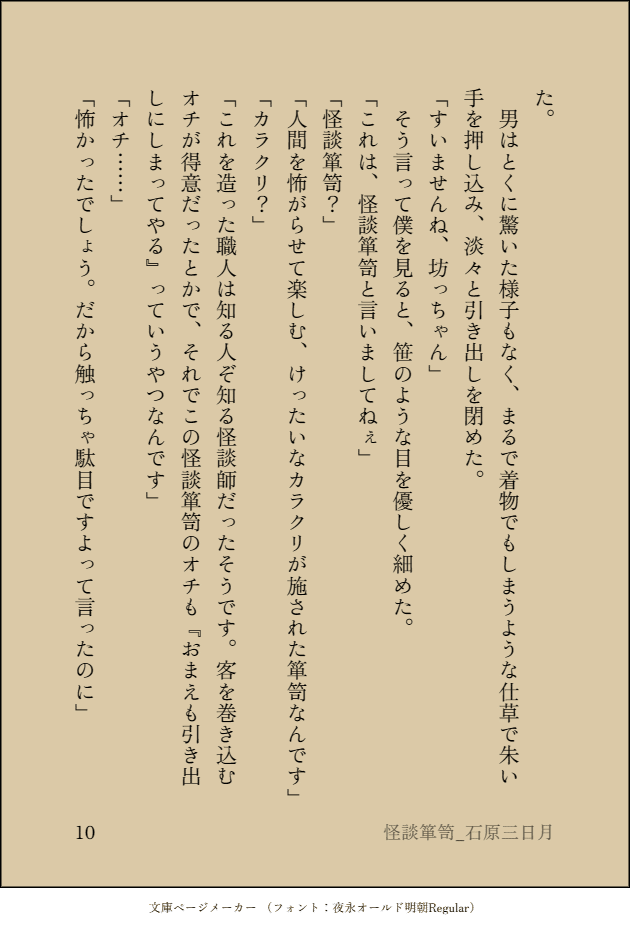
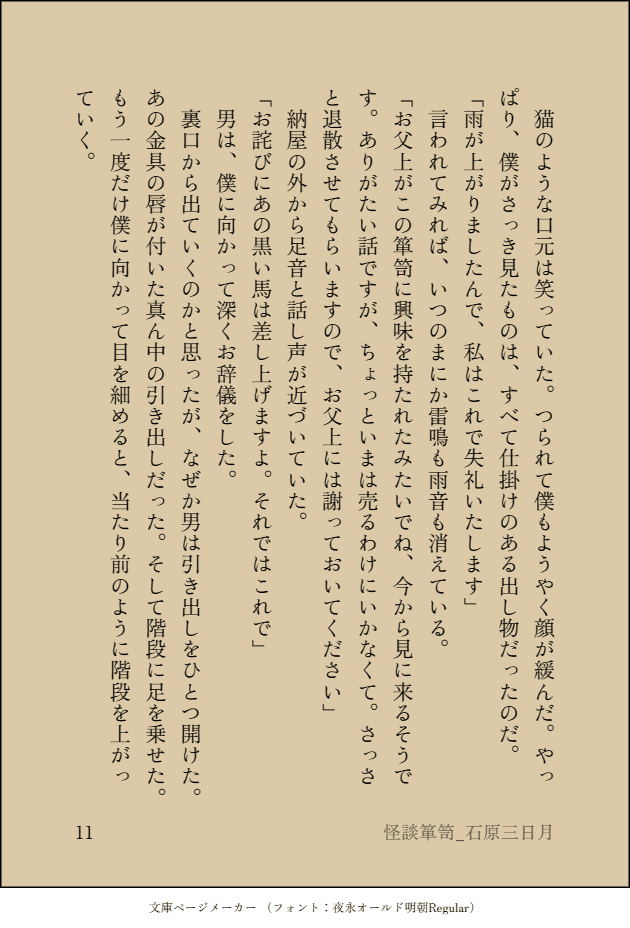
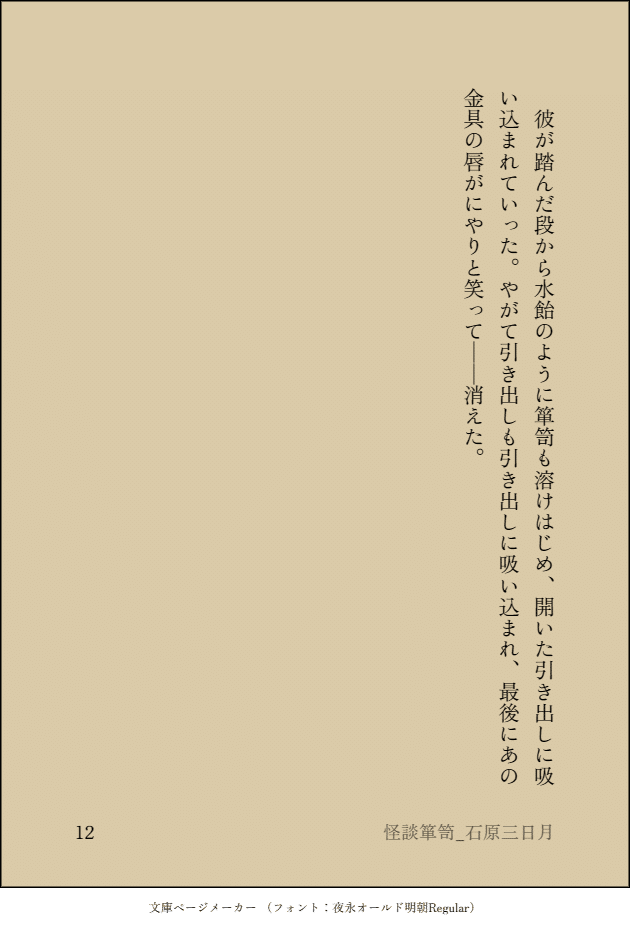
怪談箪笥
男がうちにやって来たのは、ひどい雷雨の午後だった。
荷車に大きな箪笥を乗せて、間抜けな顔をした黒い馬に引かせていた。立ち往生している男に気づいた村人が、村長である僕の父のもとへ連れて来たのだ。男は、家具商人だと名乗ったらしい。
雨が止むまで、古い納屋を使ってもらうことになった。雷が鳴る中、男と村人たちはびしょ濡れになりながら、荷台から箪笥を下ろして納屋へと運び込んだ。
それは、古い階段箪笥だった。
「村長さんにご挨拶させてください」
雨合羽を脱いだ男は、雨で冷えたのか、やけに青白い顔をしていた。目が笹の葉のように細く、なにか含みのありそうな、猫によく似た口元をしていた。村人に連れられて納屋から出て行ったが、僕とすれ違う時に少し屈むと、
「坊っちゃん、その箪笥には触っちゃ駄目ですよ」
低い声で囁いた。その目は睨んでいるのか、笑っているのかわからなかった。
納屋にひとり残されるのは少し怖かったが、僕はもう十三だし、怖いと思うのも悔しかった。それに母屋はすぐそこだから、二、三分もあれば大人たちも戻って来るだろうと思った。おそらく父も一緒に。なぜなら、男から話を聞いた父はきっと、この階段箪笥に興味を持つに違いないからだ。
僕から見ても、この階段箪笥は少し風変りなものだった。
段数は七つ。向かって左へ高くなっている。薄暗いのではっきり数はわからないが、引き出しは大小合わせて二十幾つはありそうだ。
その真ん中にある引き出しに、鉄製の黒い飾り細工がついていた。これが人間の唇のような形をしている。今にも話しかけてきそうだ。母屋には父が買い付けた値の張る家具がいくつもあるが、こんな飾り細工は見たことがなかった。
珍しい物が好きな父のことだから、きっとこの階段箪笥を買い上げるだろう。もしかしたら、それを狙って、あの男は挨拶に行ったのかもしれない。だから僕に「商品に触るな」と言ったのか。
怪談の最上段は僕の背よりも高く、納屋の低い天井の暗がりに沈んでいる。雨のせいか、いつもより闇が深い気がした。
雷が鳴った。隙間から差し込む白い光に箪笥が照らされる。ふと、僕は表面に何か書かれていることに気づいた。飾り細工にばかり気を取られていたが、どの引き出しにも朱墨で文字が書かれている。
すぐ目の前の引き出しは、「足」だった。足袋か靴下でも入れるところなのか。
他人の箪笥を開けるのは気が引けたが、これは商品だし、男の荷物が入ってることもないはずだ。そう自分に言い聞かせ、僕は引き出しを引いた。
空っぽだった。がっかりして閉めようとしたその時――全身が粟立った。
異様な気配。納屋の黴臭さとは異なる、濃厚な影の匂い。音もなく――なぜか雨の音も雷鳴も聞こえない――なにかが上から降りてくるのがわかった。
顔を上げると、最上段に白い足が見えた。
馬鹿な、ここに二階はない。屋根裏すらない。天井の裏はすぐトタン屋根だ。
さらに白い足がもう一本––––下りる。また一本。そしてもう一本––––下りる――
見る間に足が増えていく。気づけば、七段に七本の足が乗っていた。どの足も白くて細長い。まるで千歳飴のようだ。
足が床まで辿り着くと、ようやく天井付近に膝が見えた。膝から上の部分は闇に沈んで見えない。足たちはゆっくりと歩き出し、こちらへ近づいて来た。
その時、僕は気づいてしまった――七本の足がすべて右足だということに。
七本の右足は僕をぐるりと取り囲んだ。その時、箪笥から大きな声がした。
「おまえの ひだりあしを くれ」
背筋が一気に冷える。僕は自分の左足を抱えて座り込んだ。
「駄目だよ!」
必死に叫んだ。一瞬の静寂。そして、七本の足はくるりと踵を返した。
足たちは跳ねるように箪笥の前まで戻ると、僕のほうを向いて、きちんと横一列に並んだ。そして、ぴったりと動きを合わせて、深く膝を曲げた。それから一本ずつ、開けたままの引き出しの中へと飛び込んでいく。飛び込むと同時に、どの足も水飴のように溶けていった。七本目の足が飛び込むと、引き出しはひとりでに閉じた。
僕は座り込んだまま、動けなかった。今のは何だったのだろう。
足たちに囲まれた時は怖かったし、箪笥から聞こえた声にも背筋が凍った。が、僕に向かって足たちが膝を曲げた時にはその怖い気配は消えていたのだ。どういうことだろう。
僕はふと、父の収集品にある自動人形のことを思い出した。ゼンマイを巻くと、決められたお芝居の動きをする珍しいものだ。その人形は一連の動作の最後に、ぴょこんと頭を下げてお辞儀をする。ぎこちないその動作と、足たちが膝を曲げた動きはよく似ている気がした。もしかしたら、この箪笥も決められたお芝居の仕掛けがされているのではないか。
僕は立ち上がった。目の前に、べつの引き出しがあった。
次は、「背」だった。
戸惑いながら、そうっと引き出しを引いた。すぐにまた気配がした。一瞬身構えたが、階段に現れた足を見て安堵する――鳥の足だった。しかも普通に二本ある。
今度はすぐに頭と胴体も現れた。鳥は立派な孔雀だった。薄闇の中でも鮮やかな青緑色。飾り羽を引きずりながら、一段ずつ優雅に下りてくる。
だが二段、三段と下りたところで、何かがおかしいことに気づいた。僕が知っているあの美しい飾り羽とは違う。薄汚れた灰色をしていて、がちゃっがちゃっと壊れそうな音を立てていた。
孔雀は階段を下りきると、僕の前に立ち、飾り羽を大きく広げた。だが、広がったのは羽なんかじゃない――骸骨だった。
一体や二体ではない、何十何百という数の骸骨が扇状にひしめき、納屋いっぱいに広がっている。無数の真黒な眼窩が僕を見つめた。そして、あの声。
「おまえの せなかにも つけてやろう」
「いらない!」
一瞬の静寂。ぐにゃり、と孔雀は骸骨の羽を折り畳んだ。
それから孔雀は軽快に歩き出し、やはり箪笥の前で僕のほうを向き直ると、小さな頭を下げた。驚いたことに、背中の骸骨たちも頭を下げている。そして、孔雀は引き出しへ飛び込んだ。骸骨たちも飴細工のように伸ばされながら吸い込まれてしまう。引き出しが閉まった。
僕は呆気にとられながらも、恐怖と興奮の入り混じった奇妙な気持ちを感じていた。早く次の引き出しを開けてみたい。ふと足元を見ると、ひときわ幅が広くて深い引き出しがあった。
「手」と書かれていた。
これは足じゃなくて、手が階段を下りて来るのだろうか……。
はやる気持ちを抑えて、少しずつ、少しずつ引き出しを引いた。最上段を見る。何も下りて来ない。あの異様な気配もしない。僕は引き出しの端に手を置き、身体を伸ばして階段の上を覗き込んだ。
「うわあっ!」
手首を何かに掴まれた。引き出しから朱い手が二本伸びている。その手に僕の両手首はがっしりと握られ、もの凄い力で引き出しの中へ引っ張られているのだ。
目の前に、あの金具の唇があった。
「おまえも ひきだしに しまってやる」
けたたましい笑い声を上げた。
「嫌だ!」
僕は大きく身をよじった。今までなら、ここで終わるはずだった。
だが、朱い手は凄まじい力で僕の手首を掴んだまま、放そうとしなかった。焦っているうちに、じりじりと引き摺りこまれていく。恐怖と焦りで声を出すこともできない。足が震え、踏ん張りの効かなくなった僕は、さらに引き出しの中へと引っ張り込まれていった。
もう駄目だ! そう諦めた時――朱い手が離れた。
気づけば、僕の背後から二本の腕が伸びていた。大きな掌が朱い手を締め上げている。
家具商人の男だった。僕は慌てて彼の脇を擦り抜け、箪笥から飛び退いた。
男はとくに驚いた様子もなく、まるで着物でもしまうような仕草で朱い手を押し込み、淡々と引き出しを閉めた。
「すいませんね、坊っちゃん」
そう言って僕を見ると、笹のような目を優しく細めた。
「これは、怪談箪笥と言いましてねぇ」
「怪談箪笥?」
「人間を怖がらせて楽しむ、けったいなカラクリが施された箪笥なんです」
「カラクリ?」
「これを造った職人は知る人ぞ知る怪談師だったそうです。客を巻き込むオチが得意だったとかで、それでこの怪談箪笥のオチも『おまえも引き出しにしまってやる』っていうやつなんです」
「オチ……」
「怖かったでしょう。だから触っちゃ駄目ですよって言ったのに」
猫のような口元は笑っていた。つられて僕もようやく顔が緩んだ。やっぱり、僕がさっき見たものは、すべて仕掛けのある出し物だったのだ。
「雨が上がりましたんで、私はこれで失礼いたします」
言われてみれば、いつのまにか雷鳴も雨音も消えている。
「お父上がこの箪笥に興味を持たれたみたいでね、今から見に来るそうです。ありがたい話ですが、ちょっといまは売るわけにいかなくて。さっさと退散させてもらいますので、お父上には謝っておいてください」
納屋の外から足音と話し声が近づいていた。
「お詫びにあの黒い馬は差し上げますよ。それではこれで」
男は、僕に向かって深くお辞儀をした。
裏口から出ていくのかと思ったが、なぜか男は引き出しをひとつ開けた。あの金具の唇が付いた真ん中の引き出しだった。そして階段に足を乗せた。もう一度だけ僕に向かって目を細めると、当たり前のように階段を上がっていく。
彼が踏んだ段から水飴のように箪笥も溶けはじめ、開いた引き出しに吸い込まれていった。やがて引き出しも引き出しに吸い込まれ、最後にあの金具の唇がにやりと笑って――消えた。
*Amazon Kindleのほかにも、楽天Kobo、Apple Books等、各電子書籍サイトにてご購入いただけます。
*作品公開については監修・田丸雅智氏の了承を得ております。
いただいたサポートは新作の取材費用に使わせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします🌙
