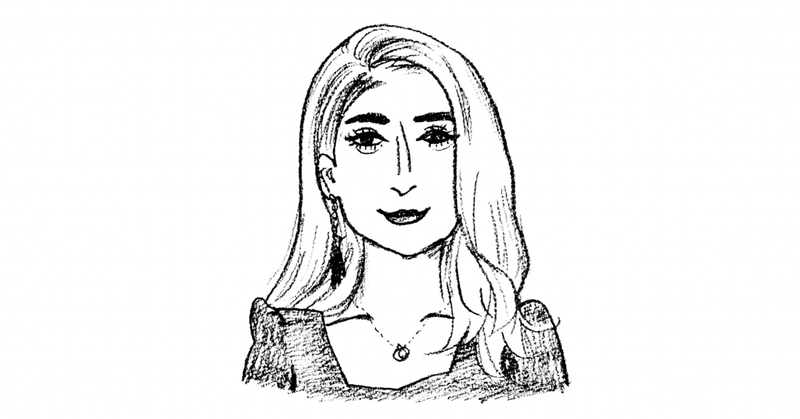
ひとりと、深夜の居酒屋で元カレを想うギャル
「ひとりと、」シリーズ 概要
数か月前、朝の珈琲と夜のお酒が楽しい街に引っ越した。
私は、ひとりが好きだけど孤独は好きじゃないから、家は仕事か食事か風呂か睡眠ぐらいでしか利用せず、平日の夜中と休日のほとんどの時間、街に出て過ごしている。カフェや喫茶店、居酒屋、バー、スナック…。長時間滞在できて、私の他に誰かがいる空間で過ごすのが好きだ。
働き盛りの27歳、独り身の一人暮らし。とはいえ特に稼いでいるわけでもないのにもかかわらず外で過ごしたい私は、安賃料の狭いアパートの一室を借りている。
せっかくなので、誰かと遊ぶ以外、ほとんどの時間をひとりで街に出て過ごす過程で、出会った人々や起きた出来事、そして何も起きていない時間まで、記録として不定期で投稿していきたいと思う。初回は、平日の深夜、近所の居酒屋で出会ったギャルとのなんてことない会話から。
※交わした会話やその時に感じたことを事細かに覚えているはずもないし、登場人物は匿名ではあるもののプライバシーには配慮したいので、事実を少し物語風に脚色した「事実×創作エッセイ」と言う名目で書いています。自分のこともちょっと良い感じに描いちゃったりしています。
ひとりと、深夜の居酒屋で元カレを想うギャル
仕事終わりにひとりで飲みに行くことが多い私は、カウンターで飲むことが多い。仕事は基本家でやり、だいたい夜中のゼロ時前後で終わる。だから家の近くに二時まで営業する居酒屋があるのはありがたかった。夜に食事をとらないと空腹で眠れないのが常だから、体に悪いことはわかりつつも、ゼロ時を超えてからお酒と共に食事をとることが多かった。深夜ラジオを聴きながら。積読を消化しながら。スマートフォンでお笑いを観ながら。店主や常連さんと話しながら。日によって、その時間にすることは様々だけれど、そのどれもが気楽にできて、帰るころには気分が晴れやかになる。だから私は、その居酒屋での時間を大切に想っていた。
もう何度目の訪問か見当もつかない、いつかの夜。いつもと同じように、芋焼酎の炭酸割を片手にもつ煮をつまんでいると、私の隣に一人の女性が座った。最初は特に気にしていなかったけれど、注文をするときに聞こえる、度を超えた酒焼けの声が気になり、店内に立てかけられているはずの時計を探すふりして彼女の顔を見た。“典型的なギャル”という言葉で言いくるめてしまっても「ウケる」と無表情で言ってくれそうなほどのギャル風情で、それでいて大人びた表情にどこかあどけなさを思わせる雰囲気を持つその女性は、不自然な視線に気づいたのか、私の方を一瞥し、そして大きく口を開けて驚いた表情を見せた。聞くと、私はその女性の元カレにそっくりのようだった。
「他の女ができたからって、一方的に振られて。あ、これ、つい先週の話」
挨拶もそこそこに語りはじめるその女性はため息をつき、もう何回目だろ。と呟いた。
「そいつね、いや、私もだけど、これまで何回もそんなこと繰り返してて。他に女ができる度に別れて、その女と別れる度に私により戻してくれって泣きついて。もう無理って口では言っても、私やっぱそいつのことが好きなんだよね。それに、泣きついてくるときはめっちゃ真剣だから、つい私も頷いちゃって」
最初の挨拶で私の方が一つだけ年下という事実がわかったからか、それとも普段からこういう口調なのかわからないけれど、まるで近所に住む幼馴染のお姉ちゃんのような軽快な口調で、深刻じみた話をまくしたてる。
「もう私限界で。でも連絡先ブロックしたくても、どうしてもできなくて。次の女とはどのくらいで別れるかな、とか考えちゃってる。よくないよね、こういうの。わかってるんだけど」
自分で質問と回答を間髪入れずにいれてくる人は、たいてい弱っていることが多い。良くないことはわかっているけど、それでもやってしまうのが人間でしょう?とでも言うかのように。そういう時は対外、知らぬうちに聞き手側も共犯者になってしまう。
「その男が他の女と付き合ってる間に新しい恋とかはしてないんですか?」
それまで「えー」「うわっ」「まじすか」のような相槌しか打てていないことにだんだんと罪悪感を覚え、遠くを見つめるその女性に問いかけると、彼女はグラスに視線を落として少し考える素振りを見せた。
「えー、うわっ、でもなー」
先ほどまでの私の雑な相槌のような、それでいて語尾に力を込めたそのイントロが少しの間続き、
「まぁ、なんか、言っちゃうけど、私もその男に振られるたびにすぐに連絡する男がいるんだよね」
そういってはにかみ、恥ずかしさを紛らわすようにお酒を口にする。
「そいつは私と元カレの関係知ってて、別れたら連絡してって言われてて。だからしちゃう」
ちゃんと悪いなとは思うんだけどね。その言葉の流れのまま彼女は店員に空っぽのグラスを渡し、おかわりを促した。
「恋愛って難しいですよね」
誰にでも言える言葉を、その人にとって誰でもない私がそう言うと、
「ほんっとにそう」
彼女はそういって天を仰いだ。
「でもなんか、最近はそれが楽しい。いつまでそんなことしてるんだ!だの早く大人になれ!だの言われるんだけどね。わかってるっての。だから最近は知り合いにはこのこと話してない。私はきっと、わざとこんな風に生きてる」
「何かに抗うように」
「そう、抗ってる。うるせーってね」
私の相槌が彼女にとっての的を射ていることに、勝手に気分が良くなってくる。
「大人になれって、嫌な言葉ですよね」
「超ウザい。体が大人になっていくのは嬉しいけど、心はガキな部分あった方が楽しくない?マジで」
“ギャル”という言葉で一括りにしたくはないけれど、彼女らはきっと、子どもと大人の狭間で人間を思うままに楽しんでいる。
それが、“ギャル”が世間に恐れられている部分であり、同時にかけがえのない魅力なのだと、私は改めて認識した。
「あーやっぱり、知らないやつに話すのが一番気が楽になるわ」
「それ、わかります」
「んね。ところで君、彼女は?」
「いないです」
「寂しいとか思う?」
「結構思いますね。でも今は誰かと付き合いたいとかはまったくないですね」
「なにそれ、笑う」
ウケる、じゃないんだ。そう思いながら、返す言葉も見当たらないので愛想笑いを浮かべると、彼女は何故か満足そうに煙草に火をつけた。
カウンターの上を彷徨う煙越しに、店主が私たちにラストオーダーを促す。
通常のラストオーダーを少し過ぎていることに気づき、タイミングを窺ってくれていた店主の気遣いに心の中で手を合わせた。
そうして私は彼女に、またこの店で会えたらいいですね、と言って会計をし、店をあとにした。
何も解決しないでいい。他人だから話せることと、他人だからできる相槌を交わすだけで、その夜は完成するものなのだ。そんな自己陶酔と共に、その日は気持ちよく眠りについた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
