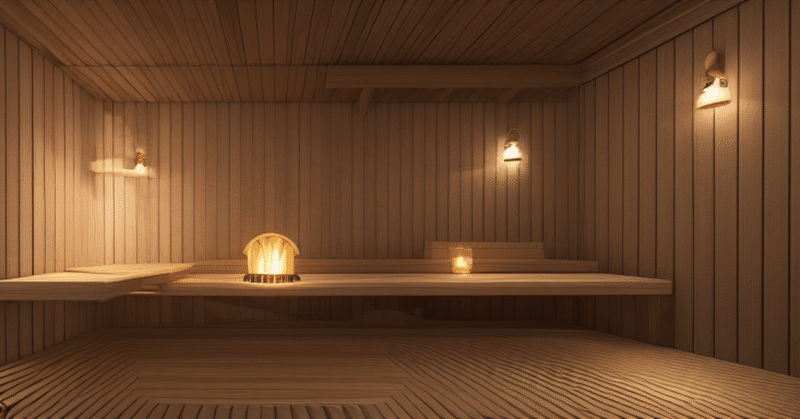
第2章 ぐらつく2つの道-2
それから、その男。いや、先輩とは定期的にサウナに通うようになり、たまたま一緒になった剣崎とも仲良くなって一緒に楽しむようになった。そして何やかんやあり、今に至るのだった。思い出に耽っていると横からチョップが飛んできた。
「セレン、ボーッとしない。早くいくぞ。どうせ彼女のことでも考えてたんだろ。」
「違いますよ、先輩のこと考えてました。」
「え。先輩ちょっと男の子から好意を向けられるのは初めてなんだよね。」
「そう言うのじゃないですから。全く、さっさといきましょう。」
正直言ってかなり面倒屈臭い。思い出は美化されてしまうものだとは、つくづくこのことなのだろう。そう感じながら、みんなの後を追い掛けた。
僕がぼさっとしている間に話は進んでおり、サウナフェスの会場となる場所に向かうようだった。笛吹さんがここだとつれてきてくれた場所はとても開けた渓谷になっていた。水は冷たく、まさにサウナの水風呂にはもってこいの水温である。また、渓谷の周りは開けた形になっており、ベンチタイム用のベンチもたくさん置ける。まさに最適である。
「サウナはテントサウナだっけか。薪はウチにある白金の間伐材を使うといい。好きなだけ使って構わないから。」
「ありがとうございます。これだと他の機材にコスト掛けられます。」
先輩はにやにやしながら笑っていた。この人はお金のことになると普段の倍は頭が働くな。と改めて感じた。
「少し、ここら辺を散策させてくれませんか。」
黒奈が横から割って入ってきた。
「ここら辺の危険になりそうな箇所を少し把握させて下さい。一応フェスで怪我人が出ることは避けたいので。」
「さすが黒奈ちゃん。そういう配慮。優しさが滲み出ているよ。」
「そいじゃあ、回ってみるか。」
笛吹さんを先頭に僕らは渓谷の周りを見回した。蝉の音がもうところどころで聞こえている。地球温暖化の影響だろうか。そう考えながら、草木の生い茂る道な道を散策していく。笛吹さんは野鳥や草木の説明をしながら案内してくれた。
「あれがカワセミだね。水辺に生息する小鳥で、鮮やかな水色の体と長いくちばしが特徴なんだよ。ヒスイ、青い宝石、古くはソニドリと呼ばれることもあるんだよ。」
「野鳥にお詳しいんですね。流石です。あ、あの建物はなんですか。教会みたいなもの。」
僕も気づいた。何だろう、あの建物は。建物2階くらいの高さの洋風の教会風の建物で、錆びれた感じである。何を目的に建てられたのだろうか。
「ここの管理をしていれば野鳥にも花にも詳しくなるよ。あれは、昔の建物だよ。俺もよく走らない。近寄らないことをお薦めするよ。危ないからね。」
「わかりました。気をつけますね。」
黒奈がスマホでメモを取りながら答えた。また、しばらく歩くと今度は変な銅像が出てきた。ウサギだろうか。何だかすごく不細工な顔をしている。
「こ、これは何ですか。」
剣崎が少し笑いながら質問した。すると笛吹さんが笑いながあら答えた。
「これは、ウサギだな。俺も何でこんなもんがあるかなんて知らないな。まあ、愛嬌があるし面白がっている。」
「確かに愛嬌はありますね。さっきの建物より危険はなさそうですし、大丈夫そうですね。」
そうこうしていると一周し終えた。
「今日はありがとうございました。また準備の時はよろしくおねがいします。」
「こちらこそ、よろしく。」
こうして僕らは、秋山溪谷を後にした。
「山道は流石にしんどいね~。夕方過ぎまでかかると思っていたけど、案外早く終わったし、ファミレスでも寄ってお昼ご飯でも食べようか。」
先輩は、意気揚々と提案した。僕らもそれに同意し、八王子付近のファミレスに寄ることになった。帰りの車の中では流石に黒奈は菓子パンを食べてはいなかった。僕は菓子パンを食べないのかと聞こうと思ったが、黒奈に殴られるのではないかと思い、言葉をお腹の中に追いやった。しかし、僕の安堵を剣崎がすぐに焦りに変えた。
「何だ、黒奈は菓子パン食べないのか。」
黒奈の厳しい視線が剣崎にぶつかる。まるで、スーパー黒奈になったかのような気の高まりだった。剣崎もこの気にやられてそれ以上口を開かなかった。隣の僕の気持ちにもなってくれ。と僕は思いながらファミレスへ早く到着してくれと祈った。先輩は、相変わらず愉快愉快と笑ながら運転をしていた。ジェットコースターの頂上を待つような不安に駆られながら、ファミレスに到着した。
「いらっしゃいませ。何名様でしょうか。」
店員さんの歯切れの良い挨拶が店内に響き渡った。「4名です。」と答え、席についた。先ほどまでずっと肩に力が入っていたので、やっと気が安まるとゆっくりと伸びをした。
「何食べる。今日は先輩が奢っちゃうから何でも好きなの頼んで。ちなみに俺は、チキン南蛮定食かな。」
「俺は、ハンバーグとグリルチキンの定食で。セレンはどうする。」
「僕は、カレードリアで。黒奈はどうするの。」
「私は、明太子スパゲッティでいいかな。あと、ポテトとドリンクバーはみんなつけますか。」
「じゃあ頼みますか。すみませんー。」
店員さんを呼び、それぞれの注文を行った。ドリンクバーで各々飲み物を注いでみんなが着席したところで、先輩が切り出した。
「正直、あれほどいい場所はないよな。」
「そうですね。あれだけ開けていて、かつ流れもそんな急でない。完璧に近いです。」
「完璧に近い?すこし気になるところでもあったの黒奈ちゃん。」
やや黒奈が真剣な顔を見せた。何だろう。やはりあの奇妙な建物が気になっているのだろうか。確かに、何か不気味な感じがしたが、そこまで危険というわけではなさそうだったが。僕は唾を飲んだ。そして、決まりが悪そうに黒奈な顔をして小さく呟いた。
「いや、あの意味わからないウサギが気に入らないのが一つですかね。」
「何だそんなことか。びっくりさせないでよ。」
「そうだぞ、黒奈。そんな真剣な顔したら、何かまずい事でもあったのかと思うじゃないか。」
「ごめんなさい。だって生理的に受け付けなくて。」
「でた。女子の生理的に受け付けない。これhぽど理不尽な言い訳はないぞ。」
「あら、剣崎君は女子に言われた事がお有りなようね。」
「う、うるさいな。別にいいだろ。」
「気になるねー。先輩も気になっちゃうな。」
剣崎はおどおどし始めた。僕に助けを求めて視線を送ってきた。
「剣崎、ここは正直に言ったほうがいいぞ。下手に詮索されると面倒だ。先輩はこういうことになるとスッポンにも負けないくらい食らいついてくるぞ。」
「セレンわかってるな。そういうことなんで、吐いちゃいなよ。」
剣崎は、渋々話し始めた。
「高校生の頃なんだけどな。好きな女の子が居たんだよ。その女の子に部活帰りに告白したんだ。」
「いいじゃん、いいじゃん。青春してるな。」
「揶揄うのはよして下さいよ。結局振られちゃったんですよ。剣崎君は生理的に受け付けてないって。何なんですか。生理的に受け付けないって。免罪符だと思ってるんですかね。」
「だってよ、黒奈ちゃん。なんか言ってやってよ。」
「仕方ないじゃない。生理的に受け付けないのは受け付けないんだから。」
「黒奈ちゃん厳しいな。」
「現実なんてそんなもんですよ。でも、あなたのこと見直したわ。ちゃんと自分の言葉で告白できる人なんてそういないわよ。きっとどこかであなたのことを生理的に受け付ける人もいるわよ。」
「黒奈。ありがとう。」
剣崎と黒奈が仲良くしているのは珍しい。僕は少し驚いた。
「ちなみに、私は生理的に受け付けないわけではないけど、そんなに好きじゃないから。」
「そこいらないだろ。」
「あなたみたいにデリカシーない人はあまり得意じゃないのよ。」
あ、また始まった。さっきの仲良しモードは一瞬しか続くことはなかった。
「ちなみにどんな子だったの。」
先輩が話題を変えようと剣崎に尋ねた。
「槍さんっていって珍しい苗字だったんだけど、背は低くてロングヘアの清楚で可愛らしい子だった。」
剣崎が思い出に浸っていたところに店員さんが料理を運んできた。
「お待たせしましっ・・・、もしかして剣崎君?」
「槍さん」
「えっどうしてここに。」
「それはこっちのセリフよ。」
僕らは混乱していた。先ほどまで話をしていた人物が目の前に立っているのだ。さらに、ピンク色の髪にピアスを開けている彼女を見ていると、剣崎の清楚という言葉からはかけ離れている容姿に何も出なかった。
「変わらないな、槍は。」
「いや、バチばちに変わっているでしょ。昔は、芋ジャージだったし、前髪ボサボサだったし、ピアスだって開けてないのよ。剣崎君とだって一度しか話したことがないじゃない。」
「いや、俺はいつも挨拶してたじゃん。」
「あれは隣の川山さんじゃなかったの。」
「河山じゃないよ。槍に言っていたんだよ。それに、俺はあんなに元気な女の子は好きじゃない。」
「ごめん、コミュ障過ぎて分からなかった。」
僕らは空いた口が塞がらなかった。剣崎のいう清楚とはよくある物静かな地味めな子らしい。しかし、まあこの変貌ぶりと言ったら驚かずにはいられない。そんなにコミュ障だった子が飲食店の店員ができるなんて意外だった。
「それはそうと、どうしてこんな風貌になったんだ。」
剣崎はこういう時にストレートに聞いてくれるから助かると内心思った。
「私、バンドを組んでいるのよ。それでイメージカラーってやつ。ピンクだからその色に合わせて染めているのよ。路上ライブとかライブハウスでライブをしているうちに、コミュ障が治っていったの。」
「すごいじゃないか。なんてバンドなんだ。」
「木工ボンドっていうの。」
僕は、きっとこの子はバンドとボンドを掛けているのだろうと思って少し失笑していた。だが剣崎は爆笑していた。
「木工ボンド。っていうバンドか。面白いな。さすが槍さんだよ。:
「そうかな。みんなには可笑しいいて言われているけど。」
「他人の事なんて気にするな。そういうエゴがなきゃゴールは生まれないんだ。」
「ありがとう。せ、せっかくなら私のライブ見に来ない?」
「本当か。是非行くよ。」
「じゃあチケットこれね。皆さんも是非きて下さい。」
そう言って彼女は厨房に戻っていった。剣崎は、とても嬉しそうだった。
「よかったな剣崎。」
僕が剣崎をこずく。剣崎もまんざらじゃなさそうだった。
「生理的に苦手な人にチケットは渡さないわよね。」
と黒奈がニヤニヤしながら剣崎を見た。
「確かに。これはチャンスじゃないか。」
先輩が続けてニヤついた。
「そ、そんなんんじゃないですよ。もう。セレンからも言ってくれよ。」
「いや、これはワンチャンあるな。」
そう言って僕も続けてニヤついた。
本に栞をはささみ、僕は本を閉じた。学生を謳歌する若者たちの眩しい文章に少し胸焼けがしていた。朝に本を読む習慣を付けてから二週間がたった。代わり映えのしない日常が今日も続いていた。そろそろ出社しなくてはと思い、思い腰をあげ会社へと足を伸ばした。
「おはようございます。」
職場に僕の声が響く。「おはようございます。」という声がまばらに返ってくる。出社してからパソコンを開きメールチェックを行う。特に目新しいメールは入っていないようだ。会社の社員用の掲示板にお知らせが一通きていた。
『水卜さんの退職のお知らせー』
僕は驚いた。水卜さんが退職するなんて。水卜さんは僕が入社した頃から気にかけてくれる優しい先輩で、仕事で分からないことがあると相談に乗ってくれる優しい先輩だった。最近でも、他の先輩社員Kともめもごとがあった。
あるプロジェクトに対し、グダグダ上司の文句を言っているばかりで会議が全く進まない不毛なものだった。僕はそんなただ時間ばかりを消費する会議が嫌いだった。そこでKに対して、
「まあ感情論は置いておいて、会議を先に進めましょうか。」
と切り出した。すると、目を見開いたKが僕を見つめる。
「感情論の何が悪いの?大事なことじゃない。」
すごい剣幕で反論してきた。僕は、虎の尾を踏んでしまったらしい。全く災難だった。その後もKの不満は尽きる事なく、大して価値のない会議が2時間も繰り広げられた。僕は、しょんぼりしながらデスクで事務作業を行なっていた。後ろから先輩が声をかけて来た。
「ちょっとコーヒーでも飲まない。」
二つ返事で答えた僕は、先輩と自販機のあるスペースに移動した。
「どうしたの、浮かない顔して。落ち込んで。」
自販機でブラックコーヒーを押した先輩は僕に尋ねてきた。
「実は、かくかくしかしかで。正直、やってらんないですよ。K先輩とは。感情論ばかりで結局時間の無駄使いもいいとこですよ。この間にも沢山の仕事ができたのに。」
僕は、水卜先輩に愚痴をこぼした。
「そうか。また、K先輩らしいというか。まあさ、君の言う事はごもっともな事なんだよ。ただ、人間不完全なもんだから愚痴もこぼしたくなるもんだよ。」
缶コーヒーを先輩から渡された。僕は缶コーヒーを開けながぼやいた。
「そうですけど。K先輩は愚痴をこぼしすぎなんですよ。蛇口開けっ放しなのかってくらい。」
水卜先輩がコーヒーを一口飲んで軽く笑った。
「はっはっは。仕事と感情を切り離すのが理想だが、情熱的である必要もあるんだよ。君だって、ある種の想い、感情があるからこそうちの会社の志望動機が書けて、こうやって仕事してるでしょ。そういうもんなんだよ。あと、K先輩は今週は生理だな。あ、これ本人には内緒ね。」
先輩はこう言って僕を宥めてくれた。最後につけるブラックジョークに僕も笑わされた。そんな優しかった先輩が会社を辞めてしまうなんて・・・。
「おはようございます。」
感傷的になっていると、水卜先輩が出社してきた。僕はいても立っても入れずに水卜さんに少し話があるのでお昼二人で食べませんかと誘った。水卜先輩は、優しくいいよと言ってくれた。それを聞き、僕は午前中ずっとお昼のことを考えていた。なかなか集中ができず、Kに小言を一言二言、いや三言くらいは言われたような気がする。まあいい。そう思いながら残りの仕事を片付け、僕は水卜先輩と一緒に会社を出て昼食を食べに行った。季節は冬真っ只中。北風が肌を撫でる。春の風を待ちわびるように僕はマフラーに身を包んだ。
「ふー、寒いな。ラーメンでも食べるか。君、嫌いじゃなかったよね。」
「大丈夫です。むしろ好きですね。でも、ラーメン食べるの久しぶりですかね。」
「そうなの。なんで。」
「いや、最近あまり外食してなくて。友達とかも最近は結婚してきて、家族で過ごすことが多くなって来ているんんですよ。」
「あね。わかるわそれ、俺の周りもそうだもん。最近じゃ独身貴族歌ってるよ。」
そんな話をしていると、ラーメン屋に着いた。券売機で焼豚ラーメンを購入し、カウンター席に座った。僕が水を汲んでくると先輩がありがとうと言って水を一口呑んだ。
「先輩。早速なんですけど、いいですか。」
「いいよ。どうした。」
「いや、今日のメールを見て驚きました。先輩、会社辞められるんですね。」
先輩は暫く黙ってコップの水を見ていた。そして、水をもう二、三口呑んでから話し始めた。
「自分の可能性ってやつ。そいつを追って見たくなったんだ。このまま、我慢しながら大してやりたくもない仕事続けていくのかなって。」
「可能性・・・。」
「うん。やっぱり大学出てからさ、自分の将来について真剣に考える時間って増えない?YouTubeとかしてる人やW杯かで活躍する選手。売れないバンドマン。みんな夢や希望を持ってる。でも自分はどうだろうって。今の自分は何なんだろうって思ってさ。」
「確かに、僕も今なんのために生きているのかって言われると謎ですね。」
「そんな時にさ、ずっと真昼ならよかったのLIVEに行ったんだよ。そしたらさ感動しちゃったよね。アーティストの才能もさることながら音響の響きとそれによる観客の熱狂。一体感によるボルテージの上昇。それでそんなLIVEを自分も作ってみたいって思って。音響系の仕事に転職しようと思ったんだよね。」
「いいですね。それ。何か一つのものを作り上げる感覚ってとてもいいですよね。」
「でしょ。」
「へいおまち。」
注文したラーメンが運ばれてきた。美味しそうだ。
「まあラーメン伸びる前に食べようか。」
「そうですね。いただきます。」
僕ら熱々のラーメンをほうほうしながら食べた。熱いけど美味しい。ラーメンを食べるとなくなる。時間が過ぎていく。永遠なんてものはこの世にないのだと訴えるかのようなものはたくさんある。先輩との別れ、残り数週間の期間で終わってしまう。こんな毎日が毎日続くのだろうと思っていた最中だったのに。
『ぐらついている。僕の心が。ぐらついている。僕の人生が。』
僕は小さく呟いた。ラーメンを食べ終えた後のスープの残りが闇のように黒く感じた。闇の奥は何か深くてぐらついていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
