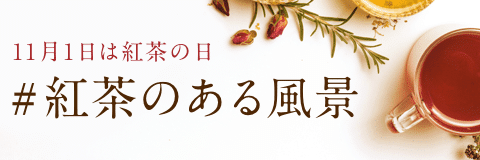紅茶のお話 「正山小種とラプサンスーチョン」
紅茶に関する記事を書こうと思い立った時、何をテーマにしようか…と考えていました。
ふと、以前のコーヒーの記事で、高級豆として「ブルーマウンテン」について触れたことがあったのですが、同じように紅茶の「正山小種(ラプサンスーチョン)」

についてちょっと書いてみようかな…と思い立ちました。
「正山小種(ラプサンスーチョン)」とは
正山小種(ラプサン・スーチョン)、烟茶(エンチャ)は、紅茶の一種である。
紅茶の茶葉を松葉で燻して着香したフレーバーティーの一種で、癖のある非常に強い燻香が特徴である。
生産地は中国福建省武夷山市周辺の一部。正山は、現地で武夷山を指す俗称。
現地では、半発酵茶の岩茶類と区別すればよいので、単に紅茶とも呼んでいる。
なお、小種 (Xiao-zhong,Souchong) とは岩茶の原料ともなる茶樹の種類のことであるが、紅茶の等級の一種であるスーチョンの語源にもなっている。
これはWikipediaにある正山小種(ラプサンスーチョン)に関する説明です。
これ見る限り、正山小種のまたの名をラスサンプーチョンと言う、というニュアンスですね。
ところで、巷で売られているラプサンスーチョン、価格はどれくらいかというと、普通の紅茶よりはややお高め(100gで1000円くらいのお店が多いですね)。
ただ、その由来を聞くともっと高そうなイメージが…。
中国における「紅茶」の誕生
中国における発酵茶には、大別して
白茶・黄茶・青茶・紅茶・黒茶
があります。
色が濃くなるにしたがって発酵度合いが上がります。
この中で紅茶は、発酵度およそ8~10割の完全発酵茶に属します。
ちなみに、日本でなじみ深い烏龍茶は青茶の一種です。
烏龍茶は、何となくイメージとして中国ではメジャーでとても歴史があるお茶…という気がしますが、実はそうでもないようです。
烏龍茶の生産が行われるようになったのは、17世紀~18世紀ごろにのお話。
発酵茶は1700年代に入ってから輸出向けに生産が拡大していったというのが実際のところで、現在でも中国では緑茶(無発酵茶)が茶の主流です。
では、紅茶はどこで生まれたのかというと、烏龍茶の故郷に近い福建省武夷山、その山中にある「桐木村」という場所とされています。
ここで17世紀の前半に作られ始めた紅茶(完全発酵茶)が「正山小種」です。
正山小種の「正山」は武夷山のこと、小種は「少量」という意味です。
なぜ量が少ないかというと、お茶の木は栽培されているものではなく、岩山に自生しているもの。
つまり、正山小種は
武夷山で、自生種の茶の木から採取した茶葉で作られた発酵茶
ということになります。
これでだけでも大量生産は無理な気がしますし、今の正山小種とは違うような…??
そんな疑念はさておき、ひとまず歴史を追ってみます。
桐木村は岩山に囲まれた場所にあり、十分な農地が確保できなかったことから、岩山に自生している茶の木から茶葉を摘むことで生計を立てていました。
しかし岩山を移動しながら茶葉を採取しているうちに、籠の中の茶葉はこすれて葉汁がにじみ、少しずつ発酵が始まってしまいます。
そのため、純粋な緑茶を作ることはできず、かと言って烏龍茶のような高度で複雑な作業工程を踏んでいるわけでもない桐木村の茶は、他の地域とは異なる独特の風味を持つようになりました。
まず、発酵の始まった茶葉をさらに揉んだため、茶葉は完全発酵して紅茶になりました。
さらに、「竜眼」

のような独特の香りがしました。これは、この地域の気候や土壌が影響したとも言われています。
さらに、乾燥工程で、乾燥が十分ではない松の木の薪を使ったため、煙が流れ込み、松脂のほのかな香りがつきました。
この3点が相まって、正山小種は独特の風味を持つに至ったのです。
正山小種からラプサンスーチョンへ
正山小種は、17世紀末ごろから中国に進出を強めていたイギリス人商人の手に渡ります。
ヨーロッパには中国や日本産の緑茶が輸出されていましたが、18世紀ごろになると紅茶の需要が高まります。
その理由はやはり「味」。
イギリスの水は、石灰岩質の土壌の影響でミネラル分が多い硬水になります。
(これはフランスなど南欧にもよく見られます)
硬水で緑茶を淹れるとどうなるかというと、
色は濃く出る
味はぼやける
という現象が起きます。
味がぼやけるというのは、硬水に含まれるカルシウム分がタンニン(渋みのもと)の抽出を妨げるからですね。
緑茶を硬水で淹れると、何とも締まりのない味になってしまいます。
逆に紅茶の場合、茶葉に含まれるタンニンが多いため、硬水でも味がぼやけにくいのです。
ヨーロッパで紅茶が流行ったのはそのような理由からです。
さらに言えば、色が濃く出るためコーヒーを連想させたこと、さらにコーヒーと同じく、ミルクを入れた時に色味が綺麗に出るのも好まれた理由でした。
当初、中国との茶貿易では緑茶の輸入が主でしたが、18世紀半ばには紅茶の方が上回るようになります。
当初、多く輸出されていた紅茶は「ボーヒー」や「ボヘア」と呼ばれていました。
両者は「武夷」の英語読みで、当時から発酵茶の聖地として武夷山が認知されていたことがわかります。
正確には、ボーヒーは紅茶、ボヘアはもう少し発酵度の低い烏龍茶に近いものを指したようです。
当時のヨーロッパの人々にとって「武夷山」

はその名前だけで憧れのブランドでした。
そして、その中でも繊細な香りの「正山小種紅茶」は、最高級ブランドとして崇められるようになります。
ところが、需要が高まるにつれ、イギリス商人はこんなことをしたと言われています。
・武夷山以外の茶葉を、「ボーヒー」や「ボヘア」として輸出
つまり産地偽装ですね。
・一層刺激的な香りを要求
他のお茶との差別化を極端化しようとしたようです。
そしてこの一層刺激的な香り…というのが、「松脂の燻煙臭」だったのです。
時は清朝末期。
世相が暗い中、中国の製茶業者たちはイギリス商人の要求に従い、
火入れをした茶葉を再度湿らせ、松脂の燻煙臭をつける
という、本来の茶の製造工程ではありえないものを作り始めます。
それが「ラスサンプーチョン」の始まりでした。
このラスサンプーチョンは大量にイギリスに輸出され、本来の「正山小種(チェンシャンシャオション)」は、「ラスサンプーチョン」という、正露丸のような強い香り(松脂の燻煙臭)がする茶に取って代わられてしまいました。
つまり、本来「正山小種」と「ラスサンプーチョン」は別物…と考えるのが妥当なようです。
言い方は悪いですが、「ブランドの乗っ取り」かな?と思います。
実際のところ、中国でもラスサンプーチョンは輸出用で、国内消費はほとんどないと言います。
一方、今でもイギリスでは、高級品として格式高い茶会で供されるなど、高級紅茶の代名詞のような存在です。
…何やら、18世紀ごろの商業主義、大量消費社会黎明期の闇を見てしまったような気もしますが…。
最近のラスサンプーチョンについては、燻煙を程よくするなど、以前に比べてかなり工程を工夫したものも見られます。
日本に輸入されているものはそういった工夫がされたものが多く、淹れても18世紀ごろのような強烈な香りにはならないようです。
18世紀ごろは、闇のピークだった…ということですね。
実は、あ、なるほど…と思ったのはこの辺りです。
コーヒーの「ブルーマウンテン」も、かつてかなり怪しげな豆が出回ったことがあります。
本来、ブルーマウンテンを名乗ることができる豆は厳密に定義されているのですが、その周辺地域の豆が「ブルーマウンテン(の方から来ました)」という形で出回ってしまったのです。
現在はだいぶ改善されたものの、正規輸入量より流通量が多いという妙な状況は続いているのですが…。
なるほど、ラスサンプーチョンも、一時はブルーマウンテンと同じような歴史を歩んでしまったのか…と思いました。
知名度が上がったり、生産量が増えるのは悪いことではありませんが、いつの時代でもその「ひずみ」が発生することはあるのだな、と感じます。
ちなみに、ラスサンプーチョンは風味がかなり香ばしく、濃厚なので、濃厚な味のスィーツ(ガトーショコラなどがおすすめかも)がよく合います。
深煎りのコーヒーに合うスィーツを参考に選んでいただくと間違いないですね。
試しに、竜眼の香りがする古代製法の正山小種は売っていないのかな??とリサーチしてみたのですが、国内ではなかなか難しそうです。
もし、見つけたらトークやTwitterなどで報告したいと思っています。
今回はここまで、ということで…。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
この記事が受賞したコンテスト
サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。