
「ドライブスルーのお葬式」(後編)
【つづき】お年寄りや車イスのひと向けに、クルマに乗ったままお焼香ができる方式を実施した、長野県上田市の葬儀会館を運営する荻原社長さんを取材しました。
「じつは、見てほしいものがあるんです」
と案内された大理石の「喫煙室」。
豪華な部屋だった。てっきりご自身が愛煙家なのだとばかり思ったら、
「私はタバコは吸わないんです」というご返事。「でも、せっかく来られたひとたちがみなさん申し訳そうに吸われているのを見ると気の毒で」。
喜んでもらいたい一心で、ついお金をかけてしまったとか。
瞑想室のようにも見えなくもない。もともとは建築の仕事を志したというだけのことはある。面白いひとだ。
「見てほしいのはここだけじゃない、まだあるんです」
ホールの奥へ奥へと案内された先に待ち受けていたのは……。

「これからの葬儀はこういうものにしたい」
聞き手・写真撮影=朝山実
長い廊下の先にあったのは、ホテルのスイートルームのような空間。入ってすぐのところに祭壇と椅子が配置されていなければ、葬儀施設と思わないだろう。奥の空間には、20人くらいが着席できるテーブルがある。
「昔のように、たとえば、おじちゃんが亡くなったら、一晩家族が集まり、ゆったり『あのとき、ああだったねえ』と想い出を語りながら食事をしながらすごす。そういう場所として使ってもらえたらと思ってつくったんですよ」
でも、と荻原さんはすこし声を落とす。
「取材に来られる人はみなさん、"ドライブスルー"にばかり目がいかれるようで、興味をもってもらえませんでした」
わたしが訪れたのは、そうした空振りの連続のあとだったようだ。
この部屋を目にして、ソワソワするというか親近感がわいた。それは、わたしの父が遺した家の気配に似通ったものを感じたからだった。

葬儀のホールといえば、コンクリート建築などの目立たないものが多い。近隣への配慮もあるのだろう。私事ながら、葬儀ホールとして賃貸している父の遺した家は、外観も室内も神戸の震災後に建てられた当時の「民家」のまま。一日一件、家族で宿泊もできるお葬式の場所として貸し出している。
事前相談の見学に来られ、「なんだ、民家じゃないか」といわれるひともいるが、ご利用いただけたひとたちからは、「田舎のおばあちゃんの家のようでおちつく」といってもらえにようになってきている。とはいえ、利用頻度は多いとはいえず、「空き家活用」の選択として正解だったのかどうか迷いもあり、だからこそ、この部屋を見て「おお!!」と思った。

「これからは少子化で、団塊の世代が亡くなっていく。『家族葬の時代』なんだと言われていますが、私の考えは、ただ人数を絞ったものにするのではない。親族が集まれる機会がなくなった中で、ひさしぶりにあった家族、兄弟が一晩をすごす。
料理も、『今晩は親父が好きだったすき焼きにしようか』ということなら、むこうに専用の厨房を設けてあるので、ご要望にそって何でも出せます。ホテルや旅館に泊まったようにして過ごしてもらえる施設として利用してもらおう。ここは、そういうコンセプトなんですよね」
厨房は広く、食事をとるためのテーブルは「最後の晩餐」仕様に思えた。
「これは人数によって、テーブルが伸ばせます。色もね、葬儀だからと暗いものにせず、あえて明るい色を選んだんです。お葬式なんだけど、楽しい思い出に耽ってもらいたい」
空間全体の印象が葬儀っぽくない。荻原さんの職歴と関係しているらしい。
「サービス業にずっと関わってきましたから。これからの葬儀で、どういう一晩を求められているんだろう。考えた結果がこれなんです。
一晩のことだから、ふだんは発泡酒だけど、今夜はおいしいお酒にしようとか。そういうのも供養だと思うんです。だから料理を盛る器もちゃんとしたものにし、おいしいものを出したい。調度品もね、白で統一したんです。
最初、建築屋さんが安普請のものをもってきたんだけど、葬儀場だというのでね、すぐにやり直させました。
ここを見ていただけますか、壁の色目も空間ごとにすこし変えてあるんですよ」
祭壇のある空間と、食卓の置かれた部屋との間仕切りの壁に近寄ってみる。広々としている印象を与えるために、あえてオープンにしてあるのだが、境界となる壁の柄が微妙に違っていた。
弔いの空間と、語らいの場。むこうと、こちらとで微妙に色合いがちがっている。種明かしをされてはじめて気づいたことだが、ちょっとした、わくわく感がある。


「家族葬」としての利用する場合に合わせて、専用の出入り口も設けられている。ドアを開けると、外の駐車場に向けて車椅子が使える長いスロープがついていた。
さらに右手の扉の向こうには、ベッドが6つ。さらに奥に進むと、浴室とトイレ。ホテル仕様で、いずれも身障者用の手すりがつけられている。
「一般葬の時の控え室や、通夜の部屋として使用してもらう以外にも、家族葬としての利用を考えています」
たとえば「家族葬」として20人利用の場合、食事などを含め、約80万円の概算だ。ちなみにドライブスルーのある「一般葬」が150万円くらい。祭壇の花や参列者の規模によって価格は変わるが、100万円以下に抑えることも可能だという。
長野県上田市の近隣では、まだまだ「一般葬」がほとんどで、「家族葬」の需要は限られている。近隣の人たちが大勢参列するお葬式が「常識」として根強いからだろう。
平均的なお葬式の規模を訊ねてみると、
「どれくらいを“小さい”というのかにもよりますが、この辺では50人から100人くらいの会葬者が一般的で、200人、300人となると大きな葬儀になりますね。
なかには20人、30人規模のお葬儀もあります。ただ、このあたりで『家族葬』をしようとすると、『なんだよ、親しくしていたのに、俺は行ったらいけないのか』と近隣との仲をこじらせることになりかねない。
東京や大阪の人が、親戚に『もう遠いから、葬儀は身内だけでやるよ』といわれるのとはちがうんです。家族葬にするのには、逆にあちらこちらに、こういう事情でと連絡しないといけなくなるから大変なんです」
都会のマンション暮らしでは、引越しの挨拶がないこともめずらしくはない。近隣の家のひとがなくなったのを、何ヶ月もしてから知るということあった。周辺とのつきあいが「疎遠」であることが前提の社会だからこそ、「直葬」「火葬式」が増加しているのだろう。
「お坊さんが立ち会わない直葬ですか? ないことはないですが、数は極端にすくない。このへんはまだ田舎だから」

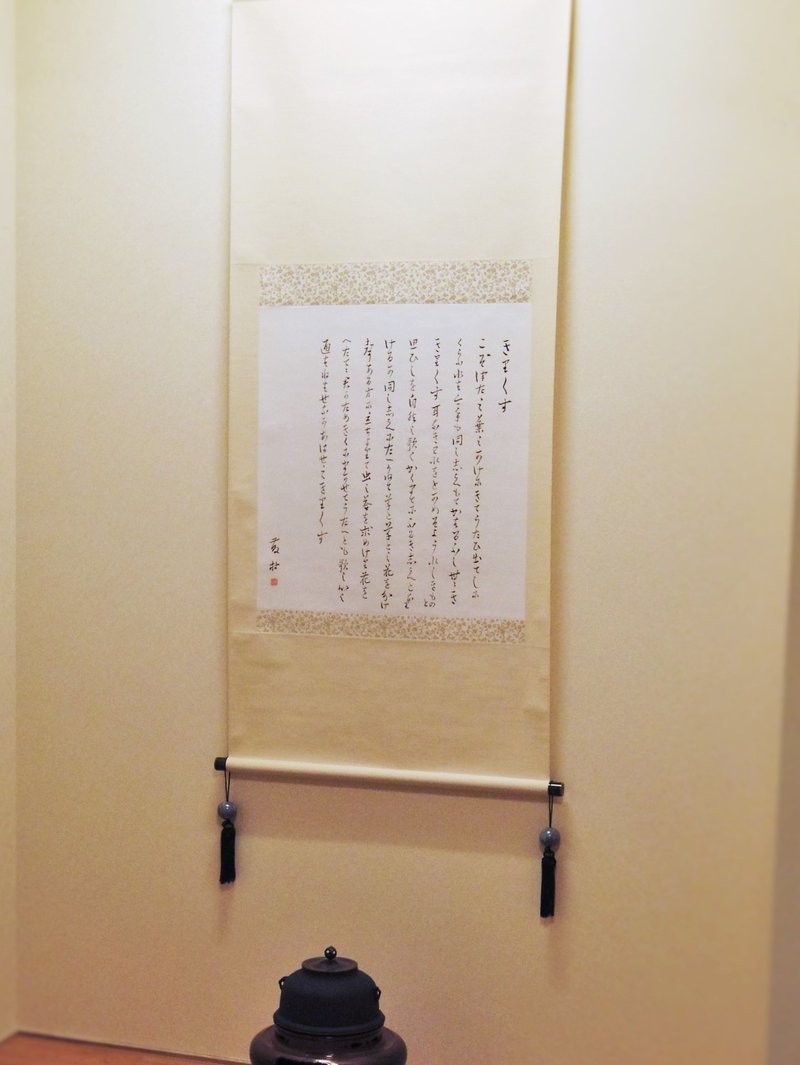
「うちはね、百まで働いてくださいといっています。このあいだ82歳の人が退職されたから、最年長はいま81歳です」
冠婚葬祭の「株式会社レクスト・アイ」の代表取締役社長の荻原政雄は、昭和25年(1950年)生まれの、67歳。会社を支えるのは自身よりも年上の、ベテランの「おばちゃんたち」だという。
「もちろん会社には定年に関する規約はありますが、元気で働けるうちは何歳でも働いてほしい。というのもベテランの人には、お客さんがついているんですよね。一人につき、千人以上は」
会社は互助会システムを基盤にしている。毎月の掛け金3000円×80回払い。トータル24万円の積み立て方式。
ベテランの「担当さん」は集金人ではなく、新規の勧誘と会員維持の戦力。10人のおばちゃんたちは、各自一軒一軒回り、ときに身の上相談に乗り、茶飲み話を交わす。そして葬儀のときには、おばちゃんが「担当」となる。
「扱いは嘱託ですけど。ほぼ毎日、常勤社員のようにしてきています。保険のおばちゃんみたいなものですね。
本人たちも、会社が必要にしてくれているというのがやりがいだし。会員さんも、他社で感じのいい営業さんがいたら、そっちに乗り換えるというのはよくあることですから」
今年の1月14日、ひとりのおばちゃんが亡くなった。
抗がん剤治療で休みをとることはあったが、復帰するとお客さんのところに通う、仕事熱心な人だったという。
「本人は最後まで働きたい。在籍のまま死にたいと言っていたんですよ。葬儀のことは自分でこまかく決めて、お別れの会は高砂殿(現在はザ・グランドティラと改称)でやってほしいと書いてあった。うちで、いちばん大きなホールです。
旦那さんもね、本人が望むようにしてもらいたいということで、告別式は密葬で、ご親族でされ来月、お別れ会をします。先になったのは、高砂殿は結婚式場なので、空いている日がなくて。
年齢は、私より一つか二つ年上。年齢も近いから、私もショックでしたが、葬儀はただ暗くて悲しいものじゃない。そこまで懸命に生きたんだから、哀しいんだけど、なんていうのかなぁ、気持ちよく送ってあげたい。だから、いま彼女のプロフィールビデオをつくって、3月11日のお別れ会のときに流そうと思っている」

荻原さんに、お葬式をする意味を訊ねると、
「残されたものが、最後のお別れする日だと思う。何もしないでいると落ち着かない。供養をすることで、気持ちがやわらぐ。人間、そういうものじゃないですか」
何もしないと落ち着かないというのは、たしかにそうだなと思った。いっぽうで、「直葬」「火葬式」など、都会ではお坊さんの立ち会わない簡略化された葬儀が増えている。
家族のいない身の取材者のわたしは、「自分の葬式は要らない」と考えたりするのだが、あとに残される家族がいないためでもある。面倒をかけない範囲で、友人に「死んだあとのことは、あなたにおまかせします」でもいいのだが。荻原さんの答えを耳にしながら、死者を弔うのは、残されたもの気持ちの問題なのだとあらためて思いもした。
「うちの互助会の会員さんたちでバス旅行するというのをやっていたんです。3千円で、お寺をめぐって食事して日帰りする。あるお家を訪ねたら、娘さんと家族三人、食事が喉を通らないといって泣いている。『どうしたんですか?』と訊いたら、飼っていた犬が亡くなったというんですよね。
見たら、薬の袋に犬の名前が書いてある。とてもじゃないけれど旅行なんか行く気分じゃない、と言われる。私も、それはそうだなと思いました」
バス旅行と犬が亡くなった話。荻原さんの話の着地点は、どこだろう。口をはさまず、うかがっていた。
「では、その人たちがどうやって立ち直っていくのか。線香をあげたりして、人が亡くなったのと同じようにするんですよね。何らかのかたちで、悲しみを、どうにかしないといけないんですよ。
たとえば息子さんが『親父の葬式は要らない』と言われる。それも、いいと思います。いいというのは、そのお父さんが息子さんに見せてきた生き方が影響しているんだと思うんです。
七五三のときに父親とあの神社に行ったなぁ。そういう記憶があると、行事ごとをなぞるのは当たり前というか。でも、そういうことを省略してきて、たとえば結婚式もやらなかった人は、お葬式もやらないんじゃないかという気はするんですよ」
そうかもしれない。結婚式もお葬式も「しない」あるいは「簡略でいい」というのは、ライフスタイルの根本にかかわることでもある。いわゆる「世間」的な交流をすくなくしたいという表明でもある。
荻原さんは、言葉を慎重に選びながら「いい、悪いじゃなくて」という。わたしよりも6歳上で、団塊の世代に近いひとだ。
工業高校の建築科を卒業し、東京の建築関係の会社に就職はしたものの「図面を描くことより、営業のやりとりが面白そうに思えた」と流通や販売の会社で勤め、互助会をベースにした冠婚葬祭会社に入社して25年になる。
「私は、お寺さんの先生に小学校の4年、5年のときに教わったんですが、法善寺の清水要秀先生にね。教わったんですよ。
1月の学校が休みのときに、学級の子供たちで行くとね、お煎餅をもらったり、ミカンを境内で食べたり、みんなで遊び、混ぜご飯をご馳走になったりする。そういうことをしていると檀家との結びつきは自然と強くなりますよ。
お葬式は要らないという考えが出てくる背景には、そういう経験をまったくしてこなかったというのもあるんじゃないでしょうか。
一月に先ほどお話したトキコさんが亡くなってから、会社に行くと欠かさず彼女の机のところに花が飾ってあるんですよ。お別れ会をするまでは、みんなも気持ちの区切りがつかないのかもしれない。
それは社員が自然と始めたことなんですよね。そうするものだというのではなくてね、私は、そういうのも含めても、何事も経験値からくるものだと思うんです」
トキコ(登紀子)さん、と呼びかけるときの声に親しみがこもっていた。
「葬儀は要らない。そういう人の判断は、いろんなものを経験してきた上での結論なのか。私には、どうもそうは思えない。だって、いっぽうでは、犬のお葬式をしようというのに、人間のほうは要らないなんて。それは、どうなんでしょう。
大事な人が亡くなって、出来ることは供養しかない。人間として、お葬式をするというのは普通だと思います。何も自分がこの仕事をしているから言うんじゃなく。私も、先日友人がなくなり、トキちゃんが亡くなり、悲しいんだけど、泣いてもいられないので、会社に来たらまず線香をあげています。それで自分の心がなぐさめられるんです」
施設をぐるりと見せてもらったなかで、豪華だったのは喫煙ルーム。床には大理石が使われていた。「私は煙草は吸わない。でも、こそこそと吸われているのを見るのはいやじゃないですか」。たったひとりだと、瞑想室にもなりそうな空間だ。

「上の人に恵まれた」からやってこれたと荻原さんはいう。会社を替わるたび慣れない仕事を覚えてきた。苦労はしたが、幸福な時間でもあったという。
最後に、ひとつ質問をした。
荻原さんは、葬儀の仕事をされることに迷いはなかったのか。
「入社したときは結婚式のほうをやっていたんです。だから葬儀と結婚式では、働く時間がまったく違う。葬儀は365日、休みなしですが、結婚式は予約があって、半年、一年前から日が決まっている。だけど、お葬儀は、電話が来ればすぐに駆けつけないといけない。
もうひとつ違いがあって、施主さんから喜ばれるんです。
こちらの対応如何で、かなしみの中で憔悴しきっているときに『癒してもらえた』と言ってもらえる。
それに葬儀の準備は、短時間でやらないといけない。夜中の3時に呼ばれ、一時間くらいで仕上げる。朝の7時にまた行って、通夜のダンドリをする。すべてやり終えたところで、『助かったよ』と言ってもらえる。その一言のためにやっているようなものですよね。
うちを一度やめてね、新聞配達の仕事をしていて、入りなおした男が言うんですよ。『オイ、新聞屋』としか言われなかったのに、この仕事は『ありがとう』と言ってもらえるって。
だから、わたしはこの仕事は公共事業のひとつだと思っています。
昔は、特殊な仕事だと見られ、職業差別を受けるようなところはあったと思います。でも、『おくりびと』という映画は観られましたか?
亡くなられた人の身体をきれにして棺におさめる、納棺師の仕事を扱った映画ですけど。観られた若い人たちから、自分もしたいというのが増えたんですよね。『お父さんの葬儀を見て、こういう仕事に就きたいと思った』という人もいます」
変化の背景には映画の影響だけでなく、JA(農協)が葬儀に新規歳入したことが大きいという。
「昔は、そんな縁起でもないものをと思われていたものが、テレビで誰がどういう病気で亡くなったのか。いまは詳しく知らされる。そうなってくると、看取りをする人に対する差別的な感覚もなくなってきたということでしょうね。
私が入社した頃は、たしかに死体を扱う仕事だというので、タブーみたいな意識はありましたよ。でも、映画で紹介されたりして、一般の人たちの考え方が変わってきたんだと思います。その一方で、いろんな壁がなくなって、『葬儀は要らない』という考えの人も出てきたんだと思いますね」

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
