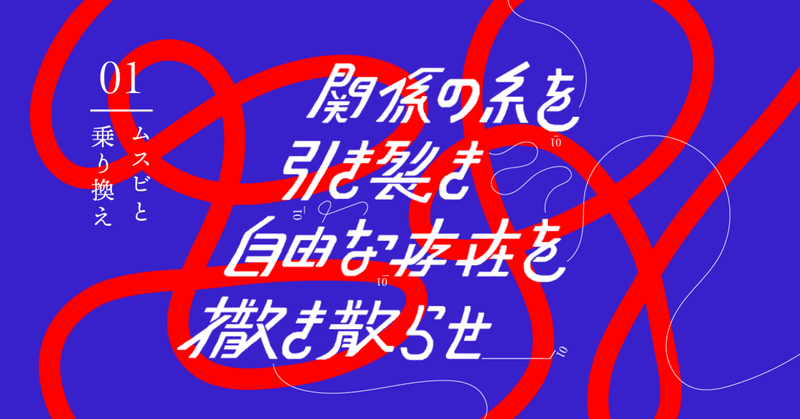
関係の糸を引き裂き、自由な存在を撒き散らせ─01 ムスビと乗り換え
わたしたちは、自立した徹底的な個としての存在なのか。あるいは、他のものたちとのきずななしには存在しえない、どこまでも関係的な生き物なのだろうか。
本連載は、関係と無関係の思想をめぐって展開される。まずは議論の導入として、男女の関係を足がかりにする。連載の最後では、議論を一気に一般化し、この宇宙に散らばるあらゆるタイプの存在どうしの関係について論じることになる。
一方には〈存在はたがいに依存し緊密に関係しあっている〉という思想があり、他方には〈存在はたがいに独立し無関係である〉という思想がある。本連載の積極的な主張は後者にもとづく。
関係の糸を引き裂き、自由な存在を撒き散らすこと。それが本連載の目的だ。
1 『君の名は。』における「ムスビ」概念
ふたつのアニメーション作品を対比することから出発しよう。ひとつ目は、新海誠監督『君の名は。』だ。
物語の主人公は、東京に暮らす男子高校生・立花瀧と、地方の糸守町に住む女子高生・宮水三葉である。ある日ふたりは、たがいの身体に入れ替わってしまう。この入れ替わりはたびたび起こり、ふたりは周囲の証言から、これがたんなる夢ではなくじっさいに起こっていることだと気づく。その後ふたりは、入れ替わりのさいにメモを残してコミュニケーションを図り、しだいに打ち解けていくことになる。
ここで着目したいのは、物語の重要概念である「ムスビ」だ。三葉の祖母は、三葉(に入れ替わっている瀧)に対して「「ムスビ」って知っとるか?」と問いかけ、つぎのようにつづける。
土地の氏神様をな、古い言葉で産霊(むすび)って呼ぶんやさ。この言葉にはふかーい意味がある。糸をつなげることもムスビ。人をつなげることもムスビ。時間が流れることもムスビ。全部、神様の力や。わしらの作る組紐も、せやから神様の技。時間の流れそのものを表しとる。より集まって形を作り、ねじれて、からまって、時には戻って途切れ、またつながり、それがムスビ。それが時間。
三葉の家系は、代々、宮水神社の巫女をつとめてきた。上のセリフにあるように、この神社では、糸守町の工芸品である組紐をつくる。ムスビ、糸守、組紐。すべて、線のイメージである。入れ替わりを経験する三葉と瀧は、ムスビという線によってつながれている。
だが、ある日を境にして、入れ替わりは起こらなくなってしまう。その理由を探るため、瀧はかすかな記憶を頼りに、糸守町へと赴く。そこで瀧は、三葉をふくめた糸守町の人びとが、じつはすでに三年まえに、彗星の直撃によって死亡していたことを知る。ふたりの入れ替わりは、時間を超えて生じていたのだ。
瀧は、再度入れ替わりが起こることを願い、三年まえに奉納した三葉の口噛み酒を飲む。そして目が覚めると、三年まえに彗星が直撃した当日の三葉に入れ替わっていた。瀧は、三葉の祖母から、かつて自分も入れ替わりを経験したことがあると聞かされる。その話を聞いた瀧は、ふたりの入れ替わりは糸守の人びとを彗星の直撃から守るために起こった、という確信を抱くにいたる。
2 ムスビの線とセカイ系
瀧と三葉はムスビの線によってつながっている。しかも、このふたりの入れ替わりには、「世界を救うため」という大きな意味が存在する。新海誠の作品はしばしば「セカイ系」と称されるが、『君の名は。』もまたそうした作品であると言える。
セカイ系とは、東浩紀の定義にしたがえば、「主人公と恋愛相手の小さく感情的な人間関係(「きみとぼく」)を、社会や国家のような中間項の描写を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」といった大きな存在論的な問題に直結させる想像力」 を意味する。
瀧と三葉は、「世界の危機」を救うために出会った。糸守の町を守るために入れ替わった瀧と三葉。ふたりをつなぐムスビの線は、必然的な運命の糸である。
このムスビの強度は、物語の終盤にしかけられた忘却と喪失感という装置によって最高潮に達する。ふたりのはたらきによって、糸守の人びとは救われた。しかし、それぞれの身体にもどったふたりは、入れ替わりの記憶をなくし、たがいの名前も忘れてしまう。物語の終盤では、なにか大事なものを忘れているという喪失感を抱きながら、日々を送るふたりが描かれる。きみが不在であるからこそ、それへの希求は高まり、ムスビの強度は増していく。
これと類似の構造は、新海のべつの作品『秒速5センチメートル』にも見て取ることができる。同作でも序盤できみとぼくとの特別な関係が描かれたあとで、中盤以降では、きみの影にとらわれながら空虚な生を送りつづけるぼくが描かれる。
(ただし『秒速』が最後までストイックに喪失感に留まりつづけるのに対して、『君の名は。』は最後できみとぼくの再会を描き、救済をあたえている点が異なる)
3 きみとぼくの内的関係
これらの新海作品に見られるきみとぼくの関係は、哲学用語で言えば「内的関係」にあたる。内的関係とは、関係項にとって本質的・必然的であって、項から切り離すことのできない関係を意味する。きみとぼくをつなぐムスビの線は、ぼくという存在の本質を構成している。それゆえに、きみの不在は、意味が欠けた空虚な生をぼくにもたらすことになるのだ。
ところで筆者には、新海の作品に見られるこうしたエモーションに共感することはできない。ぼくに一挙に意味をあたえ、救済をもたらすことのできる関係など存在しない、と考えるからだ。ムスビの線をぶったぎり、自由に生きればいい。そのように思う。
そもそも、喪失感をもたらす忘却は、ほんとうの忘却ではない。きみを忘却しているということ自体は忘却されていないからこそ、喪失感を抱くことが可能になる。そこにはほんとうの忘却が欠けているのだ。
きみのことを端的に忘却すればいい。ぼくはぼくであり、きみはきみで、世界は世界だ。それぞれがたがいに別個の独立した実在性をもつ。そうしたものたちが、たまたま出会っているにすぎない。だから、いつだって自由に別れ、べつの新たなきみと自由につながることができる。こうしたドライな間柄にこそ、むしろ深いつながりが見いだせるのではないか。そんな予感がある。
4 〈物語〉シリーズにおける「乗り換え」概念
ふたつ目のアニメーション作品へ移ろう。新海の作品に見られる関係性とは対照的なあり方を描いたものとして、西尾維新原作の〈物語〉シリーズを挙げることができる。男子高校生・阿良々木暦と、「怪異」にかんする問題を抱えた少女たちとの物語だ。
阿良々木暦が、恋人の戦場ヶ原ひたぎに電話をかけるシーンがある。その会話のなかで阿良々木は、「僕よりも条件の良い奴がお前に告白してきたら、そのときどうする?」と聞く。それに対して戦場ヶ原は、「そのときは100%乗り換えると思う」と即答する。そして、「絆に絶対なんてないことを私は知っている」と語りだす。
乗り換え可能な関係。それは「外的関係」である。外的関係とは、関係項にとって偶然的であり、項から切り離すことが可能な関係を意味する。それは、絶対的な絆ではない関係だ。阿良々木と戦場ヶ原とのあいだには、そうした関係がある。権利上、つねに乗り換え可能な関係。むしろそれゆえに、ふたりはこの関係性を大事にしているかのように見える。
ところで〈物語〉シリーズのうちには、多くの外的関係が散りばめられている。たとえば、怪異の専門家でアロハシャツを着た中年男性・忍野メメは、「人は一人で勝手に助かるだけ」が口癖だ。怪異のトラブルを抱え、助けを求めにきた戦場ヶ原に対して、「助ける?そりゃ無理だ。きみが勝手に一人で助かるだけだよ、お嬢ちゃん」と返答する。忍野と、彼に「助けられる」人たちとのあいだにあるのは、外的関係だ。
忍野は重要人物でありながら、〈物語〉シリーズの最初の作品である『化物語』以降では、ほとんど登場しなくなる。アニメの表舞台とは無関係な外部へと姿を消してしまうのだ。アニメ・シリーズそのものからの乗り換えをしているとも言える。とはいえ、『終物語』の重要なシーンでは、ふたたび阿良々木たちのところに戻ってくる。自由な乗り換えをこなすキャラクターだ。
〈物語〉シリーズは、ミクロな乗り換えがつぎつぎと生じることによって、全体のストーリーが進展していると言える。そもそも忍野に限らず、〈物語〉シリーズに登場するあらゆるキャラクターが自立的である。多くのキャラクターたちは、描かれないところでなにをしているのかわからない。彼らはみな、隠された部分をもつ。そうしたキャラクターたちがたまたま出くわし、会話をすることによって、物語が進展していく。
〈物語〉シリーズの進展を支えるのは、このような無数の遭遇、ミクロな乗り換えである。一本のムスビが強力な情緒的展開を生み出す『君の名は。』とはまったく異なっている。
本連載が目指すのは、ムスビから乗り換えへの乗り換えだ。
▶▶ 連載02「無縁」の原理
本記事は『中央評論』311号所収の拙論「ムスビと乗り換え──関係と無関係の思想をめぐる試論」を元に再編集したものです。同誌はあまり流通していない大学内向けの雑誌であり、また刊行から時間が経っているので、noteにて公開いたしました。同誌の特集「リアリティの哲学」には、拙論以外にもおもしろい論文がたくさん含まれているので、機会があればぜひ手にとってみてください!
ヘッダー画像制作:村上真里奈
研究をしながら、分かりやすい記事をすこしずつ書いていきたいと思います。サポートしていただけると、うれしいです!
