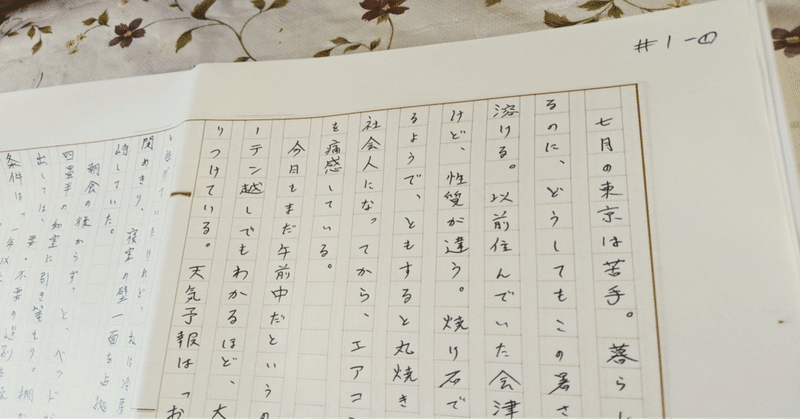
校正の極意
文芸誌の編集者たちは先ほどからずっとテーブルの上に残された原稿用紙の束をまるで突然入ってきた犬が漏らした糞のように見ていた。
「どうするんですか編集長。本気でこんなもの来月号に載せるんですか?」
「いや、載せなきゃまずいだろう。断ったりしたらうちの幹部連中に絶対文句言ってくる。私がわざわざ編集部に持って来てあげた原稿を掲載拒否するなんてね。どうやら今の文芸誌にはろくな審美眼を持つ人間がいないようだ。全員総入れ替えしたらいいのではないか。なんなら客員編集員として私の教え子の教授を二人でも三人でもつけてあげるからそれでどうかねなんてね。あとあの先生、新聞にコラムの連載持ってるからそこでうちを叩くかもしれない。先日気まぐれで某有名文学賞を主催する文芸誌に原稿を持ち込んだのだが、残念ながらその編集者たちは私の原稿がまるで読めなかったのだ。私はその現実を目の当たりにしていかに日本の知性か劣化したかを思い知った。彼らは内容どころか字さえ読めなかったようで私の原稿を無碍に扱ったのだなんて書くかもしれない。そうなったら絶対に世間は俺たちを叩きに叩くだろう。とにかくこの原稿は載せなきゃいけない。だけどそのまま載せたら俺たちは確実に笑い物になる。だけどそれよりもやばいのは載せたら載せたで書いたあの先生自体が笑い物になる事だ。勿論お弟子さんや信奉者さんたちはあの人のこの酷すぎるにも程がある小説を無理やり褒めて世間を騙そうとするだろう。だけどお前らもよくわかっているようにこの小説は糞のような味噌でも、味噌のようなクソでもなくて正真正銘のただのクソだ。騙そうたって騙せるもんじゃない。だが俺たちは載せるしか選択肢はない。だからせめて載せるにはちゃんとまともな出来のものにしなくちゃ」
「だけどこんなものどうやって編集するんですか?あの先生に書き直させるんですか?僕らじゃ無理でしょ?ああいうタイプはプライドが飛んでもなく高いから何言っても君たちのような学識のない人間には私の深遠なる思考は決して理解できないのだよとか言って拒否るに決まっているじゃないですか。さっきの先生の自信満々の態度見て俺あの人もしかして文学賞狙っているんじゃないかって思えてきました」
「だろうな。っていうかさっきも露骨にそんな態度見せていたし。もしろ受賞して当たり前だってぐらいの。でどうせ賞取ったら私個人は文学賞なんて欲しくはありませんが、編集部の方々がどうしても賞に推薦したいとか仰りますんでねとか偉そうにふんぞり返って言うに違いないんだよ」
編集長のこの軽口にその場にいたものは乾いた笑いで答えた。すると編集長は角にいた新人の女性の編集者の方を向いて言った。
「君、よかったらあの先生の担当編集者になってくれるか?」
女性編集者はいきなりの頼みにビビってしまった。彼女は若いからこの文芸評論家の名前こそ知っているが、その著作はほとんど読んでいない。それなのになんで自分がこの高名な文芸評論家の担当に指名されるのか。
「いや、あの先生若い子が好きだから、いっつもどうして君はパーティの席に若い女性を呼ばないのだ。君の編集部に女性が一人もいないことはあるまいとか聞いてくるんだ。だから君のような若い女性の意見だったら少しはまともに聞いてくれるかなって思ってさ」
「だけどこんな酷い原稿どうやって書き直させればいいんだろう。自信ないですよ。正直に酷いって言ったら怒るだろうし」
「そこをうまくなんとかしてくれよ。先生の文章は難しすぎて私たちのような若い読者にはわからないところがあるとか言ってさ。そうしたらあの先生鼻伸ばして書き直すかもしれん」
「酷い!それじゃ私がホステスみたいじゃないですか!わかりましたよ!やりゃいいんでしょ?でも結果がどうなっても知りませんからね!」
というわけで女性編集者は翌日早速文芸評論家の自宅に向かったのである。文芸評論家は山の手の瀟洒な住宅に住んでいたが、彼は呼び出しベルに応ずると玄関に出て来て、フランスかぶれらしくレディーファーストで編集者を迎えた。
「あなたのような素敵な方に出会えた事に感謝します。さあこちらへ」
編集者は客間の内装のあまりの豪華さにいささか緊張してしまった。
「どうですかね。まぁこんなブルジョワ趣味丸出しの下品な部屋はお気に召さないかもしれませんが、ごゆるりとなさってください。そういえばフローベールもプルーストの部屋もこんなブルジョワ趣味の部屋だったそうですが、彼らはそこに住みながらあの不滅の名作を書いていったのです。真の文学は知的な戯れにあるのであって現実の有象無象などどうでもいいと言えばどうでもいいものです。あなたはタバコは吸いますか?」
「いえ、吸いません」
「それは残念。しかしそれは世代というか時代の問題なのでしょう。私が何故あなたに煙草を吸うのか聞いたかといいますとね。あなたを見てゴダールの『勝手にしやがれ』に出てくる女の子を演じるジーン・セバーグを思い出したのです。彼女はクリント・イーストウッドと付き合っていましてね。あなたイーストウッドのことは知っていますか?知らなかったら私が一から教えて差し上げますが」
「クリント・イーストウッドについてはなんとなく知っています。嵐の二宮君が出ていた映画の監督で昔は西部劇とか刑事ものの映画の俳優をやっていたっていう」
「あなた、それを知っているといえますか?なんですかなんとなくって言うのは。そんなものは知っているうちに入らないんですよ。私としては素直に知らないと言ってくれた方がありがたいのです。今からクリント・イーストウッドについて少しお話ししましょう」
編集者は文芸評論家のイーストウッド話に真からにうんざりした。それで頃合いを見計らって原稿の事を口に出した。すると文芸評論家は不思議そうな目で彼女を見た。
「はて?今あなた原稿がどうしたと聞きました?あの完璧な傷ひとつない水晶について私が今更何をすればいいのかと。そうかあなた私のインタビューを取りに来たのですね。あなたたちは多分『あの衝撃的な処女作を提げてデビューした高名な文芸評論家が己が人生を語る!』とか馬鹿な大衆向けの煽り文句で私のあの純粋なる大傑作を売り出そうとしているのでしょう。私自身はそんな下品な宣伝などして欲しくないのですが、私とてあなた方の雑誌の売り上げが思わしくないことは承知しています。ですから私も一肌脱ぎましょう。あなた方の宣伝に協力して差し上げます」
文芸評論家のあまりにおめでたい勘違いぶりを見て編集者は呆れて赤字で埋め尽くされた原稿を叩きつけてやりたかったが、しかし我慢我慢ととりあえずは文芸評論家の話を聞く事にしたのである。
「私は散々インタビューでも言った通り、昔から太宰治や三島由紀夫を信奉する文学青年とやら軽蔑していたんですよ。太宰や三島のような知的にも体力的にも運動神経の鈍い連中が文学の聖典と崇められる日本の文学界に絶望してましてね。私が小説を書いたところでどうせ連中には理解できないだろうと思って小説など書く気にはなれませんでした。だけどですね。こうして還暦を過ぎた時突然小説が私の脳髄に降りて来たんですよ。まるで泉の水滴が落ちてくるように。それからその水滴に導かれるがままに小説を書き上げたのです。まぁ、脳髄に落ちた水滴に導かれるままに小説を書いてしまったのです。あのあなたナボコフという作家を知っていますか?あの『ロリータ』を書いた人ですけど」
「一応何冊か読んでいますが」
「はは流石に文芸誌の編集に携わるだけあって初歩的な知識は持っておられるようだ。私は別にナボコフなど評価していないんですけど、最近彼が五十を過ぎてから初めて書いた小説があの『ロリータ』だったという事を知りまして私は彼に親しみが湧きましてね。まぁどうということはないのですが、小説というものはこのように老い果てた老人にも降りてくるものなのです。勿論私の小説はナボコフなんぞより遥かに出来がよく、素晴らしいものですが」
編集者は先程からの文芸評論家の御託に真からうんざりした。ナボコフの処女作がロリータだって?お前はそんな情報をどっから強い入れたんだ。外国文学研究者は専門外の事は非常に無知だと言われてるけどお前はまんまそれに当てはまっているじゃないか!イーストウッドがどうしたああした。ゴダールがああしたこうしたもううんざりだわ!大体偉そうに他人をこき下ろしていながらどうして自分と自分の書いたひど過ぎる小説を冷静に評価できないんだ!もう一度原稿を読み直せ!そして赤字の部分をちゃんと直せ!彼女は文芸評論家の前に原稿を叩きつけてこう叫んだ。
「先生お話はもういいですからせめて赤字の誤字脱字くらいはちゃんと直してください!あなたの小説は酷過ぎて私たちにできるのはそれぐらいしかありませんから!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
