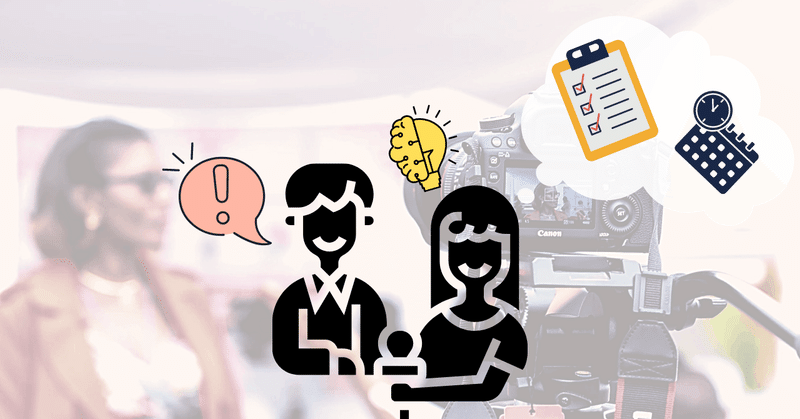
ザ・インタビュー
剛堂堅伍は日本で一番のベストセラー作家であるが、同時にとんでもなく偏屈な作家として編集者たちから恐れられていた。この男は自他ともに認めるほど性格が悪く、そのせいで彼の担当の編集者の中にはノイローゼになって退職したものさえいる。
その剛堂をとある週刊誌がインタビューしようとしていた。偏屈の極みと恐れられ、性格が日本の作家でダントツに性格が悪いと言われる剛堂のインタビューは細心の注意を持って行わねばならない。ある大手新聞の記者が以前彼のインタビューを行ったが、インタビュアーの記者がイケメンであったのが剛堂の気に入らなかったらしく、新聞社に圧力をかけて文化部から無理矢理異動させたそうである。だか彼は出せば百万部は硬いと言われる超人気作家であり、そのかなり右に行ったり、左に行ったりのどうにでも取れる政治的も発言は左右どちらの支持者にも熱狂的な支持があり、勿論その小説は大衆に熱狂的に支持され、エンタメ作家であるにも関わらず、ノーベル文学賞に推す声すらあった。小説やエッセイの掲載は勿論、彼がちょっと推薦のコメント出したぐらいでその小説や映画は急に客足が伸びたりする。そして彼の貴重な肉声が聞けるインタビューは掲載誌が即売り切れになるほど人気がある。だから各出版社の人間は是が非でも彼とお近づきになりたいがためにあらゆる機会をとらえて彼との接触を試みるのであった。
この週刊誌を発行している出版社は今まで剛堂堅伍の本を出した事がなかった。別に嫌われているとかそんな事はなく、ただ彼と交流がなかっただけである。週刊誌の編集部一同はこのインタビューをきっかけに剛堂とお近づきになり、小説を連載してもらおうと考えていた。そうすれば目玉記事を書くほどの取材能力のある記者がいないこの雑誌も他の週刊誌を超えられるし、いずれ単行本化されて出版されれば社内の我々の地位も爆上がりする。剛堂とのインタビューが決まった時、編集部の面々は編集長の周りに集まってこの大事なインタビューを成功させるためのミーティングを重ねていた。
「イケメンじゃダメなら剛堂さんと同じ不細工なオッさんで良くないですか?それだったらあの人も安心するでしょ?」
「いや、そりゃダメだ。剛堂さんはあの通りプライドの高い人だから自分がどんな扱われ方をされているかを変に勘繰るんだよ。一度なんかの情報誌がお前と同じようなこと考えてオッさんをインタビュアーにしたんだけど、後で剛堂先生、私は今までの作家人生でこんな酷い扱いは受けた事はない!私のインタビューなどあの薄汚い記者で充分てことか!わかったよ!私は君たちにとってその程度の人間ってことか!って大激怒してその記者しばらくして倉庫担当に左遷になったってことだ」
「え〜っ、なんですかそれ。無茶苦茶じゃないですか!」
「そうなんだけどさ。でもそれでも剛堂さんとお近づきになるとメリットがありすぎるほどあるんだ。で、みんな他になんかないか?剛堂さんを満足させるインタビューを出来る方法。思いついたら言ってくれよ」
編集長のこの問いに編集者の一人が手を挙げた。
「じゃあ女の子にやらせればいいじゃないですか。ここに今年入りたての新人いるでしょう?彼女にやらせれば」
そう言いながら編集者は今言った新人編集者を指差した。突然指差された新人はびっくりして口を開け、何故かドヤ顔で編集者たちを見回した。
「いや、ダメだ。それは尚更ダメだ」
「はぁ?」と件のドヤ顔女子は編集長の言葉を聞くなり物凄い顔をして声を上げた。だが編集長はこのかなり自分を高く見積もっているドヤ崩れ顔の女子をほっとして話を続けた。
「剛堂さんは多分すっごい女好きだと思うんだけど、さっきも言ったようにすんごいプライドが高いから逆に怒るわけだ。この間某社のほとんど男だらけの編集者しかいない女性雑誌が同じように去年入った女の編集者にインタビューさせたんだけど、その後異様なぐらい激怒して、こんなにバカにされたのは初めてだ!私は若い女を寄越せばなんでもかんでも自白剤みたいに喋ると思っているのか!君たちはこの作家の私をただのスケコマシだと見ているのだろう。私は大変傷ついた。御社とは二度と仕事はしない!って出版社の社長に直接クレーム入れたんだ。まぁ、その結果その若い編集者はファッション誌に強制異動させられた。その他、剛堂にちょっとでも意見する奴、逆に何も言わない奴、ひたすら真面目にインタビューする奴、逆におちゃらける奴、剛堂の話に大ノリになる奴、逆に全く乗らない奴、ひたすらおべっかを使う奴、逆に全く使わない奴、その他剛堂の機嫌を損ねた奴は無理にもほどがある難癖をつけられてみんな異動させられた。うちだってインタビューに失敗すりゃ同じことになる。なんたって出版界では剛堂先生の権力は絶対だからだ。だから俺たちのために絶対このインタビューは成功させなきゃいけないんだ。みんななんかいい考えないかよ?」
編集長の話の無茶苦茶さに皆頭を抱えた。誰を選んでもインタビューの失敗は目に見えていた。もう生贄を捧げるも同じであった。インタビューが失敗したらそのインタビューをした編集者にはとんでもない罰が待っている。確かにうちからは剛堂の本は出していない。だがベストセラー作家剛堂の権力は出版社を股にかけている。かといって今更インタビューをやめると言ったら事態はもっと悪くなる。編集長は再び口を開いた。
「もしかしたら君たちの中には剛堂の読者だっているだろ?なんか剛堂の気に入りそうな食い物とか、お菓子とか、それとやっぱり好みの女だよ。あの人がムッツリスケベだって事は他の出版社の連中から聞いて知っているんだよ。あの人は知的な女ってのがタイプらしい。なんかピッタリしそうな才色兼備な女性我が社にいるか?他の編集部覗いて探してこい。
「あっ、編集長」と不細工なオッさんの事を話した編集者が声を上げた。
「その知的な人だったらわざわざ他の編集部に行かなくたっているじゃないですか。今自分のデスクで必死に校正やってる三雲さんですよ。彼女だったらピッタリじゃないですか!」
彼はそう言い終えると同時にペーパー相手に睨めっこしている三雲さんを指差した。他の編集者はあっと声を上げ、あっそうかそうか三雲さんがいたんだと口々に言ったが、編集長は不満げな顔をして止めた。
「いや、三雲さんじゃ逆に無理だろ。彼女はなんでうちにいるんだかわからないぐらい知的レベルが高すぎる。なんたって国立大首席の元高級官僚だぜ。彼女あんまりにも頭が良すぎて作家連中なんかびびってインタビューになんかならねえよ。彼女作家の言いたい事予測してみんな喋っちゃうんだから。彼女と同じように国立大を卒業した作家なんか無茶苦茶ブチ切れて君らは高学歴の俺をバカにするためにあんなの寄越したのかって文句言っていたじゃないか。あのプライドの高い剛堂さんに三雲さんぶつけてみろ。もう俺たちは一斉に異動だよ」
「いや、彼女あの件に関してはすっかり反省して二度とあんなミスはしない。これからは知能をあなたたちレベルに合わせるって言ってくれたんですよ。それに編集長も知っているように確かに彼女は一見近づき難い感じがしますけど、話せばすごい人当たりがいいじゃないですか。そのギャップが逆に剛堂さんにすごくアピールするんじゃないですかね。おっ、この娘はインテリっぽいけど意外に話もできるぞって」
編集長は編集者の言葉を聞きたしかにそれがいいかも知れぬ、どうせ誰がやってもインタビューは失敗に終わるのだし、彼女に生贄になってもらおうと考えた。編集長はしばし黙り込みそして部下に「そうしよう」と力強く言うと、そのまままっすぐ三雲さんのデスクに行って声をかけた。
声をかけられた三雲さんは待ってましたとばかりに振り向いた。彼女は校正をやっているふりをして実は編集者たちの会話を最初から聞いていたのだ。彼女はかけていたインテリ美人眼鏡をくいっと上げたキメ顔で編集長に私になにかご用ですかと聞いた。そして続けて編集長が何も話してもないのにこう言いだした。
「編集長、今直々に指名された剛堂さんのインタビュー。私、引き受けさせていただきます。私、先日しでかしたミスは絶対にしません。あの一件私は自分が一種の偏見に囚われていた事を学びました。下手に相手を過大評価し過ぎて実態を見失ってしまったのです。私はこの失敗から大事な事を学びました。まずインタビューの前には徹底的に相手をリサーチしてデータを取る事。それからそのデータをまとめ上げて、最良のプランを練る事。そして自分をその最良のプランを実行できるように鍛え上げる事。この三つを徹底的に鍛え上げればインタビューは間違いなく成功するでしょう」
「はぁ、今話していたこと聞いていたんですか?私あなたにまだ何も話していないんですけど?」
「ハッ、しまった。先読みし過ぎて編集長が私に向かってインタビュアーの指名をした幻聴を聞いてしまいました。編集長はその幻聴の中で君しかインタビュアーはできない。君のようにインテリでなんでもこなせる人間じゃないと剛堂さんはとても扱えないとおっしゃっていました。編集長、今おっしゃろうとした事、この幻聴と相違ないですか?」
編集長はこの三雲さんの言葉に思いっきり引き、この人にインタビュアーを任せられるのかと不安になったが、しかしもう彼女に賭けるしかないと決意し、改めて三雲さんに剛堂のインタビュアーの指名をしたのだった。
三雲さんは剛堂堅伍のインタビュアーに指名されるとその場で編集部にあった剛堂の小説からエッセイまでの全著作をわずか三十分で読み、それから剛堂が寄稿した雑誌を残らず調べ尽くした。さらに剛堂堅伍の出身地や学歴まで調べ上げ剛堂がどのように人格を形成したかを分析した。彼女は分析にあたって社会学や精神分析の他、剛堂の出身地に関する雑学本や血液型の本まで活用して精緻に剛堂堅伍という人間を解剖した。それが終わると彼女は剛堂のデータと彼が小説やエッセイで常時使用する言葉から彼女が分析した剛堂堅伍像をAIに取り込み対策法を抽出したのである。彼女はそのAIが出した対策法をさらにアップデートさせてより完璧なものにした。彼女AIと共同で作り上げたプランの見事さに感動し、そして笑った。パーフェクト。これで剛堂堅伍のインタビューは大成功だ。
ここで三雲さんについて軽く触れておこう。彼女は先に書いた通り高級官僚出身の異色にもほどがある編集者である。しかし三雲さん自身は別に官僚などなりたいとは思っていなかった。彼女は幼い頃から世界に羽ばたくジャーナリストを目指していたのである。彼女はそのために経験を積まねばと、高校時代は受験勉強などそこそこにして、コンビニやファーストフード店のバイト。大学時代は派遣で保険のバイトなどをしていた。官僚でさえ彼女にとって経験の一つに過ぎなかった。官僚を辞めるまで順風満帆だった彼女はこの週刊誌の編集部に入って最初の初めての挫折をした。それが先に編集長や彼女自身が語った出来事である。彼女はその失敗で自分の思い込みで相手を高く見積り過ぎた事を反省した。いや、相手を精緻に分析せずただ著作の印象だけをもってインタビューに臨んだ事を反省した。だから今度は相手を徹底的に調べ尽くしてさらにAIを活用して対策を練る事にした。
三雲さんはわずか二時間のうちに剛堂のインタビュー対策案をまとめると編集長に向かって自信満々の表情で彼の連絡先を聞いた。編集長は呆気に取られたが、もはや三雲さんしかいない、もしインタビューを失敗したら生贄になってもらうという思いをたっぷり込めて三雲さんに彼のメールアドレスと電話番号を託した。
さてインタビューの当日である。三雲さんは取材場所のホテルのロビーで二時間前からスタンバっていたが、やがてにチビで不細工の剛堂が現れた。三雲さんは彼を見て自分のデータと寸分狂わない事を確認しインタビューの成功を確信した。データは全て揃っている。後はAIで導き出したプランをそのまま演じるだけでいいと彼女は早速少し膝を屈めて剛堂の方へと向かった。こうすれば剛堂に背の小ささを自覚させてしまうこともない。これは三雲さんが保険のバイト時代に身につけたやり方である。こうして背を相手より低く見せれば客に威圧感を与えることはなくセールストークに持っていくことが出来る。三雲さんはこの方法でバイトであるにも関わらず支店の月の営業成績トップになった事がある。彼女はそのままの姿勢で剛堂に近づいて挨拶をした。
「初めまして剛堂先生、私、今回インタビューをさせていただくまるまる出版まるまる誌の編集の三雲丸絵と申します」
剛堂は三雲丸絵のこの背丈の違いを意識させない姿勢にとりあえず満足したようで、彼はそれに対して「今回インタビューを受けさせていただく剛堂堅伍です。人からは大作家と呼ばれていますが、まだまだ修行中の身です。こちらこそよろしく」と背筋をピンと張ってわざとらしいまでに謙譲ぶった言葉で応えた。
二人はそのままインタビュー場所である地下のレストランに行こうとエレベーターに乗ったのだが、そこにはおそらくルームサービスか何かで部屋から回収したのであろう食器を乗せたワゴンを持ってベルボーイがすでに乗っていた。剛堂はこれを見て怒髪天をついてベルボーイを怒鳴りつけた。
「なんで君は私と彼女がエレベーターに乗ろうとしているのに、さっさと外にでんのだ!ほう〜、そういうことか。君はホテルの従業員として客のもてなしかたの教育は一通り受けているだろう。なのにそれでも君はこのベストセラー作家の剛堂堅伍と彼女がエレベーターに乗って来たのにエレベーターから出ようとしなかった。それはおそらく君は一般人である彼女しか見とめなかったからだろう。彼女は一般人。しかも一人。いくらワゴンでもエレベーターのスペースは充分にある。適当に挨拶してそのままエレベーターに乗っていればいいと君は思ったのだ。おそらく君は最初にこのベストセラー作家である剛堂堅伍を最初に見とめていれば先生申し訳ありませんと深々と地のつくほど頭を下げてエレベーターから出て行ったはず、なのにどうして出よう考えようともせず無礼にもそのまま乗っていたのか。それはこの私を人とは思わなかったからだ。またバカにされた!私などこの一流ホテルでは人扱いされないのか!私など見ないふりをされなければいけないのか!私はいつかこのホテルのラグジュアリールームに泊まれるぐらい有名になってやると自分に言い聞かせて今まで小説を書きまくっていたのに、まさかこのホテルの従業員からそんな人を人とも思わない扱いを受けようとは!ホテルのオーナーに直接電話して問いただしてやる!このベストセラー作家の剛堂堅伍がこのホテルに入るのに相応しいかどうか!さぁ、今すぐ電話だ!」
剛堂はそう叫ぶとベルボーイがとっくにエレベーターに出てそこで平身低頭して謝っているにも関わらず、一人興奮してポケットからバミューダ製のスマホを取り出して電話をかけようとした。だがその時三雲さんはもはや泣いて土下座しているベルボーイの前に立って手を内に礼儀正しくお辞儀をしてこう言った。
「剛堂先生、申し訳ありません。これもインタビューをセッティングした私の不手際のせいです。先生をエレベーターに乗せる前にホテルのフロントに誰も乗せないよう指示することまで頭が回らなかった事をお詫びします。しかし先生今からフロントに指示を出しても周知が行き渡るまで時間がかかるでしょう。ご足労をかけますが、私がエスコートしますのでそこの周り階段で地下まで降りませんか?」
そう言いながら三雲さんは剛堂の手をとった。これは彼女が保険のバイトに散々出くわした悪しきクレーム客の対策で学んだ方法であった。彼女はAIで作成したプランに従ってこの方法を実践したのである。その彼女の読みが当たったのか、剛堂はこの三雲さんの思わぬ行動に一瞬驚きを見せたものの、素直に彼女に誘われて一緒に地下のレストランへと向かった。
しかし剛堂はレストランでもまた揉めてしまったのだ。剛堂はレストランで案内された席に座ったのだが、そこで注文を取りにきたウェイターにブチ切れてしまったのだ。
「君は何故そんなに腰をかがめて私に注文を取ったんだ。君は他のテーブルの客にはそんなに腰をかがめてバカ丁寧に注文を取っていなかったではないか。私たちだけだ。いや私だけだ。君はこのテーブルでまずベストセラー作家である私に注文を取りにきた。それはいい。だが何故そんなに腰をかがめる必要があるのか?ひょっとして君は私を悪しきクレーマーだと思っているのではないか?ホテルからあの人クレーマーだから対応には気を遣ってとか言われたのか?こんな過剰なもてなしはそうに違いない。ああ!私はこのホテルからベストセラー作家ではなくて迷惑極まりないただのクレーマーだと思われていたのか!まさかここまでまともな人間扱いされていなかったとは!ホテルのオーナーに電話をかけて私をクレーマーだと思っているか確認してやる!」
剛堂はエレベーターの時と同じようにウェイターが泣いて土下座しているにも関わらず電話をしようとした。しかしその剛堂の手を握りしめて三雲さんが声をかけた。
「先生、ここのシェフの料理はとっても美味しいと評判なんですよ。だけどそのシェフはもう少しで帰ってしまいますの。早くその方にシェフに注文を伝えさせなければ」
これも三雲さんの機転であった。これは彼女が半月ほどバイトをしていた銀座の高級クラブで学んだテクニックであった。剛堂はこれにすっかり参ってしまい。躾けられた猿のように大人しくなってしまった。
美人のインタビュアーの前でその名人シェフが作ったらしき料理を食べて剛堂はひどくご満悦であった。彼は上機嫌に自分の事をペラペラと喋りまくった。
「ふふふ、僕ってホントに嫌なやつだろう。気に入らない事があるとすぐこうやって人にあたってしまうんだ。自分でもこの癖は治さないととは思っているんだが、治らないんだなぁ〜。でも人に当たり散らした後は何故かすっごく書けるんだ。この間なんてね、一晩で四百ページ書いたよ。凄いだろ、四百ページ!」
「ネガティヴなものが時に力になると先生はお考えでしょうか?」
「そう、そうだね。作家っていうのは陰気な連中が多くてね。いつも人を羨んで生きているんだ。この日本で一番売れている天才の僕だって例外じゃないよ。ひょっとしたら僕が一番ネガティヴだったりするんじゃないかな、グフフ!だけど意外だろ?このベストセラー作家の日本で一番稼いでいる僕がこんなネガティヴな人間だったなんて」
「いえ、先生は私のイメージ通りの人でしたよ。先生の著作を読んで分析した通りの人でした」
「ははは、そうか。さすが僕のインタビューをするだけあってしっかりと読み込んでいるんだなぁ、ハハハ」
インタビューは無事に終わった。三雲さんはインタビューが終わった時剛堂にインタビューでこれだけ自分の事を喋ったのは初めてだと言われた。彼女はこの結果に大成功だと確信し編集部に電話をかけてインタビューの成功と、明日までに原稿を仕上げる事を伝え喜び勇んで自宅へと向かった。
そして翌日である。朝の一番に会社にきた三雲さんは暗い顔をした編集長がデスクに座っているのを見た。彼は三雲さんを見て力のない声でこう告げた。
「三雲さん、明日から子会社に異動だから。あの剛堂先生、昨日のインタビューに大変ご立腹でね、あの女は僕をまるで赤子のように扱った。このベストセラー作家で日本で一番の天才の僕をあなたのようなクレーマーはこうすれば簡単みたいな感じで扱ったんだ!おかげで僕はあのホテルの連中の前で大恥を掻いた。インタビューはそれ以上に酷かった。僕がせっかく誠実に自分の事を語ったのに、あの女はそんな事言わなくてもわかってますよって感じで先生は私のイメージ通りだなんて抜かしやがったんだ!だから僕は彼女に向かって自分は君にわかるほど単純な人間じゃないとインタビューじゃありえないぐらい長い時間をかけて話したんだが、あの女はそれでもそうですかなんて言いながらせせら笑っていたんだ!こんな屈辱今まで味わった事はない!私の小説を御誌に連載してもらいたいならあのバカ女のクビを切れ!ってね。せっかく頑張ったのに気の毒だけどゴメンね。一応インタビュー記事は無署名で使わせてもらうから。あっ、子会社の方はコンピュータ関係の本出してるとこだから多分三雲さんにも会うんじゃないかな。剛堂先生にも会う事ないだろうし」
三雲さんはこのあまりに突然の辞令に驚きそして叫んだ。
「なんでそうなるよ!私完璧すぎるぐらい完璧に仕切っただろうが!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
