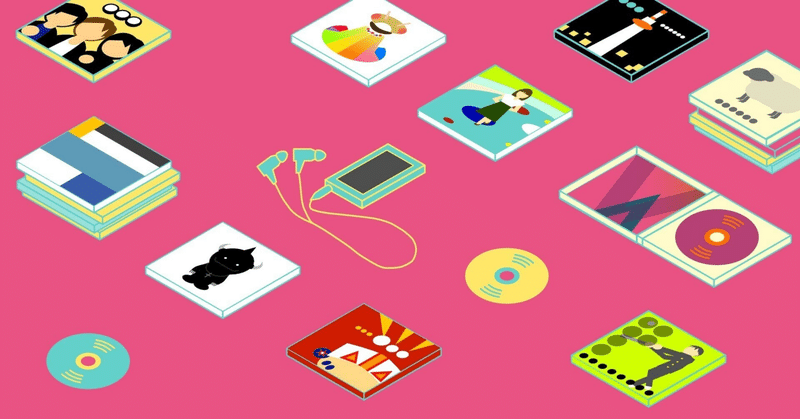
あるロックバンドの受難
現代ではロックは完全に時代遅れのものになってしまった。確かにロックのコンサートはいまだに客が入り、世界のライブ興行収入のトップ3を独占することもある。だが現在若者たちは誰もロックなど聴いていない。彼らはヒップホップやKPOPにすっかり夢中となりロックなんぞに見向きもしなくなった。ロックを聴いているのは年寄りと年寄り一歩手前の蛹だけである。この老人たちと老人もどきは人生の半ばをとっくに過ぎても、いつまでもロックを聴き狂っていた思春期を引きずっていた。
そんなロックファンの老人たちの救世主として我が日本からエターナル・ボーイズが彗星の如く現れた。このビートルズとボブ・ディランとフーとドアーズとブルース・スプリングスティーンとクラッシュとエルビス・コステロとU2とスミスとニルヴァーナとオアシスとレディオヘッドとコールドプレイ等、かつての若者たちが愛したロックをすべてミキサーにぶち込んだようなバンドは老人と老人もどきにとってロックの福音であった。老人たちは最初このエターナル・ボーイズを若いのに洋楽をよく知っているじゃないかと上から目線で見ていた。だが老人たちはYouTube等でバンドの曲を繰り返し聴いているうちすっかり彼らの信者となってしまったのだ。エターナル・ボーイズには老人たちがロックに求めていたものがすべてあった。バンドは彼らの思春期の全てを捧げたあのロックをより純化した形で鳴らしていた。老人たちは揃って熱狂的に彼らをロックの救世主と讃え、彼らこそ今の世界のロックシーンを塗り替えると豪語した。
エターナル・ボーイズのデビューライブには大勢の観客が詰めかけたが、その大半は老人であった。この事実は若者がもはやロックなど聴かないという悲しい証明であるが、それでもライブ開始前の会場は異様な熱気に満ち、まるで巣鴨のフジロックやサマソニみたいな盛り上がりっぷりであった。観客の老人たちは今か今かとバンドの登場を待っていた。
ライブ会場に流れていたのは老人たちが昔散々聴いていた不滅のロッククラシックばかりであった。ここでアーチスト名はいちいち書かないが、老人たちはそれらのロッククラシックを聴いてたちまちのうちに思春期に戻ってしまった。ロックの衝動そのままに大人たちを反発して校舎の窓ガラスに投げまくっていたあの頃。肉体と精神の相克に悩みまだ病気とつぶやいていたあの頃。そう、俺たちはまだ思春期って病気に取り憑かれているんだ。老人たちはすっかり悩み多かった少年時代に還り、ひたすらエターナル・ボーイズの登場を待ち続けた。
その彼らの前にエターナル・ボーイズは颯爽と現れた。バンドはステージに出て満員の客席を見て喜んだか、よく見たら客が年寄りしかいないのに気づいて固まってしまった。客席のおじいさんたちは自分たちをなんか目を潤ませて見ている。ボーカルの歌タロウはこの老人だらけの観客になんて挨拶していいかわからず、とりあえずロック好きの人たちなのかと考えてとりあえず挨拶をこう始めた。
「皆さん、わざわざ僕たちエターナル・ボーイズのライブにお越しいただいてありがとうございます。皆さんのような僕らの生まれる遥か昔からロックを聴いていた方たちから見たら、僕たちみたいな若僧なんてまるで幼稚園児みたいなものだろうし、僕らのライブなんてお遊戯会に見えるでしょうが、それでも僕らのロックへの愛は本物です。これから小一時間精一杯演奏しますのでよろしくお願いします!」
エターナル・ボーイズはこう自分たちのライブに来てくれた老人たちに向かって礼儀正しく挨拶した。だが老人たちはこの挨拶に全く盛り上がらず、それどころか不満気にため息をついたり、挙げ句の果ては舌打ちまでしたりした。バンドはこの客の老人たちの反応に戸惑ったが、しかし演奏で挽回してやると素早く頭を切り替えて見事な演奏で結局ライブは大成功に終わったのである。
さてオープニングにハプニングらしきものはあったものの、エターナル・ボーイズは見事ライブを成功させた。この大成功にメンバーたちは喜んで互いの健闘を讃えながら楽屋へと入ったのだが、中に不機嫌な顔をしたレコード会社のスタッフがいたのですぐに口を閉じた。レコード会社のスタッフはそのエターナル・ボーイズのメンバーに対してお前ら座れといい、彼が座ったの見てにこやかに話し始めた。
「ライブお疲れ。とりあえず成功してよかったよ」
メンバーはこの言葉を聞いてさっきスタッフが不機嫌そうに見えたのが自分たちの勘違いだったと思って安心した。しかしそのレコード会社のスタッフは急に厳しい顔になってこんな事を言い出したのだ。
「だけど、あのオープニングのMCはいただけないな。ああいうオールドスクールのロックオーディエンスに僕らの生まれる遥か昔からロックを聴いていたとか言ったり、自分たちのライブを幼稚園のお遊戯みたいに見えるだろうとか自分たちの若さをアピールして過剰に遜ったりしちゃダメだよ。君たちはライブに来てくれたオールドスクールのロックオーディエンスを立てているつもりだろうが、それが却って彼らを馬鹿にして傷つけてしまっているんだ。君たちも見ただろ?あのロックオーディエンスの熱狂ぶりを。それを見て君たちはおじいちゃんとはとても思えないって思っただろ?あのロックなオーディエンスは幼稚園のお遊戯会を見に来てるんじゃなくて、君たちの半径五メートルのリアルなロックを聴きに来ていたんだよ。まぁ、こんな事君たちに言ってもなんだかわからないと思うからもっとわかりやすく言おうか。つまりロックオーディエンスはライブにいる瞬間だけは、自分たちを焼却炉行きの順番を待ってる年寄りじゃなくて、悩めるロックボーイズだって思いたいんだよ。そんなオーディエンスに僕らの生まれる前からロックを聴いてたとか、自分たちが幼稚園みたいに見えるだろうとか現実を思い出させるような、例えば彼らの年齢や老化について触れるような事を、相手を褒めるつもりでも、絶対に言ったらダメなんだよ。あのMCでオーディエンスは君たちに腹が立てただろう。中には君たちの発言に失望して二度とライブ行くのはやめようと思った人間もいるかもしれない。今日はもうしょうがないから次からは絶対に気をつけるんだぞ。いいか?これからはロックオーディエンスに現実を突きつけるんじゃなくてリアルを与えろ。現実とリアルってのはおんなじ言葉に見えるってか、全く同じ意味の言葉だけど、実は事実と真実ぐらい違うものなんだ。現実ってのは事実だ。ライブ後にオーディエンスがおしっこ漏らしているのに気付いたとか、オーディエンスがライブ中に道に迷って隣のマンションに無断侵入したとか、その観客が再入場出来ないのに腹を立ててあたり構わず怒鳴り散らしたとか、そういうどうしようもない事実が現実だ。リアルはそれとは違う。リアルってのはロックを愛する全ての人間が半径五メートルの中で掴んだ真実なんだ。希望であったり、絶望であったり、愛だったり、喜びだったり、悲しみだったり、そういうもの全部を含めたものがリアルなんだ。俺の言ってる事わかったか?君らはあのロックオーディエンスの消えない光なんだ。それを忘れるんじゃないぞ」
こうレコード会社のスタッフはこう長く熱くまくしたてたが、当のエターナル・ボーイズのメンバーは見事なまでに何一つ理解出来なかった。メンバーの頭の中ははてなマークで覆い尽くされ、訳わっかりませ〜んといった顔をしていた。長い話が終わってしばらくしてからボーカルの歌タロウが口を開いた。
「あの~、申し訳ないんですけど、僕お話の内容全く分かりませんでした。お前らだってそうだよな?」
タロウに聞かれたメンバーは戸惑いながらも頷いた。メンバーの同意を確認してタロウは再びスタッフに言った。
「大体僕ら元々ロックなんか知りませんから。バンドだって最初はback numberみたいに朝ドラの主題歌になるようないい曲作りたいって思って始めたのにアンタらやうちの事務所がロックバンドがそんな甘っちょろいことやんな!ちゃんとしたロックやれってせっつくから、しょうがなくおじいちゃんが聞いてるような洋楽ロックみたいなのをやってやっただけじゃないですか?それでも不満なんですか?ただの挨拶程度でこんなにガミガミ言われるんだったらもうロックやめて元のback number路線に戻りますよ」
このタロウの言葉に他のエターナル・ボーイズのメンバーも深く頷いた。そしてエターナル・ボーイズのメンバーはレコード会社のスタッフをまっすぐ見た。その顔はこれ以上自分たちにロックやらせるならいつだって契約を破棄してもいいぜとフォント太めの下手くそな文字で顔に書いてあった。だがレコード会社のスタッフはそれに全く怯まなかった。
「ロックを辞めたいならいつだって辞めてもいいさ。だがな、ロックじゃない君らなんて誰が相手すんだ。君らはback numberみたいなバンドやりたいという。まぁそういうのがやりたいんだったら俺も止めはしないさ。だけどな、世間にはback numberのコピーみたいなバンドはたくさんいるんだ。大体back number自体が〇〇〇〇中の〇〇〇〇バンドじゃないか。君たちはロックをやめてそのback numberの何百番煎じにでもになるのか?そうなったとしても君らの才能ならある程度は成功するかもしれない。だがああいうバンドのファンは大抵若い女の子たちだ。彼女たちは非常に気まぐれだ。back numberに飽きたら次は別のバンド。それも飽きたらK-POPと見境なく他に映るんだ。だけどロックオーディエンスは違う。君たちのライブに感動したオールドスクールのロックオーディエンスは死ぬまでずっと君たちの信者であり続けるだろう。何故なら君たちは彼らが絶望の中で掴んだ唯一の希望だからだ。彼らが死んだとしてもまた次の老人がすぐに現れ君たちの信者になるだろう。僕は以前ロック信者の増減について調査したんだが、その結果ロック信者はあと二十年は増え続けるだろうというデータが取れた。つまりお前らはあと二十年以上活動出来るんだ。それどころか世界中のオールドスクールのロックオーディエンスに受け入れられればU2やゴールドプレイクラスにブレイクすることができるかもしれない。さぁ、選択するんだよ。ロックを選んで最低二十年の安定した将来をとるか、back numberの真似をして二、三年で忘れ去られるか。どっちがいいんだ!」
こういきなり決断を迫るスタッフにエターナル・ボーイズのメンバーは動揺した。ああジジイ相手に二十年稼ぎまくるか、back number風のバンドに戻って朝ドラの主題歌を目指すか。いや、この二者拓一はもう決まったようなものだ。音楽一本で稼ぐことすら難しくなった現代で二十年分の収入が保証されるなんて奇跡だ。だがそれでもバンドは悩んだ。あのジジイたちをどうやって相手にすればいいんだ?
「あの」と再びボーカルのタロウが口を開いた。
「あなたのお話聞いて僕らやっぱりロックやった方がいいかなって考えてるんですが、あのライブの時オーディエンスの方々になんて挨拶すればいいのかなって思いまして。さっきみたいにな言い方だとオーディエンスの方怒っちゃうみたいだし。いっそMCなしでいいですか?」
「そりゃダメだ。君たちはクラシックやジャズをやってるわけじゃないんだから。ロックは演奏の巧さを競うんじゃなくて、共感を与えるものだからだ。ライブに出てきて何も言わずにただ演奏したって共感なんて与えられないよ。MCは共感を与えるためには絶対に必要不可欠なんだ」
「じゃあどうやってMCすりゃオーディエンスの方々にその共感ってのを与えることが出来るんですか?」
「別にそんな難しく考えることじゃない。いつも友達同士で喋っている事を言えばいいんだよ。君たちこの間のフェスに出た時楽屋でベテランロッカーにいぢめられた事をずっと文句言っていたじゃないか。ああいう老害がいつまでも業界仕切っているから日本は世界から取り残されるんだとか、世界では若者たちが音楽界の中心で活動しているのに日本は老人がいつまでも居座っているからまともに発展しないんだとか言っていたじゃないか。あんな事をMCで言えばいいんだよ」
このスタッフの発言にバンドのメンバーはびっくりした。
「えっとお、そんなこと言ってホントにいいんですか?そんなこと言ったらあのオーディエンスさんたちブチ切れるんじゃないですか?」
「いや、ブチ切れるはずがない。なぜならあのオールドスクールのオーディエンスは常に自分たちを若者の側だと思っているからだ。この超高齢化社会では老人に見える彼らだって若者なんだよ。彼らだって上の世代に抑圧されているんだ。それだけじゃない。彼らは自分たちのちょっと下の世代の立場が上な人間にだって抑圧されている。彼らは自分たちの置かれた現状に義憤を感じてこう思うのさ。こんないつまでも地位にしがみついた老害たちなんか今すぐ消えてしまえばいいのにってね。君たちはあくまで彼らを自分たちと同じような若者だと思って接したらいい」
「それでいいんすか、それであのオーディエンスさんたちに気に入られるんですか?」
「そうだ。でもオーディエンスさんなんて敬称なんかつけなくていいんだよ。ふつうにオーディエンスでいいだろ。あいつらは君らの仲間なんだぜ。彼らに呼び掛けるときはお前らとか仲間意識を持って呼ぶんだ」
「それでいいんすか。それで僕ら最低二十年は食ってけるんですか?」
「そうだ。でもロックオーディエンスなんて演歌ファン並みにしぶといからもっと長く食っていけるかもしれない。下手したら一生分はね」
エターナルボーイズはスタッフの言葉を聞いてガッツポーズをとった。そうさアイツらは見てくれこそうちのじいちゃんみたいだけど俺たちと同じ若者なんだ。やってやるぜこれからは熱きロック魂で奴らをノックアウトさせてやる!エターナル・ボーイズのメンバーはレコード会社のスタッフに深くお辞儀し「ありがとうございました!」と大きな声で礼を言った。
こうしてレコード会社のスタッフのありがたい御神託を受けたエターナル・ボーイズは早速次のライブからそれを忠実に実行した。するとバンド瞬く間にメジャーになってしまった。ロック雑誌はこぞって彼らを取り上げ、熱狂的にバンドを称えた。バンドは雑誌のインタビューの中でもスタッフに言われた通り老人が牛耳っている日本の政治と音楽業界を批判し若者の力で日本を変えるんだと息巻いた。この熱き言葉にとある雑誌の白髪頭に杖をついたおマンチェの格好したライターは興奮してこいつらはマジでロックを変えると書きまくった。
その熱狂の中、エターナル・ボーイズのファーストアルバムが発売されたのだが、発売された途端SNS界隈ではとんでもない騒ぎになった。今まで若者に虐げられていたオールドスクールのロックオーディエンスは突然蜂起したかの如くエターナル・ボーイズのファーストアルバムの画像をアップし始めたのである。彼らは水分がなくなりかけたシワだらけの体にビートルズ風やらストーンズ風やらグラム風やらパンク風やらおマンチェ風やらグランジ風やらオアシス風やらとにかくロックレジェンドたちの服を思い思いに羽織り、エターナル・ボーイズのファーストアルバムと一緒に写真に収まったが、その写真に写った彼ら姿は、皆押し入れから久しぶりに服を出したのを着ているせいか、どれもどこかしら穴が空いていた。セックスピストルズの格好をしているオーディエンスなど本物よりもはるかに穴の大きなジーンズを履いていたが、それは明らかに虫食いのせいだった。
我らがエターナル・ボーイズはこのオーディエンスの盛り上がりに呼応してますますロックに過激になっていった。「地位と名誉にあぐらをかいている老害はみんな死ねばいい!」「俺たちのような若者が世の中を動かすべきだろ?」「俺たち若者で今こそ革命を起こそうぜ!」オールドスクールのロックオーディエンスはこれらの久しぶりに聞く反体制の言葉を聞いて俺たちはエターナル・ボーイズと共に世の中を変えるんだと気勢を上げた。彼らはエターナル・ボーイズがいる限り自分たちはこのロックというリアルを生きていけるのだと信じた。
だがそのロックのリアルも現実という真のリアルには勝てなかった。エターナル・ボーイズとオールドスクールのロックオーディエンスにはやはり埋められぬほど深く広い世代の溝があったのである。エターナル・ボーイズのメンバーは何をやっても周りから絶賛されるので完全に調子に乗っていた。ライブのMCもどんなに過激な事を言いまくってもオーディエンスは喝采してくれた。それで調子に乗ったエターナル・ボーイズはじゃあもっと過激にやってやれととあるライブでこんなMCをしたのである。
「俺、最近年金問題に興味持ってさ、それでいろいろ調べたわけだよ。で、とんでもないことに俺たちの税金が全部ジジイの年金のために分取られてるって事を初めて知ったんだよ。ふざけんなよって思ったね。お前らもムカつかね?何であんな死にかけのジジイの延命措置のために俺たちの税金使われなくちゃいけねえんだよ。俺たちが総理大臣になったらジジイどもは即死刑だね。こういうジジイこそ真の老害なわけよ。息してるだけの役立たず。ジジイさっさと死ね!今すぐ死ね!お前らだってそう思うだろ?」
オールドスクールのロックオーディエンスは自分たちに向かって放たれたこのあまりに現実的な言葉を聞いて驚きのあまり頭が真っ白になった。ああ!近所のガキどもからいぢめられる現実からロックのリアルに救いを求めるために、少ない年金を割いてこのライブに来ていたのに、そのロックからこんなひどい仕打ちを受けるなんて思わなかった!
「お前らどうしたんだよ。お前らだってジジイ死ねって思ってるだろ?ほらジジイ死ね〜!ジジイ死ね〜!ジジイ死ね〜!」
すっかり静まり返ったライブ会場にエターナル・ボーイズの煽りだけが虚しく響いた。しかし完全に調子に乗りまくっているバンドはこの惨状に全く気付かず仲間内でジジイ死ね死ねコールをやって馬鹿笑いしていた。やがてそれも飽きたのかエターナル・ボーイズは再びオーディエンスの方を向いてまた煽り始めた。
「オラ、お前ら恥ずかしがってないでちゃんとコールしろよ。いつもやってるだろ?いくぜ!ジジイ死……」
ボーカルのタロウがここまで言いかけた瞬間客席からステージに向かって椅子やらビール瓶やら杖やらうんこやら尿瓶が一斉にステージに投げられた。エターナル・ボーイズはこの予想できない事態に慌てふためいて楽器を放り出してステージを逃げ出し始めたが、オールドスクールのロックオーディエンスは客席からステージに上がり込んでエターナル・ボーイズを取り囲んでしまった。そして彼らは一斉にバンドを指差してこう叫んだ。
「お前らが死ね!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
