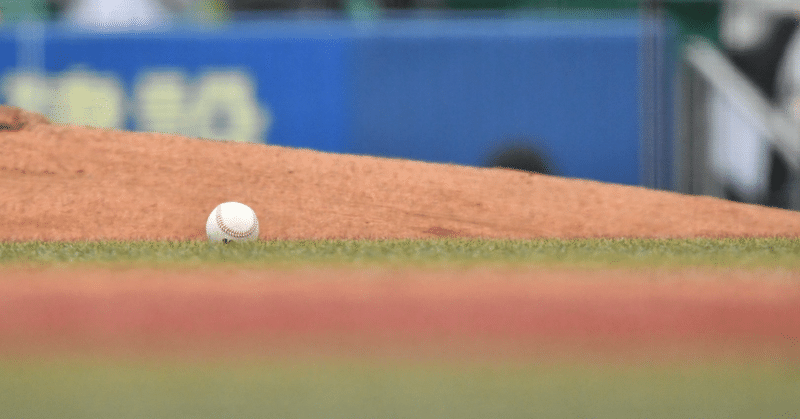
不気味さの中にある真意とは―鈴木忠平『嫌われた監督』
僕が2021年に読んだ本の中で、ダントツでベスト1の本を紹介したい。
鈴木忠平さんの『嫌われた監督』である。
落合博満さんが中日ドラゴンズで監督を務めた8年間を追った本だ。著者の鈴木さんは当時、ドラゴンズの番記者である。
とにかくページをめくる手が止まらない。480ページという分厚さだが、一気に読んでしまった。
リーダビリティあふれる記述
「事実は小説よりも奇なり」という言葉がある。この本でつづられる落合ドラゴンズの物語は、その辺の小説よりも読者をぐいぐい引き込んでいく。ドキュメント性あふれる本だ。
この本は、章ごとに視点が変わる。それは選手だったり、フロントだったり、コーチだったり様々だ。色々な人物の視点から、落合博満という人物が語られていく。
川崎憲次郎さん視点の1章と、荒木雅博さん視点の12章は、上質なミステリを読んでいるかのようなどんでん返しが待っている。
主人公でありながら、決して自身の視点では物語が語られない。それが落合さんの不気味さをより醸し出している。
不気味さに翻弄されながらも、プロフェッショナルとして個を確立していく選手の姿に目が離せなくなる。
落合博満は、観察する人
落合さんは、とにかく選手を観察する。そして些細な違いを見つけると、それに応じた手を打っていく。
番記者である著者に、落合さんは次のように語る。
「ここから毎日バッターを見ててみな。同じ場所から、同じ人間を見るんだ。それを毎日続けてはじめて、昨日と今日、そのバッターがどう違うのか、わかるはずだ。そうしたら、俺に話なんか訊かなくても記事が書けるじゃねえか」
落合さんにとっては、同じものを毎日観察することがルーティンになっている。一見、変わりないように見えたとしても、ルーティンを怠らないことで、微々たる違いや変化を見つけていく。
落合さんは、試合を見るときも当然観察を怠らない。
落合は、ひとつひとつの事象の向こうに人間心理を見ているようだった。空振りをしたバッターのスイングと表情に矛盾はないか。マウンドにいる投手の仕草とボールの軌道に関連性はないか。相手が苦悶の表情の裏で舌なめずりしているのか、それともポーカーフェイスの裏で冷や汗をかいているのかを見抜こうとした。
動くべきか待つべきか。押すべきか引くべきか。落合の決断はそれらを判断材料にして下されているようだ。
この観察眼が、ドラゴンズの聖域に対してメスを入れることになる。そのときの選手たちの波紋や葛藤もこの本の見どころだ。
一つのものを観察するルーティンは、単調で飽きがきそうだが、非常に重要である。サッカーを観る上でも仕事の上でも同じだ。いかに些細な変化を見逃さずに観察できるか。僕も身につけたい手法だ。
プロフェッショナルは、孤独である。
選手の責任と監督の責任、その線引きをはっきりさせるのが、落合流だ。
落合さんは、チームのためのバッティングに徹した和田一浩に、こう伝える。
いいか、自分から右打ちなんてするな。やれという時にはこっちが指示する。それがない限り、お前はホームランを打つこと、自分の数字を上げることを考えろ。チームのことなんて考えなくていい。勝たせるのはこっちの仕事だ。
自分の数字(成績)を向上させるのが選手の仕事、チームのことを考えて勝たせるのが監督の仕事、というわけだ。
この線引きを明確にすることで、責任をはっきりさせる。だから、選手にとっては逃げ道がないように見えるし、こわいし、情がないように見える。
真のプロフェッショナルは、他者に寄りかかるのではなく、己の実力のみ頼りにする。だから誰もが孤独な戦いを強いられる。しかし、そうやって個々を高めた組織は、勝てる組織になるのだ。
監督としての最後のシーズンの終盤、荒木雅博が禁止されていたヘッドスライディングを解禁する。その姿を見た落合さんは、著者にこう告げる。
あれは選手生命を失いかねないプレーだ。俺が監督になってからずっと禁じてきたことだ。でもな、あいつはそれを知っていながら、自分で判断して自分の責任でやったんだ。あれを見て、ああ、俺はもうあいつらに何か言う必要はないんだって、そう思ったんだ。
この言葉から、落合さんは、自分で判断し、自分の責任で動く個の育成を志向していたことがうかがえる。そのための8年間だったのではないだろうか。
読みものとしても面白いし、学びもある。歴史に残るスポーツノンフィクションだ。
