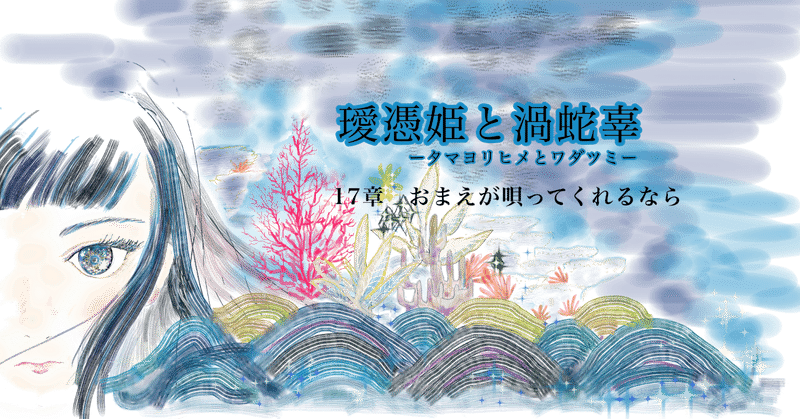
璦憑姫と渦蛇辜 17章「おまえが唄ってくれるなら」③
「ああワダツミか………」
還っていく魂の丸く白く光る幽けき光の群れの中にふたりはいた。
しばし彼の腕の中でそれを見送った後、
「兄ぃさも還ったのか……」
とタマヨリは尋ねた。ワダツミはうなづく。
「会ったか?」
「ああ、会った」
「なんか、話したか?」
「俺をタマとよんだ」
「……そうか」
タマヨリは満足そうに笑った。晴れ晴れとした、八重の蕾がほころぶにも似た笑みだった。
「そうか、そうか……じゃあもうなんてことないさぁなぁ」
ワダツミの腕から降りたタマヨリは『いさら』を拾って突き立て、それに背を預けてどかりと座り込んだ。目を覚ましても疲労が残っていたのだろう。
瞬きの間隔が長い。重い瞼を押し上げてワダツミを見上げた。
「おれがワダツミでもワダツミがおれでも、兄ぃさには全部タマなんじゃなぁ。おれがどんな姿でも、おれの魂がわかるなら、もう、なにひとつも恐いことがなくなった」
「……『竜宮』へ行くつもりか」
「ああそうだ。……ワダツミ?お前、入墨が消えている……!」
云われて気づいた彼は腕を見、肩を見、それから片手を頬に押し当てた。
その場にはタマヨリしかいなかったが、見る者がいれば美しさに息を飲んだことだろう。波光色の髪も海の深さを写した瞳も、霞ませるものはひとつもなくなって、海の化身は頑強な体躯に雅致を纏っていた。
「戦はおさまったのか?磯螺が約束を守ってくれたんか?なあワダツミ、これで『海境』をくぐれるなぁ……」
「肚竭穢土の皇子は、沖の小島に足止めをくらった。礁玉の軍も身動きが取れぬであろう。これで収まるほど賽果座は無欲ではないだろうが……、いっときは双方引くほかなかろう」
「なら、よかった………」
「礁玉は俺の首が欲しかろうなあ」
くつくつと喉で笑うワダツミに、何がおかしいのかとタマヨリは変な顔をした。
「あれはそういう女だ」
「なんだか礁姐とやり合うのを楽しみにしてるみたいじゃな、なんでそうなる?お前、女心ちゅうものを考えたことが一度でもあるか……」
「少なくともあの女を見縊ったことはない。肚竭穢土の騎馬隊とも互角か、うまくやればそれ以上だろう。ただ圧倒的に数が足りんからな、長引けば不利だったがな」
決別した女と兵を交えることに愉悦を見出している。タマヨリの知る男女の情交とはかけ離れているが、礁玉が相手ならまかり通る気がしないでもないように思った。
「ん……おれには、分からんが………。いずれにしても人が死ぬのは嫌じゃからな」
白い玉は幾年かぶりの地上が名残り惜しく去りがたいように、ゆっくりと漂っていた。あっちへふらふらこっちへふらふらと蛍火のように動く様は、物思わしげであった。
それを視線の端に捉えたワダツミは鼻で笑うと、
「人など元より儚きものだ」と云った。
「見てみろ」
と顎で指し示す方には、かたまって渦まきながら海へと向かう魂の行列ができていた。
「山野を埋め尽くしてもまだ足りぬ死者どもを見ただろう」
「ああ。思った以上にたくさんおった」
「生者など、その死者どもの累積の爪の先ほどにも満たぬ数のわずかなもの。この世に浮かんだ死者の澱でしかない。すぐ死ぬ。陰府こそが人の本来の住処、地虫と同じよ。少しばかり陽の当たるこの世へ顔を出しても、すぐに引っ込む。暗く湿った地の底が相応なのだ」
「ああ確かに。生きとる者より死んどる者の数の方がはるかに多かった………」
「弱きものはすぐ死ぬのだ。弱きが群れてかたまって、つまらぬことばかり繰り返して老いていくだけ。怪我や病い、獣に襲われた穴に落ちた火に焼かれた水に浸かったと面白いほど簡単に死んでいく。………そんな生き物とは別の我らがどうして気にかけてやる道理があるのか………」
「だからだよ」
分かってないなという顔でタマヨリは云った。
「儚く脆いからかけがえがないんだよ」
ワダツミは首を傾げた。
「弱いから助けあって、弱いから懸命になるんじゃ。それが人の有り様じゃなかろう?」
「何をしたところでこの世に在ることなど、かりそめでしかない」
「だから、命はすぐに消えてしまうから、次へ渡すんじゃ。そうやって連綿と繋いできたのが、あの死者たちじゃ。累々と死を重ねても『命』は絶やさなかった」
「まあおまえが何を思おうと、事実は変わらんだろうが」
「ああ変わらんだろうが。おれはそれが愛おしいんじゃ。ほんの束の間の命だから、しあわせになろうとする。しあわせにしようとする。しあわせであってくれと願うんじゃ。おれだってそうありたい」
ワダツミは深く息を吐くと、
「それがおまえが『竜宮』へ行く理由なのだな」と訊ねた。
「え…………っと」
「人ならぬ者の力を地上にのさばらせぬため、俺もろとも海へ戻ると」
「当たらずとも遠からず、じゃな」
「嘘がある」
「………なんじゃ」
「おまえはしあわせにはなれない」
タマヨリは黙ってしまった。
『竜宮』へ行くということは、人らしさの一切を捨てるということだ。神の領分へ組み込まれるということだ。
「俺の願いは、半分叶うがな」
困り顔のタマヨリにワダツミは笑った。タマヨリはその様を見てこれがあのワダツミだろうかと目をしばたかせた。
何かに洗われたような不思議なほど穏やかな目だった。
タマヨリは弾かれたように立ち上がり、ワダツミの両手をとった。
「知ってた!おれは何も覚えとらんと云って、『竜宮』を追われたことも戻れぬことも、体を引き裂かれたことも、お前ひとりに丸投げした。押しつけて逃げたのがおれじゃ。
おれはな、人の真似事がしたかったんだろうなぁ、人のように生きたらしあわせじゃと思ったんだろうな。
ワダツミを置いて生まれ変わって、それですっかり良いような気がしとった。
お前を抜きにしてしあわせになんてなれるはずなかったのに。だって、泣きてえほど故郷に帰りたいのは、分かる。
それは最初っからおれの疼きだ。おれの中にもお前中にもそれは予めあった。だから何度岐れても何度でも出会う」
タマヨリが云い終わるのを待ってワダツミは手をほどいた。その後は鉾の柄を掌の中で遊ばせて黙っている。
「……何か答えてよ」
「別段、押しつけられたとも逃げたとも思ってはおらん。お前はお前のやり方で生き延びた。賢しいやり口だが蓋を開ければ人の真似事がしたかったと………、それだけのことだ」
「ん、うん、そうか」
「そうだな、覚えておらぬのなら教えてやろうか。『竜宮』を」
「ああ」
「『竜宮』は『真海』の中心、神の地だ。ゆえに憂いがない。憂いを許さない。
神代を幾星霜重ねるうちに『竜宮』は衰え始めた。そこに新たに生まれた海神に求められたのはただ強さだけだった。欠片の憂いも許さぬ強さを。
どんな剣も切ってみなければ、切れ味は分からん。我らは切った。求められるままに切って切って切りまくった。
我らは生まれながらの残虐な神だったらしい。剣が切れるからと云って神々は腹を立てた。
美しい珊瑚森があってな、我らはそこを憩いの地としていた。乱暴が過ぎると宮殿を追われていたのだ。構わなかった。そこで目にとりどりの魚を、耳に人魚の唄声を得た。
ある日、神々の雷がその珊瑚森を貫いて我らの身体を裂いた。
頭から二つに割られ、そのまま足元に開かれた『下海』へ引摺り込まれた。
裂かれた半身と半身は手を伸ばしあって互いを求めた。僅かも残らぬ力で手を伸ばしたが、届かなかった。お前は必死になって身を捩るから目も鼻も臓物も裂け目から溢れ出て『下海』の仇者に喰われてしまった。そのまま力尽きて沈んでいくのを俺は見ていることしかできなかった。
判っただろう………。
『真海』の老耄をはじめ、姑息な神々を俺は信用せん。
『海境』を開いてやるなどと甘言につられて尻尾を振っては、お前も俺もまた奴らのいいようにされるだけだ」
「『竜宮』のこととなるとワダツミはたくさん話してくれるんじゃな。おれは行ってみたい」
「だから………」
「ワダツミは故郷がいっとう大切で、でも同じくらい憎たらしいんじゃな」
タマヨリはニコリと笑った。
「だから王にならなければ気が済まんのじゃろ。大丈夫じゃ、おれとワダツミで夢みてぇにすげえ『竜宮』を創ろう」
「地上のこと、全て忘れてもか?」
「兄ぃさがまたおれを見つけてくれるなら、いい」
「母を殺し父と姦通してもか?」
「それはぜーーーったいにしない。母上とはもう離れて生きていくほかない。そうさせてくれ、ワダツミ」
それを拒否もせず諾ないもせずワダツミは、満ちてくる潮の飛沫を浴び続けていた。
タマヨリが立ち上がると群れから逸れた白い玉が数個誘われるように近づいて、ふよふよと周りを飛んだ。その蛍火の中で血の気の失せた青白い顔が乞うように動かない笑みを浮かべた。
「お前の云ったことは、俺に於いて反転する。なぜならお前は俺の背なのだ」
「またよく分からんことを云うなぁ」
「半分だ」
「半分?」
「お前が『竜宮』へ還るなら、俺がおまえの願いのどれか半分は叶えてやる」
「え?」
「喜べ」
「え、ああ嬉しいよ。うん、とても嬉しい!ワダツミの半分とおれの半分を足して、願いはひとつ叶うわけじゃな」
「…………」
「『ひとつ』、叶うんじゃ」
「半分と半分でようやくひとつ分とはな」
ふいっと横を向いたワダツミの肩にも蛍火は揺らめき、やがて登る月の輝きの中にすべて消えていった。
終わり
18章へ続く
読んでくれてありがとうございます。
