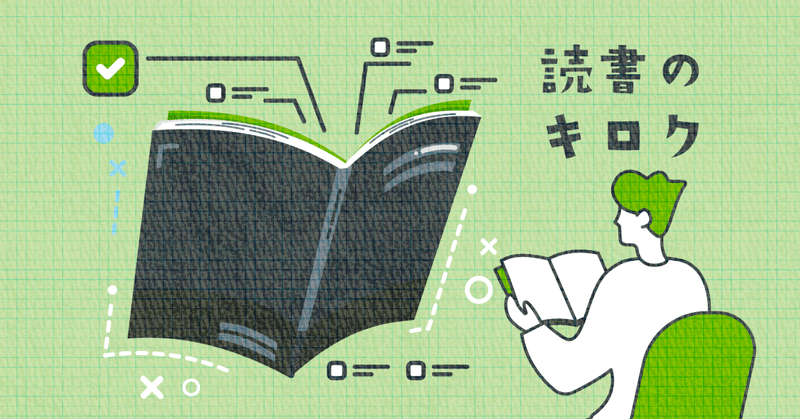
知識は理解。理解は優しさ
喃語
私の次男は車が大好きです。町中を走る車を見て、社名を答えるのはお手の物。この前は新しく覚えたテスラももう車の横姿を見ただけで答えられます笑。親も唖然です。
そんな次男ですが、ベンツのことは、ベンチュと発音するのです。大分前から、ベンツに関しては知っていて何度も発音しているのですが、どうにも「ツ」が発音できません。
そんな折り、最近次男が通う発達支援の先生から喃語について教えていただく機会がありました。おおーと思う部分が多かったので共有させていただきます。
多くの赤ちゃんがまず発音するのは、「ママ」とか「パパ」とかだと思います。経験則からもその通りだと実感するかと思います。これはもちろん、ママだよーとかパパだよーとか言っているからと理由もありますが、口の発達の要因が大きいようです。
私としては昔の人が、あかちゃんが始めに話す言葉を、親の愛称にしちゃえという風に思いました笑。ちなみに我が子は、バスが好きすぎて、バスを見たときの「バ!」でした笑
マやパ、バは、口を開けながらゆっくり息を吐くと出せる音だそうです。だから口の動きとして出しやすく始めに話すそうです。
次にア行。口を開けたままの状態で息をはけるようになると、出せます。
次の段階はタ行とナ行、舌の発達に伴い、上顎に舌をつけると発音できます。問題の「チュ」と「ツ」ですが、「チュ」は思いっきり口をとがらせればいいのに比べ、「ツ」は「チュ」よりも少し緩めないと発音できないそうです。だから、微妙なさじ加減が難しく、ツのつもりがチュになるのだそう。
その次は、カ行、ハ行。この行も舌を使うのですが、ビタっと上顎につけるのではなく、中途半端な位置で使います。その中途半端具合が難しいから、タ行・ナ行の次なのだそうです。
最後に、サ行、ラ行、ヤ行。ここが最後に難しい理由は時間の都合上聞けませんでしたが、難しいのでしょう笑。
やっぱり中途半端というか微妙なさじ加減というのは、経験によるところが大きいのかなと思います。人生酸いも甘いも絶妙なさじ加減が大切ですもんね。
改めて考えると、マ行、タ行、ナ行が早口言葉に多い理由も納得です。マ行は口を閉じなければいけないし、タ行とナ行は舌を上顎につけなきゃいけません。定番の「生麦生米生卵」なんて、嫌らしいほどマ行、タ行、ナ行入ってます笑。考えた人はきっと意地悪ですね笑。
理解すると優しくなれる
この喃語の仕組みを教えてくださった先生は、「子どもが言葉をはっきり話せないのは発達の関係上仕方のないことです。親御さんが早口言葉を言うのが難しいように、お子さんも難しい気持ちを抱えています。大切なことは伝わることなので、お子さんの発語が少々違っていても否定するのではなく、伝わったよということを示してあげてください。」とおっしゃっていました。
とても納得したと同時に共感しました。
書き直しを何度も強要すると書きたいという気持ちがそがれる。言い直しを何度も強要すると話したいという気持ちがそがれる。間違いは悪、正しいが正義という構図。
ただ練習の数が少ないだけなのに。なんならまだ発達が追いついていないだけなのに。それはまだその子にとって時期が早いだけなのに。
教員時代のモヤモヤが言語化された気持ちでした。
そりゃあ、正しく話さないといけない、正しく書かないといけないというプレッシャーを受けるくらいだったら、「だまっていよう」とか「書かないでいよう」という気持ちになりますよね。
だから子どもたちはスピーチや作文をいやがるんだと、なんだかつながった気がします。それは指導者側の責任でもあったのですね。と理解できました。
〇年生だからという理由で、これはできる、これができなきゃなんて・・・今思い返すとなんと傲慢なことか。発達を理解すると、子どもに優しくなれます。
優しくなれないときは、発達への間違った理解や心理への無知なときが多いかと思います。子どもはこの年齢になったらこういうことができるはずだ!とか、子どもがどんなプレッシャーや苦しさを抱えているかとか。そういったことを理解しようとしていないとき、子どもへ厳しくなってしまうのかと思います。
もっというと、子どもに対してだけではありません。パートナーに関して。同僚に関して。上司に関して。不満や愚痴をもつとき、その人を理解しようとしていない場合が多い気がします。
理解から始まる優しさ。私とともにはじめてみませんか?
親として必要なこと
こういう経験からか、私は〇〇すれば、こうなる!のようなハウツー本よりも脳科学、心理学の本を読むのが好きになりました。あれだけ自己啓発系の本を読みあさり、とにかく行動じゃ!!とやっきになっていた私がです。
自分の仕事が教育に携わっていなかったら、きっと発達とか教育とかの知識を入れようと考えることはなかったと思います。そうなったときどんな子育てをしてしまうのだろうかと想像するだけでも不安です。
でも実際に、教育や発達の仕事ではない親御さんなんてごまんといます。というかそちらの方が多いかもしれません。ましてや私のように教育に携わりながらも、発達に関する知識が全然ない人もいるかもしれません。
するとどうしても子育て方針は、自分が受けてきた子育て法か学校のいいなりかのどちらかだと思います。どちらも必ずしも悪いとも限りません。が、いいとも限りません。
学校に通う経験や子育てを受けた経験は、だれしも通ってきただけに、子育てに関する考えはなにかしら一理ある理論だと思います。
その上で、それが子どもに対して合っているのだろうか、と振り返る必要はあるかと思うのです。共働きが増え、勤務時間外でも対応を求められたり、祖父祖母は遠くに住んで助けを求められなかったりと、子育てについて考える余裕をなくす理由はどれだけでもあります。きっと今後も増えることでしょう。
しかし、不登校・発達障害・いじめ等の子どもに何かあった後なら、なんとかして子育てについて真剣に考えるかと思います。勉強するかと思います。
本当に何かあってからでいいですか?逆にそうならなければ、必要ないですか?
そんなことを考えるきっかけの一部になれたらと思い、今後も週一回記事を更新していきます。記事を更新しない日は、私の子育て日記的なことをつぶやいています。よろしければ今後もよろしくお願いします。
優しい世界を目指して。
最後までお読みいただきありがとうございました。何かの参考になれば幸いです。素敵な一日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
