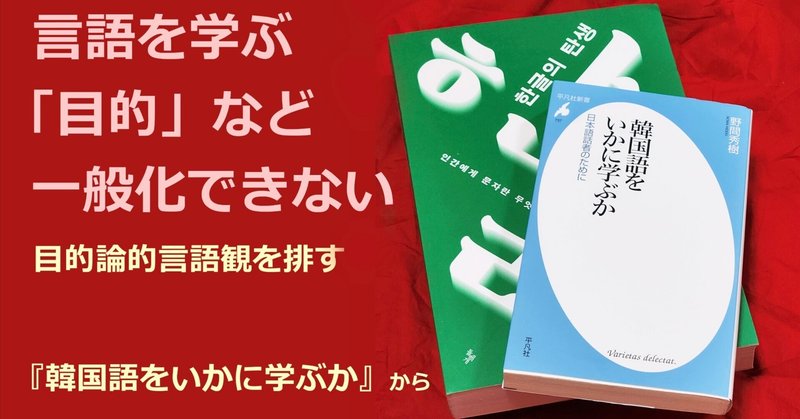
言語を学ぶ「目的」など一般化できない。目的論的言語観ではだめだ。
野間秀樹著『韓国語をいかに学ぶか』(平凡社新書)の第4章「〈教える〉ことから〈学ぶ〉ことを見る--師よ、師たちよ!」からの抜粋です。現在の言語教育の圧倒的な主流である言語道具観、そして目的論的言語観を批判しています。私たちの〈ことば〉を、〈学び〉を、取り戻すために。
言語の「目的」など一般化できない――目的論的言語観の限界
〈何かの目的のもとに言語を傅(かしず)かせる思想〉を〈目的論的言語観〉と呼ぼう。〈目的論的言語観〉は〈言語道具観〉と表裏一体の思想であり、言語を矮小化して位置づける典型的な思想の一つである。言語教育と言語学習は、この観点からも見ておかねばならない。
言語研究の分野でも、人がことばを発するのは、何某(なにがし)かの目的や意図といったものがあるからだ、という考えに基づく研究が少なくないが、これも目的論的言語観である。言語活動において表現意図というものは当然あり得るわけだが、言語が発される根拠を、知らず知らずのうちに全て表現意図に帰してしまうところが、目的論的言語観の見えにくい陥穽である。
言語教育の分野でも、能動的なコミュニケーションの意義を強調する余り、しばしば目的論的言語観に陥ってしまう。can-do などという発想にもそうした思想が見え隠れしている。誤解を招いては困るが、象徴的に言うと、子供ではあるまいし、人は〈やりたいことができた!〉だけを目標に言語を学ぶわけではない。言語は確かにサバイバル的な言語場で決定的な役割を果たす。やりたいことができるか、言いたいことが伝わるかは、ある言語場では深刻であり、深刻でないまでにしても、重要である。ヨーロッパのような多言語空間では、そうした課題が真っ先に浮かび上がるのである。
しかし、人は明示的な目的のもとにのみ行動するわけではない。さらに言えば、言語に定式化して示せるような目的のためにのみ、言語を使うわけではない。漠然たる目的や、茫漠たる無目的のためにも、人は言語を営む。「おしゃべりを楽しむ」とか「ただなんとなく話す」とかなどとことばにされた「目的」は、後付けされたものに他ならない。言語研究の理論化の過程などでしばしば言われる、話し手の「目的」や「意図」といったものは、事実上、ほとんど後付けされたものである。
こんなところでいきなり〈愛〉などを引き合いに出すのも、何だが、ことばは時として愛の形そのものでもある。愛の形に「目的」などあろうか。言語化されたことばを、後に「愛を表現する」などといった「目的」や「意図」が後付けされているだけである。会話は、私とあなたの対位法である。二人で行く先を創り上げたり、気がついたらどこかへ辿り着いているのであって、それは予め共通の行く先など存在しない言語である。その証拠に、愛の言語もしばしばなかったことにされてしまう。
あるいは、言語を学ぶにあたって、あまり声高(こわだか)には語られないけれども、学習者の心のどこかに常にあるとも言ってよい、言語における心理的な欲望、社会的な欲求といった漠然たるものも、決して軽視できない。あるいは知的に、スマートに、エレガントに、さりげなく、あるいは親切だったり、配慮だったり、共感だったり、共有だったり、そうした心の領分に関わる営みとしての言語である。
言語教育におけるマニュアル化されたcan-do という発想が、しらけたもの、あまりに単純素朴なものに見えてしまう最大の原因は、言語のこうした多様な性質が隠されてしまうところにある。目的があって行動がある、その目的のために言語を「使う」、そう主張するとき、ここでも言語は単なる道具である。can-do という発想では、発音などは目的のためにしばしば軽視される。でもね、例えば学習者はね、かっこよく発音したいのです。それって、言語じゃないの? 言語教育の問題ではないの?
実は問題は言語教育に留まらない。さらに言うと、言語哲学などで語られる「文」や「命題」が、しばしば空虚で現実の言語から遊離しているように見えるのも、「論理」や「真偽」などといったものが、「目的」のもとに位置づけられてしまっているものばかりだからである。そこでも言語は「論理」のための道具である、それ自体はいいだろう。いけないのは、いつしか、そのためだけの道具であるかのごとく、語られてしまっていることである。そこからは大切なものが抜け落ちる。「言語は」とか「ことばは」とか「意味は」とか「文は」といった語り方は、例えば「言語哲学」というような枠のように、どんなに限定をつけても、しばしばいきなり恐ろしい一般化の働きが剥き出しになる。こうした一般化は言語を語る様々な言説に現れ、言語は道具に矮小化され、貶められる。
先にも述べた。論理的なことも語れるし、非論理的なことも語れるのが、言語の凄いところなのだと。センスもナンセンスも語れるのが、言語である。「目的」だの「論理」だのしかない「言語」など、言語の半分はそっくり抜け落ちている。というより、そうした語り方では、言語の豊かなありよう自体を、完全に見失っている。それは言語の本質を見失っているということに他ならない。従って言語教育のあるべき姿からもかけ離れる。
今一つ、言語道具観や目的論的道具観に何が欠けているかを、〈母語〉という観点から照らしてもよい。母語にとっては、言語は自己の存在そのものに限りなく近いものである。自己の存在に限りなく近いものとしての言語、そこには目的だの道具だのといった動因(モメント)など必要もない。〈常に既に在る〉のが母語だからである。母語とは「コミュニケーション」の名で強調される対他的な動因を云々する以前の現前(げんぜん)であって、私たちが〈在る〉ことの世界に関わっている。ことばで他者に関わろうとすることを問題にする以前に、母語は自らに既にそこに存在するのである。そこでいくら「コミュニケーション」の術語を拡大解釈しても、なお掬いきれないような地平にある、〈言語〉の姿が、母語を見つめると、見えてくる。言語教育や言語学習はこうした姿をたとえ一刹那であれ、見ようとしているのか?
非母語もまた、母語に準ずるとまでは行かないまでも、母語の存在のようなありようを希求することがあってもよい。母語のようなありようを非母語が共にすることがあってもいいはずだ。例えば〈あの人の語る言語が、ちょっとでいい、私も欲しい〉、言語学習にあっては、それだけでも学習の存在理由を既に充足している。それは「目的」だの「意図」だのでは括れないありようである。
人は向こう岸に渡るために泳ぐだけでなく、泳ぐためにも泳ぐ。目的のために生きるだけでなく、生きることを生きるのであり、目的のために言語を使うのではなく、〈言語を生きる〉のである。象徴的に〈生きる言語〉と言ってもよい。〈共に生きる言語〉と言えば、よりリアルになるかもしれない。そういうなかで、目的も意図も語ることができるし、道具としての働きも重要な一部として位置づけることができるのである。こうした豊かなありようを、他ならぬ言語教育や言語学習が考えてもよいではないか?
言語道具観や目的論的道具観が言語教育や言語学習において問題なのは、それが言語のありようそのものを矮小化し、「コミュニケーション」という美名のもとに、言語の総体としてのありようを私たちが問う機会を、永遠に失わせるイデオロギーだからである。
『韓国語をいかに学ぶか』野間秀樹著、平凡社新書。pp.250-255。
「スキ」などいただければ、大変励みになります!
●『韓国語をいかに学ぶか』の「はじめに」と目次を読む:
●note:K-POP,もう体験してしまった共感! 言語を学ぶことは,誰にも止められない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
