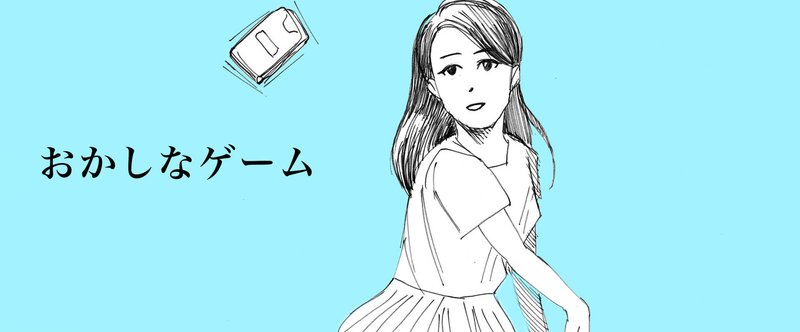
【5分小説】おかしなゲーム
とんでとんでとんで、夕日にテラっと輝いてタポンと落ちた、佑子の携帯。
まだ新しい、ドコモの新型。
僕は、そのドコモの新型が川の中に吸い込まれて消えてゆくのを見届けた。
「さ、さ」と佑子は急かす。
次は僕の番だ。
あぁ、名残惜しいが、僕のはどうせ使い古し。
けれどもやっぱり愛用の携帯を、よりにもよって濁った川の中へ投げ捨てるなんて気が進む訳も無く。
「ほらぁ」と佑子。僕はやっとの想いで決心を固め、わざとらしく「えい!」と叫んだ。
-
佑子と付き合い始めたのは5年前の夏休み。
僕は映画サークルに入っていて、佑子は僕の処女作のヒロインだった。
2人とも、まだ大学生の頃の話だ。
夏休みを利用して、奥多摩のキャンプ場までロケに来ていたのだが、まぁ初監督で、そもそもリーダーというモノに向かない僕は始終焦って勝手が掴めないまま昼が過ぎ…。気付けばただの、大学生によるバーベキューキャンプと化していた。河原でだらだら遊んでいたロケ班は、夜になると花火を始める始末。僕は始終うかない顔をしていたに違いない。居酒屋で3ヶ月バイトして買ったビデオカメラが三脚に乗っかったまま、恨めしそうに遠くを見ている。
「映画サークル、やめようかな」とか、そんなコトを考えて、ただ悶々。すっかり上の空だったせいか、背後に近づく佑子に気付かなかった。
「っと!あぶない!!」とっさに火花を避ける。
佑子は子どもみたいに大喜び。カメラの値段を知らないのか、無邪気な悪戯にしてもさすがにいけない。
「撮ってる?」と佑子。
「いや、撮ってない…」
「花火、撮ってよ。」
それから、僕は佑子と休日の度に2人で出掛ける様になった。
-
カメラを背負って、路地裏を散策したり、公園の子どもと遊んだり(一度だけ保護者の方に怪訝な顔をされて以来控えているが)とにかく、映画では無い映像を撮って歩いた。
アレ撮りたい、コレ撮って、と、佑子はいつも楽しそうにズンズン歩く。
僕がビデオカメラで撮る様に、佑子は携帯電話で写真を撮るのがお好きな様で、たまにお昼に食べたパスタとか、偶然見つけたノラ猫とか、他愛も無い写真をバシバシ送ってくるのであった。
僕は案外それが気に入っていて、撮りためた映像と一緒にPCのフォルダに溜め込んだ。5年前の画像たちは、今も実家のPCに入っているだろう。
今は就職して一人暮らし。買い換えた愛用のノートブックには仕事関係のデータしか入って無い。僕と佑子は遠距離恋愛と言う程でも無いが、会おうと思えば2時間はかかる。気がつけば、お互い26歳。月に一度会うだけになってしまっていた。
正直、別れる事を考えた事もある。
佑子は月一のデート(と言っても、映画を見て夕飯を食べるくらいだが)をイベントの様な趣で楽しんでいた様だったし、向こうも向こうで実家の定食屋が忙しそうだったので、会う回数が少ない事は気にならなかった。
しかし、もう26歳だ。イヤでも先の事を考える。
ケッコン。それは現実味が無かった。
そんなコトを頭の片隅で考えながら、横浜の街を歩いていた。桟橋の手前で佑子が思いついた様に振り向く。
「ね、ゲームしない?」
「どんな?」
佑子がこう切り出したのは初めてでは無い。以前も横断歩道の白い部分だけをぴょんぴょん飛んでみせたり、真夜中の線路でスタンドバイミーごっこをしたり、彼女はいつも勝手に新しい遊びを発明してきた。
今回もてっきりその類かと思い、気の無い返事をした訳だ。
「まず、2人の携帯をね、この桟橋から投げ捨てるの」
「はぁ?」
「一ヶ月以内に、携帯電話なしで私を見つけられたら、私たちの勝ち」
そんなバカな、と言いかけて止めた。佑子は真剣な顔でまっすぐこちらを見つめていた。
「勝ち…って?」
「結婚しよ」
沈黙。正直に言う、僕は意味が分からなかった。ゲームの意味も。彼女の真意も。ただ、佑子の顔は依然として真剣そのものだった。
僕が映画監督を諦めて就職する事を決めた日、佑子は同じ顔をしていた。この顔の佑子には、なんとも言えない無視できない強さがあった。
「もし、会えなかったら…?」
自分でも可哀想な程に気弱な声が出た。こういう時、主導権は向こうにある。
「会えなかったら、それでおしまい」
なんで?どうして?言い出したらきりが無いのは分かっていたし、あの顔の佑子に何を言っても聞かない事も分かっていた。
「一ヶ月以内…夏が終わるまで。制限時間は十分あるわ。携帯電話が無くても出会えたら、それはきっと、そういうコトなのよ」
佑子はにっこり笑った。
そうすると、ポケットから携帯を取り出し、迷い無く桟橋から放り投げた。まるで、願掛けのお賽銭を投げ入れるかの様に。
こうして、僕と佑子のおかしなゲームが始まった。
-
「就職、するよ」
喉から出た言葉の響きに、自分自身が戸惑った。え、と佑子は聞きかえす。が、僕はまた黙ってしまう。
「就職しようと、思う。ほら、内定決まってたとこ…」
どうも自分の言葉に違和感がある。それはそうだ。この四年、僕は映画監督になる事ばかり考えていたのだから。それは、佑子が一番良く知っているはずだ。顔を見れば、何を言いたいのか分かった。
「WEBの制作会社…だから、ほら、WEB上で公開する動画とかも作れるしさ…」
佑子の言葉が怖くて、言い訳気味に慌てて付け足す。あぁ、うそ。映画監督の下積みにしては、遠すぎる。あの時の佑子の顔は、2年経った今でも覚えてる。真剣な顔でまっすぐ僕を見て、なんだか怖いくらいだった。
そして一週間前も、桟橋の上で佑子は同じ顔をしていた。
おかしなゲームのルールはいたってシンプルだった。お互いの携帯を捨てること。そして、一ヶ月以内に、僕が佑子を見つけること。
駅の改札の向こうで、佑子は手をふった。いつもより、少し長めに。僕たちは5年付き合った。5年。初めから特別熱々だった訳では無いが、やはり5年経つと違う。
最初の頃は、佑子から送られてくる写真つきのメールを、いちいちPCに転送して取っておいたものだが、あれはバイトの帰りだったか、佑子から届いた満月の写真を「昨日のと似た写真だ」と思って消してしまった。
それがクセになって、それからは一度見たらそれきりだった。いや、事実、もっとひどかった。
後で見れば良いと思って、すぐに見なくなり、ついには見ないまま消えてしまう写真もあった。(と言っても、一日に何枚も送られてくるワケでは無かった。一日、一枚、といった所だ。毎回、タイトルが付いていて、写真と併せて見るとなかなか面白いと初めの頃は感心すらした)
例のゲームを持ちかけられた日、写真の事でケンカになった。僕は、佑子が交際5周年の記念に送った写真を、デートの当日まで見ていなかったのだ。
「信じられない」飽きれた様に、はき捨てる様に呟いた。
ちょうど映画館に入るところだったし、佑子の言い方に少しカチンと来て、僕はその写真を結局見なかったのだ。
そして映画を見終えた後、例の事件である。
「交際5周年の記念…」
誰も居ない部屋、間抜けにも声に出してみる。ベットに横たわり、何も無い天井を見ている。一人暮らしを始めて1年が経つが、未だに未開封のダンボールが積まれた殺風景な部屋。ここを未だに自分の城だとは思えていないのだ。
実家には、今でもビデオカメラや三脚が眠り、本棚にはキューブリックとか黒澤明の本がぎゅうぎゅうに入っているだろう。学生の頃は、よく佑子も遊びに来ていた。
あれから一週間しか経っていない。いつもは平気で一ヶ月間も空けれるが、今回は訳が違う。
「会えなかったら、それでおしまい」
佑子の言葉が、鉛の様に腹に残っていた。明日は日曜で会社も無い。佑子の実家に行ってみよう。実家の定食屋のエプロンをした裕子が、ルール違反よと、むくれる顔が目に浮かんだ。久し振りにあの店のエビフライを食うのも悪く無い。気持ちが軽くなったのを感じて、いつの間にか眠っていた。
「え…?」
頓狂な声が廊下に響く。
「店が潰れたって…いつです?」
急に伺うのは失礼だと思い電話をしたのだが、電話口に出たのは知らないお兄さんだった。彼の話では、佑子の実家の定食屋は数ヶ月前に潰れて、今はカフェとして営業していると言うのだ。聞きなれないカタカナの店名を教えてくれたが、耳を素通りしていった。
僕は、首筋が熱くなるのを感じた。
会えない。
携帯も無く、住む場所も変わり、本当に音信不通になったのだ。
会えない、そんなまさか。
正直に告白する。ゲームを持ちかけられた時、住んでいる場所を知っているという保険があり、どこか高を括っていたのだ。いざとなれば、遊びは終わりだと、こっちから会いに行けば良いと。そう思っていた。
しかし現実は違った。
この広い世間で、僕たちが偶然再会するなんて在り得るのだろうか。僕は、迷子の子供の様に立ち尽くしていた。
-
佑子と僕が、おかしなゲームを始めて3週間が経った。タイムリミットまで、あと一週間。あれから僕は、毎週日曜日には地元に帰り、何かしら手がかりが無いかと探していた。
「一ヶ月以内に、携帯電話なしで私を見つけられたら、私たちの勝ち」
横浜の桟橋の上、佑子は言った。
「会えなかったら、それでおしまい」
もちろん、会えた時の約束も覚えている。結婚しよ、と佑子は言った。ごく自然な、柔らかい言い方で。
3週目、つまり地元に戻るのも3回目だ。僕と佑子は地元が近かった。大学を挟んで、自転車で10分かからない場所だ。そのせいか、デートは専ら地元の映画館か喫茶店と決まっていた。もしや、と思って映画館も喫茶店も行ったが、佑子の姿は無かった。
映画館では、2人で最後に見た「さくらん」がまだやっていた。それはそうだ、まだ一ヶ月しか経っていないのだから。喫茶店のマスターに何となく訪ねる。佑子は来ませんでしたか、と。マスターはひげもじゃの口元を緩ませ、逃げられたのかい、と悪戯っぽく笑った。必死に探そうと思えばもっと出来たのだ。
例のなんとかというカフェで、元あった定食屋一家の情報を聞いてまわる事も出来ただろうし、なんなら近所の友人宅を、一軒一軒回ってもいい。
しかし、それは出来なかった。なぜなら、あの喫茶店のマスター同様、なんだフラれた男が未練がましい、と笑われるのがオチだと思ったからだ。もっと言うとストーカーだと気味悪く思われる恐れすらある。
事実、僕はただ単にフラれただけなのかも知れない。
日が落ちてきた。風が涼しい。
夏が終わる。
-
僕の勤めている会社に来る仕事は、実に退屈だ。IT企業と聞こえは良いが、僕がやりたい動画制作の依頼など極々たまにしか無い。たまにあったとしても、会社の名前が入ったロゴが、奥から手前に派手に飛び出てくるとか、そんなクリエイティブとは真逆の依頼ばかりである。
ゲームオーバーまで、あと一週間。(12時をまわったので、あと六日か)
佑子が居なくなる。
つい先日まで、まったく現実味の無い事だった。
居なくなる事は、結婚と同じくらい、現実味の無い事だった。僕は、珍しく上司に頼んで仕事を持ち帰らせてもらった。残りの時間を彼女が居るかも知れない地元で過ごしたいと思ったからだ。ここに居れば、何かつかめるかも知れない。
なんとかかんとか株式会社、爽やかなスカイブルーのロゴが編集ソフトの中で踊っている。それをしばらく見つめていた。大学までの二十数年間を過ごした、実家の部屋。たまに帰れば身体の一部の様に落ち着く場所。仕事の合間にコーヒーをすする。母がいれるコーヒーは少し甘めだ。スカイブルーのロゴは、なんとも切ない動きを繰り返し再生していた。
繰り返し、繰り返し。
ハードディスクに保存しようとした時、デスクトップにあるフォルダの名前が目に留まった。
「佑子写真」
毎日飽きもせず送ってきた、佑子からの写真。驚きはしなかった。それは、5年前からずっとそこにあったのだから。ただ、僕が忘れていただけで。
少し見るのが怖かった。
佑子が昔送ってきた写真を一人で眺めるなんて、まるで終わった過去の思い出を懐かしむ様な行為じゃ無いか。しかし、このまま本当に思い出になってしまうよりかは感傷を押し殺し、少しでも手がかりを探す方がずっとマシだ。
フォルダを開くと、懐かしい写真がパッと鮮やかさを取り戻した。こうして見ると、やはり月の写真が多いと思う。なるほど、並べて見ると、毎日表情が微妙に違う。なんで気付かなかったのだろう。
あと、猫の写真。猫顔ってワケでは無いが、佑子はどちらかと言うと「猫」である。気まぐれで姿を消すところなんて、まさにそうじゃないかと、ディスプレイの前でクククと笑う。
それに、なんと言っても食べ物!女友達と外食した時なんか、毎回の様に送ってきたっけ。甘いものに目が無く、パフェなんて様々な角度から捉えられていた。
なぜ気がつかなかったんだろう。佑子は毎日違うモノを見ていたのだ。奥多摩で始めて話した時から、佑子は僕に“素敵なモノを見つける目”をおすそ分けしてくれていたのだ。
そして、そのおすそ分けを、毎日メールで送り続けてくれていた。僕は、それに気がつかなかった。
-
毎日、地元の街を走り回った。美味しいと言っていたレストラン、海岸のベンチ、変な看板のお店。とにかく、写真に写っている場所は全部回ろうと思った。枚数は膨大だが、行動範囲は限られている。残り5日でも回れるだろうと考えていた。
残り四日、何も無し。
残り三日、何も無し。
残り二日、何も無し。
そして最後の朝が来て、ようやく写真に写っている場所を回りきった。妙な達成感。これで後ろを振り向くと佑子が、なんて展開すら期待した。8月の末。公園に人影はない。みんな家で溜まった夏休みの宿題でもやっているんだろうか。少し汗ばむ、穏やかな昼下がり。公園のベンチに腰をかけた。
佑子を見逃してはいけないと自転車では無く徒歩で動き回っていたのだから、足が棒の様だった。
「疲れた」
そう言って僕は泣いた。
佑子と横浜の桟橋でゲームを始めてから、今日で一ヶ月が過ぎようとしている。僕ははじめて佑子を失った事を実感し、泣いた。
この数日間で巡り歩いてかき集めた、佑子の場所。佑子が送ってくれた時と全く同じ場所もあったが、全く変わってしまった場所もあった。(喫茶店などは変わっていなかったが、裏路地なんかは大分無くなっていた)
日常にある、楽しいコト、キレイなモノ。
そういう事に気付けなくなってしまったのは、いつからだったのか。佑子は、僕が夢を諦め就職をした事よりも、そういう事に鈍感になってしまった事の方が悲しかったのだろうか。今となっては分からない。涙が頬をつたう。
全く、意地が悪い。こんなクリア出来もしないゲームなんて、反則だ。仮に真意が分かったからと言って、彼女の居場所が分かるワケでもないのに。
ふと、何かが頭の中で弾けた。いや、もしかしたら。
僕は立ち上がって時計を見た。まだ間に合う。僕は、最後の心当たりの場所に向かった。
奥多摩。あの日、花火をした河原に佑子は居た。さも当然の事の様に。
「…なにしてんの」
僕が疲れきった顔で言うと、佑子は笑う。
「お父さんとお母さん、仕事辞めて暇になったからね。旅行よ」
「…旅行ね」
「だって、潰れちゃったものは仕方ないもの。とりあえず、お疲れ様って」
ご両親はと聞くと、コテージを指差す。
もちろん、言いたい事は山ほどある。
そもそも、お前ってヤツは…
だいたい、オレがどれだけ…
山ほどあって、どれから言っていいのやら。
佑子は、素足になって川に入り、嬉しそうに水を蹴った。僕は飽きれて、でも嬉しくて、それをただ眺めていた。
ここの光景は、5年前と何も変わっていない。
「まだ途中だったでしょ?」
「え?」
「バーベキューで中断したままだったでしょ。ロケ…」
僕は黙って荷物の中からビデオカメラを引っ張り出す。
砂利を避けて、安物の三脚を立てる。
会社、辞めるつもりだから、しばらく指輪は我慢してくれよ。
お揃いの携帯電話でも、代わりに買おうか。
そう言うと、佑子はどっと笑った。
サポートも嬉しいですが、よかったら単行本を買ってください!
