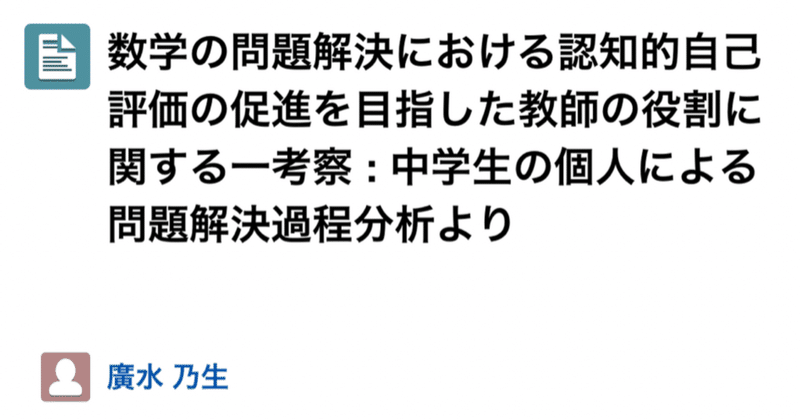
恩師の教え『心理学研究と教育学研究のちがい』
話すことはあっても書いたことはない話。
1990年、研究能力もないのに入学した大学院。
「ある教授YSが『研究能力だけでなく教育への情熱がある若者の可能性に期待するのが教育学の本質ではないか』と合否判定の教授会で発言して入学が許可された者が今回の合格者の中にいる」という噂を新入生歓迎飲み会で耳にした。
先輩たちは「誰なのだろう」とキョロキョロしていた。
オレは他所を見ながら内心「それってオレだ…」と、そして、YS教授がいなかったらオレは今ここにいなかったんだなと悟った瞬間でもあった。
大学で研究してるだけのやつなんて、本当に教育をどうにかしようなんて思ってやってないだろ、と本当に失礼な気持ちも少なからず持っていた。
能力もないのに受験した大学院も、アカデミアへの殴り込みみたいな気持ちもあったと思う、根がロックだから。
でも噂を耳にした瞬間、そんな傲慢な思いをもっていた自分を恥じた。
むしろ、これ(研究能力だけでなく教育への情熱がある若者の可能性に期待するのが教育学の本質ではないか)ってオレも支持している価値観だ。
オレがもしダメな学生と認定されたら、YS教授の信念を、自分の大切な信念を否定することになる。
オレはやるしかなくなった、教育学研究を。
しかし、もともと論文を書くなど、根気のいることが苦手な自分にとって2年間集中して研究していくなんて困難であった。
東京の大学院ともなると、ちょっと田舎では見ないレベル感の方がたくさんいた、先生も学生も。
自論は展開できても、研究の土台がなさすぎて、議論になりもしなかった。
でも先生方や特に先輩には大変お世話になって、だんだん研究の進め方や考え方が身についていった。
2年目になって、ようやく修士論文の方向性を見つける感じで、実質12月までには書き上げなければならないから、あと半年ちょっとで調査などを進めてまとめ上げなくてはならなかった。
先輩に助けられて、何とかギリギリで論文を提出できた。
しばらくして審査結果を聞きに、指導教官であるYS教授の部屋へと行った。
「廣水くんも、もう就職か、進学か、進路が決まってることと思うから、一応、通しておいたよ。」とYS教授。
『一応』???
僕は扉の前に立ったまま、すかさず聞き返した。
「先生、『一応』ということは、何か十分でないと思われたことがあったのですか」
「うん」
「それは何ですか?」
「廣水くんが書いた論文は、今では数学教育学会で最近流行ってきてよく見る形のものだから、論文として問題はないんだけど、僕からするとこういった論文は教育学研究論文でなくて心理学の研究論文なんだよね。」
「心理学の研究?」
「廣水くんの論文は、子どもたちの数学的な活動をビデオ撮影して逐語から認知科学に基づいて分析して知見を得ているでしょう。これは、子どもの認知活動、心理的な面を調査しているに過ぎない。
教育というのは、そういった認知面だけでなく介入する場面があってどう子どもたちが変わっていったかというところにダイナミクスがある。
介入そのものがない研究は、教育学研究論文とは思えないんだよね。
認知や心理の調査研究だけなら、それは教育学研究ではなくて、心理学研究だと考えてる。」
これが僕が大学院で一番強烈に学びになった言葉だった。
扉の前に立ち尽くしたまま、「もう一年残ります。」と言った。
それは、僕が入学できたのは、このYS教授の鶴の一声、このYS教授の教育観によるものだったからだ。
この先生が認めてくれない形で修了するわけにはいかなかった。
なぜなら、それは僕を入学させた彼の信念を否定することになるし、ひいては僕の信念も否定することになるからだ。
それから約30年経ったのだが、この出来事は、僕のひとつの軸を成していた。
2004年から2018年までコミュニティファシリテーションの探究をしできたが、ずっとこだわっていたのは、心理的な見立てと介入の機能性だからだ。
修士論文でいうと2年目までが心理的な見立てで、3年目に加筆したのが介入の機能性だった。
この二段構えはその後の自分の活動の骨格となっていた。
その後、ある大学院の(数学教育学でない社会科学系の)博士後期課程に入学したのだが、博士論文は書けず単位取得退学とした。
本当のことかわからないが、のちに入試のとき修士論文が評価されていたことを耳にした。
自分では何とか形にしたとても稚拙な論文だとずっと長い間思い込んでいたので、客観的な評価としてそうであったなら救われるなとそんな気持ちにもなった。
大学院から論文に向き合って10年間、先輩と共に数学観や数学的信念についての研究を積み上げていた。
これらをまとめることはないまま、数学教育学から身を引いた。
そうして紛争解決やファシリテーションの道へと開いていくのだが、それも10数年やって身を引いた。
これの繰り返しのようでいて、対象領域は変わっていってるようでいて広がり、探究の原則は変わっていないようにも思える。
今は、これらの流れを汲んだ形で、Sustainability Transformation推進に取り組んでいる。
が、まだまだ道は遠い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
